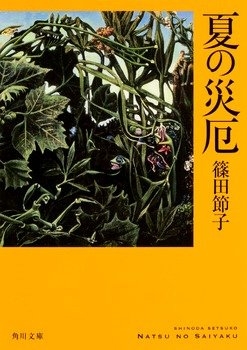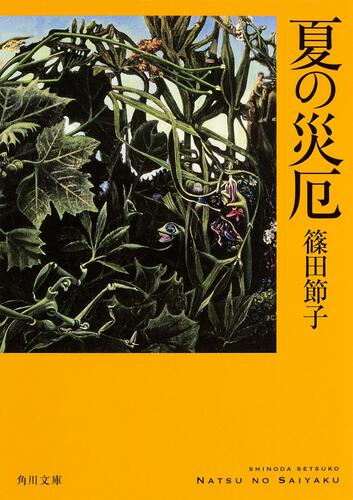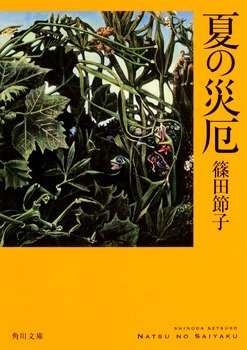コロナウイルスの脅威は未だ収まる兆しを見せません。この未曽有の危機に立ち向かうにはどうすればよいのか――。いまから25年前に発表された篠田節子さんの『夏の災厄』は、未知の感染症をテーマにしたパンデミック・ミステリです。前例の無い事態に後手に回る行政、買い占めに走る住民たち、広がる混乱と疑心暗鬼……。今日の状況を予見しただけでなく、この災厄を乗り越えるためのヒントも提示する本作の、冒頭部分を6回に分けて公開します!
>>前話を読む
◆ ◆ ◆
気になるケースにぶつかれば、調べておく。責任とか義務とかいうものを超え、それは今、房代の生きがいになっている。二十年以上のブランクを経て、この仕事に復帰して五年目。新しい機械の操作や横文字にはずいぶん苦労させられたが、ここ一、二年、仕事の醍醐味がわかってきた。
時計は十二時を過ぎているが、眠くはない。人生も折り返し地点を過ぎると、体のほうが寝る時間を惜しみ始めるらしい。少しでも安い卵を買おうとスーパーマーケットの広告に目を凝らしていた、四十代の頃の焦燥感や閉塞感がうそのようだ。
静まり返った室内に、青柳のそろばんの音が響く。本人曰く機械類は昔から苦手で、そろばんの方がよほど便利だそうだ。確かに青柳のレジスターや電卓の打ち間違えは頻繁だ。最近まで、帳尻を合わせないまま帰ってしまっては、小西を怒らせていたが、ついに数日前、始末書を書かされた。それ以来、金額が合うまで帰れなくなった。
房代はカルテの束の中から、昨日のあの幻の匂いを嗅いだ患者の物を探し当てた。ポケットから眼鏡を取り出して鼻にひっかけ、カルテを裏返すと「富士大学付属病院へ移送」とある。そうだった。あの患者を紹介した先は、富士病院だ。この市で、夜間の受け入れ態勢が整っているのは、そこしかない。病院でどのような診断が下されたかは、報告書を見るまでわからない。
房代は、カルテの表を見て、そこにもまた今日来た男性患者との共通点を発見した。住所が窪山町だ。発熱、頭痛、そして奇妙な匂い、よく似た症状でやってきた患者二人は、ごく近くに住んでいる。女の年齢は、三十三歳だった。
「あらま、厄年だ」
「へえ?」
青柳が、覗き込む。
「俺と同じ。こっちはその上、天中殺だ」
「何が厄年だよ。あんた今年の夏で四十六でしょうが。それとも四十二から先は年をとらないっていうの?」
「いやあ、二十五からだね」
「そんなこと言ってるから、いい男が、こんなとこのパートで食いつなぐハメになるのよ」
へへっ、と青柳は笑う。青白い顔に大きな目が潤むように光っている。細面の顔に鼻筋の通った青柳は、今でこそ頰に縦皺が寄っているが、若い頃はかなりの美青年だったにちがいないという。それが災いしたものかどうか知らないが、同棲を繰り返して結婚したことはない。以前勤めていた小さな輸入品販売会社を辞めたのも、社長の囲っていたインドネシア人ダンサーに手を出したからだという、もっぱらの噂だ。
青柳は処理を終えたカルテを無造作に揃えると、キャビネットに突っ込む。
「ほら、カルテをしまったら、ちゃんと鍵をかけて」
房代は注意する。計算間違いも多いが、この男は始終鍵をかけ忘れる。
「へい、へい。看護師さんは偉いですよ。一晩で二万五千円になるんだから。あたしら事務屋は時給千五百円だ」
「くだらないこと言ってないで、さっさと仕事終わらせたらいいでしょうに」
「あんまり早く帰ると、別の仕事があるんですよ。何せ、あたしはヒモですからね」
あまりに真に迫った言い方で、房代は思わず苦笑した。
青柳の現在の同棲相手は、ラブホテルの女性経営者だ。噂によると色黒の体重九十キロはあろうかという五十女だそうだ。青柳の自宅は一応市内にあるが、彼がそこにいたためしはない。昼間は女の経営するラブホテルのフロントにいるらしいが、そのラブホテルがどこなのか青柳は決して他人には教えない。緊急時に連絡できないので、所在をはっきりさせるように、と小西に再三言われても、にやにやするばかりである。
レジの金の勘定がまだ終わっていない青柳に「お先に」と声をかけて、房代は部屋を出た。
深夜だというのに、外はまだむっとするほど暑い。ミニサイクルで漕ぎだすと、ジョーゼットのブラウスの下で、胸や背中が汗でびっしょり濡れた。
旭診療所の鵜川医師は、その頃まだ診療室で学会誌に目を通していた。白いTシャツに作業ズボン姿の鵜川日出臣は、小柄なせいもあって四十五という歳には見えない。必要以外のときは白衣を着ない、という方針は、十五年前に大学病院を追い出されて以来、貫いている。鵜川にとって白衣をぬぐというのは、医師としての権威をぬぐということであり、それがすなわち彼の生き方であった。
時計をちらりと眺めてから、再びページに視線を落とす。いつものようにワクチンの副反応に関する情報を探しているのではない。
彼の頭には、一時間前に診た患者のことがひっかかっている。
高熱を出して妻に付き添われてきた男は、さかんに片手で目を覆う仕草をしながら言った。
「頭が、割れるように痛いんですよ、先生」
男は、診療所のすぐ裏手にある不動産屋の主人だった。普段は鵜川の所を「アカのやっている診療所」と呼んで、少し離れた医院に行っていたが、深夜のことでそこでは診てもらえなかったらしい。
聴診器を取り出すと、男の妻は、夫の派手な緑色をしたゴルフシャツをまくり上げるのに手を貸した。とたんに男はぼそりと言った。
「香水、変えたな。おまえ」
「何、言ってるんですよ」
妻は素っ気なく答える。
「甘ったるい匂い、ぷんぷんさせて。男でもできたか?」
「さっきから、変なことばかり言って」
下らない冗談につきあってはいられない、と言わんばかりに、妻は白髪の目立つ髪をかき上げる。香水どころか、その顔には口紅もついていない。
熱い息に少しあえいで、不動産屋は鵜川に言った。
「注射、やって下さいよ、先生。一発で効くやつを。あした、朝からでかい仕事が入ってるんですよ」
鵜川は苦笑しながら、聴診器を手にする。注射、というのを、鵜川は滅多に打たない。風邪程度なら、寝ていれば治る。必要外の薬剤を体に入れることは、本来、体が備えている防衛機能を損なう。特に静脈注射の激烈な効果は、いくつもの危険と引き換えだ。そうしてまで仕事をしようとする人々の生き方に、鵜川は疑問を投げかけてきた。彼が、地元の医師会から、色つきとみなされ排除される原因はここにもある。
つぎに鵜川は患者の喉を診ようと明かりを男の顔に近付けた。そのとたん、男は悲鳴を上げて椅子から転げ落ちた。
「勘弁してください、先生。目を焼かれるみたいです」
両手で顔を覆って男は
鵜川は尋常でないものを感じた。何かの理由で瞳孔が開いているのか、それとも脳のどこかに異常があるのか。冗談かどうかわからないが、ありもしない香水の匂いがする、とも言った。
いずれにせよ、自分の所には手に負えないと判断して、病院への紹介状を書く。昭川市内の医院はたいてい富士大学病院を紹介する。市内で唯一、設備の整った大病院だからだ。が、鵜川はあえてそこを避けた。
富士病院に限らず多くの大学病院の体質は、より人間らしい医療を、という鵜川の持論に反するからだ。彼は迷うことなく隣市の
男は注射一本で、どうにかなると思っていたらしい。紹介状を渡され少し戸惑い、不満そうな顔で出ていった。鵜川はその後ろ姿を見ているうちにふと気になって学会誌をめくってみたが、参考になるような記事はない。短い息を吐き出して、鵜川は地肌が透けて見えそうに短いクルーカットの頭を叩いた。
その翌日、やはり患者の尋常でない症状に気づいた医師が、市内に一人いた。
市の郊外にある内科病院、「若葉台クリニック」に、一人の患者がやってきた。谷を隔てた窪山地区からやってきた男は、家族の話によれば、前日昭川市の夜間診療所で熱中症と診断されたと言う。ここに連れてこられたときは、痙攣を起こしかけていた。顔色は蒼白でひどい熱だ。首筋に手を当ててみると板のように堅く、体は反り返っている。
もちろん症状がひどいこともあったが、七十歳間近の院長は、市内の多くの開業医のように、風邪や熱中症でかたづけることはしなかった。
「ちょっと髄液を取っておこうか」
家族にそう言いながら、
点滴によって痙攣の収まった患者のズボンを下ろす。ベッドの上で腰を曲げさせ、キシロカインを注射した後、腰椎の突起を確認して針を刺す。初老の患者は、呻き声を上げた。
「ちょっとがまんしててよ」と院長は、声をかけた。注射器の中を上がってくる液は、本来、水のように透明でなければならなかったが、このとき肉眼で見てもわかるほどの濁りがあった。
かなり進んでいる、と院長は判断した。患者が両手で頭を押さえ、体を海老のように曲げたのと針を抜いたのは、ほとんど同時だった。患者が激しい勢いでその場に嘔吐し、ベッドから転げ落ちそうになったのを看護師が辛うじて支えた。
しまった、と院長は青ざめた。急いで応急処置の準備をする。だがすでに容体は急変していた。そして針を抜いてから数分後に心臓は停止した。
老医師の判断自体に間違いはなかった。またその手順にも、穿刺方法にも誤りはなかった。しかしタイミングと患者の運が悪すぎた。めったに起きない事故が起きてしまったのだ。
炎症により頭蓋の中でむくみ、異常に圧力を上げていた脳は、腰に針を刺され髄液を抜き取られた刺激によって、その機能をいっぺんに止めてしまったのである。
少なくとも若葉台クリニックの院長は、この時点では重大な過失を犯してはいない。しかし結果は無惨なものになった。
事実が知れたら一悶着起きることは間違いない。「運が悪かった」は、突然に家族を失った人々には通用しない。たとえ裁判を起こされたりしなくても、若葉台クリニックのような個人病院の場合、医療過誤を疑われるトラブルは致命的だ。
うろたえる家族に、院長は事実と異なる説明をした。茫然としたまま、男の妻と長男は医師の言葉を受け入れた。そして老医師は異なる病名の死亡診断書を書き、採取した髄液を廃棄した。
(第5回へつづく)
▼篠田節子『夏の災厄』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321411000060/