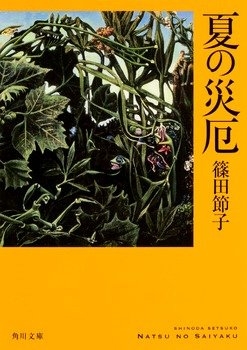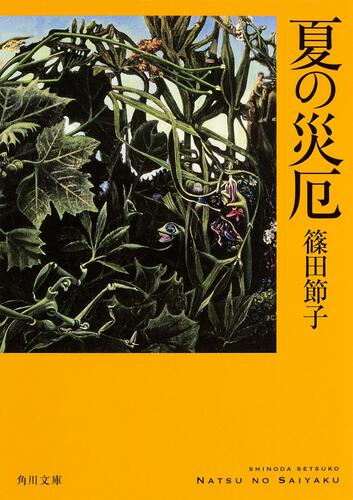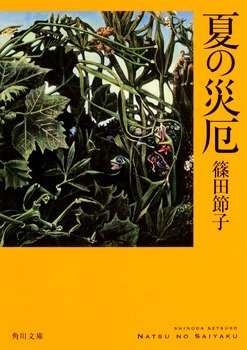コロナウイルスの脅威は未だ収まる兆しを見せません。この未曽有の危機に立ち向かうにはどうすればよいのか――。いまから25年前に発表された篠田節子さんの『夏の災厄』は、未知の感染症をテーマにしたパンデミック・ミステリです。前例の無い事態に後手に回る行政、買い占めに走る住民たち、広がる混乱と疑心暗鬼……。今日の状況を予見しただけでなく、この災厄を乗り越えるためのヒントも提示する本作の、冒頭部分を6回に分けて公開します!
【関連記事】海堂尊さんによる解説を特別公開!▷「本書はパンデミックが蔓延しつつある現代社会における予言書的な寓話だ!」※リンクはページ下部「おすすめ記事」にもあります。
◆ ◆ ◆
プロローグ
1989年 インドネシア ブンギ島
バンダ海は、インドネシア東部、北はセラム、西はフロレス、南はティモールの各海に接して広がる、約七万三八○○平方キロメートルの海域である。北部のブル、セラム両島の東から南に連なり、タニンバルなどの島々に
そのバンダ海のほぼ中心部、バンダ諸島の最南端に、群青色の海面をつきやぶるようにして、天に向かって
火山島、ブンギである。
帝国主義時代のオランダの地図に、香辛料の産地としてかろうじてその名を
ブンギ島の周囲は五キロメートル、伊豆諸島の
オランダ統治時代は、島の中央にそびえる休火山の中程までナツメグの木が植えられ、島民は白人の差し向けた土地管理人の下で、奴隷としてその栽培に携わっていたが、現在その木々は打ち捨てられ、人々は海に戻って、遠い昔から行なってきた丸木舟による漁で生計を立てている。いや、これもまた「いた」と過去形で語るべきであろう。島の人口は、約四百人だった。半年ほど前までは。
女は、ふらつく体を起こすと足元の桶を手にした。
水を汲みにいかなければならない。かたわらの赤ん坊は静かだ。昨夜までひどく泣いていたが、だんだんその泣き声もかすれ、明け方には
女の名は、プスパという。十四で村の男と結婚し、十六で最初の子を産み、二十二になったこの年、夫を失い、上の子供たちと別れ、七カ月前に生まれた末の子と二人きりになった。
竹で編んだ扉を開けたとたん、プスパは両手で
プスパは片手で目を押さえたまま、空いた手で桶を拾うとよろよろと砂の上に下りた。
ブンギは水が貧しい。島民はそれぞれの家の貯水タンクに雨水を溜め、そこから竹の
アーモンドの木をくりぬいた舟が、乗り手もなく家々のしっくいの壁に立て掛けられている。木は芯まで乾ききって、ひび割れる寸前だ。
プスパは這うようにして、家の裏手に回る。わずか数メートルの距離が、隣の島に渡るほどに遠い。それでも生き残っている唯一の家族、赤ん坊と自分のために、水を汲んでこなければならない。
閉めきった家々の戸口から、鼻をつく臭気が漏れてくる。どこの家にも
プスパも照りつける太陽の下、片手に桶を抱え、片手でしっかりと目を押さえながら歩みを進める。
照りつける太陽の光が
きつく目を閉じて歩いていくと爪先に何かが当たった。衰弱した体では姿勢を立て直すこともできず、膝から崩れるように倒れた。桶でしたたかに胸を打ち、しばらく息ができなかった。うずくまったままプスパは、両手で目を覆っていた。
炎天下を死神が
家の裏手の貯水タンクにようやくたどりつき、プスパは桶を持ち上げたまま、立ちすくんだ。桶のふちに体をひっかけ、頭をタンクにつっこんでいる者がいた。隣の家の少年だ。
肩に手をかけ、揺する。気温が高いせいで、少年の皮膚は温かい。しかしその体はぴくりとも動かない。水を汲みにここまできて絶命したのだ。
死体を
風向きが変わった。薄い煙が流れてきて少しむせる。集落の端では、このところ毎日煙が上がる。少し前までは夕方に限られていたが、いまは四六時中だ。村人は、死体をそのまま村の背後の丘に埋めることはしない。
まともに動ける者がほとんどいなくなった今でも、人々は自らの体を引きずるようにして木々を拾い集め、先に逝った者の体を焼く。家族を焼きながら自分も絶命し、焼けた死体の傍らに新しい死体が転がる。
ちょうど五年前から、この島を訪れるようになった医師たちが、病死体は必ず焼くように、と教えていった。医師たちは、インドネシア人ではなかった。デンパサールから双発機と貨物船とモーターボートを乗り継ぎ、一昼夜もかけてこの島にやってくる、色白の何かわからない言葉を話す東洋人だった。
彼らは島民の病気を
雨水は煮沸して飲むこと、死体は焼いてから埋めること、ある種の病人のそばには妊婦や幼い子供を近づけてはならないこと、体の具合が悪くなるのは、決してだれかの
プスパはあの医師たちを待っていた。赤ん坊はまだ息がある。沖合から響いてくる鈍いエンジン音を待ち焦がれていた。
医師たちは、丸一日かけて島民の一人一人の健康状態をチェックし、子供たちの一人残らずに予防接種をし、甘い菓子やミルクまで与えて帰っていった。
それだけではない。瀕死の状態になった者を魔法のように生き返らせる薬も持っていた。
しかし昨年の今頃、頻繁にやってきた彼らは、この二カ月間、来ない。島民が一番必要としているこのとき、彼らの乗った船が沖合に姿を現すことはなくなった。
奇妙な病気が島内に流行し始めた半年ほど前、医師たちは様々な器材を持ち込み、村人を検査し治療した。その頃はまだ生きていた夫や上の子供たちとともに、プスパも血や尿を採取され、喉の粘膜をこすりとられ、驚くほど多量の薬を与えられた。
体を反り返らせ
島民の大半が病気に冒され、医者の来る日を痛切に待ち暮らすようになるに従い、彼らがやってくる周期は長くなった。いつかプスパはその理由を尋ねたことがある。夫を失ったばかりの頃だ。医師たちは同様の病気が国の全域に発生し、手が回らないのだ、と答えた。
しかし唯一の救いがあった。子供たちだけは病気にかかっても必ずしも死なないのだ。数年前から始めた予防接種の効果だ。島民はあらためて、医師たちに感謝した。
そして二カ月前、医師たちは、州の役人を伴っていつになく大きな船でやってきて人々に言った。まだ元気な子供たちだけでも首都の病院に移したいと。
異議を唱える者はいなかった。そしてプスパは上の男の子二人と別れた。この病気の流行が収まるまでの数カ月間を生き延びることができれば、また会える。医師たちや役人はそう言い、プスパもその言葉に
百人ほどの子供を連れた船が出ていった直後、船着場脇のコンクリートの防波堤が、
空を揺るがすばかりの音を最後に、島はひっそりと静まりかえった。子供たちの甲高い声は消え、鳥の声も聞かれなくなった。
このときになって島民は、この奇病が
それでもプスパは濃緑色の葉の間に、死んだ鳥の赤い羽色を見たことは覚えている。ずいぶん鳥が死ぬものだ、と不思議に思った。あれがこの事態の前兆であったのだろう。森の神々の怒りかもしれない、と多くの島民は考えた。それから神々をなだめるいくつかの儀式が行なわれたが、いっこうに効き目はなかった。
百人近く生き残っていた島民は、ゆっくりと、しかし確実に数を減らしていった。
プスパは手桶を引きずり、家の近くまできた。目を堅く閉じ手探りで扉を探す。そのとたん爪先に何かが引っかかった。そのまま頭から砂につっこむようにして、その場に倒れた。桶がひっくり返り、濁った水がプスパのTシャツを濡らして、砂に吸い込まれていく。すでに起き上がる力は残っていない。目を覆うこともできずに、プスパはかすかな吐息を洩らした。ゆっくりと瞼が開いていった。もはや眩しさを感じることもなくなった眼球はたちまち熱い風に乾き、数匹の蠅が寄ってきた。
島の人口はゼロになった……。
(第2回へつづく)
▼篠田節子『夏の災厄』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321411000060/