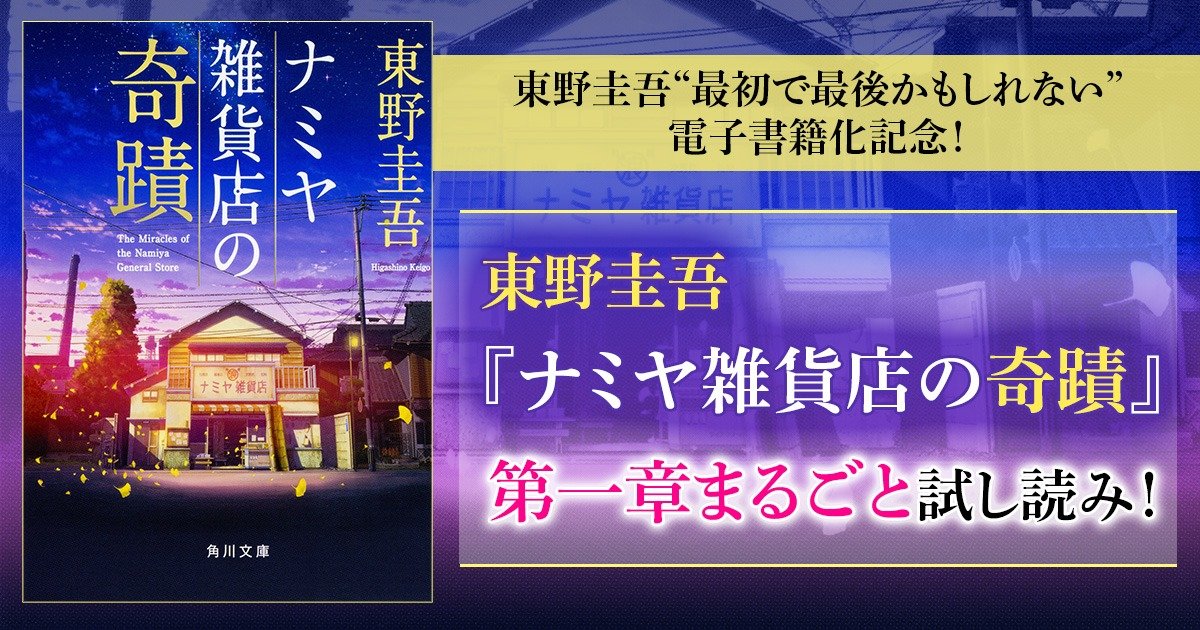これまで著書の電子化をしてこなかった東野圭吾氏が、ついに電子書籍の配信をスタートすることになりました。それに合わせてカドブンでは、記録的ベストセラーとなった『ナミヤ雑貨店の奇蹟』の第一章をまるごと試し読み公開します!
>>前話を読む
◆ ◆ ◆
何が、と敦也は
「だって、テレビ電話があればいいのにって書いてある。この人、ケータイを持ってないのかな。それともテレビ電話の機能が付いてないのかな」
「病院内じゃケータイを使えないってことだろ」翔太が答えた。
「でも、マンガなどに出てくる、とも書いてる。この人きっと、テレビ電話機能の付いたケータイがあるってことを知らないんだよ」
「まさか。ありえねえよ、今時」
「いや、きっとそうなんだと思う。よし、教えてやろう」幸平は、台所でテーブルに向かった。
「おい、なんだよ。また返事を書く気か。からかわれてるだけなんだぞ」敦也はいった。
「でも、そんなのまだわかんないし」
「からかわれてるに決まってる。このやりとりも聞かれてて、今頃は先回りして手紙を書いてるさ。──いや、待てよ」敦也の頭に
「何だよ、急に。どうしたんだ」翔太が訊く。
「いいんだよ。すぐにわかる」
やがて、書けた、といって幸平がボールペンを置いた。敦也は横に立ち、
『二つめの手紙をよみました。いいことをおしえてあげます。テレビ電話ができるケータイがあります。どこのメーカーでもあります。病院にばれないように、こっそりつかえばいいと思います。』
「こんな感じでどうかな」幸平が訊いてきた。
「いいんじゃないか」敦也はいった。「何でもいいよ。さっさと封筒に入れろ」
二通目の手紙にも『月のウサギ』宛ての封筒が同封されていた。幸平は自分の書いた手紙を折り畳み、そこへ入れた。
「俺も一緒に行く。翔太は、ここにいろ」敦也は懐中電灯を持って、裏口に向かった。
外に出ると、幸平が牛乳箱に手紙を入れるのを見届けた。
「よし、幸平はどこかに隠れて、この箱を見張ってるんだ」
「わかった。敦也は?」
「表に回る。どんなやつが手紙を入れるのか、見届けてやる」
家の脇を通り、物陰から表の様子を
しばらくそうしていると、背後から人の気配がした。振り返ると、翔太が近づいてくるところだった。
「何だよ。家の中にいろっていっただろ」敦也はいった。
「誰か、現れた?」
「まだ来ねえよ。だから、こうしてるんだろうが」
すると翔太は途方に暮れたような顔になった。口は半開きだ。
「なんだよ。どうしたんだ」
そう尋ねた敦也の顔の前に、翔太は封筒を出してきた。「来たんだ」
「何が?」
だから、といって唇を
4
『再度の御回答ありがとうございます。悩みをわかってくださる方がいるというだけでも、少し気が楽になります。
ただ本当に申し訳ないのですが、今回の御回答については、ナミヤさんの意図が今ひとつ、といいますか、正直なところ全く理解できておりません。
おそらく私の不勉強、教養のなさが原因なのだろうと思います。そのせいで、せっかくナミヤさんが私を励まそうと思って書かれたジョークが理解できないのでしょう。誠にお恥ずかしいかぎりです。
よく母は私に、「わからないことがあるからといって、すぐに人に教えてもらおうとしてはだめだ。まずは自分できちんと調べなさい」といいます。それで私も、なるべく自分で調べるように努力しています。でも今回は、どうしてもわかりませんでした。
ケータイとは何のことでしょうか。
カタカナでお書きになっていることから、外来語ではないかと思って調べたのですが、見つかりませんでした。英語ならば、つづりは「catie」あるいは「katy」あたりかと類推しましたが、違うようです。英語ではないのでしょうか。
この「ケータイ」の意味がわからないかぎり、ナミヤさんの貴重なお言葉も、私にはまさに「馬の耳に念仏」、「猫に小判」でしかありません。どうかお教えいただけますと助かります。
お忙しいのに、こんなことに付き合わせて、本当にごめんなさい。
月のウサギ』
『月のウサギ』からの三通の手紙をテーブルに並べ、それを囲むように三人は椅子に座った。
「整理しよう」翔太が口を開いた。「今回も牛乳箱に入れた幸平の手紙は消えていた。幸平は物陰からずっと見張ってたけど、牛乳箱に近づいた者はいなかった。一方、敦也は店の前を見張ってた。誰もシャッターには近づいていない。だけど三通目の手紙が放り込まれた。ここまでの話で、何か事実と違ってることはあるかな」
ねえよ、と敦也は短く答えた。幸平は黙って
「つまり」翔太は人差し指を立てた。「この家には誰も近づいてないのに、幸平の手紙は消えて、ウサギさんからの手紙は届いた。牛乳箱もシャッターも、じっくり調べたけど何の仕掛けもなかった。これはどういうことだと思う?」
敦也は背もたれに体重を預け、頭の後ろで両手の指を組んだ。
「それがわからねえから、こうして悩んでるんじゃないか」
「幸平はどう?」
幸平は丸い頰を振った。「わかんない」
「翔太、おまえ、何かわかってんのかよ」
敦也が訊くと翔太は三通の手紙を見下ろした。
「変だと思わないか。この人、ケータイのことを知らないんだぜ。外来語だと思ってる」
「ふざけてるだけだろ」
「そうかな」
「そうだよ。今時、ケータイのことを知らない日本人なんていねえよ」
すると翔太は一通目の手紙を指した。
「じゃあ、これはどう? 来年のオリンピックって書いてあるよな。でも、よくよく考えてみたら、来年は冬も夏もオリンピックなんてないぜ。この間、ロンドンオリンピックが終わったばかりだ」
あっ、と敦也は思わず声を漏らした。それをごまかすために、顔をしかめ、鼻の下を擦った。「勘違いしたんだろ、きっと」
「そうかな。そんなことを間違うかな。自分が目指してる大会だぜ。テレビ電話の存在も知らないみたいだし、少しズレすぎてると思わないか」
「それは思うけど……」
「それ以外に、もう一つあるんだ」翔太は声をひそめた。「すごくおかしいことが。俺、さっき外にいる時に気づいた」
「何だ、一体」
翔太は一瞬
「敦也のケータイ、今、何時になってる?」
「ケータイ?」ポケットから取り出し、表示を確認した。「午前三時四十分だ」
「うん。つまり、ここへ来てから一時間以上は経ってる」
「そうだな。それがどうかしたのか」
「うん、まあ、ついてきてよ」翔太が立ち上がった。
再び裏口から外に出た。翔太は隣の倉庫との隙間に立ち、夜空を見上げた。
「最初にここを通った時、月が真上にあることに気づいた」
「俺も気づいてたよ。それがどうかしたか」
翔太は、じっと敦也の顔を見つめてきた。
「変だと思わない? 一時間以上も経ってるのに、月の位置が
翔太が何のことをいっているのかわからず、一瞬当惑した。だがすぐに意味を理解した。心臓が大きく跳ねた。顔は熱くなり、背筋には冷たいものが走った。
携帯電話を取り出した。時刻は午前三時四十二分を示している。
「一体どういうことだ。どうして月は動いてないんだ」
「今は、月があまり動かない季節だとか」
幸平の意見を、「そんな季節、ねえよ」と翔太が
敦也は自分の携帯電話と夜空の月とを交互に見た。何が起きているのか、さっぱりわからなかった。
そうだ、と翔太が携帯電話の操作を始めた。どこかに電話をかけているらしい。
その顔が
「どうしたんだ。どこにかけてるんだ」敦也は
翔太は黙ったままで携帯電話を差し出した。聞いてみろ、ということらしい。
敦也は電話を耳につけた。飛び込んできたのは、女性の声だった。
「午前、二時、三十六分、ちょうどを、お知らせします」
三人は家の中に戻った。
「ケータイが壊れてるわけじゃない」翔太はいった。「この家がおかしいんだ」
「ケータイの時計を狂わせる何かがあるってことか?」
敦也の問いに翔太は頷かなかった。
「ケータイの時計は狂ってないと思う。ふつうに動いている。でもその表示は、実際の時刻とは違っている」
敦也は
「この家の中と外では、時間的に隔絶されてるんじゃないかと思う。時間の流れ方が違うんだ。ここでの長い時間も、外ではほんの一瞬でしかない」
「はあ? おまえ、何をいってんの」
翔太は再び手紙に目を落としてから、敦也を見た。
「この家には誰も近づいてないはずなのに、幸平の手紙は消えて、ウサギさんからの手紙は届く。本来、そんなことはありえないはずだ。じゃあ、こう考えてみたらどうだろう。誰かが幸平の手紙を持ち去り、それを読んでから、次の手紙を持ってきている。ところがその誰かの姿が俺たちには見えない」
「見えない? 透明人間かよ」敦也はいった。
「あっ、わかった。幽霊の仕業だ。えっ、ここ、そんなのが出るのか」幸平が身体を縮めて周囲を見回した。
翔太はゆっくりとかぶりを振った。
「透明人間でも幽霊でもない。その誰かは、この世界の人間じゃないんだ」三通の手紙を指して続けた。「過去の人なんだよ」
「過去? 何だよ、それ?」敦也は声を
「俺の説はこう。シャッターの郵便投入口と牛乳箱は、過去と
ウサギさんは過去の人なんだ、と翔太は締めくくった。
敦也は、すぐには声を出せなかった。何をいえばいいかわからなかったからだ。考えることを脳が拒否している。
「まさか」ようやく、そういった。「そんなこと、あるわけねえよ」
「俺もそう思うよ。だけど、それ以外には考えられない。違うというなら、敦也が別の説明を考えてよ。筋の通った説明をさ」
翔太にいわれ、敦也は返答に窮した。無論、筋の通った説明などできない。
「おまえが返事なんか書くから、話がややこしくなっちまったじゃないか」半ば八つ当たりで幸平にいった。
「ごめん……」
「幸平を責めなくたっていいだろ。それに、もし俺の説が当たっているなら、これはすごいことだぜ。俺たち、過去の人間と手紙のやりとりをしてるってことになる」翔太は目を輝かせた。
敦也は混乱していた。何をどうすればいいのかわからなくなった。
「出よう」そういって立ち上がった。「こんなところ、出ていこう」
驚いたように二人は彼を見上げた。どうして、と翔太が訊いた。
「だって、気味が悪いじゃねえか。面倒臭いことになったら厄介だ。出よう。身を潜める場所なら、ほかにいくらでもある。この家にいくら長くいても、実際の時間は殆ど止まったままなんだろ。ずっと朝が来ないんじゃ、潜伏してる意味がない」
しかし二人は同意してくれなかった。どちらも浮かない顔で黙り込んでいる。
「どうしたんだ。なんとかいえよっ」敦也は怒鳴った。
翔太が顔を上げた。その目には真剣な光が宿っている。
「俺は、もう少しここにいる」
「はあ? 何のために?」
翔太は首を
「何のためかは自分でもよくわからない。でも、今自分がすごい経験をしてるってことはわかる。こんなチャンスはめったに……いや、たぶんもう一生来ない。だからこのチャンスを無駄にしたくない。敦也は出ていけばいいよ。だけど俺は、もうしばらくここにいる」
「こんなところにいて、どうする気だ」
翔太はテーブルに並べた手紙を見た。
「とりあえず、手紙を書く。過去の人とやりとりできるなんてすごいことだから」
「うん、そうだ」幸平も
敦也は二人を見ながら少し後ずさりし、大きく首を振った。
「おまえら、おかしいよ。何を考えてるんだ。昔の人間と文通して、何が楽しい? やめろやめろ。おかしなことに巻き込まれたらどうするんだ。俺は関わり合いになりたくない」
「だから、敦也は出ていけばいいといってるじゃないか」翔太が表情を和ませていった。
敦也は大きく息を吸った。反論しようと思ったが、言葉が出ない。
「勝手にしろ。何があっても知らないからな」
(つづく)
あらすじ
悪事を働いた3人が逃げ込んだ古い家。そこはかつて悩み相談を請け負っていた雑貨店だった。廃業しているはずの店内に、突然シャッターの郵便口から悩み相談の手紙が落ちてきた。時空を超えて過去から投函されたのか? 3人は戸惑いながらも当時の店主に代わって返事を書くが……。悩める人々を救ってきた雑貨店は、再び奇蹟を起こせるか!?
著者 東野圭吾(ひがしの けいご)
1958年、大阪府生まれ。大阪府立大学電気工学科卒業後、生産技術エンジニアとして会社勤めの傍ら、ミステリーを執筆。1985年『放課後』(講談社)で第31回江戸川乱歩賞を受賞、専業作家に。1999年『秘密』(文藝春秋)で第52回日本推理作家協会賞、2006年『容疑者χの献身』(文藝春秋)で第134回直木賞、第6回本格ミステリ大賞、2012年『ナミヤ雑貨店の奇蹟』(KADOKAWA)で第7回中央公論文芸賞、2013年『夢幻花』(PHP研究所)で第26回柴田錬三郎賞、2014年『祈りの幕が下りる時』(講談社)で第48回吉川英治文学賞、さらに国内外の出版文化への貢献を評価され第1回野間出版文化賞を受賞。
書誌情報
発売日:2014年11月22日
定価:本体680円+税
体裁:文庫版
頁数:416頁
発行:株式会社KADOKAWA
公式書誌ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/321308000162/