東野圭吾『ナミヤ雑貨店の奇蹟』
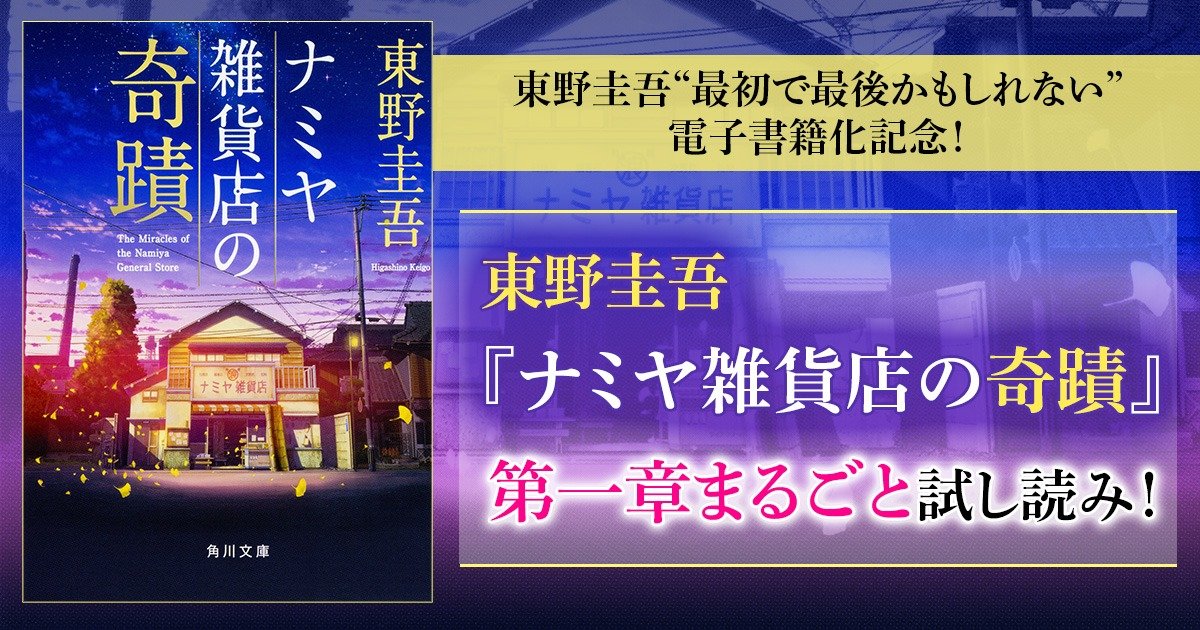
全世界累計1300万部突破のベストセラーが読めるのはここだけ! 東野圭吾“最初で最後かもしれない”電子書籍化記念!『ナミヤ雑貨店の奇蹟』第一章「回答は牛乳箱に」試し読み#3
これまで著書の電子化をしてこなかった東野圭吾氏が、ついに電子書籍の配信をスタートすることになりました。それに合わせてカドブンでは、記録的ベストセラーとなった『ナミヤ雑貨店の奇蹟』の第一章をまるごと試し読み公開します!
>>前話を読む
◆ ◆ ◆
「誰を?」翔太が訊く。
「恋人。病気の。彼女の合宿や遠征先とかへ連れていけたら、ずっと一緒にいたままで、彼女は練習できるし試合にも出られる」
「いやあ、それは無理だろう。病人なんだぜ。しかもあと半年の命っていう」
「でも動けないかどうかはわからないよ。車椅子での移動ならできるとか、そういうレベルだったら、連れていけるんじゃないの?」
「もしそれができるんなら、こんなふうに相談してこねえよ。たぶん寝たきりで、動かすわけにはいかないんだ」
「そうなのかなあ」
「そうなんだよ、たぶん」
おい、と敦也は声をかけた。
「いつまでくだらねえことをしゃべってるんだ。ほっとけっていってるだろ」
二人は気まずそうに口をつぐみ、
「敦也のいってることはわかるんだけど、なんか放っておけなくてさ。だってこのウサギさん、かなり本気で悩んでるみたいだぜ。どうにかしてやりたいじゃないか」
敦也は、ふんと鼻を鳴らし、身体を起こした。
「どうにかしてやりたい? 笑わせるなよ。俺たちみたいな者に何ができる? 金はない、学歴はない、コネもない。俺たちにできることといえば、けちな空き巣狙いぐらいだ。それにしたって、ちっとも計画通りに運ばない。何とか金目のものを奪ったと思ったら、逃走用の車が故障ときてる。だからこんなところで
敦也がまくしたてると、翔太は首をすくめるように
「とにかく、さっさと寝ろ。朝になったら、通勤客が動きだす。それに紛れて逃げるんだ」そういうと敦也は再び横になった。
ようやく翔太が障子紙を敷き始めた。しかしその動きは遅い。
なあ、と幸平が
「何かって?」翔太が訊く。
「だから、返事をだよ。このままだと、なんか気になって……」
「馬鹿か、おまえは」敦也はいった。「そんなことを気にしてどうすんだよ」
「でもさあ、何か書いてやるだけでも、ずいぶん違うと思うんだよね。話を聞いてくれただけでもありがたいってこと、よくあるじゃないか。この人はさ、誰にも悩みを打ち明けられずに苦しんでるんだよ。大したアドバイスはできなくても、あなたの悩みはよくわかりました、がんばってくださいって答えてやったら、きっと少しは気持ちが楽になるんじゃないかな」
けっ、と敦也は吐き捨てた。「だったら、好きにしろよ。どんだけ馬鹿なんだ」
幸平は立ち上がった。「何か書くものないかな」
「文房具があったみたいだぞ」
翔太と幸平は店に出ていくと、しばらくごそごそしてから戻ってきた。
「書くもの、あったのか」敦也は訊いた。
「うん。サインペンは、どれも書けなくなってたけど、ボールペンは書けた。あと、
「おまえ、今いってたじゃないか。あなたの悩みはよくわかりました、がんばってくださいって。そう書けばいいだろ」敦也はいった。
「いやあ、それだけだとちょっと素っ気なくないかな」
敦也は、ちっと舌を鳴らした。「勝手にしろ」
「さっきのはどうよ。彼氏も一緒に連れていったらどうだっていう案」翔太がいった。
「それができるんなら、こんなふうに相談してこないだろうっていったのは、翔太じゃないか」
「さっきはそういったけど、一応確かめてみたらどうかなと思ったんだ」
幸平は迷い顔を敦也に向けてきた。「どう思う?」
知らねえよ、と敦也は横を向いた。
幸平はボールペンを手にした。だが書き始める前に、また敦也たちのほうを見た。
「手紙の出だしって、どんなふうに書くんだっけ?」
「ああ、なんかあったな。拝啓とか前略とか」翔太がいった。「でも、別にいらないだろ、そんなのは。この相談の手紙だって、何も書いてないし。メールのつもりで書けばいいんだよ」
「あっ、そうか。メールだと思えばいいんだ。えーと、メールじゃなくて、手紙読みました、か。て、が、み、よ、み、ま、し、た……と」
「声出さなくていいよ」翔太が注意した。
幸平が文字を書く音が、敦也の耳にも伝わってきた。かなり筆圧が強いようだ。
しばらくして、できた、といって幸平が便箋を持ってやってきた。
翔太がそれを受け取った。「
敦也も横から
『手紙よみました。たいへんですね。あなたのなやみはよくわかりました。ひとつおもいついたのですが、あなたのいくところへカレもつれていけばいいのじゃないですか。あまりいいアイデアを出せずにすみません。』
「どう?」幸平が
「まあ、いいんじゃないの」翔太が答え、なあ、と敦也に同意を求めてきた。
どうでもいいよ、と敦也はいった。
幸平は便箋を丁寧に畳むと、同封されていた『月のウサギ』宛ての封筒に入れた。「箱に入れてこよう」そういって裏口から出ていった。
敦也は、ため息をついた。
「全く、何を考えてやがるんだ。見ず知らずの他人の相談に乗ってる場合かよ。翔太まで一緒になって、何をやってるんだ」
「そういうなよ。たまにはいいじゃないか」
「何だよ、たまにはって」
「だってさ、ふつうなら俺たちが誰かの悩みを聞くなんてことないだろ。俺たちになんか、誰も相談しようとしない。たぶん一生ないぜ。これが最初で最後だ。だから一回ぐらいいいじゃないかってこと」
ふん、と敦也はまた鼻を鳴らした。「そういうのを身の程知らずっていうんだ」
幸平が戻ってきた。
「牛乳箱の
「そりゃそうだろ。今時、牛乳配達なんて──」ない、といいかけたところで敦也は言葉を切った。「おい、幸平。おまえ、手袋はどうした」
「手袋? それならここにあるよ」テーブルの上を指した。
「おまえ、いつの間に外したんだ」
「手紙を書く時。だって、手袋を
「馬鹿野郎っ」敦也は立ち上がった。「便箋に指紋が付いたかもしれないだろ」
「指紋? 何かまずかった?」
とぼけた顔で訊く幸平の丸い頰を、敦也は引っぱたきたくなった。
「いずれ警察は、俺たちがここに潜んでたことに気づく。もし牛乳箱の返事を、『月のウサギ』とかいう女が回収しなかったらどうなる。指紋を調べられて、一発でアウトだ。おまえ、交通違反で指紋を採られたことがあるだろ」
「あ……たしかに」
「ちっ、だから余計なことをするなといってるのに」敦也は懐中電灯を
牛乳箱の蓋はぴったりと閉じられている。幸平がいうように、たしかに固い。それでも力ずくで開けた。
敦也は中を懐中電灯で照らした。ところが何も入っていない。
裏口の扉を開け、中に向かって問いかけた。「おい、幸平。おまえ、どこに入れたんだ」
幸平が手袋を嵌めながら出てきた。
「どこって、そこの牛乳箱」
「入ってねえぞ」
「えっ、そんなはずは……」
「入れたつもりが、落っことしたんじゃねえか」敦也は懐中電灯で地面を照らした。
「絶対にそんなことないよ。たしかに入れたって」
「じゃあ、どこへ消えたんだ」
さあ、と幸平が首を
「なんだ、どうした」敦也が訊いた。
「店のほうで物音がしたから様子を見に行ったら、郵便用の小窓の下にこれが落ちてた」翔太が青ざめた表情で差し出したのは、一通の封筒だった。
敦也は息を
しかし──。
そこに人影はなかった。誰かが立ち去った気配もなかった。
3
『早速の御回答ありがとうございます。昨夜、おたくのポストに手紙を
ナミヤさんの疑問はもっともです。私も、できることなら、彼を遠征先や合宿先に連れていきたいです。でも彼の病状を考えますと、それは不可能です。病院でしっかりとした治療を受け続けているから、まだ病気の進行を遅らせられているのです。
それならば私が彼の近くで練習すればいいのではと思われるかもしれません。ところが彼が入院している病院のそばには、私が練習できるような場所も設備もないのです。練習が休みの日だけ、長い時間をかけて会いに行っているというのが現状です。
こうしている間にも、次の強化合宿への出発日が近づいてきます。今日、彼の顔を見てきました。しっかりと結果を出してきてくれといわれ、はい、とうなずいてしまいました。本当は、行きたくない、あなたのそばにいたいといいたいのですが、ぐっと我慢しました。そんなふうにいえば、彼が
離れていても、せめて顔だけでも見られたらと思います。マンガなどに出てくる、テレビ電話があればいいのにと夢想したりします。現実逃避ですね。
ナミヤさん、私の悩みに付き合ってくださり、本当にありがとうございます。こうして手紙で打ち明けているだけでも、幾分心が楽になります。
答えは自分で出さねばならないと思いますが、何か思いついたことがあれば、お返事ください。逆に、もう何もアドバイスできることはないと思われるのなら、そのように書いてください。御迷惑はおかけしたくありませんので。
いずれにせよ、
よろしくお願いいたします。
月のウサギ』
最後に手紙を読んだのは翔太だった。彼は顔を上げ、二度
わかんねえ、と敦也はいった。「一体、どうなってんだ。何だ、これは」
「返事じゃないの? ウサギさんからの」
そう答えた幸平の顔を、敦也と翔太は同時に見た。
「なんで来るんだよっ」二人の口から同じ
「なんでって……」幸平は頭を
敦也は裏口を指した。
「おまえが手紙を牛乳箱に入れたのは、ほんの五分ほど前だ。すぐに見に行ったら、その手紙が消えてた。もしその手紙をウサギとかいう女が取り出したとしても、これだけの返事を書くにはいくらか時間がかかるだろう。それなのに、その直後に二通目の手紙が放り込まれた。いくらなんでもおかしいだろ」
「それはおかしいと思うけどさ、ウサギさんからの返事だってことはたしかじゃないの? だって、俺が訊いたことについてちゃんと答えてるし」
幸平の答えに、敦也は反論できない。たしかにその通りなのだ。
貸してみろ、といって翔太の手から手紙を奪った。改めて読み返してみる。幸平の回答を知らなければ、書けない内容だった。
「くっそー、どういうことだ。誰かにからかわれてんのか」翔太が
「それだ」敦也は翔太の胸のあたりを指した。「誰かが仕組んでやがるんだ」
敦也は手紙を投げ捨てると、そばの押入を開けた。中には布団や段ボール箱が入っているだけだった。
「敦也、何やってんの?」翔太が訊いてきた。
「誰か隠れてないか、確かめてるんだ。幸平が手紙を書く前のやりとりを盗み聞きして、一足先に返事を書き始めてたに違いない。いや、盗聴器って手もあるか。おまえらも、そのへんを探してみろ」
「ちょっと待ってよ。どこの誰がそんなことをするわけ?」
「そんなこと知るかよ。どこかの物好きだ。この廃屋に忍び込んだ人間をからかうのが趣味なんだろ」敦也は仏壇の中を懐中電灯で照らした。
しかし翔太と幸平は動こうとしない。
「なんだよ。どうして探さないんだ」
敦也が訊くと翔太は首を捻った。
「いやあ、違うと思う。そんなことをする人間がいるとは思えないなあ」
「事実、いるじゃねえか。それしか考えられないだろ」
「そうかなあ」翔太は釈然としない様子だ。「牛乳箱から手紙が消えたことは?」
「それは……何かのトリックだろ。手品と同じで種があるんだよ」
「トリックねえ……」
再び二通目の手紙を読み返していた幸平が顔を上げた。「この人、ちょっとおかしいよ」
(つづく)
あらすじ
悪事を働いた3人が逃げ込んだ古い家。そこはかつて悩み相談を請け負っていた雑貨店だった。廃業しているはずの店内に、突然シャッターの郵便口から悩み相談の手紙が落ちてきた。時空を超えて過去から投函されたのか? 3人は戸惑いながらも当時の店主に代わって返事を書くが……。悩める人々を救ってきた雑貨店は、再び奇蹟を起こせるか!?
著者 東野圭吾(ひがしの けいご)
1958年、大阪府生まれ。大阪府立大学電気工学科卒業後、生産技術エンジニアとして会社勤めの傍ら、ミステリーを執筆。1985年『放課後』(講談社)で第31回江戸川乱歩賞を受賞、専業作家に。1999年『秘密』(文藝春秋)で第52回日本推理作家協会賞、2006年『容疑者χの献身』(文藝春秋)で第134回直木賞、第6回本格ミステリ大賞、2012年『ナミヤ雑貨店の奇蹟』(KADOKAWA)で第7回中央公論文芸賞、2013年『夢幻花』(PHP研究所)で第26回柴田錬三郎賞、2014年『祈りの幕が下りる時』(講談社)で第48回吉川英治文学賞、さらに国内外の出版文化への貢献を評価され第1回野間出版文化賞を受賞。
書誌情報
発売日:2014年11月22日
定価:本体680円+税
体裁:文庫版
頁数:416頁
発行:株式会社KADOKAWA
公式書誌ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/321308000162/


































