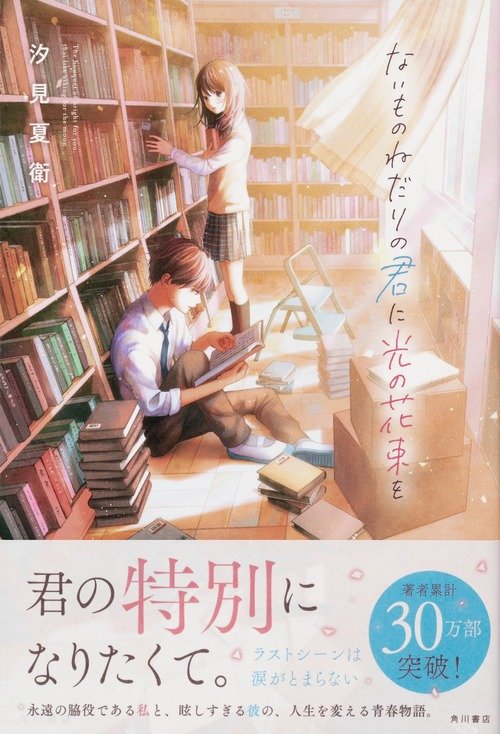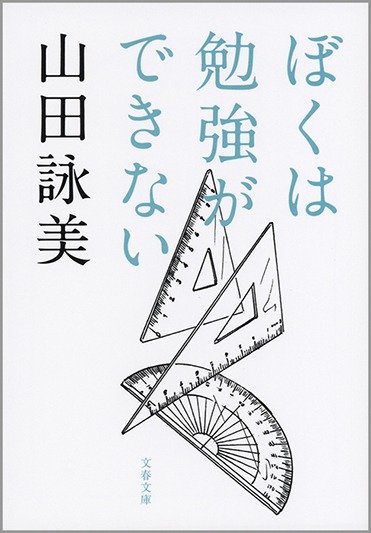学生に読んでほしい作家No.1! 汐見夏衛が描く、世界が輝いて見える希望の物語。
6月18日(木)に発売された『ないものねだりの君に光の花束を』の刊行を記念して、6回に分けて試し読みをお届けします!
平凡であることにコンプレックスを抱く女子高生が、クラスの人気者でアイドルとしても活躍する男の子と出会い、「普通」や「特別」とは何かを考えていく物語です。昨今話題となっている誹謗中傷問題にも触れ、今必ず読むべき内容となっています。
◆ ◆ ◆
一章 遠い隣
席替えとは、今後の明暗を決定的に分ける運命の大事件、と言っても過言ではないと思う。
どの席になるか──窓から何列目の前から何番目か、だけでなく、前後左右に座るのは誰か、気になる人の姿が視界に入れられる位置か、苦手な子と接触しないで済むか。それら全ての要素が絡み合って、これから先約二ヶ月の学校生活が決定づけられる。
新しい席になった瞬間に、世界が変わる。教室が別世界になる。
しかもその行方を自分の力で左右することはできず、全ては運によって決まる。
言うなれば、席替えは誰かが勝手に起こした革命のようなもので、私たちは無力な一市民だ。唐突な変革のあと、世界は劇的に良くなるかもしれないし、劇的に悪くなるかもしれない。
それでも私たちは、強制的に与えられた新たな現実を、ただ受け入れることしかできない。
近くに仲のいい友達が座れば天国だし、親しく話せる子が周りにひとりもいなければ地獄だし、仲良しのふりをしているけれど本当は大嫌いな人が隣になったりしたら、もっと地獄。
好きな人と少しでも近づけたら天国だし、離れて顔も見えない位置になったら地獄だし、彼の近くに自分よりもずっとずっと可愛い子がいたら、もっと地獄。
でも、そこが天国だろうが地獄だろうが、私たちは決められた場所に座るしかないのだ。
そして本日、二学期最初の席替えを迎えた私は今、まさに地獄に落とされたところだ。
小さく折り畳まれたくじ紙を開いて番号を確認し、廊下側のいちばん後ろの席を引き当てたと分かったときには、念願
ちなみに好きな人は特にいないので、片想いの相手から遠い席になったから、などといった可愛らしい理由ではない。
むしろ、真逆だ。
「うわー、俺また二番目なんだけど! 寝れないじゃん!」
「俺いちばん後ろー、イェーイ」
「誰か席交代して!」
「やったー、隣だね!」
「また離れちゃったー!」
「先生ー、早く次の席替えして下さーい!」
新しい座席で悲喜こもごもの声を上げるクラスメイトたちの騒がしさをいいことに、私は隣席をちらりと見て大きな
ぴんと背筋を伸ばしきって、書道の教科書の最初のページにでも載っていそうな真っ直ぐな姿勢で座っている男子。
姿勢だけでなく、その横顔もまるで彫刻作品のように端整なつくりをしている。
鈴木真昼。私がこのクラスでいちばん隣に座りたくなかった人物だ。
絶望を顔に出さないように必死に耐えていると、ふいに「おっ」と声が聞こえてきて、荷物を抱えた男子が私の前の席に座った。
「真昼近いじゃん、ラッキー」
にっと笑って言ったのは、彼とよく一緒にいるグループのひとり、
「授業で分かんないとこ当てられたら、よろしくな!」
「うん、もちろん。俺で分かることなら」
鈴木真昼は穏やかな笑みを浮かべて答える。そのままふたりは何か話し始めた。
周囲に座る生徒たちもそれぞれに、新しく近くの席になった人と
でも、よく見ていると明らかに、お喋りに興じるふりをしながらも彼のほうへちらちらと視線を送っては、
顔には出さないけれど、完全に色めき立っている。
それもそうだろう。なんせあの鈴木真昼が半径二メートル以内にいるのだから、興奮を抑えきれないのだ。
同じ高校、同じ学年、同じクラス。でも、彼の存在感は群を抜いていて、とにかく格別だった。
座っているだけでも、なぜか妙に目を
彼の一挙手一投足を、みんなが気にしている。
陳腐な言い方だけれど、オーラというやつなのだろう。
「
私の思考を遮ったのは、春の空気のように甘く柔らかく、それでいて真夏の陽射しのようにくっきりと鮮やかな声だった。
反射的に目を向けると、鈴木真昼がこちらを見ていた。作りものみたいに
「話すの、久しぶりだね」
まさか話しかけられるとは予想していなかったので、驚きと動揺が私の
「うん……そうだね」
彼と言葉を交わすのは、五月以来だった。
私たちは出席番号──うちの高校の名簿は男女混合で作られている──が十三番と十四番で並んでおり、新年度の座席表は番号順だったので、前後の席に座っていたのだ。それで必然的に何度か話をしたことがあった。
と言っても、ほんの二、三回、「次の移動教室どこだっけ」とか、「英単語テストの範囲、分かる?」などと彼に
たったそれだけのことなのに、誰もが認める《主人公》の彼が、平凡で地味な《脇役》の私と交わした取るに足らないやりとりを、よく覚えていたものだ。即座に記憶から抹消されたっておかしくないのに。
『顔だけでなく性格も
「これから隣同士だし、色々よろしく」
私の湿っぽい考えなどつゆ知らず、鈴木真昼は初夏の風のように
「色々って……」
私が思わず訊き返すと、
「染矢さんって、国語も英語も得意でしょ。俺苦手だから、分かんないとこあったら、よろしくね」
「いやいや……私なんて平均点に毛が生えたくらいのものだから、鈴木くんに教えられるようなことないよ。……こちらこそ、理数系よろしく」
なんとか平静を装って、当たり障りのない返答をしてみたものの、落ち着かない。
お願いだから、もう話しかけないで。そう心の中で懇願しながら荷物の整理をしていると、ふいに担任が「そろそろ体育館に移動するぞ」と声を上げた。これから全校集会が行われることになっているのだ。
私はほっと息をついて席を立ち、足早に出口へと向かった。
ドアを開けた瞬間、冷房のきいた室内とは全く違う、湿っぽい熱を
思わず
私が立ち止まって振り向くと、何だか慌てふためいた様子で駆け寄ってくる。
「羽奈……どうしたの?」
「どうしたの、じゃないよ!」
彼女は興奮を隠さないテンションで私の両肩をがっしりとつかんだ。
「影子、真昼くんの隣だったじゃん!」
「あー、……うん、そだね」
「マ、ジ、で、
私は思わず小さく噴き出してしまう。
たぶんクラスのほぼ全員が──女子だけではなく恐らく男子も、鈴木真昼の隣の席をゲットした私を、心の中では羨ましく思っているだろうけれど、さすがに誰も顔や口には出さなかった。
でも、羽奈は違う。変に格好をつけたりせず、面と向かってその思いを口にする彼女は、本当に素直で正直で、憎めない性格だなと思う。
ただ、誰もが羨むあの席は、私にとっては精神衛生上非常によろしくない場所なのだけれど。
「いいなあ、影子。最初の席でも前後ろだったのに、今度は隣とか! 運よすぎ! 前世でどんだけ徳積んだの? これから二ヶ月近く、あの天然記念物級にキレーな横顔をいつでも好きなだけ見つめ放題でしょ。羨ましすぎるんだけど!」
羽奈は私の腕にしがみつきながら早口に
私は堪えきれない笑みを口許に
「私も一度でいいから真昼くんの隣に座ってみたーい! 次の席替えのときは神社でご
「ご祈禱って。渋いな」
またしても噴き出した私の反応にもめげずに、彼女はさらに続ける。
「真昼くんとお近づきになりたい、なんて高望みはしないからさあ、せめて不自然にならない程度にあの顔をじっくり拝める位置に陣取ってみたいわけよ。だって、テレビの向こうにいるはずの人間を、生で! 肉眼で! 見れるんだよ? クラスメイトの特権じゃん!」
「あはは……まあ、そうだよね」
私は羽奈の言葉にこくりと
まるで夢物語のような話だけれど、クラスメイトの鈴木真昼は、いわゆる『芸能人』だった。
本格的な歌とダンスが売りの人気アイドルグループ、〈
そんな彼が、なぜか芸能コースの存在で有名な某高校ではなく、ごく普通の私立高であるうちの学校に通っているのだ。
合格者説明会の朝、たくさんの新入生に交じって彼が体育館に現れたときのどよめきは、それはそれは
「あの鈴木真昼がクラスメイトなんて、確かに日本中の女子が悲鳴あげちゃうような環境ではあるよね」
私の言葉に、羽奈が「ほんとそうだよ!」と力強く頷いた。
「真昼くんって呼んでることなんか知られたら、ボコボコにされかねないって」
真昼くん、という呼び方は、うちのクラスの女子のほとんどが採用しているものだ。ちなみに男子はたいてい『真昼』と呼び捨てにしている。
というのも、クラスに鈴木姓の男子がふたりいて、分かりやすく区別する必要があるためだ。
だからみんな当たり前のように親しげな呼び方をしているわけだけれど、これもクラスメイトの特権というやつか。
芸能人としての彼は、テレビでもSNSでも『真昼』と呼ばれることがほとんどだけれど、現実の知り合いとして下の名前で呼ぶというのはハードルが高い。その証拠に、他のクラスの人たちは『鈴木くん』と呼んでいた。もちろん、彼に話しかける勇気と図太さを持った人はそれほど多くはなかったけれど。
でも、実際彼は、現役アイドルでありながら、下の名前で気安く呼んでもにこにこと許してくれるような、穏やかで優しげな雰囲気を常にまとっていた。
(つづく)
▼汐見夏衛『ないものねだりの君に光の花束を』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000671/