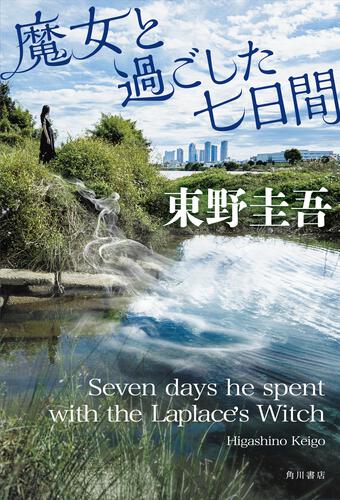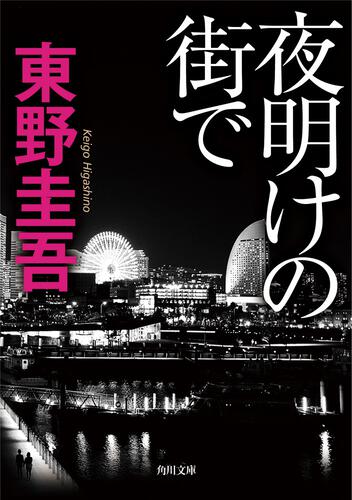ベストセラー作家・東野圭吾氏の著作100作目は、累計200万部を超える「ラプラスの魔女」シリーズの最新長編! 本作は、元刑事の父を亡くした少年の前に不思議な女性・円華が現れ、ともに事件の真相を追い求めるというストーリー。少年の冒険、警察ミステリ、空想科学という要素が組み合わさった圧巻の傑作の冒頭試し読みを、特別公開いたします。
『魔女と過ごした七日間』試し読み
1
中学校の正門を出たところで空を見上げ、陸真は眉をひそめた。灰色の雲が分厚く広がっている。やっぱり降るのか。天気予報で雨のマークを見ておきながら、たぶん大丈夫だろうと思って傘を持たずに出てきてしまった。七月に入ったというのに、梅雨明けは遠そうだ。
今日は真っ直ぐ帰ったほうがいいかもなと思いつつ、気づけばいつもの道を歩いていた。自宅のマンションとは逆方向だ。
やがて辿り着いたのは、駅前にある十階建てのビルだ。都会のオフィスビルを連想させる洗練されたデザインで、壁面が金属のように光を反射させている。
市が運営する複合公益施設だった。中には市役所や図書館、コミュニティセンターなどがある。完成したのは五年ほど前で、最新の設備がいろいろと整っている。
陸真は正面玄関から中に入っていった。入館料は無料だし、面倒な手続きも不要だ。ただしあちらこちらに設置された防犯カメラが、入場者の姿を捉えている。公にはなっていないが、父の克司によれば、それらの映像はリアルタイムで警察によって監視されているらしい。不審な動きを見せる人物がいたりすれば、AIが即座に警報を発するそうだ。顔認証によって指名手配中の犯人を見つけられるから、手続きなしで誰でも出入りできるのも当たり前というわけだ。
エレベータホールには誰もいなかった。エレベータは一階に止まっていたらしく、陸真がボタンを押すとすぐに扉が開いた。中が無人であることを確認して乗り込むと、三階のボタンに続いて、『閉』のボタンを押した。
間もなく扉が閉じ始めた。ところが、あと三〇センチほどで閉まるというタイミングで外から何かが転がってきて、扉の間に挟まった。センサーが働き、扉は開いた。
挟まっていたのは、テニスボールより少し小さめの赤い玉だった。材質は木のようだ。
再び扉は閉まりかけたが、さっきと同じように赤い玉を挟み、またしても開いた。陸真は『開』のボタンを押し、玉を拾い上げようと屈んだ。すると、ごめんなさい、と女性の声が聞こえた。陸真が顔を上げると、車椅子が目に入った。小学校低学年と思われる男の子が乗っている。そしてその後ろに人がいた。小柄だが大人の女性だった。声を発したのは、この人らしい。
「中に人がいると思わなかったので」女性が申し訳なさそうにいった。
「あ……大丈夫です」
女性が赤い玉を拾い上げ、車椅子を押しながら入ってきた。陸真が『開』ボタンを押し続けていることに気づいたらしく、ありがとうございます、と礼をいってきた。
「何階ですか」陸真は訊いた。
女性は操作パネルを見て、「あたしたちも三階です」といって微笑んだ。
奇麗な人だな、と陸真は思った。大きくて少し吊り上がった目が印象的だ。
女性が肩に提げていたトートバッグから取り出したものを見て、はっとした。けん玉だったからだ。彼女は赤い玉をけん先に取り付け、バッグに戻した。玉はけん玉用のものだったのだ。だがなぜ糸が付いていないのか。
陸真は先程の光景を振り返った。彼女はエレベータの扉が閉まるのを防ぐため、赤い玉を転がしたらしい。その思惑通りに玉は扉に挟まったわけだが、そう簡単にできることだろうか。転がすタイミングが遅ければ扉が閉まってしまうし、逆に早ければ玉は通り過ぎてしまう。
ダメ元で転がしてみて、たまたまうまくいった──そう考えるしかなかった。
エレベータが三階に着いた。陸真は『開』のボタンを押し、彼女たちが降りるのを待った。ありがとうございます、と車椅子の少年がいった。女性は黙って頭を下げてきた。
三階は図書館だった。学校の帰りに寄るのは陸真の日課になっている。ここなら何時間いても無料だし、陸真を楽しませてくれるものがたくさんある。
目当ては冒険小説だった。最近のものではなく、二十年から三十年ほど前に書かれた作品にお気に入りが多い。その頃だとスマートフォンはないし、インターネットも今ほど普及していない。だから登場人物たちは、必要な情報を手に入れるため、活発に動き回る必要がある。時には敵のアジトに潜入したりもするのだ。仲間と連絡を取り合う方法もかぎられているので、いろいろと工夫しなければならない。そういったハードルを知恵と勇気で乗り越えていく──そんなところが陸真をわくわくさせるのだった。こういう時代に生まれたかったなあと本を読むたびに思う。
冒険小説のコーナーをじっくりと眺め、本日の一冊を選んだ。ソ連の軍人が最新鋭の原子力潜水艦を使い、アメリカへの亡命を企てるという内容だ。書かれたのは約四十年も前らしい。かつてソビエト連邦という国があったことを陸真は教科書で習い、知っていた。
読み始めて間もなく、自分の選択が正解だったことを確信した。これまでに読んだことのないタイプの作品だったが、抜群に面白く、先が気になって仕方がない。とはいえかなり分厚い本だから、今日一日で読み終えるのは無理だろう。明日からしばらくは本探しに苦労することはなさそうだ、とほくそ笑んだ。
あっという間に時間が過ぎていき、気づけば窓の外は暗くなっていた。しかも窓ガラスに水滴がついている。陸真は窓に近寄り、外を見下ろした。街灯に照らされた歩道を行く人々は、全員が傘をさしている。
床をこするような音が斜め後ろから聞こえた。振り返ると車椅子の少年と女性が近づいてくるところだった。
「かなり本降りになってきたね」女性が外を見ていった。少年に話しかけたのか、独り言なのか、わからなかった。
不意に彼女の顔が陸真のほうに向いた。「傘、持ってないみたいだね」
「あ……はい。傘を持って出るかどうか迷ったんですけど、大丈夫かなと思って」
「朝は微妙な天気だったものね」そういってから彼女は、「近いの?」と訊いてきた。
「えっ?」
「家。ここから近い? それとも電車で通ってるの?」
陸真は首を横に振った。「歩いて十五分ぐらいかな」
「わりと遠いね」彼女は苦笑し、首を傾げながら腕時計を見た。「いいことを教えてあげる。あと十五分ほどしたら、この雨は一旦やむ。今は五時半だから、五時四十五分頃ね」
「えっ、そうなんですか」
「ただし、その時はまだ外に出ちゃだめ。五分ぐらいしたら、また雨が降ってくる。大事なのは、その次。十分後ぐらいに、また雨はやむ。そうしたら急いでここを出たらいい。三十分ほどは降ってこないはずだから。だけどそのチャンスを逃したらおしまい。次に降りだしたら、そのまま朝までやまない」
あまりに断定的な口調に、陸真は当惑した。
「その情報、ネットか何かに出てるんですか」
「そんなところには出てないんだけど」女性は、ふっと吐息を漏らした。「信用できないよね。ごめんなさい、忘れてちょうだい」
行こうか、といって女性は車椅子を押し始めた。
「ちょっと待ってください」陸真は彼女の前に回り込んだ。「どうして糸を付けてないんですか」
「糸?」
「けん玉の……」
ああ、と彼女は表情を崩した。「大した理由じゃない」
「糸なんていらないからだよ」そう答えたのは車椅子の少年だ。後ろを振り向き、「あれ、見せてやって」と女性にいった。
「こんなところで?」
「いいじゃん。誰も見てないし」
女性は困ったように周囲を見回した。たしかに書架に遮られて、人目はない。
「じゃあ、一度だけ」彼女はトートバッグに手を入れ、けん玉を出してきた。そして赤い玉を外し、陸真のほうに差し出した。「上に投げて」
「上に?」
「そう、真上に」
わけがわからなかったが、いわれた通りにすることにした。陸真は赤い玉を上に五〇センチほど投げ、落ちてきたのをキャッチした。
「もっと高く」女性がいった。
陸真はさっきより少し力を入れて投げた。一メートル強といったところか。落ちてきたのを、また受け止めた。
もっと、と彼女はいった。「もっと高く放り投げて」
「ええー」
陸真は、さらに力を込めて放った。だが投げた瞬間、しまったと思った。力を入れすぎたのだ。案の定、玉は勢いを落とすことなく天井に当たった。角度を変え、落下してくる。
受け止めようと陸真が身構える前に、目の前を何かが横切った。次の瞬間、かちゃん、という甲高い音が聞こえた。
女性が伸ばした腕の先にけん玉があった。赤い玉は見事にけん先に収まっている。
陸真は唖然とした。あんな状態で落ちてくる玉を、けん先でキャッチしたというのか。玉は回転しているから、穴が真下を向くのはほんの一瞬のはずだ。しかしインチキなんかではなかった。
「ほらね」車椅子の少年が誇らしげにいった。「いった通りだろ?」
「じゃあ、あたしたちはこれで」
女性はけん玉をトートバッグにしまうと、車椅子を押しながら歩きだした。バイバイ、と少年が手を振ってくれた。だが陸真はそれに応じる余裕などなく、ただ立ち尽くし、去っていく二人を見送った。
その後は読書どころではなくなった。あの女性は何者だろうか。あんなことが可能なのか。インチキをしたようには見えなかったが、やはり何らかのトリックだったのか。
本から顔を上げ、何気なく窓の外に目をやり、はっとした。立ち上がり、窓際に駆け寄った。
雨がやんでいる──。
壁の時計で時刻を確かめた。五時四十八分だった。彼女は四十五分頃に一旦雨はやむが、五分ほど経ったらまた降りだすといっていた。
陸真は時計と窓の外を交互に眺めた。すると再び雨が降りだしたのがわかった。時刻は五時五十分になっていた。
本を棚に戻し、帰り支度をして図書館を出た。エレベータで一階に下り、エントランスホールから外を眺めた。
雨の降り方が少しずつ弱まっていくのがわかった。そしてついにやんだのは、午後六時ちょうどだった。あの女性がいっていた通りだ。もはや予言としか思えない。だとすれば信じたほうがよさそうだ。陸真はビルから外に出た。
今にも水滴が落ちてくるのではないかと思いつつ、帰路を急いだ。自宅のマンションに到着したのは午後六時二十分だった。幸い雨は降らなかった。
部屋で服を着替えているとスマートフォンが鳴りだした。克司からだ。
「はい」
「俺だ」
「わかってる」
「ちょっと用ができて、帰りが遅くなる。晩飯、適当に食っといてくれ」
「わかった」
「冷凍庫にピラフが──」
最後まで聞かずに電話を切った。冷凍ピラフ? そんなみみっちいものを食えるかよ。近所の洋食屋に電話して、ハンバーグ定食を注文しよう。
ざあざあという雨音が窓の外から聞こえてきた。陸真はスマートフォンで時刻を確かめた。午後六時三十分だった。
次に降りだしたら、そのまま朝までやまない──女性の声が耳に蘇った。
(この続きは本書でお楽しみください)
作品紹介
魔女と過ごした七日間
著者 東野 圭吾
定価: 1,980円(本体1,800円+税)
発売日:2023年03月17日
その夏、信じられないことばかり起きた。「ラプラスの魔女」シリーズ!
AIによる監視システムが強化された日本。
指名手配犯捜しのスペシャリストだった元刑事が殺された。
「あたしなりに推理する。その気があるなら、ついてきて」
不思議な女性・円華に導かれ、父を亡くした少年の冒険が始まる。
少年の冒険×警察ミステリ×空想科学
記念すべき著作100作目、圧巻の傑作誕生!
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322208000298/
amazonページはこちら
シリーズ作品紹介
ラプラスの魔女
著者 東野 圭吾
定価: 836円(本体760円+税)
発売日:2018年02月24日
作家デビュー30周年記念作品!
遠く離れた2つの温泉地で硫化水素による死亡事故が起きた。検証に赴いた地球化学研究者・青江は、双方の現場で謎の娘・円華を目撃する――。東野圭吾が小説の常識をくつがえして挑んだ、空想科学ミステリ!
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/321612000242/
amazonページはこちら
魔力の胎動
著者 東野 圭吾
定価: 748円(本体680円+税)
発売日:2021年03月24日
悩める人々の前に現れた彼女は、魔女
成績不振に苦しむスポーツ選手、
息子が植物状態になった水難事故から立ち直れない父親、
同性愛者への偏見に悩むミュージシャン。
彼等の悩みを知る鍼灸師・工藤ナユタの前に、
物理現象を予測する力を持つ不思議な娘・円華が現れる。
挫けかけた人々は彼女の力と助言によって光を取り戻せるか?
円華の献身に秘められた本当の目的と、切実な祈りとは。
規格外の衝撃ミステリ『ラプラスの魔女』とつながる、あたたかな希望と共感の物語。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322003000371/
amazonページはこちら
著者プロフィール
東野圭吾(ひがしの・けいご)
1958年、大阪府生まれ。1985年、『放課後』で第31回江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。1999年『秘密』で第52回日本推理作家協会賞、2006年『容疑者Xの献身』で第134回直木賞を受賞。12年『ナミヤ雑貨店の奇蹟』で第7回中央公論文芸賞、13年『夢幻花』で第26回柴田錬三郎賞、14年『祈りの幕が下りる時』で第48回吉川英治文学賞を受賞。その他の著書に『殺人の門』『探偵倶楽部』『さまよう刃』『夜明けの街で』『ラプラスの魔女』『魔力の胎動』など多数。