東野圭吾『ナミヤ雑貨店の奇蹟』
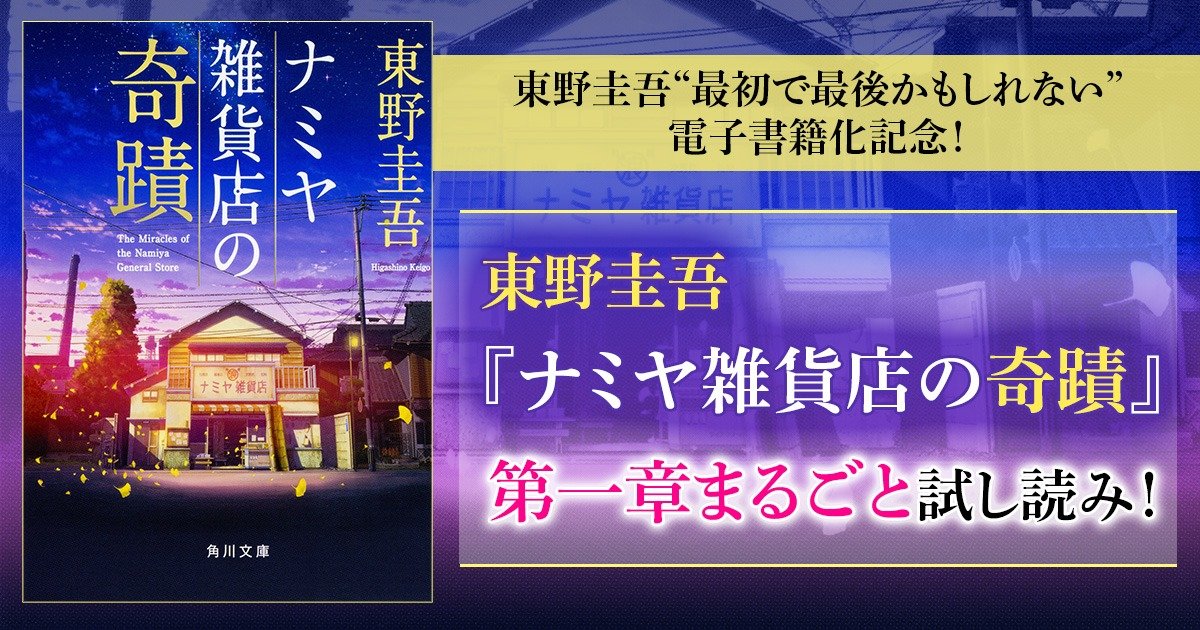
全世界累計1300万部突破のベストセラーが読めるのはここだけ! 東野圭吾“最初で最後かもしれない”電子書籍化記念!『ナミヤ雑貨店の奇蹟』第一章「回答は牛乳箱に」試し読み#1
これまで著書の電子化をしてこなかった東野圭吾氏が、ついに電子書籍の配信をスタートすることになりました。それに合わせてカドブンでは、記録的ベストセラーとなった『ナミヤ雑貨店の奇蹟』の第一章をまるごと試し読み公開します!
◆ ◆ ◆
第一章 回答は牛乳箱に
1
あばらやに行こう、といいだしたのは
「何だよ、それ。手頃なあばらやって」
「手頃っていったら手頃だ。身を潜めるのにちょうどいいっていう意味だ。下見に来た時、たまたま見つけたんだ。まさか、本当に使うことになるとは思わなかったけどさ」
「ごめんな、二人とも」
敦也はため息をついた。
「今さら、そんなことをいったって、どうしようもねえよ」
「でも、どういうことなのかな。ここへ来るまでは何の問題もなかったのに。ライトを
「寿命だよ」翔太があっさりといった。「走行距離を見ただろ。十万キロを超えてた。老衰と同じだ。寿命が尽きかけてたところで、ここまで走ってきて完全にダウンしたんだ。だから盗むなら新しい車にしろっていったんだ」
幸平は腕組みをし、うーん、と
「もういいよ」敦也は手を振った。「翔太、その廃屋ってのは近いのか」
翔太は首を
「よし、じゃあ、行ってみよう。案内してくれ」
「いいけど、この車はどうする? ここに置いといても大丈夫かな」
敦也は周囲を見回した。彼等がいるのは、住宅街の中にある
「あまり大丈夫じゃないけど、動かないんだから仕方がない。おまえら、素手ではどこにも触ってないよな。だったら、この車から足がつくことはないはずだ」
「運を天に任せるわけね」
「だから、そうするしかないっていってるだろうが」
「確認だよ。オーケー、じゃあ、ついてきてくれ」
翔太が軽やかに歩きだしたので、敦也は後に続いた。右手に提げたバッグが重い。
幸平が横に並んできた。
「なあ、敦也。タクシーを拾ったらどうかな。もう少し行けば、広い道に出る。あそこなら空車が来ると思うんだけど」
敦也は、ふんと鼻を鳴らした。
「こんな時間に、こんな場所で、怪しげな男三人がタクシーを拾ったら、さぞかし運転手の記憶に残ることだろうな。俺たちにそっくりの似顔絵が公開されて一巻の終わりだ」
「でも運転手が、俺たちの顔をじろじろ見るかな」
「じろじろ見るやつだったらどうする。じろじろ見なくても、ちらっと見ただけで顔を覚える才能のあるやつだったらどうする」
幸平は沈黙して少し歩いてから、ごめん、と小声で謝った。
「もういいよ。黙って歩け」
高台にある住宅地を三人は歩いた。時刻は午前二時過ぎ。似たようなデザインの家が建ち並んでいるが、明かりの
道には緩やかな
「なあ、どこまで行くんだ」幸平があえぎながら
もう少しだ、と翔太は答えた。
実際、それから間もなく翔太の足が止まった。そばに一軒の家が建っている。
さほど大きくもない店舗兼用の民家だった。住居部分は木造の日本建築で、間口が二間ほどの店舗はシャッターが閉じられている。シャッターには、郵便物などの投入口が付いているだけで、何も書かれていない。隣には倉庫兼駐車場にしていたと思われる小屋が建っている。
ここか、と敦也は訊いた。
「ええと」翔太は家を眺め、首を
「何だよ、はずって。違うのか」
「いや、ここでいいと思う。でもなんか、前に来た時とは印象が違うんだよな。もう少し新しかったと思うんだけど」
「前に来たのは昼間だろ。そのせいじゃないのか」
「かもしれない」
敦也は
「雑貨屋? こんな場所で? 人が来るのかよ」敦也は思わずいった。
「来ないから、つぶれたんじゃないの」翔太がもっともなことをいう。
「なるほど。で、どこから入るんだ」
「裏口がある。
こっちだ、といって翔太は建物と小屋の隙間に入った。敦也たちも後についていった。隙間の幅は一メートルほどだ。進みながら空を見上げた。真上に丸い月が浮かんでいた。
たしかに裏には勝手口があった。扉の横に小さな木箱が付いている。何だこれ、と幸平が
「知らないのか。牛乳箱だ。配達の牛乳を入れるんだ」敦也が答えた。
「へえ」感心したような顔で幸平は箱を見つめていた。
裏口の扉を開け、三人は中に入った。
靴脱ぎには埃まみれのサンダルが一足あった。それをまたぐようにして土足で上がり込んだ。
入ってすぐのところは台所だった。床は板張りで、窓際に流し台とコンロ台が並んでいる。その横には2ドアの冷蔵庫があった。部屋の中央にはテーブルと椅子が置いてある。
幸平が冷蔵庫を開けた。「何も入ってないや」つまらなそうにいう。
「当たり前だろ」翔太が口を
「入ってないっていっただけだ」
隣は和室だった。
和室から先は店だ。敦也は懐中電灯で照らしてみた。商品棚には、わずかながら品物が載っている。文房具や台所用品、掃除用具といったところか。
仏壇の引き出しを調べていた翔太が、ラッキー、といった。「
数本の蠟燭にライターで火をつけ、あちらこちらに立てた。それだけでずいぶんと明るくなった。敦也は懐中電灯のスイッチを切った。
やれやれ、といって幸平が畳の上で
敦也は携帯電話を取り出し、時刻を確認した。午前二時半を少し過ぎたところだ。
「あっ、こんなものが入ってた」仏壇の一番下の引き出しから、翔太が雑誌のようなものを引っ張り出した。どうやら古い週刊誌のようだ。
「見せてみろ」敦也は手を伸ばした。
埃を払い、改めて表紙を見た。タレントだろうか。若い女性が笑顔で写っている。どこかで見たことがあると思い、じっと眺めているうちに気がついた。母親役などで、よくドラマに出ている女優だ。現在の年齢は六十代半ばというところか。
週刊誌を裏返し、発行時期を確認した。今から約四十年前の日付が印刷されていた。そのことをいうと、二人とも目を丸くした。
「すげえなあ。その頃って、どんなことが起きてたんだろ」翔太が訊く。
敦也はページをめくった。体裁は今の週刊誌と殆ど変わらない。
「トイレットペーパーや洗剤の買い占めでスーパーが大混乱……か。なんかこれ、聞いたことがあるな」
「あ、それ知ってる」幸平がいった。「オイルショックってやつだ」
敦也は目次をさっと眺め、最後にグラビアページを見てから週刊誌を閉じた。アイドルやヌードの写真はなかった。
「この家、いつ頃まで人が住んでたんだろうな」週刊誌を仏壇の引き出しに戻し、敦也は室内を見回した。「店には少し商品が残っているし、冷蔵庫や洗濯機も残っている。あわてて引っ越したって感じだな」
「夜逃げだな。間違いない」翔太が断定した。「客が来なくて、借金だけが膨らんだ。で、ある夜荷物をまとめてとんずら。まっ、そんなところだろ」
「かもな」
「腹減ったなあ」幸平が情けない声を出した。「この近くにコンビニないかな」
「あったとしても、行かせないからな」敦也は幸平を
幸平は首をすくめ、
「それに、この埃だらけの畳じゃ、横にもなれないぜ」翔太がいう。「せめて何か敷くものがあればなあ」
「ちょっと待ってろ」そういって敦也は腰を上げた。懐中電灯を手にし、表の店に出た。
商品棚を照らしながら店内を移動した。ビニールシートのようなものがあれば、と思ったのだ。
筒状に丸めた障子紙があった。これを広げれば何とかなるかもしれない。そう思って手を伸ばしかけた時だった。背後で、かすかな物音がした。
ぎくりとして振り返った。何か白いものが、シャッターの手前に置かれた段ボール箱に落ちるのが見えた。懐中電灯で箱の中を照らす。どうやら封筒のようだ。
一瞬にして、全身の血が騒いだ。誰かが郵便口から投入したのだ。こんな時間に、こんな廃屋に郵便が届くわけがない。つまり、この家の中に敦也たちがいることに気づいた何者かが、彼等に何かを知らせてきたということになる。
敦也は深呼吸をし、郵便投入口の
少しほっとして、封筒を拾い上げた。表には何も書かれていない。裏返すと、丸い文字で、『月のウサギ』と書いてあった。
それを持って和室に戻った。二人に見せると、どちらも気味悪そうな顔をした。
「何だよ、それ。前からあったんじゃないのか」翔太がいった。
「今、投げ込まれたんだ。この目で見たんだから間違いない。それに、この封筒を見てみろよ。新しいだろ。前からあったものなら、もっと埃だらけのはずだ」
幸平が大きな身体を縮こまらせた。「警察かな……」
「俺もそう思ったけど、たぶん違う。警察なら、こんなまどろっこしいことはしない」
そうだよな、と翔太が呟いた。「警察が、『月のウサギ』とは名乗らないよな」
「じゃあ、誰なんだよう」幸平が不安そうに黒目を動かした。
敦也は封筒を見つめた。持った感じでは、中身はかなり分厚い。手紙だとすれば、長文のようだ。投入者は、一体何を彼等に伝えようとしているのか。
「いや、違うな」彼は呟いた。「これは俺たち宛ての手紙じゃないぞ」
どうして、と尋ねるように二人が同時に敦也を見た。
「考えてみろよ。俺たちがこの家に入ってから、どれだけ時間が経った? ちょっとしたメモならともかく、これだけの手紙を書くとなれば、少なくても三十分やそこらは必要だ」
「なるほど。そういわれりゃそうだ」翔太が
「まあ、たしかにな」敦也は改めて封筒に目を落とした。固く封がされている。意を決して、その部分を両手で摘んだ。
「何するんだよ」翔太が
「開けてみる。中を見るのが、一番話が早い」
「でも俺たち
「仕方ないだろ。宛名が書いてないんだから」
敦也は封を破った。手袋をしたまま指を入れ、中の
「何だ、これ」敦也は思わず呟いた。
幸平と翔太が横から
それはじつに奇妙な手紙だった。
(つづく)
あらすじ
悪事を働いた3人が逃げ込んだ古い家。そこはかつて悩み相談を請け負っていた雑貨店だった。廃業しているはずの店内に、突然シャッターの郵便口から悩み相談の手紙が落ちてきた。時空を超えて過去から投函されたのか? 3人は戸惑いながらも当時の店主に代わって返事を書くが……。悩める人々を救ってきた雑貨店は、再び奇蹟を起こせるか!?
著者 東野圭吾(ひがしの けいご)
1958年、大阪府生まれ。大阪府立大学電気工学科卒業後、生産技術エンジニアとして会社勤めの傍ら、ミステリーを執筆。1985年『放課後』(講談社)で第31回江戸川乱歩賞を受賞、専業作家に。1999年『秘密』(文藝春秋)で第52回日本推理作家協会賞、2006年『容疑者χの献身』(文藝春秋)で第134回直木賞、第6回本格ミステリ大賞、2012年『ナミヤ雑貨店の奇蹟』(KADOKAWA)で第7回中央公論文芸賞、2013年『夢幻花』(PHP研究所)で第26回柴田錬三郎賞、2014年『祈りの幕が下りる時』(講談社)で第48回吉川英治文学賞、さらに国内外の出版文化への貢献を評価され第1回野間出版文化賞を受賞。
書誌情報
発売日:2014年11月22日
定価:本体680円+税
体裁:文庫版
頁数:416頁
発行:株式会社KADOKAWA
公式書誌ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/321308000162/


































