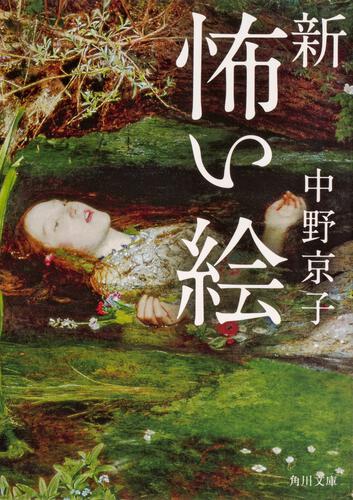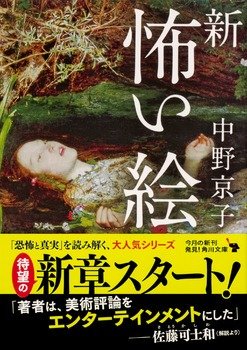名画の新しい楽しみ方を提案する中野京子さんの『怖い絵』シリーズから、選りすぐりの作品を特別試し読み! 今回は、スペインを代表する画家フランシスコ・デ・ゴヤの作品をご紹介します。
ゴヤ 『鰯の埋葬』
謝肉祭(カーニバル)はカトリック圏における、れっきとした宗教行事である。
四旬節(イエスの受難をしのぶ四十日間の節制)には肉断ちして精進するため、その前の三~八日間が肉食に告別するためのカーニバルに充てられた。carnivalの語源が、俗ラテン語carnem(肉)とlevare(取り除く)からきたとする所以だ(異説あり)。この短い期間、道化や滑稽劇、仮面舞踏などを許された人々は、いわば狂宴を心ゆくまで愉しんだ。
スペインではカーニバル最終日(「灰の水曜日」前日)に、なんと鰯を埋葬してドンチャン騒ぎをする風習まで加わった。いつごろからのものか定かではないが十八世紀にはもうあって、ずっと続いている。現在では埋葬というより縁日風で、鰯を炙ってワインのつまみに食べるという形だ。
思い出されるのは、日本での節分。家の門に柊と鰯の頭を飾り、鰯を食す。柊の鋭い棘が鬼の目を刺し、腐りやすい鰯はその臭気で邪気を払うとされたらしい。大衆魚で誰にも手に入りやすかったのも鰯が選ばれた一因だろう。それはスペインにも通じる。
鰯の埋葬起源譚はいくつかあるが、一番よく知られているのは──
四旬節の肉食禁止を下々の者へも徹底させるため、王が大量の鰯を下賜した。ところが届いた時には全て腐って有難迷惑この上なく、処理するのにわざわざ埋めねばならなかった。もとより肉などそうは食べられない庶民なのだから、むしろ肉を食わせろ、という気分になる。それでも怒りを笑いへ転換させ、小さな棺に鰯を一匹入れて練り歩くという滑稽な行事に仕立てあげた。
ゴヤの本作は、制作年がわかっていない。一八一二年の目録に未掲載なので、おそらくそれ以降の、一八一九年までの間に描かれたと推定される。六十六歳から七十三歳の間だ。当時としては相当な老人のはずなのに、彼の汲めども尽きぬ活力は、画面の、陽気を通り越して狂騒状態の登場人物全員を束にしても楽々と打ち負かしている。
人間が狂気じみているのは必然なので、狂気じみていないことも別種の狂気だ、というパスカルの言葉は、ゴヤにもあてはまるかもしれない。彼はここに至るまですでにもう夥しい数の惨死者や拷問に喘ぐ人々、この世の地獄を描き続けてきた。日常を逸脱した異常さに近づかずにはおれず、異常さの中に露わとなる人間というものの性を描かずにおれなかった。愚劣さへの激しい憤り、痛めつけられるものへの悲哀、何もできないもどかしさ、苛立たしさ、焦り、恐怖、そうした感情の波をもろにかぶりつつ、いったん絵筆を取ると、全身がただ眼となった。鰯の埋葬に狂乱する人々を描く時も、ゴヤはクールであったろう。そしてそれこそがパスカルの言うとおり、「狂気じみている」。
本作には下絵が残っており、それを見ると、中央で踊っているのは修道士たちで、旗には司教冠や骸骨の他に「モルトゥス(=死)」という言葉が記されていた。そんなありふれた表象を、今のこのニヤニヤ笑いする巨大な顔に変えたことでゴヤらしさ満開となった。真っ黒で重たげな旗の中の薄気味悪い顔は、地上の人間どもを冷笑しているうちに、いつのまにやら笑いだけを残して消えてゆくのではないか、まるでチェシャ猫のように……。
美しすぎる青い空と白い雲だ。黒い旗がいっそう目立つ。木々の緑と群衆は、自在なタッチで荒々しく省略され、なぐりがきに近い。仮面と素顔も必ずしも明確ではなく、中央で踊っている者たちと見物人もまた容易に入れ替わるだろう。
右端に、魚らしきもの(鰯と思われる)を手にする男がいる、悪魔がいる、闘牛士がいる、兵士がいる、司祭がいる、道化師がいる、熊までいる。なのに祭やダンスに必須の楽士は見当たらない。笛だのラッパだの太鼓だのが演奏されていたはずなのに画面にないのは、ゴヤが聾だったことと無関係ではあるまい。四十六歳で原因不明の病気によって聴覚を失ったゴヤは、全くの無音の中でこれを描いた。写実ではないのだから、聞こえていれば演奏者を後で付け加えられただろうが、関心がないと気づかないのかもしれない。見たいものはくまなく見る。だが音の存在には気づかない。
絵の主人公は(ニヤニヤ顔はのぞいて)、中央で踊る白いドレスに白い仮面ないし白い化粧、そして赤すぎる頬紅の二人だ。衣装は下着ではなく、ナポレオン時代、つまりつい先年のフランスで大流行した、モスリンのシュミーズ・ドレス。両手両脚を大きく広げ、あられもない恰好で踊り狂う。
特に左の一人。すぐ後ろに黒ずくめの悪魔が似た動きをしているので、いっそう目が吸い寄せられる。人体比は正しくない。太腿が長すぎ、ふくらはぎが短すぎる。腕などパペットじみて、デッサンがおかしい。
おそらくこうした点を指して、ゴヤは絵が上手いのか、と疑問をもつ人が少なくないのだろう。では想像してほしい。この人物描写をアカデミックな手法で、完璧な人体比のもとに、手足の関節も自然な曲げ方で描いたらどうなるか──静止してしまうだろう。酔いも動きも伝わるまい。この一見ヘンテコな描き方がここでは何よりふさわしく、またこの人物が女装の男だと見る者に知らしむるのだ。
彼女たちは彼らである。仮装や仮面は何のためか。自己を解放するためのものだ。価値を転換するためのものだ。社会の序列も礼儀作法も性も個も捨てて、変容するためのものだ。ルイ十五世は仮面舞踏会で「立ち木」となり、マリー・アントワネットは宮廷劇場で庶民の娘に扮した。ありとあらゆるものが転換される。
画面前景左に抱き合う男たちがいる。うっとりと相手の胸にすがる醜い仮面の男装姿は、若い美女かもしれない。それとも美青年かもしれない。男女か、男同士か、女同士か。いずれにせよ祝祭にはエロスがつきもの。
自分でなくなった者たちのエネルギーは凄まじい。気分もすぐさま転換するであろう。笑いは怒りに、陽気さは恐怖に、エロスは残酷さに激変し、思ってもみない方向へと暴発するだろう。ゴヤはそれを見てきた。
不幸なスペイン。
長いイスラム支配からようようのことで抜け出てまもなく、ハプスブルク家の王に取って代わられた。彼ら青き血の一族が自滅すると、ブルボン家がやって来る。彼らを追い出したのは、同じフランス人のナポレオンだ。もうこのころにはすっかり他国の王を戴くことに慣れきっていたスペイン人は、ナポレオンの兄たる新王が、旧態依然の異端審問を廃止し、近代化しようとしたことに猛反発する。そしてかつてのブルボン王の息子を王にするため戦ったのだ。
ゲリラという言葉はベトナム戦争と結びついたイメージだが、実はスペイン語からきている。「戦争」(ゲラguerra)に「小さい」という意味の接尾語(-illa)を付けて、「小さい戦争」(ゲリーリャguerrilla)だ。統制のとれたナポレオン軍に対し、スペインの民衆が手近なものを何でも武器にして、何度も何十度も小さな戦いを重ねて──イギリスの援軍があったとはいえ──ついに勝利を勝ち取った。
しかし歓声を上げて迎え入れた復古王フェルナンド七世は、父王カルロス四世よりはるかに暗愚だった。自分のために命を賭けて戦った者を自由主義者として大量処刑したばかりか、異端審問所を再開させ、専制政治を敷いてスペインを前以上の闇に落とす。
ゴヤはこの経緯をずっと見続けてきた。ゴヤ自身、フェルナンド七世の王政復古直後、『裸のマハ』の存在を知られ(スペインはヌード絵画厳禁)、異端審問所から呼び出しをくらった。幸いにして有力者の口添えで事無きを得たが、場合によっては逮捕や裁判もありえた。
ゴヤという複雑きわまりない芸術家は、心は民衆の側にあっても、民衆と同じ心を持っていたというわけではない。むしろ民衆の愚かさ、影響されやすさに絶望していたのではないか。この『鰯の埋葬』はその絶望のあらわれのようにも感じられる。
祭のエネルギーは戦いのエネルギーとなったが、その結果はどうだったか。もしこの絵が推定年代最後の一八一九年制作だとしたら、ゴヤが宮廷を離れて「聾の家」にこもるのは同年であり、その家の壁に『我が子を喰らうサトゥルヌス』をはじめとした「黒い絵」シリーズを描きだすのは翌年であり、さらに数年後にはフランスへ亡命するのだった。
フランシスコ・デ・ゴヤ(1746~1828)は、ほぼゲーテと同時代に生きた。五百点近い油彩画、三百点を超すエッチングとリトグラフなど、膨大で多彩な作品群の魅力は今なお褪せないどころか、日々命を新たにするようだ。
(中野京子『新 怖い絵』より)
ゴヤの作品は、国立西洋美術館にてまもなく開催される「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」でも見ることができます。同展で展示されるのは《ウェリントン公爵》という作品です。

フランシスコ・デ・ゴヤ 《ウェリントン公爵》 1812-14年 油彩・板 64.3×52.4cm ©The National Gallery, London. Bought with aid from the Wolfson Foundation and a special Exchequer grant, 1961
ロンドン・ナショナル・ギャラリー展とは
ヨーロッパ絵画を網羅する質の高いコレクションで知られる「ロンドン・ナショナル・ギャラリー」が、200年近い歴史で初めて開催する館外での大規模な所蔵作品展。ゴッホの《ひまわり》、フェルメール の《ヴァージナルの前に座る若い女性》、ゴヤの《ウェリントン公爵》など、今回は61作品、すべてが初来日という、開催前から注目を集めている美術展です。
https://artexhibition.jp/london2020/
会期:2020年6月18日(木)~10月18日(日)
※6月18日(木)~6月21日(日)は、「前売券・招待券限定入場期間」とし、前売券および招待券のをお持ちの方と無料鑑賞対象の方のみご入場いただけます。
会場:国立西洋美術館
開館時間:午前9時30分~午後5時30分 (金曜日、土曜日は午後9時まで) ※入館は閉館の30分前まで
休館日:月曜日、9月23日 ※ただし、7月13日、7月27日、8月10日、9月21日は開館
※日時指定制となります。詳細は展覧会公式サイトをご確認ください。
※国立西洋美術館では入場券の販売はございません。
中野京子が贈る名画の新しい楽しみ方 角川文庫「怖い絵」シリーズ
- 『怖い絵』
https://www.kadokawa.co.jp/product/201012000707/ - 『怖い絵 泣く女篇』
https://www.kadokawa.co.jp/product/201012000708/ - 『怖い絵 死と乙女篇』
https://www.kadokawa.co.jp/product/201012000710/ - 『新 怖い絵』
https://www.kadokawa.co.jp/product/321909000205/
関連記事:注目の「ロンドン・ナショナル・ギャラリー展」を観るならこの2冊! 美術鑑賞がもっと楽しくなる文庫をご紹介