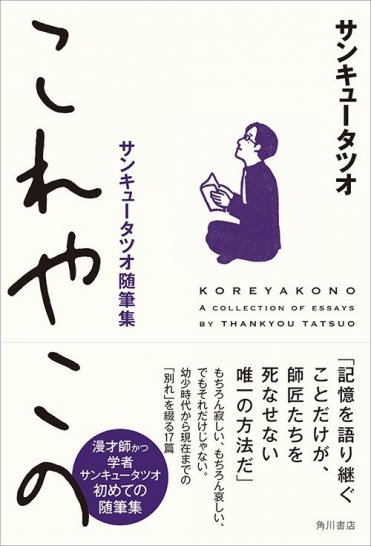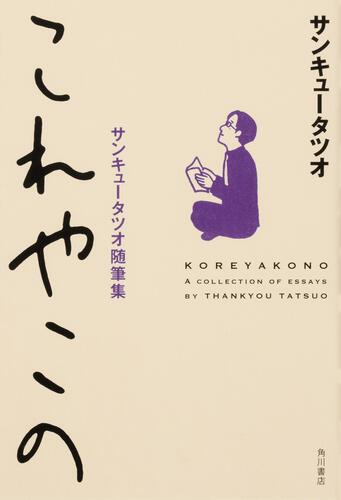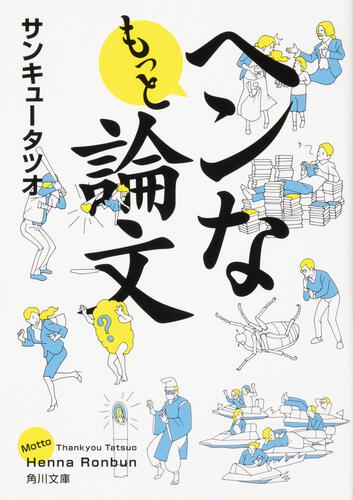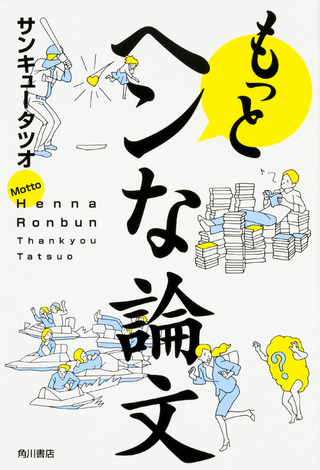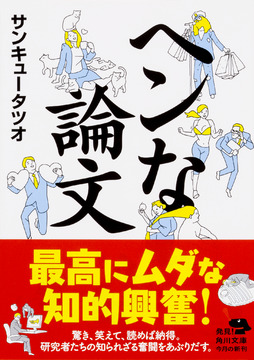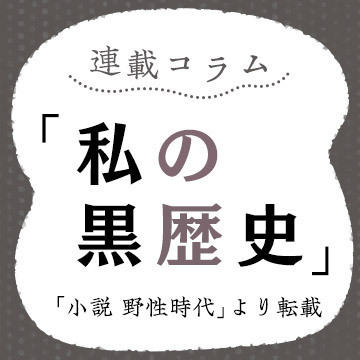これやこの サンキュータツオ随筆集
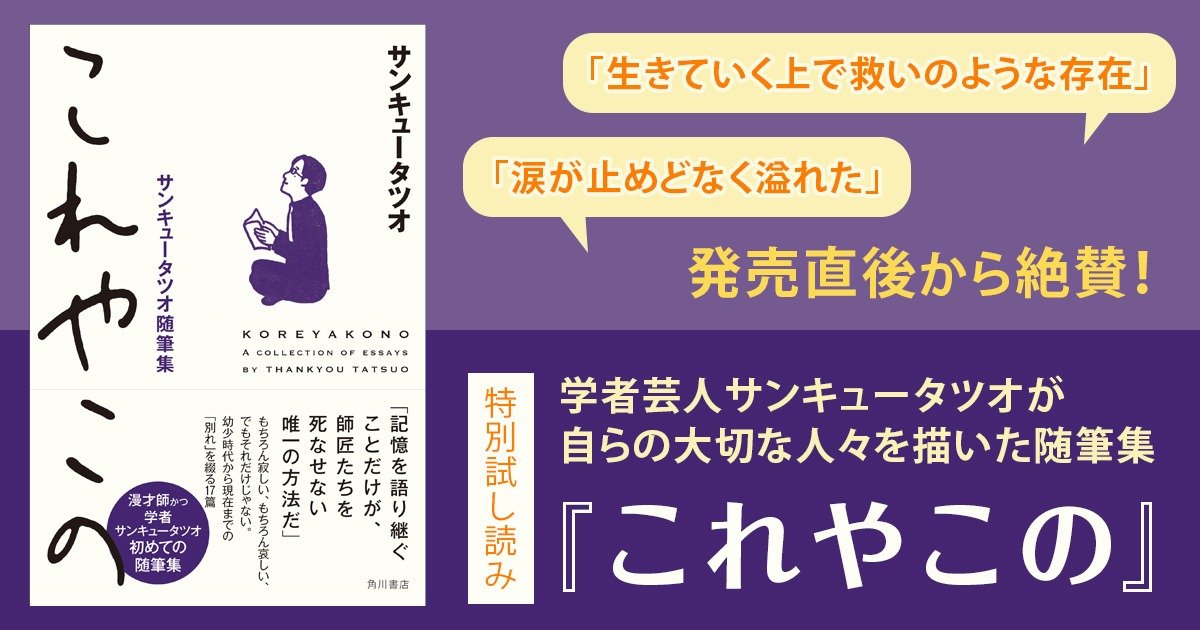
「私は癌になりました。死ぬ前に処分をするので手伝ってください」 サンキュータツオ『これやこの』試し読み #1 黒い店
「生きていく上で救いのような存在」「涙が止めどなく溢れた」など、発売直後から絶賛の感想が寄せられている『これやこの』。
漫才師で日本語学者でもあるサンキュータツオが、亡くなった人たちのことを題材に描いた17編の随筆集です。
ご自身の大切な人、大事な思い出、後悔や懺悔も含めて、さまざまな思いを巡らせるきっかけになるよう、試し読みを公開します。
黒い店
「古本業界は隙だらけですよ。本が売れなくなったって言っているけど、うちは売り上げあがってますからねえ。十年一日のごとくおんなじことやってて本が売れないなんて言っている連中がいる限り、うちはまだ続けられるんです。だから感謝しないといけませんな、ハッハッハ」
ご主人はパイプの愛好者であった。
パイプに刻みタバコをつめながら、いまの古本業界でまだだれもやっていないことはなにか、ずっと語り続けて、吸いはじめると自慢話とも苦労話ともつかぬ話が続く。
私がその古本屋「上野文庫」でアルバイトをはじめたのは、大学3年になった1990年代後半。店は
東京、といっても、歩きタバコしているおじさんがいたり、寝間着みたいな
生き馬の目を抜く新刊本屋で頭角を現したこの人物は、御徒町にある古美術商の主人と出会い、嫁ぐあてのなかったその娘と、入り婿という形で婚姻関係をもった。形ばかりは夫婦という関係ではあったが、実情としては後見人にちかい。古美術商が亡くなったあとに経営能力のない娘にかわり、婿として土地と建物を引き継いで古本屋を開業した。私は大学生だったが、心のどこかにロマンチストな乙女がいたので、徹底的にリアリストな大人に触れ新鮮だった。
「古本には、白い本と黒い本というのがあるんです。白い本とは真面目な本で、神保町に行けば探せる本なの。でも黒い本というのは、私なんかでも一生に一度出会えるかどうか、そういった珍しい本ね。図版やデータが載ってて、明治や大正に出版されたもの。カフェー関連や講談、落語の速記、鉱石ラジオ。うちはそういう黒い本しか置かないの。時代はスキマ産業に傾くんですよこれから!」
ご主人の声は高くて大きい。自信家を絵に描いたようだが、不思議と嫌味がない。
ランチはいつも上野の鈴本演芸場の裏にある焼肉屋だった。信じられないほどうまい焼肉に若い私は毎度驚くのだが、そんなものは当たり前だと言わんばかりに手慣れた感じで焼肉を食べる中川のご主人は、ひたすらしゃべりながら肉を焼いた。とにかく肉をよく食べる人で、50代とは思えないパワフルさだ。
このご主人は当時国内でも数少ない「セドリ」をする古本屋だった。近場の古本市だけではなく、新聞の死亡記事で著名人が亡くなると「週末ここの遺族が、蔵書の価値がわからないから、文字通り蔵にある本を全部市に出す。おそらくそこにここで売れる本が出る」といって地方の古本市にまで出向き、出会ったことのない一冊だけのために出張する。空振りに終わる日もあるのだが、それでも宝と出会えるその瞬間が好きで古本をやっているのだ。そのほかに週末あの地方でなんか変な本が出るらしいとか、久しぶりにあの地方に行ってくるとか、まだネットも普及していない時代にご主人の情報ネットワークは尋常ではなかった。
本来であればこんな効率の悪いことは多くの古本屋はしないのだが、このジャンルは強い、と知られている古本屋ならばできる。この一冊のためならば、いくら出しても惜しくない、という顧客をこのご主人は多く抱えていた。
「本を見た瞬間に、買うお客さんの顔がイメージできないものは、落としません」
これもご主人がよく言っていたことだった。
その道を究めたお客さんたちが、最後の望みをかけて「上野文庫」にやってくる。長いコレクター人生で一度も見たことがない、存在は活字でしか知らなかったという本も、見つけてしまう古本屋。当然、おなじ本でもほかの店よりも高い値段がつくのだが、それでもコレクターたちはこの古本屋に押しかける。どの棚の本も、おなじ場所に二週間はいない。必ず買い手がつき、棚は常にそんなご主人の目にかなった超一級の本たちがひしめきあっている状態だった。本棚から彼らの声が聞こえてくるようだった。いまにも一冊ずつが自分で動き出しそうな、元気な棚なのだ。
こういう本屋になると、コレクターたちがご主人に情報をもってくる。こういった本があるとか、こういうコレクターがいるとか、こういうイベントがあるなど。自然に中川のご主人が「まとめサイト」化していくのだった。
棚ごとにコンセプトがあるこの黒い本専門の古本屋で私が働くことになったのは、なかでもひときわ輝いていた「速記本」の棚があったからだ。そこには落語の速記本が山ほどあった。ほとんどの人が、生涯で一度も手に取らない明治生まれの速記本。四代目橘家
古本屋のアルバイトというと、ただ漫然とレジに座っているだけという
週末の地方や、平日の古書協会の古本市で落札した(入札制なのである)本の束を、この書庫まで運び、整理をし、棚に出せるまで美しくし、値札をつける。不要な本をまたまとめて売りに出す。とにかく本を運ぶのが仕事のメインで、この作業が永遠に終わらない。
たとえば宝塚は、時代を経ても人気の絶えないジャンルであるが、上野文庫も「宝塚」の棚があった。「歌劇」などの雑誌は創刊号から揃いで常備しているのでストックも大量にあるのだが、この「歌劇」がカラーで重い紙をつかっており、一年分だけでも持ち上げるのに一苦労だ。これを何年分も永遠に束にしつづけ、棚に置いていく。こういったことをほとんどすべての棚でずっと行っているのだ。当然、こういう努力をせずに、市場で仕入れた本の束をそのまま店の棚に入れてただ売れるのを待っている古本屋もなかにはある。言ってみれば自由度の高いベンチャーなのである。店のコンセプトも、仕入れ方も、値段のつけ方も、すべては店長の裁量にかかっている。
ここには、土地柄か変わった売り手もいた。ホームレスが本を売りに来るのである。しかし、ただのホームレスではなく、高く売れる本を見極める眼力があるホームレスなのだ。毎週の古紙回収の日の早朝に、都内のゴミ置き場をあさって、値段のつく本を探し出しては、それをもっとも高く売れる古書店に持ち込む。資本金がなく生活できる特殊技能である。こうして生活をしている人もいるのだから、この世界はたまらない。
「君は床に置いてある本も決して踏まないね。えらい。褒めてやる」
山のように積まれ、所せましと置かれている本を、私はまたぐことが
まるで立川談志のような古本界のカリスマだったが、当然敵も多かった。値段の偵察にきては、あとでやり方をさんざん非難する書店もあったが、一方で素直に感服し教えを
ここには人間たちが蓄積してきた「情報」が集まっていた。
「私も早稲田の仏文科を出たんですよ。
共通の師がいることがわかり、近づきがたさと親近感の両方を覚えはじめていた。
「さっきそこのレコード屋で
ご主人のアンテナは幅広かった。だれも持っていないような落語のテープやレコードも持っており、そうかと思うと韓国の「ポンチャック」というジャンルの歌や
1998年、高校野球では
私は目録の作り方から、良い本の選び方、本屋ごとの入札の癖などの手ほどきをうけ、また本の補修の方法なども教わった。毎日が発見の連続である。
こうして数年が過ぎた。
「私は癌になりました。死ぬ前に処分をするので手伝ってください」
ある日、ご主人は笑顔でこういった。
悲しむでも嘆くでもなく、サラッと自然にこういった。
数ヶ月後、ご主人は灰になった。奥さんは夫が亡くなったことをどれほど理解しているのかわからなかった。葬式には古本屋仲間が何人か来たほかは、ほとんど来なかった。
在庫は愛人がもっていって売り物にした。ご主人には子どもも親もいない。
その後、上野文庫があった場所は、
https://twitter.com/39tatsuo/status/1290124315686367233
お盆までの時期、Twitterで「#これやこの」のハッシュタグをつけて亡くなった人や、ご自身の思いをつぶやくと、サンキュータツオさんが反応してくれるかもしれません。
書誌情報
書名:これやこの サンキュータツオ随筆集
著者:サンキュータツオ
発売日:2020年6月26日(金) ※電子書籍同時発売
定価:本体1400円+税
体裁:四六判並製・264ページ
装丁:國枝達也、カバーイラスト:大嶋奈都子
ISBN:9784044005504
発行:株式会社KADOKAWA
https://www.kadokawa.co.jp/product/321907000688/
目次とそのエピソード
「これやこの」…渋谷らくごを引っ張ってくれた二人の師匠
「幕を上げる背中」…駆け出しの頃を支えたライブスタッフ
「黒い店」…上野御徒町の古本屋の店主と大学生だった自分
「バラバラ」…「早稲田文学」で出会った老作家
「時計の針」…大人になった今思い出す、中学校教師の話
「明治の男と大正の女」…祖父母にしかわからない二人の関係
「空を見ていた」…仲良しだったいとこが残した一枚の写真
「鈍色の夏」…2019年夏、生きる気力を失った自分を助けてくれたもの ほか
著者について
サンキュータツオ
1976年東京生まれ。漫才師「米粒写経」として活躍する一方、一橋大学・早稲田大学・成城大学で非常勤講師もつとめる。早稲田大学第一文学部卒業後、早稲田大学大学院文学研究科日本語日本文化専攻博士後期課程修了。文学修士。日本初の学者芸人。ラジオのレギュラー出演のほか、雑誌連載も多数。著書に『もっとヘンな論文』(角川文庫)、『学校では教えてくれない! 国語辞典の遊び方』『ヘンな論文』(ともに角川文庫)、『ボクたちのBL論』(春日太一との共著、河出文庫)などがある。
サンキュータツオ ツイッター/https://twitter.com/39tatsuo