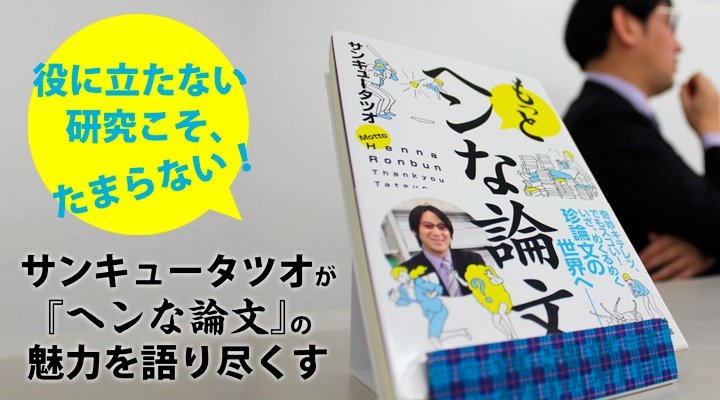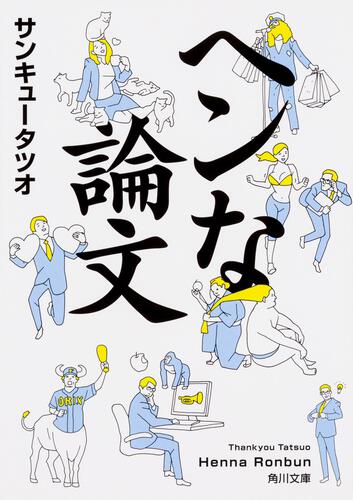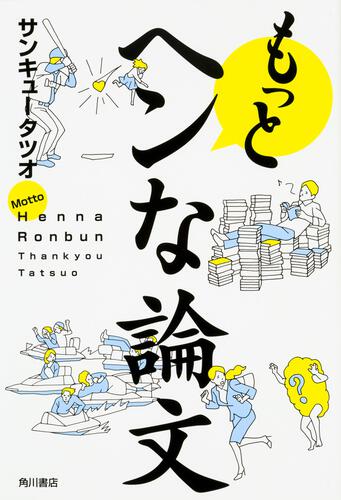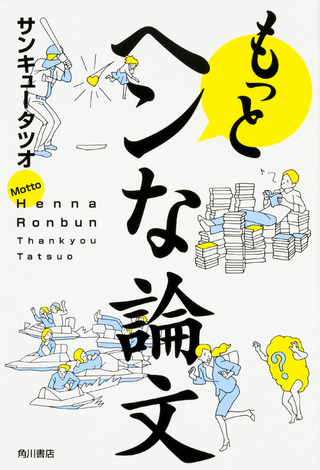「プロ野球選手と結婚する方法」「「浮気男」の頭の中」などの珍テーマを大マジメに研究する数々の論文を発掘し、著書『ヘンな論文』『もっとヘンな論文』で新たな知的エンターテインメントへと昇華させたサンキュータツオさん。12月15日、母校である早稲田大学で読書企画サークル「ブックポータル」が開いたトークショーに招かれ、珍論文からあふれ出る研究者たちの情熱について大いに語った。
「修士より上になると図書館に個室をもらえるの、知ってる? どれだけ仮眠したか、あそこで」というタツオさんの学生時代のエピソードから和やかに始まったトークショー。聞き手は同大3年の戸塚興さんと高橋良輔さんが務めた。
一見おかしな論文に、研究者の情熱が溢れる瞬間がある
聞き手: そもそも珍論文に興味をもったきっかけは何だったのですか?
サンキュータツオさん(以下、タツオ): 僕は文学研究科というまったく潰しの効かない道を選んだのですが、覚悟の上で入学したはずでも「自分の研究はお金にならないだろうな」「世の中の誰がこんな研究を望んでいるんだろうか」という不安を常に抱えていました。そんな時、図書館で自分の専門外の珍論文に触れることがあって、「こんなに時間をムダにしてる人もいるのか!」とすごく癒やされたんですよ。もちろん、実際にはムダじゃないんですけどね。初見でなかなかそれがわからないようなものがおかしくってたまらないですね。
聞き手: 著書に掲載された論文はどれもユニークですが、何を基準に選んだのですか?
タツオ: 一見、何やってんだって笑っちゃうんだけど、研究者の情熱が溢れる瞬間があって学問の深淵に触れることができる論文を選んでます。僕、お笑い芸人なんでよく誤解されるんですけど、別に珍論文をクサしているわけではなくて、基本的に尊敬の念をもって紹介したいと思ってます。
聞き手: 面白いけれど掲載しきれなかった論文もあるんですか?
タツオ: もちろん! 2000年代の人工知能研究は変な論文がたくさんあります。たとえば大人がいない隙に子どもがロボットを破壊しようとする「ロボットいじめ」をいかに防ぐか、という研究を真剣にやっていたり(笑)。でも、当時は変な研究に思えても、家庭用ロボットが実用化されている今なら理解できますよね。変な研究が世に広く知られるまでにだいたい10年から20年くらいの誤差がある、というのが最近わかったことです。

「未来も役に立たない論文」がたまらない
タツオ: でも未来も役に立たないだろうなっていう論文をなるべく選んでます(笑)。
特に思い入れがあるのは『もっとヘンな論文』で紹介した山田廸生先生の『「坊っちゃん」と瀬戸内航路』。山田先生は在野の研究者として船の研究をしていた方で、今から125年前に夏目漱石が松山中学に赴任した際にどんなルートで東京から松山まで行ったのかを徹底検証した、いわゆる「特定厨」みたいな人なんですよ。わかったところで別に……っていうテーマに研究人生で培ったスキルを総動員して大興奮している感じが本当にたまらないですね。僕がこれまでの人生で読んだ中で一番興奮したミステリーでした。
本物の学者が本気を出すとこれだけのことがわかってしまうのか、と震撼しました。
『ヘンな論文』のほうでも、キャリアの最後の10年を湯たんぽに賭けた伊藤紀之先生という研究者を紹介しました。湯たんぽって、なんで?ってだれしも思うと思うんですけど、伊藤先生は国内の家政学においてはすごい権威で、もう他に研究することがないくらいいろんなことを知っている方なんです。で、研究の世界で「何でそんなことやるの?」っていうものは、たいがい新しいテーマなんですよね。伊藤先生の場合も、茶器も花瓶も陶器も磁器もいろんな先行研究がある中で、誰もやってないのが湯たんぽだったわけです。
湯たんぽをだれも定義していない。歴史を整理していない。そこに全キャリアの蓄積を投入していくという、クレイジーでグレートな研究です。
聞き手: 新しい研究だからこそ、一見変なものに見えるんですね。
タツオ: 泥臭くて地道で報われないけれど、とにかく人を感動させる論文、っていうんですかね。こういう論文に心打たれる経験をみなさんにもしていただきたいです。だから単に、向こう側にいる人をこっち側から笑い飛ばすようなことはしたくない。向こう側の風景をみなさんに見せたいという思いで本にしています。

聞き手: もしタツオさん自身が論文を書くとしたら、どんなテーマを選びますか?
タツオ: やっぱり古典ですかね。こんなことを言うと関わってる全ての人が激怒すると思うんですけど、日本の古典文学の研究って何の役にも立たないように思えますよね。でも「日本人とは何か」「日本人とはどういうものの見方をしてきたのか」のルーツを探る上でものすごく興味深い素材だと思います。君たちは古典って興味ある?
聞き手: あまり……ないですね(笑)。
タツオ: 僕も大学に14年いて最後の3年くらいまで魅力が全くわからなかった。でも大人になってから面白さに気づくものってたくさんあって、その最たる例が古典。だって年とったら最終的にみんな俳句詠んでるじゃんか(笑)! なかでも古典の研究者たちは、若い頃からその価値や面白みを理解できていた感受性豊かな方々です。そんな方々の論文を読むだけでも、さまざまな教養が溢れだしていて楽しいです。 いま、何か知らないことや興味が持てないことがあるなら、これから知ったり興味を持ったりする楽しみがあるんだと思ってもらいたいな。
学生: 僕らもいつか古典に目覚めると……?
タツオ: 絶対目覚めるから! 間違いない!
役に立たない方向へ徐々に振り切る姿が最高!
聞き手: 『ヘンな論文』『もっとヘンな論文』の続編を出すとしたら、どんな本にしたいですか?
タツオ: 一人の研究者を縦で追ってみたいですね。小説を読むときってデビュー作から入ってキャリアを追う読み方があるじゃないですか。研究者も、どんな研究を経て今に至るのかがわかると面白いんじゃないかな。

たとえば湯たんぽの伊藤先生にはいろんな研究の蓄積があるんです。まずヨーロッパのファッション・プレート(最新ファッションを伝える版画)にどっぷりハマって本まで出版して、さらに浮世絵も東京都北区にある飛鳥山が描かれた作品ばかりをコレクションしている。靉光という寡作の画家の絵もお持ちで、学芸員よりも詳しい部分もある。「知の巨人」ですよ。この先生は1回ハマると全部わかるまで止まれない人なんだな、ってよくわかりますよね。
しかも伊藤先生は元々有名ブランドのロゴをデザインしたり、日本にシステムキッチンを紹介したりと、めちゃめちゃ役に立つことをしている人なんです。そんな人が徐々に役に立たなさそうなニッチな方向に振り切っていく感じが、本当にたまらない。この感じを皆さんにも知っていただきたいです。
それから、今70歳近い先生たちっていろんな学問領域が細分化される前の時代を知っていて、横断的な知識がある最後の世代なんですよね。家政学の先生でも夏目漱石を読んでいて、なおかつ絵にも詳しかったり。だから彼らの研究遍歴を聞いて、残しておくことが今のこの国を支える礎を知ることになるんじゃないかな。先生たちがお元気なうちにしっかり取り上げてみたいですね。
取材・文/浜田 有希