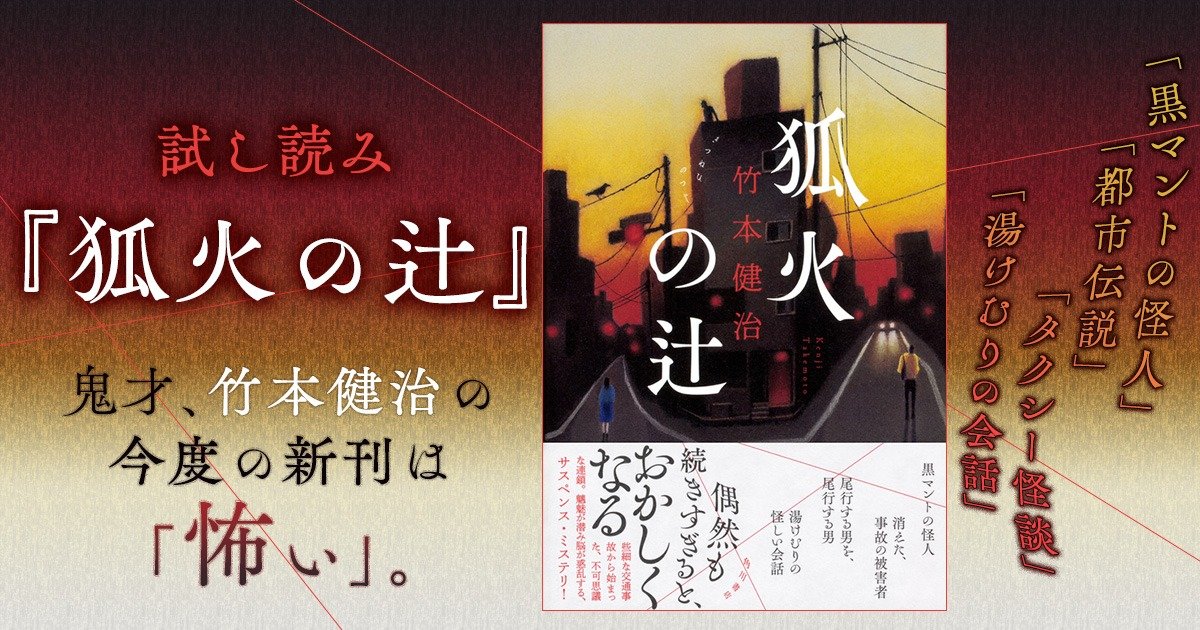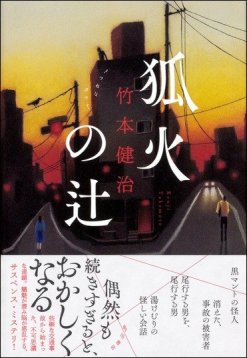竹本健治の4年ぶりの新作へ、作家・麻耶雄嵩氏をはじめ、ミステリ本の応援団/(書店関係者:レビュー抜粋)から高評価のコメントが続々!
4日連続、本文ハイライト部分を立ち読みで紹介!
これはホラーか、サスペンスか、ミステリーか? ぜひ、ご自分の目で確かめてください!
麻耶雄嵩 (作家)
残りページが少なくなっても、とっちらかったままの都市伝説たち。もっとだらだらと読み続けていたかった
OB会での出来事
それが起こったのは温泉宿での大学サークルのOB会のさなかだった。
部屋は午前十時から予約を入れていたので、午後には参加者のあらかたが顔を
部屋での支度がモタつき、出遅れてしまった彼女はまず遊戯室、そしてロビーとまわってみたが、どちらにもタカトの姿はなかった。きっと外に出てしまったのだ。彼女は慌てて旅館の玄関を出、表通りにとび出した。
石畳の緩い坂が右手から左手へと下り、そちこちに同じような温泉旅館が並んでいる。急いで見まわしたが、タカトの姿は見えなかった。左手にずっと下っていけば海に出る。そちらだろうか? いや、以前いっしょに
スニーカーなので鎌倉で山道を歩かされたときのような失敗はない。けれども白壁や生垣に挟まれた坂を五十メートルばかり走ると、さすがに息が切れた。角の土産物屋をやり過ごすと大通りだ。そこにとび出して左右を見まわすと、いた! 右手の歩道のずっと先にタカトとスグルの姿が見える。やっぱりあたしの直感に間違いなかった。そう、タカトのことはあたしがいちばんよく分かってるんだから。
タカトとはサークルで知りあい、二年ほどつきあっていた。最後の半年はほとんど
どうしてあんなにすんなりと別れてしまったんだろう。そう考えると自分でも不思議な気持ちになる。きっとお互い新しい生活に
彼女は二人のほうへ駆け出した。スグルがいるのはちょっと余計だけど。いや、はじめはいきなり二人きりになるより、そのほうがいいかな。──と、そんな計算もはいったとき、二人は何か喋るのに夢中な様子のまま車道を渡りかけた。
そこに一台の車がかなりのスピードで近づいた。
危ない! という言葉が出るまもなく、タカトの体が凄まじい勢いで持っていかれた。
全身の血が抜け落ちたような気がした。
宙を舞ったタカトの体が地面に落ち、粉を詰めた布袋のように転がった。
車はいったん切り裂くようなブレーキ音を立てたが、再びスピードをあげて彼女の横を通り過ぎた。けれども彼女の眼は倒れたタカトに
彼女が「いやあああああっ!」と声をあげたのはそのあとだった。ようやくそれで硬直が解けたように駆け出したが、そこまでのおよそ三十メートルの距離が
タカトのシャツは大きく裂け、そこにみるみる真っ赤な血が
そこからは混乱していてあまり順序立てては憶えていない。救急車が来るまでもずいぶん長い時間がかかったように思うし、そのあと受け入れ可能な病院を電話で捜すのにもけっこうかかった。そのうちに警察も来て、スグルは自分がそちらの対応で残るからお前が病院にいっしょに行けと言ってくれた。その間、彼女は泣いてばかりだった。
病院に運ばれる時間も長かった。最初のうちは意識がなかったタカトだが、途中でぽっかりと眼をあけ、「あれ?」などと呟いてキョロキョロしたのには心底ほっとした。
ようやく病院に着き、タカトはストレッチャーに乗せられて治療室に運びこまれ、彼女は廊下のソファで待つように言われた。午後なので患者の姿は少なく、廊下は端から端までがらんとして、そんななかでただぽつねんと時を待っているのはひどく心細かった。
やがてスグルと今回の幹事の先輩が旅館の仲居さんに連れられてやってきて、彼女は救われた気分になった。
「どうなんだ、様子は?」
「分かんない。救急車のなかで意識が戻って、そのあとはけっこう元気そうにしてたけど」
「じゃあ大丈夫かな。それにしても、こんなときにこんなことになるなんて」
「僕と喋るのに夢中になってて、車が来てるのに気がつかなかったんだ。もっと気をつけてればよかった」
スグルは後悔の言葉を繰り返した。
そんなところに看護師さんが治療室から出てきた。ひと通り処置もすみ、脳の検査でも異状はなかったということで、そのまますんなりベッドに案内された。
あちこちの包帯やガーゼが痛々しかったが、タカトは元気だった。「心配かけてすまんな」と、申し訳なさそうに笑ってみせる。そんな様子を見ていちばんほっとしていたのは仲居さんかも知れない。
「もう、気が気じゃなかったんだから。よかった。本当によかったあ」
彼女も張りつめていたものが解けて、タカトの毛布に顔を
「お前、一度死にかけたのを助けられてるんだから、そのぶんも命を大事にしないとな」
「そうよお。もう、こっちが心臓止まるかと思っちゃった」
「それにしても、撥ねた車、そのまま逃げちゃったんだろ。ひでえな。色とかナンバーとか、憶えてないのか」
「もうナンバーどころじゃなかったから。色は赤っぽい茶色だったような気がして、警察にもそう言ったんだけど。君は憶えてる?」
スグルに水を向けられて初めてその記憶を辿ったが、ナンバーどころか色さえもろくに思い出せなかった。
「そうか。ただ、いちおう君も目撃者なんだから、あとで警察にいろいろ訊かれると思うよ」
そう言われて口には出さなかったが、もしもタカトがどうにかなっていれば、車のことを何も憶えていないことをどんなに後悔しただろうかと思った。
タカトの話では、怪我の状況だけならすぐ退院してもいいと言われたが、どのみちこの状態では夜の飲み会に参加するわけにいかないから、医者の勧めに従ってひと晩入院することにしたそうだ。
先輩が仲居さんといっしょにそのことを伝えに戻るというので、スグルを病室に残し、彼女は二人を玄関まで送った。
改めて仲居さんをよく見ると、年齢は五十に近そうだが、日本的な
そうして話をしながら玄関近くまで来たとき、妙なことがあった。それまで会話に加わっていた仲居さんの気配がふっと途切れたので、何の気なく振り返ると、その仲居さんが少し離れた後方で凍りついたように立ち止まっていたのだ。
印象的なのはその表情だった。恐怖というのではない。けれども何かにひどく驚いたような、放心したような表情だった。一瞬、どうしたんですかと尋ねるのも
こちらの呼びかけに仲居さんはすぐ走り寄り、
「すみません。私、時どきボンヤリしてしまう癖があって」
気恥ずかしそうにそう言い訳をしたが、二人を送り出し、病室に戻ったあとも、あの何とも言えない表情は胸の片隅にひっかかって残った。
〈第2回へつづく〉
▼竹本健治『狐火の辻』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321909000204/