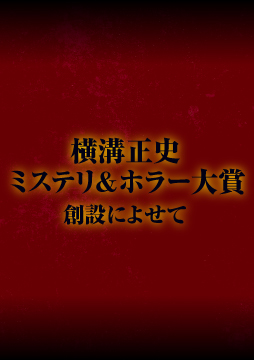杏子の夜道恐怖症を克服させようと試行錯誤する遼一だが、杏子は次第に本気で「記憶屋」を探し始めて――。
>>前話を読む
◆ ◆ ◆
携帯が鳴って、我に返った。
真希からのメールだ。「昨日のサッカー録画してたら貸して」。取りに来い、と返信してやる。
真希は五分もしないうちにやって来た。DVDを渡してやると、嬉しそうに受け取って礼を言う。
何気なく時計を見るともう十一時過ぎだった。こんな時間に、男の部屋に女子高生が一人でDVDを借りに来るのもどうかと思うが、そこは幼なじみとして信用されているということなのだろう。
(十一時、……澤田先輩は出歩けない時間帯だな)
真希が無頓着なのか、それとも杏子以外の女の子はこんなものなのか。
ついでとばかりにCDの棚を物色している真希を眺めながら、ぼんやりと思う。
「……おまえさ、記憶屋って」
「え?」
知ってる? と、続ける前に、振り向いた真希を見てはっとした。しまった、ぼんやりしすぎた。不用意だった。
「……や、何でもねえ」
ごまかして、雑誌を開く。おまえCD選んだらさっさと帰れよ遅いんだから、と言うつもりで再び口を開きかけたところで、
「記憶屋? って、記憶消してくれるっていうあれ?」
あっさりと返ってきた答えに、思わず顔をあげた。
「知ってるのか」
「女子高生なら誰でも聞いたことくらいあるんじゃないの? 皆そういう話好きだし」
何でそんなこと聞くの、と真希は怪訝そうだ。
遼一は雑誌を閉じた。
「それ、いつ頃から流行ってんの」
「さあ……去年か一昨年くらいじゃないかな。あ、でも昔おばーちゃんたちが言ってたよね? 似たような話。リバイバルされたんじゃない?」
「ストーリーとかあんの?」
「えー……存在そのものが伝説なんじゃない? ストーリーは知らない。あ、でも、イタズラで記憶屋を呼び出した子が記憶消されちゃったとか、そういうのはあったかなあ」
そこで「被害者」が登場するわけだ。しかし、随分曖昧な被害像だった。
「他には?」
「駅の伝言板にメッセージ書いとくと記憶屋が来るとか、公園のベンチで待ってると会えるとか、けっこう色々聞くけど」
やはり、細部が追加されることはあっても、中心となるストーリーがない。自分が被害者になるのではという危機感を感じない。
「記憶屋に会ったって子とか、いねえの?」
「いないよー。だって記憶屋に会ったら、記憶屋に会ったって記憶も消されちゃうんだよ? 覚えてるわけないじゃん」
「……じゃあどうして噂が広まるんだよ」
「そこはそれ、都市伝説だから……とか?」
「理由になってねえって……」
そもそも都市伝説はそういう不確かなものだから、真剣に検証する方が馬鹿馬鹿しいのだが。
一度閉じた雑誌を、再び組んだ膝の上で開く。と、思い出したように真希が声をあげる。
「あ! でも、西高の子が、記憶屋に記憶消された子と友達……とか聞いた気がする。何か、失恋して、元彼のこと忘れたいって、記憶屋探してた子がいたんだって。皆本気にしてなかったんだけど、結局その子、いつのまにかすっかり元彼のこと忘れてて、自分が記憶屋探してたことも覚えてないんだって」
「……あるじゃんストーリー。早く言えよそれを」
「え?」
「こっちの話」
しかし、だとしたら、やはり記憶屋伝説というのは、「記憶屋という怪人」の目撃談ではなく、「人が、忘れるはずもないことを突然忘れる」という不思議な現象に、記憶屋という原因をくっつけただけのものだ。「ドクター」は、記憶屋を「怪人系」の都市伝説だと言っていたが、主役であるはずの怪人像がはっきりしないという点で──その性質上仕方がないことかもしれないが──記憶屋は異質なのかもしれない。
「ネットより口で伝わる話の方が色々あるって意外だな。ちょっと興味あって、さっきサイト見てたんだけど、そんなに詳しく載ってなかったぞ」
「そりゃ、もともとこういうのって口コミで伝わるもんでしょ?」
そうは言っても、このネット社会において、リアルの口コミによる情報が一番多く、早いというのは気になるところだ。ということはやはり、記憶屋は、局地的に流行している、かなりローカルな都市伝説ということだろうか。
「一応念のために確認しとくけど、その西高の子っていうのが誰なのかとかは、わからないんだな?」
「うん。でも、確かな話だって」
「確かじゃねえだろ、誰かわからないんだから」
どこかで聞いた、誰かが会った。それならばどうにかして辿っていけるはずなのに、何故か噂のもとには行き着かない。都市伝説のセオリーだ。
十年以上前に近所の老人たちに聞いたのを別にすれば、遼一は杏子から聞かされるまで、記憶屋の噂を耳にしたことはなかった。しかし、女子高生の間では知られているらしい。起承転結もない話なのに、何がおもしろくて流行しているのか、遼一には理解できない。遼一にはわからない何かが、彼女たちの心にヒットしたのかもしれない。
「ね、遼ちゃんはどう思う? 記憶屋。いると思う?」
いつもは女子高生の間の噂話など鼻で笑って相手にしない遼一が、珍しく自分の守備範囲の話題に興味を持っているらしいと知って、真希は嬉しそうに訊いてくる。床に手をつき、身を乗り出すようにして、デスクチェアに座ったままの遼一を見上げた。
「いるとかいないとか議論するレベルじゃないだろ。ありえねえし」
「えー、夢がない! いたらいいなーとか思って気になってたんじゃないの?」
記憶を消す怪人のどこに夢があるのだ。女子高生は謎だ。
「現実的に考えたら、記憶なんて消そうと思ってほいほい消せるもんじゃないし、消していいもんでもないだろ」
「そーかもしれないけどぉ」
これ以上の情報は得られそうもない。それに、あまり真希が記憶屋の話に興味を持つのも、なんとなく嫌な気がした。もう話は終わり、と態度で示すため、わざと冷めた口調で言う。
不満そうな真希に、半分背を向ける形で再びデスクに向かった。
「おまえもう帰れ。若い娘が、深夜に男の部屋に長居するんじゃありません」
「うー……はあい」
しぶしぶ立ち上がり、DVDを片手で胸に抱くようにして出て行く。
母親と真希が、「気をつけてね」「お邪魔しました」と言葉を交わすのが聞こえた。
窓を開け、一応、真希が無事に斜め向かいの家に入っていくのを確認する。自宅のドアを開けたところで真希が気づいて、こちらに向かって手を振った。
窓を閉め、ついでにカーテンも閉めてから、Macに向き直る。
都市伝説関係の掲示板を覗いてみたが、記憶屋に関する書き込みは見つからなかった。
「マイナーでローカルな都市伝説……か」
一部の人間だけに伝わる話には、もしかしたらと思わせる信憑性がある。話そのものは馬鹿馬鹿しいほど作りごとめいているのに、何故か気になって仕方がなかった。
杏子も、そうだったのだろうか。
記憶屋という、子どもだましの都市伝説に、何かを感じたのだろうか。
真っ暗な帰り道、どこへも行けなくなっていた杏子。
噂の中の怪人が、一筋の光のように思えたのだろうか──それが、溺れる人の前に浮く一本の藁よりも、まだ頼りない光でも。
実在するわけもないと、杏子自身も、本当はわかっているはずだ。わかっていて、そんなものに縋るしかないことが問題なのだ。
「……ていうか、まず俺を頼れって話……」
ぐしゃぐしゃと片手で前髪をかきまわした。
架空の怪人よりも頼りにされていない、という現実に多少落ち込む。
根深い問題らしいから、会って数週間の自分を頼れというのは難しいかもしれない。それを考えれば、仕方ないことかもしれないが。
そうだとしても、藁にも縋る思いだというなら、自分にだって縋ってくれてもいいのではないかと、思うのだ。
(そりゃ、俺は天才脳外科医でも催眠術師でもカウンセラーでもないけど)
いくら探しても見つかるはずもないと、わかっているものを探し続けるよりは、目の前にいる自分を見てほしい。少しくらいは頼って欲しい、一緒に悩むくらいしかできなくても。
いっそ気が済むまで探させた方がいいのかもしれないと、頭ではわかっている。杏子が、存在しない記憶屋を探し疲れて、自分自身で少しずつでも変わっていくしかないのだと気づくまで待てばいい。もしかしたら杏子自身、簡単な方法などないのだと自分を納得させるため、形だけ探しているにすぎないのかもしれない。
どうせ、見つかるわけがない。そんなことはわかっていた。自分も、おそらく、杏子も。
それなのに、何故か胸のあたりでわだかまる、この不愉快な焦燥感は。
*
杏子は、あまり学生ラウンジや食堂に顔を出さなくなった。一緒にとっていた講義が休講になったせいもあり、三日ほど姿を見ていない。さすがに心配になって、彼女の友人に訊いてみた。
杏子は最近図書館に籠もって調べものをしているらしい。昼食時に探しに行くと、一番奥の席で山ほど本を積み上げてメモをとっている彼女を発見した。
「飯食わないんすか?」
そう訊いたら、もう食べたから、とすまなそうに断られる。
少し瘦せたような気がした。積み上げられた本の後ろにカロリーメイトの空き箱を見つけたが、見なかったふりをする。
「先輩今日、これから講義入ってます? 俺もう終わりなんですけど」
「あ、うん……あたしも今日はフリーだけど、この後用事があって」
盗み見た背表紙には、統一性のあるタイトルが並ぶ。「現代都市伝説」「消えるヒッチハイカー」「都市の怖い噂」。
それらを遼一の目から隠すようにかき集め、杏子は立ち上がった。
「用事?」
「明るいうちに行かないと。ほらあたし、暗くなったら出歩けないし」
苦笑しながら言うのが痛々しいような気がして、胸の奥に苦いものが湧く。
本の上に重ねられたルーズリーフのメモから、「伝言」「緑色のベンチ」「公園」「人目を避ける?」といくつかの走り書きだけが読み取れた。
「……どっか行くんですか? 帰り、遅くなるかもしれないなら俺つきあいますけど」
「ううん、暗くなる前に帰る。ありがと。一人じゃないと会えないかもしれないし」
誰に? とは訊けずにいるうちに、杏子は本を抱えて貸し出しカウンターへと歩いていってしまう。
立ち尽くし見送った。
ふいに、じわりと恐怖が背中を這い上がった。
(何だこれ)
自分が何を恐れているのか、わからない。
後を追って図書館を出たが、杏子の姿は、もう見えなかった。
〈第5回へつづく〉
▼織守きょうや『記憶屋』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321506000128/