夢幻の街 歌舞伎町ホストクラブの50年
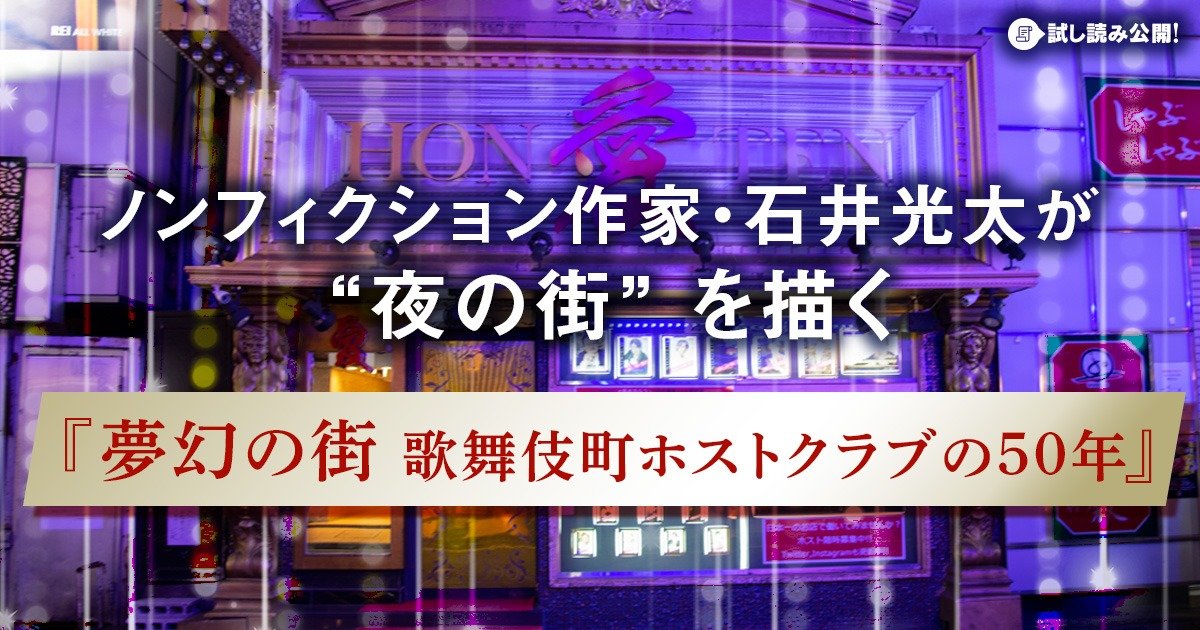
【歌舞伎町ホストクラブ激動の50年史】 華やかなだけではない“夜の街”の真実を描く! 石井光太『夢幻の街 歌舞伎町ホストクラブの50年』#3 愛本店
新型コロナウイルス流行の震源地とされ、“夜の街”と呼ばれた新宿歌舞伎町。虚構と真実の入り混じる街で、ホストたちはどんな半世紀をたどってきたのでしょうか。
ホストブーム、浄化作戦、東日本大震災、愛田武の死、そして新型コロナ……今まできちんと描かれることのなかった激動の半世紀に、ノンフィクション作家の石井光太さんが迫った『夢幻の街 歌舞伎町ホストクラブの50年』。9月25日発売の書籍を一足先に公開します。
――これは、生きる場所を求めて歌舞伎町に集まった若者たちの、泡のように儚い夢と重い現実の物語である。
―――――
第一章 「愛」の時代
愛本店
昔も今も歌舞伎町のホスト街の〝大門〞は、ゴジラ像がそびえる新宿東宝ビル(旧新宿コマ劇場)の裏の歌舞伎町花道通りに立つ五メートルほどのホストの看板だ。
ネオンが輝きだす午後七時頃から、どこからともなく若い女性たちが外灯に群れる蛾のように看板の前に集まって、店を物色しはじめる。ホストも店から出てきて、女性たちに声を掛ける。
「イケメンいかがですかー」
「三千円で飲み放題うたい放題っすよ」
路上での客引きは禁じられているので、すれ違いざまに囁くように言う。女性がそれに乗せられて看板の先に進めば、無数のホストクラブが蜘蛛の巣のように建ち並び、獲物を待っている。
歌舞伎町のホスト街は意外に狭く、実際は歌舞伎町二丁目の、三、四百メートル四方ほどのラブホテル街の一部を占めているにすぎない。だが、そこに密集する雑居ビルは、地下から最上階までホストクラブで埋めつくされており、分厚いドアの奥からBGMが重低音で響いている。
ここがホスト街になったのは、一九七三年にできた愛本店を中心に店が放射状に増え、広がっていったためだ。今あるホストクラブの大半は、愛本店から枝分かれしてできた店か、真似てつくられた店と言っても過言ではない。すべてのホストクラブは遡れば愛本店という源流にたどり着く。
昔から、ホストクラブにやってくる女性客の大半は、夜の街で働く女性たちだった。歌舞伎町花道通りや区役所通りを挟んだ隣の区域には、キャバクラや風俗店が林立していて、仕事が終わればいつでも遊びに来られるようになっている。ホストクラブは、そうした夜の女性たちを栄養分にして成長してきた。
とはいえ、初期の一九八〇年代にはホストクラブの数は今より圧倒的に少なかった。ホストクラブの看板は、看板屋による手描できあり、主要な店は愛本店の二号店である「ニュー愛」の他、「国際」「千扇」「シルクロード」「キャッツアイ」「夜の帝王」の七店。それ以外には無許可営業の小型店が何軒かあるくらいで、いずれも暴力団と濃厚な関係を持っていた。
一九八六年、十九歳の細身の男が、絵看板の前を通り過ぎ、面接のために愛本店へと入っていった。本名は戸塚孝司、源氏名は零士。十一年後にマスメディアにNo.1ホストとして登場し、両手でワニの口の動きを真似て「ガブガブいっちゃうよー」という言葉を流行らせて、ホストクラブの存在をお茶の間に広めることになる男だ。
零士は静岡県掛川市の生まれだった。複雑な家庭で生まれ育ち、高校を一年で中退してからはテキ屋の下で働いたり、バーで水商売をしたりして生き抜いてきた。時代はバブルの隆盛期であり、同級生たちは次々と一流企業に就職していった。このままでは細々と水商売をつづけていくか、暴力団組員になるしか道は残されていない。
鬱屈していたところ、たまたま深夜番組のホスト特集で愛本店が映っているのを目にした。東京にはホストクラブという商売があるんだ。ここなら学歴も職歴もない自分でも受け入れてもらえて、同級生に負けない金持ちになれるんじゃないか。そう考えて上京することを決めた。
愛本店での面接では、社長の愛田武が直に対応した。当時四十六歳。黒髪にパーマをあてて口髭を生やし、眼鏡は金縁、指輪には巨大なエメラルドがついている。武は、静岡なまりの零士に細かいことは一切訊かず、ニヤリと笑って言った。
「住むところを決めて、スーツとネクタイを用意してもう一度来なさい。そしたら、うちで面倒を見てあげるから」
武は、若者がホストを志して訪ねてくれば、誰も彼も受け入れていた。零士は武の懐の深さに感謝し、当時乗っていた車を売り払い、その金で板橋区の安いアパートを借りてスーツを新調した。
愛本店では、十代後半から二十代半ばを中心とした八十人くらいのホストが働いていた。ゆったりめのダブルのスーツに黒い革靴で身を包み、髪はポマードでガチガチに固めるというヤクザのようなスタイルだ。校内暴力が全国的な問題となり、暴走族が社会現象となっていた時代、ほとんどが硬派を売りにした不良上がりの者か、親の借金や貧困が原因で家庭から逃げ出してきた者だった。
店は、一部(午後七時〜午前零時)と、二部(午前零時半〜午前六時半)にわかれて営業していた。客層はまったく異なり、一部に来るのは社交ダンスを目的としたお金持ちのマダムで、二部は仕事を終えた風俗嬢が主だった。
零士は言う。
「愛は二部制での営業だった。一部は社交ダンスが中心でホストは二十代半ばから上で二十人くらいいた。二部は酒と接客が中心で、ホストは若手ばかりで六十人くらい在籍していたよ。
店の花形は、圧倒的に二部のホストだった。こっちの方が売り上げを出せるからな。二部でがんばって指名客をたくさん手に入れて、店でベスト10くらいに入れれば、二十五歳を超えてもホストとして重宝してもらえる。逆にそうなれなければ、クビを宣告されるか、一部に回って社交ダンスの世界で生きるように命じられる。
だから、二部の若手ホストは一部のことを『ホストの墓場』なんて呼んでいた。そこで働いているのはホスト崩れか、ババアを相手に社交ダンスをしているダサい連中だって考えだったんだ」
愛本店が二部制を取っていた背景には、ホストクラブの成り立ちと関係している。
ホストクラブは、東京駅八重洲口前にあった「ナイト東京」から誕生したと言われている。一九六五年に、オーナーが閉店したグランドキャバレーを改装して、女性がステージで社交ダンスを楽しめる店をオープンしたのである。
主要な客層は富裕層のマダムたちで、社交ダンスを踊るのを目的として集まっていた。店の奥には男性ダンサーが多数待機しており、マダムはその中からお気に入りを選んで踊りのパートナーに指名する。マダムはその男性ダンサーにおひねりを渡す他、休憩の際に飲み食いをさせる。
ナイト東京の男性ダンサーは店に雇われているのではなく、「場代」と呼ばれる入場料(一九七〇年頃で一カ月七千円ほど)を自分で払って店に入り、マダムからもらう金で生計を立てていた。
こうしたことから、男性ダンサーにとって生活をしていくのは決して容易いことではなかった。マダムから指名がかからなければ場代だけ払って赤字になってしまうし、おひねりとて金額が決まっているわけではない。ごく一部の人気者以外は食べていくのもやっとだった。
やがて男性ダンサーの中には収入を安定させることを目的に、ナイト東京を真似た社交ダンスの店をつくる者が出てきた。これまでに知り合ったマダムを客として引っ張り、飲食もセットで提供すれば、飲食費、おひねり、それに他の男性ダンサーから徴収する場代まですべて自分のものにできる。こうしてつくられた小型の店が「女性専用クラブ」と名乗って増えていき、ホストクラブの原型になっていった。
愛田武もこうした店でホストとして働いていた一人だった。一九四〇年、新潟県北蒲原郡中条町で九人きょうだいの六番目に生まれた彼は、経済的な理由から中学卒業後間もなく農家へ養子に出された。義親の命令は絶対であり、夜明けから日没まで大変な農作業に明け暮れなければならない日々がつづく。武は将来に絶望し、ある日夜逃げして東京へ向かった。
東京ではまず寝具販売会社でセールスマンをして貯金をつくり、二十代の半ばからそれを元手に防犯器具会社やカツラ会社を起こした。だが、事業はものの見事に失敗して、多額の借金を背負う。武は今さら新潟の家に出戻るわけにいかず、途方に暮れた。
友人がそんな武に言った。
「ホストって知ってるか? 女性専用のクラブで女性を接待する仕事があるんだ。おまえ、話がうまいから合ってるんじゃないか」
ホストは無一文でも実力次第でのし上がれるという。武はホストになって再起を果たすことを決める。
武は二十八歳で「ロイヤル」という店に入った。格別ハンサムというわけではなかったが、話術が抜群に上手だったことから、すぐにエースへと成長していった。引き抜かれる形で渋谷にあった「ナイト宮益」、先述の「ナイト東京」を経て、一九七一年に独立して新宿二丁目に自らの店「愛」、翌年には二号店「ニュー愛」をオープンさせた。歌舞伎町の愛本店は、そのまた翌年に拡大移転した店だった。
七〇年代から八〇年代にかけて、こうしたホストクラブは社交ダンスを目的とする場からアルコールを飲みながら男性から接待を受ける場に変貌を遂げつつあった。だが、老舗は歴史的な経緯から、店内にはかならず社交ダンス専用のステージを設置して、それを楽しみにしている女性客を一定数抱えていた。愛本店が営業時間帯の一部を社交ダンス用、二部を飲食を伴う接待用にしていたのは、その名残だ。
現在でこそ、ホストクラブは飲食業として広く認識されているが、当時は風俗などと同じアンダーグラウンドな仕事と考えられていた。女性客がホストクラブに通っていることを口外するなんてありえなかったし、男性もホストであると名乗ることはなかった。この時代にホストクラブで働くのはどんな人々だったのか。
零士は言う。
「ホストっていうのは、表の世界で生きていけない人間がお忍びで働く空間だったんだよ。そこで数年間働いて金持ちの女をつかまえ、その金で表の世界に出て商売をするみたいな感じだな。
だからホストは明かせないような過去を持っている連中ばかりだった。施設を脱走してきたとか、ヤクザに追われているとか、同性愛者であることがバレて故郷にいられなくなったとか。重大事件の加害者だって奴なんかも普通にいた。そういう連中が源氏名を名乗って正体を隠して働ける場だったんだ。
親父(愛田武)が、何も訊かずに大勢の人間を雇っていたのは、それをわかっていたからだろ。ホストたちだってお互いのプライベートに踏み込むことはタブーだった。連絡先の交換だってしない。そいつの本名が何であり、辞めたらどこで何をしているかなんてことはまったくわからなかった。街からいなくなったら、『あいつは上がったんだな』って思うだけだ」
ホストクラブはアンダーグラウンドな世界だからこそ、一般社会で生きていけなくなった人々の受け皿になっていた。彼らはそこでホストとして数年間働くことによって、金を貯めるか、パトロンを見つけてヒモになるかして、社会復帰の足掛かりをつかもうとしていたのである。
ホストクラブには、このように社会に属することのできない者たちが数多く集っていた。店は、どのようにホストたちを束ね、利益を出していたのだろう。その仕組みについて、零士は述べる。
「歌舞伎町に七店あったホストクラブは、基本的には愛の見様見真似だから同じだったと思ってもらっていい。その上で愛本店の話をすれば、店はいくつかのホストの派閥によって成り立っていた。何人かのエースホストがいて、その下に若手ホストがついてヘルプをしながら勉強をさせてもらったり、メシをおごってもらったりする。最大派閥だと二十人くらい、小さな派閥だと四、五人だ。
派閥は完全なタテ社会だな。先輩たちはみんないかついヤクザみたいな奴らばかりで、上の言うことは絶対だ。もちろん、不条理なことだってたくさんあったよ。『顔がムカつく』とか『なに立ってんだよ』とか言われてどつかれるのは毎日のことで、よその店のホストとケンカになった時は『殴り込みに行ってこい』と言われて突撃させられることもある。できませんなんて答えようものなら、逆にリンチを食らう。そういう世界が嫌なら、とっととホストなんて辞めちまえっていう雰囲気だったね」
不良グループの上下関係が、そのまま店で成り立っているようなものだったのだろう。
当時のエースホストには三種類のタイプがあった。一つが、アイドル系のホストで大勢の女性を店に呼ぶことができるタイプだ。こういうホストは一日に複数の女性客をうまくさばいていかなければならないためにヘルプにつく若手ホストをたくさん抱えるので、最大派閥になるのが常だった。
二つ目が、女性社長など一回で多額の支払いをしてくれるマダムを抱えているマダムキラー系のホスト。頭の回転の速さや、口のうまさで勝負する。三つ目が、風俗嬢を暴力などで支配して金を吸い上げる武闘派と呼ばれるホストだ。
愛本店には五台の固定電話が置かれていて、新人ホストは入店すると電話番を任されることになる。店に掛かってきた電話を受け、派閥のホストたちにつなぐ役割だ。
新人ホストは電話の取り次ぎを通じて先輩ホストたちに顔を覚えてもらい、派閥から声が掛かるのを待つ。その期間、店からは「まかない」と称される食事が出されるが、派閥に加わればホストになったと見なされて出なくなる。その代わり、派閥のトップに頭を下げて一人前になるまで食わせてもらわなければならない。
零士は電話番をはじめて五日目に、店のNo.1ホストだった檀一成から声を掛けてもらった。先の分類に当てはめれば、若手ホストを二十人近く抱える最大派閥のアイドル系ホストだった。
晴れてホストとしての一歩を踏み出したが、店内の派閥の壁は想像以上に高かった。若手はテーブルの灰皿やアイスペールを取り替えるとか、ボトルを運ぶといった役割を担っていたが、親切心から別の派閥のテーブルで同じことをしようものなら、耳をつんざく怒声が飛んできた。
「おめえ、俺らの客を盗るんじゃねえぞ!」
相手の派閥のホストに灰皿で頭を殴りつけられたり、店の外へ連れて行かれて殴る蹴るの暴行を受けたりすることもあった。他の派閥の客に手を出すどころか、挨拶をすることさえ禁じられていた。同じ店のホストでも、派閥という鉄のカーテンに隔てられていたのである。
一般的に、若手ホストが派閥で序列を上げて一人立ちできるようになるには数年の下積みが必要だった。多くの女性客に指名してもらうか、力のある客に気に入られるかしか周りを認めさせる術はない。
女性客の指名を得られるようになるには、それなりに時間がかかった。この時代は広告を見て遊びに来るような客はいなかったので、先輩のテーブルについて接客をし、その女性が連れてきた友人と親しくなって指名客になってもらうしかない(指名客が連れてきた友人等を業界用語で「枝」と呼ぶ)。だが、他の先輩ホストの力が強いので、新人ホストが枝を手に入れられることはほとんどない。
初めの頃、零士も地道に業績をつみ上げていこうとしていたが、思わぬ出来事があって周りから注目を浴びることになったという。
ある日、店の専務から「これを四谷のビルにあるスナックLのママに届けてほしい」と言われて荷物を渡された。零士は言われるままにタクシーに乗り込み、芸能事務所サンミュージックの前にあった雑居ビルに入っている店を訪れた。Lでは年配のママが連絡を受けて待っていた。零士が荷物を渡したところ、ママからこう言われた。
「愛本店の新人の子ね。ありがとう。もうすぐパパが帰ってくるから、紹介してあげるわ。ちょっとだけ待ってて」
零士が隅の席にすわって待っていると、しばらくして恰幅のいい中年男性が片足を引きずりながら現れた。両脇には美しい銀座のホステスたちをはべらしている。男性はママから耳打ちされると、零士に向かって「よく来たな、うちに寄っていきなさい」と言ってビルの別フロアに連れて行った。
その部屋には豪華なテーブルや革張りのソファーが置いてあり、豹のはく製などの装飾品が並んでいた。この中年男性は仕手筋(株を操作して利益を儲ける人)で、株で築いた莫大な財産でビルを丸ごと購入し、一部を住居として使用していたのだ。後で知ることになるのだが、ちょうど同じ年に全国で上映していたヒット映画『マルサの女』で山崎努が演じる脱税犯のモデルとなった人物だった。
中年男性は食事をご馳走してくれ、こう言った。
「愛の若い衆なら売れるまで生活も大変だろ。いつでもうちに食事をしに来ていいからな」
上京して間もなかった零士は、こんな金持ちがいるのかと感動し、言葉に甘えて翌日から家へ通いだした。明け方に愛本店での仕事を終えると、そのまま家へ行って朝食をご馳走になり、豹のはく製の脇で昼過ぎまで眠って出勤する。目を覚ましたら、なぜか家にアントニオ猪木などの著名人が遊びに来ていることもあった。
派閥のホストたちの間に、零士がこの男性と親しくしているという噂が広まったのは少ししてからだった。零士は知らなかったのだが、男性はその筋の世界では誰もが知るドンのような人物だったのだ。この一件を通して、派閥のホストたちから「零士は大物をたぶらかす才能がある」と評価されるようになった。大物に気に入られるというのが一つのステイタスなのだ。
こうして注目を浴びたことが、零士の運命を変えた。武の妻の榎本朱美に目を掛けられたのである。
〈第3回へつづく〉
※次回は9/23(水)に公開します。
―――――
書誌情報
書名: 夢幻の街 歌舞伎町ホストクラブの50年
著者:石井光太
発売日:2020年9月25日(金) ※電子書籍同時発売
定価:本体1600円+税
体裁:四六判並製・320ページ
装丁:國枝達也、カバー写真:森山大道
ISBN:9784041080238
発行:株式会社KADOKAWA
https://www.kadokawa.co.jp/product/321811001053/
目次
プロローグ 男たちの漂流
第一章 「愛」の時代
愛本店/朱美とニュー愛/暴力団との癒着/バブル崩壊
第二章 ロストジェネレーション
男の園/トップダンディー/ロマンス
第三章 革命
ロマンス黎明期/記録の男/広告革命/ホストの女/芸能人
第四章 ホストブーム
第一波/客層の変化/第二の波/仁義なき戦い
第五章 歌舞伎町浄化作戦
都知事/協力会結成/栄枯盛衰
第六章 寵児
グループ戦略/イケメン戦略/滅亡
第七章 落城
レジェンド/お家騒動/愛の買収/巨星堕つ
エピローグ 新型コロナの震源地と呼ばれて
著者について
石井 光太(いしい・こうた)
1977年東京都生まれ。国内外を舞台にしたノンフィクションを中心に、児童書、小説など幅広く執筆活動を行っている。著書に『絶対貧困 世界リアル貧困学講義』『遺体 震災、津波の果てに』『「鬼畜」の家 わが子を殺す親たち』『浮浪児1945- 戦争が生んだ子供たち』『43回の殺意 川崎中1男子生徒殺害事件の深層』など多数。



























