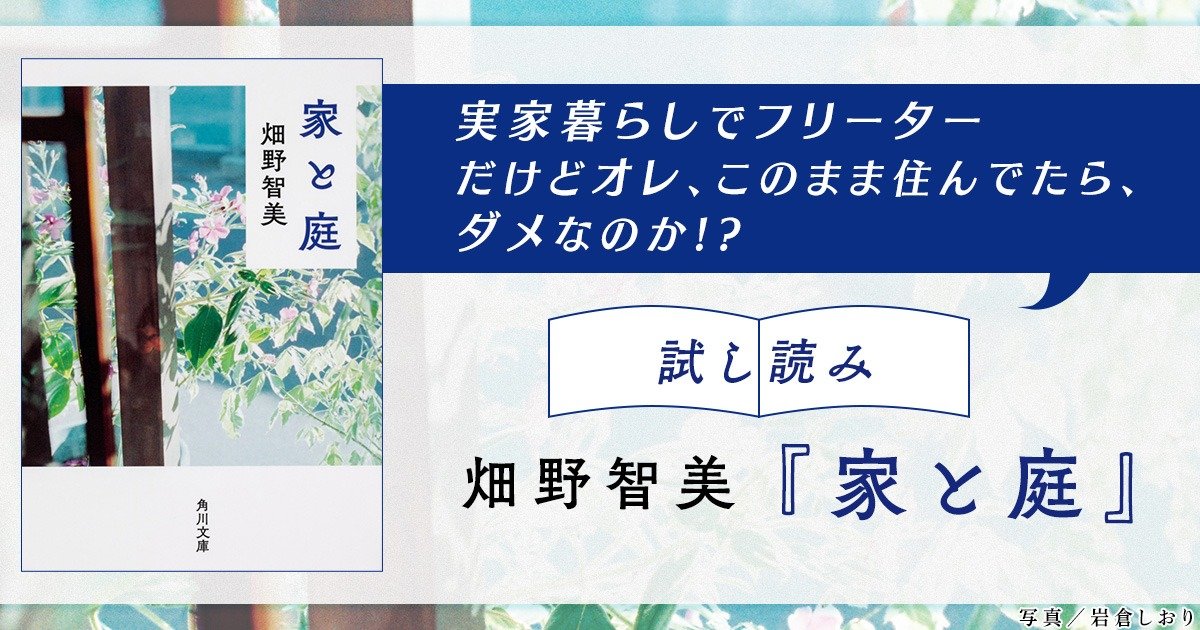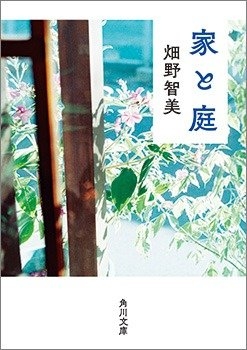好評発売中、畑野智美さんの『家と庭』は、下北沢に生まれ育ったフリーター男子・望の恋と仕事と決意の物語。本作の冒頭を4回に分けて試し読みを特別公開します。
>>前話を読む
◆ ◆ ◆
二十二時まで働いて家に帰ると、リビングでお母さんと文乃ちゃんと弥生がロールケーキを食べながら、喋っていた。
「ただいま」
「おかえり」三人が声を揃える。
葉子ちゃんとメイは帰ったのかと思ったが、
「ごはん、食べるでしょ」お母さんはソファーから立ち上がって、台所へ行く。
「うん」
洗面所で手を洗ってうがいをしてからリビングに戻り、文乃ちゃんと弥生の正面に座る。
「葉子ちゃん、なんだって?」二人に聞く。
「分かんない」嫌そうな顔をして、文乃ちゃんは首を傾げる。
弥生は困っているような顔で、首を傾げる。
葉子ちゃんは七年前、大学卒業と同時に結婚して家を出た。都内に住んでいるからメイを連れてしょっちゅう帰ってくる。しかし、一回り離れている弥生にとっては、姉妹でも仲がいいとは思えない相手だろう。そして、オレと文乃ちゃんにとっては、天敵とも言える相手だ。特に、葉子ちゃんと文乃ちゃんは子供の頃から仲が悪くて、お互いに近寄らないようにしている。
「大騒ぎしてるだけで、どうせすぐに帰るでしょ」文乃ちゃんが言う。
普段の文乃ちゃんは、おとなしくて優しい。それなのに、葉子ちゃんの話をする時だけは、口調がきつくなる。
「でも、メイの転園手続きもしてきたみたいだよ」
「そうなの?」弥生が言う。
「昼間、そう言ってた」
「幼稚園って、今は春休み?」
「そうじゃん」
オレと弥生は、壁に貼ってあるカレンダーを見上げる。
今日で三月が終わる。
幼稚園が始まるのは、学校と同じで六日か七日頃からだろう。何があって出てきたのかは分からないが、一週間で葉子ちゃんの機嫌が良くなってお
「アパートにでも、住めばいいのよ」この話はこれ以上したくないとアピールするように、文乃ちゃんはテレビのボリュームを上げる。
うちが持っているアパートは二つある。両方とも単身者向けのワンルームだ。親子二人でも狭いというほどではないだろうけれど、住人は学生やフリーターばかりだ。夜中まで騒いでいる声が薄い壁越しに聞こえるらしく、大家さんから注意してくださいと電話をかけてくる住人がたまにいる。前は、ばあちゃんがアパートの周りを掃除するついでにやんわり注意すると静かになったが、今年の初めから入院している。お母さんが注意してもいまいち聞いてもらえず、しばらく静かになった後でまた同じクレームの電話がかかってくる。
そんな所に葉子ちゃんが住むとは思えない。この家で生まれ育ち、結婚後は
「アパート、あいてないのよ」お母さんが
「今月、何人か引っ越したじゃん」
就職が決まった学生が出ていって、何部屋かあいたはずだ。
台所に戻るお母さんにオレもついていき、
「もう次の人、決まってるの」
「そうなんだ」
「でも、うちも部屋あまってないじゃん」弥生は手を伸ばし、オレの唐揚げを食べる。
「……和室か屋根裏?」
玄関を入ってすぐ右手に和室があり、左手に風呂と洗面所とトイレが並んでいる。その並びにばあちゃんの部屋がある。廊下の奥のドアを開けると、台所とダイニングとリビングになっている。和室の前の階段で二階に上がる。階段下は納戸になっている。二階は四部屋あり、文乃ちゃんとオレと弥生がそれぞれ一部屋と両親の部屋だ。二階の廊下の奥にある階段から屋根裏に上がれる。
あいているのは和室と屋根裏だけだ。和室は狭くて陽当たりが悪いし、屋根裏は広いけれど天井が低くて荷物でいっぱいだ。
ばあちゃんは入院中だから部屋があいているといえばあいているが、必ず帰ってくると家族全員が信じている。
「そんな部屋でいいって葉子ちゃんが言うと思う?」テレビを見たまま、文乃ちゃんが言う。
「思わない」オレと弥生は、声を揃える。
「わたしか望に出ていけって言い出すよ」
「文乃ちゃんには言わないだろ」
「言うよ! 葉子ちゃんはわたしの気持ちなんて考えないもん」
「大丈夫だよ。もし言われたら、オレがどうにかするから」
葉子ちゃんと文乃ちゃんは四歳離れている。文乃ちゃんとオレは一歳しか離れていない。葉子ちゃんが知っている文乃ちゃんと、オレが知っている文乃ちゃんは、きっと違う。
「望も出ていったら、駄目だからね」文乃ちゃんは手を伸ばし、オレのシャツの
「分かってるよ」
「駄目だからね」
葉子ちゃんとメイが風呂から出てきた声が聞こえて、文乃ちゃんはオレのシャツから手をはなしてリビングを出ていく。足音は聞こえないが、二階に上がったのだろう。
「どうするんだろ?」
年が離れているからか、葉子ちゃんと文乃ちゃんが騒いでオレがオロオロしている時も、弥生は冷静だ。大人みたいな態度をとることもあり、なんとなく不安になる。春休みが終われば高校三年生になるのだからもう大人だ。考えたくないが、お姉ちゃん達にもオレにも言えないようなこともしているだろう。でも、何があってもオレにとって、弥生は小さな女の子のままだ。
「葉子ちゃんに話を聞いてからじゃん」
「そうだよね」
「なんか話してなかったの?」オレは唐揚げを食べて、味噌汁を飲む。
「わたしが帰ってきた時には、文乃ちゃんとメイがリビングで絵本読んでて、葉子ちゃんはソファーに寝転がってスマホ見てた。葉子ちゃんと文乃ちゃんは、近くにいるのにわざとらしいくらい口きかないの。ごはんの時は、お母さんが宝塚のことを話してただけ」
「そうなんだ。弥生はどう思う?」
「何が?」
「葉子ちゃんがうちに住んだら」
「どっちでもいい。でも、色々と
「そうだよな」
この七年間で、文乃ちゃんとオレと弥生が作り上げてきたルールがある。話し合ったりしたわけではなくて、生活していくうちに決まっていった。それが葉子ちゃんには通用しない。メイを連れてきてくれるから遊びにくるのはいいが、ずっといると思うと鬱陶しい。
メイがリビングに駆けこんでくる。アニメのキャラクターが描かれたパジャマを着ている。
「文乃ちゃんは?」
「部屋に行っちゃった」オレが答える。
「ええー」
「なんだよ。望おじちゃんとも遊んでくれよ」箸を置き、メイを抱き上げる。
高く上げると、メイは笑うのと叫ぶのが混ざったような声を上げる。
電話が鳴る。
「望か弥生、出てくれる?」台所でお母さんが言う。
「弥生、出て」
「嫌だよ。こんな時間にかけてくるのお父さんでしょ」
お父さんは、三年前から単身赴任でジャカルタに行き、プリンター工場で工場長をやっている。毎日ではないけれど、週に三回か四回は国際電話をかけてくる。
「どっちか出てよ。お母さん手が離せないの」
「お兄ちゃん、出てよ」
「分かったよ」
メイをソファーに下ろしてから、電話に出る。
「はい、
「あっ、あの、夜分遅くにすみません。つきかげ荘の二〇二号室の
「ああ、えっと、ちょっと待ってもらえますか?」
保留ボタンを押して、受話器を置く。
「お母さん、アパートの人。つきかげ荘の森さんだって」
「森君ね。はい、はい」
手を洗って台所から出てきて、お母さんは電話に出る。
「もしもし、お電話代わりました。お風呂でしょ。今日、修理の人に電話したんだけど、来週になるんですって。今の時期は忙しいみたいで」
そこまで話し、何度かうなずく。
「そうよね。困るわよね。ここら辺は銭湯なくなっちゃったから」
またうなずく。
「じゃあ、うちに来なさいよ。すぐ近くだから。場所、分かる?」
つきかげ荘からうちまでの道を説明して、電話を切る。
うちの前の坂道を上り、突きあたりを左に曲がって最初の角を右に曲がった先に、つきかげ荘はある。その先にもう一つのアパートのげっこう荘が建っている。
「どうしたの?」弥生がお母さんに聞く。
「お風呂が水しか出なくなっちゃったらしいの」
「ガス止められてんじゃないの?」
「そうかと思ったんだけど、火は使えるみたいなのよね」
「そうなんだ」
「銭湯ないからうちのお風呂に入ってもらうから」
「なんで?」見たことがないくらい、弥生は嫌そうにする。
オレが入った後の風呂でも、弥生は入らない。正月にお父さんが帰ってきた時には、お父さんが入った後の湯船を徹底的に掃除していた。葉子ちゃんや文乃ちゃんにも似たような時期はあったし、十代の女の子はそういうことが気になるのだろう。知らない男が入った後の風呂なんて絶対に入りたくないに違いない。
「しょうがないでしょ。一週間もがまんしろって言うの」
「うちで入らなくてもいいじゃない。東北沢まで行けば、銭湯あるでしょ」
声を荒らげる弥生を見て、メイは
「一駅も先のお風呂に行けなんて言えないでしょ。森君、お金ないんだし。銭湯って四百円くらいするのよ。あら? 今はもっとするのかしら?」
「わたし、先に入るから」
リビングから出て、弥生は階段を駆け上がって二階に行き、すぐに駆け下りてくる。そのまま、風呂場に駆けこむ。
「どうしたの?」葉子ちゃんがリビングに入ってくる。
「思春期じゃん」
「遅くない?」
「さあ」最後の一個の唐揚げを食べる。
ごはんを食べ終えて片づけをしていたら、玄関のチャイムが鳴った。
「望、出て」洗い物をしながら、お母さんが言う。
「はい、はい」
三十五年前、お父さんとお母さんが結婚した時に、前の家を壊して、この家を建てた。風呂場のタイルを貼り替えたり、トイレをウォシュレット付きにしたり、洗面所の水道管を直したり、修復はしているが、新しくする必要がないと感じるところはそのままだ。だから、インターホンはない。チャイムがピンポーンと鳴るだけだ。しかも門の前ではなくて、ドアの横にチャイムがついているから誰でもうちの庭に入れる。不用心だと思うけれど、強盗に遭ったり不審者が入ってきたりしたことは一度もない。
「はい」
つきかげ荘の森さんだろうから、確認せずにドアを開ける。
しかし、そこには林太郎が立っていた。
「あっ」林太郎は驚いたのか、丸い目を更に丸くする。
「何やってんの?」
「あの、お風呂を借りに」
手にはコンビニの袋を持っていた。中に、お風呂セットと着替えが入っているようだ。
「つきかげ荘の森さん?」
「はい」
「
「はい」
バイトには森が二人いるから、シフト表にも林太郎と書く。森林太郎って変な名前ってさんざんからかい、森
「ああ、森君、いらっしゃい。ここ、すぐに分かった?」お母さんも玄関に出てくる。
「はい。でも、入っていいのか分からなくて」
「そうよね」
門から玄関まではバラのアーチになっていて、その先に家があるのが見えにくい。
「どうぞ、あがって」
「お邪魔します」
林太郎は、玄関に入ってきて靴を脱ぎ、うちに上がる。
「今、一番下の子がお風呂入ってるから、奥で少し待っててもらえる?」
「ああ、はい」
お母さんは台所に行き、オレと林太郎はリビングに行く。
葉子ちゃんとメイは、荷物とハリーのカゴを持って和室へ行った。
「本当に、お風呂借りていいんでしょうか?」林太郎は、絨毯の上に正座する。
「いいんじゃん」
「でも、なんか、東京でこういうことって、おかしくないですか?」
「なんだよ? こういうことって?」
「ご近所付き合いとか」
「東京でも、うちはこういうことするんだよ」
最近は家賃も銀行振込みだし、アパートの住人がうちに来ることは滅多にない。でも、オレが子供の頃は、家賃を手渡しで払いにきたついでにごはんを食べていく人がたくさんいて、アパートの住人同士の交流も盛んだった。うちの庭で、春には花見をやって、夏にはバーベキューをやった。お酒を飲んで騒いでいると近所の人も集まってきた。オレはそういう大人達を見ていた。
ばあちゃんがうるさい住人を注意すると静かになったのは、人間関係がちゃんとできていたからだろう。お母さんもばあちゃんみたいに、ごはんを振る舞ったりしたいみたいだが、今の住人とは引っ越しの時くらいしか顔を合わせない。あとは、電話で文句を言ってくるだけだ。
「でも、一番下の子って、妹さんですよね?」
バイト中に話したから、林太郎はうちの家族構成を知っている。
「そうだよ」
「女子高生ですよね?」
「そうだよ」
「女子高生が入った後のお風呂に入っていいんでしょうか?」
「駄目に決まってんだろ。弥生が出たら、風呂のお湯入れ替えて、オレが入った後にお前が入るんだよ」
「望さんがお風呂に入っている間、僕は何をしていたらいいんですか?」
「花見でもしてろ」
「はい」
林太郎は、窓の外を見る。
夜になると街灯があたり、桜の花はぼんやり白く光って見える。
(第3回へつづく)
▼畑野智美『家と庭』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321909000280/