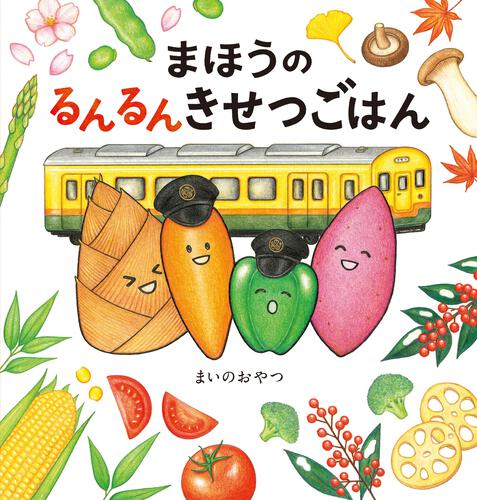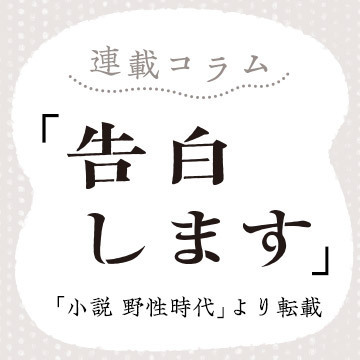8
車は、住宅街の道路を走っていた。
インパネのデジタル時計は、午前八時二十分を示している。ちらりと、すぐ横にある小学校のグラウンドを見た。青いフェンスの内側には、桜の木々が並んでいる。散った花びらが、アスファルトの道路をピンク色に染めていた。
ルームミラーを見ると、後部座席でジュニアシートに座った唯奈が、無表情で景色を眺めている。その腕には、プーさんのぬいぐるみが抱かれていた。
「もう着くよ。……今日はいけそう?」
「ママ……まど、開けて」
と言った。花粉が入るので嫌だったが、唯奈が言うならしかたない。運転席で操作して後部座席の窓を開けると、四月の朝陽に暖められた空気が車内に流れ込んだ。
車を校門近くに停める。振り返ると、前を見ていた唯奈と目が合った。
「着いたよ。どうする?」
もう一度訊くと、唯奈は「いく」と言って、シートベルトを自分で外し始めた。奈緒子は、ホッとして笑顔になる。腕を伸ばして、唯奈の隣の座席に置いてあったランドセルを取ると、後部座席の窓を閉めて車を降りた。唯奈の座席のドアを開けて、執事のように降りてくるのを待つ。唯奈は車から出ると、母親の顔をじっと見た。
「お迎えは?」
「いらない。今日は、ミサちゃんたちと帰る」
「そっか。じゃあ、ママおうちで待ってるね」
にっこりと微笑んだが、唯奈は笑顔を返してはくれなかった。車の中を
「……ママは、わかんなかったの? いまはもうないけど」
「何が?」
「くさくなかった?」
「車の中? え、臭かった?」
「やっぱり、ママには見えないんだね」
そう言って走り出そうとする唯奈の腕を、奈緒子は捕まえた。
引き戻して、小さな両肩を
「ねぇ唯奈。それさ、何回も言ってるけど……そろそろちゃんと教えてくれてもいいんじゃない? 唯奈には、何が見えてるの?」
丸い、大きな
「……あかずめ」
……やっぱりそれか。奈緒子は、
「あのね、唯奈。大丈夫だよ。あかずめなんていないの」
「いるよ。おばあちゃんが言ってた。あかずめは、人を閉じこめてころすんだって。“ちっそくのいえ”のおねえちゃんがそう言ってたって。だから、おばあちゃんも」
「おばあちゃんのことは、事故なの」
思わず語気が鋭くなった。
「あの人は……ママたちが車に着く前に死んじゃってたの。そうだったよね?」
唯奈は黙っている。その表情が
「……ごめん。ほら、もう行く? それともやっぱり、今日もおうちでママと遊ぶ?」
「ううん、いく」
唯奈はきびすを返した。ランドセルを揺らして走る。
しかしすぐに足を止めて、振り返った。
「……ずっとママのとなりにあったよ。くろいおうち。くるまのなか」
そう言って、運動場の方へ駆けて行った。
郁子の死から、三か月が経とうとしていた。
事件の後、奈緒子たちは東京に戻った。郁子がいなくなれば、冠村に
村を出てからも、唯奈は不安定だった。ときどき何もない空間をぼんやり眺めていたかと思うと、「くさいにおいがする」と訴えることが何度かあった。それだけでなく、トイレや浴室や車の中に入るのを嫌がるようになった。最近は落ち着いてきたが、東京に戻った直後は、日常生活もままならないほどだった。
車の外から後部座席を見ると、ジュニアシートの上に、プーさんのぬいぐるみが座っていた。
……あの日、唯奈が“窒息の家”に行った理由は、やはり、郁子にプーさんをそこに忘れたと聞かされたからだった。りゅうじくんに「あくま」だと吹き込まれても、あのぬいぐるみを手放す気にはならなかったのだ。
“窒息の家”に行った唯奈は、何とたった一人であの大広間までたどり着いたそうだ。
〈おねえさん〉はにっこりと微笑みかけ、手招きした。その笑顔に恐怖心が少しだけ和らいだという唯奈は、襖を閉めて〈おねえさん〉に近寄ろうとした。
しかし、その直後に〈おねえさん〉は消えてしまい、あたりは真っ暗になった。パニックになった唯奈は慌てて大広間から出ようとしたが、襖が開かなかったらしい。戸惑っていると、家全体に漂っていた腐臭――唯奈はただ「くさいにおい」と言っていたが――が強くなり、どこからか「がりがり」という音が聞こえたらしい。これに関しては、何の音なのかよく意味がわからない。とにかく、恐怖のあまり大声で泣いていると、しばらくしてから奈緒子が入ってきたという。
だが、奈緒子には唯奈が泣き叫ぶ声など、一切聞こえなかった。
郁子のときもそうだった。車内の声も音も、全然外に漏れていなかった。
そして、開かなくなった襖。今さっき、唯奈から聞かされたことにつながる。
あかずめは、人を閉じ込めて殺す。
恐らくあのとき唯奈は、殺されかけていたのだ。あかずめに。
〈おねえさん〉――あの、セーラー服の女の子に。
すでに唯奈の後ろ姿は見えなくなっていた。
奈緒子はドアを開けて運転席に乗り込むと、車を発進させた。
ラジオからは、機械音声じみたアナウンサーの声が流れている。
『――東京都
続く言葉は、想像したとおりだった。「介護疲れ」「うつ状態」「包括的な支援体制が求められる」――少し前までならどこか
殺した方につい同情してしまう。「頑張ったんだよね」と共感してしまう。
もちろん、彼らのしたことは間違っている。愚かしいことだと思う。
それでも、心は揺り動かされてしまう。
奈緒子は、母が残したメッセージを思い出した。
郁子が亡くなる一日前、ベッドの枕元に置かれていた
なおこへ
かえって きたときは うれしかった
たくさん めいわく かけました
このいえは いきぐるしい
あとは じぶんで なんとかします
あの、ミミズがのたくったような字が目に焼き付いて離れない。「感謝」と「謝罪」、そして最後の「決意」。その三つに挟まれた「いきぐるしい」という言葉こそ、母の本音のような気がした。
あれを読んだとき、母が自分と同じ、感情のある人間だと思い出した。
食べて、寝て、
いらいらした娘と、
母もまたそんな家を「息苦しい」と感じていたのだ。
だから彼女は、自ら“窒息の家”に向かった。
理性を取り戻しているうちに、これ以上、娘と孫の負担にならないように、自分自身を「なんとか」しようとしたのだろう。
だとしたら、彼女が最後に見せた表情――あれは、会心の笑みだったのだろうか。ようやく娘を自由にしてやれることへの喜びから表れたものだったのだろうか。
それとも――
赤信号につかまる。停車しているとふいに、ある男性の声がよみがえった。
「――すると、ええと、あなたが車に戻ったとき、郁子さんはすでに亡くなられていたということですか」
事件から数日後に家を訪ねてきたのは、スーツ姿の、すらりとした若い刑事だった。初めて見る顔だ。奈緒子は、ひどく驚いていた。“窒息の家”で起きた事件については疑いがかからないと、山路が言っていたからだ。
「……何度も申し上げたとおりです。これ以上お話しすることはありません」
「しかしですね、郁子さんのご遺体には、いくつか不可解な点があるんですよ」
若い刑事は、ボロボロの黒い手帳を片手に食い下がる。
チラリと見ると、門の外にはもう一人、黒いコートを着た、刑事と
しかたなく、奈緒子は会話を続けるしかなかった。
「郁子さんのご遺体には、首を絞められたり、口や鼻を
「おかしいと思います」
「え?」
「何か、理屈では説明がつかない……不思議なことが……あの家では起こるんだと思います。でも、私にはわかりません」
奈緒子に言えるのはそれだけだ。それ以上のことは知らないし、知ろうとも思わない。あの家のことは一刻も早く記憶から消し去りたい。
失礼します、と玄関扉を閉めようとした。
けれども、刑事が足でそれを阻止する。
「ちょっと、待ってください」
「帰ってください。あの家については、もうお話しできることはないですっ」
「では、あの家でなく、この家で起きていたことの話をしましょうか」
「……どういう意味ですか?」
「郁子さんのご遺体には、いくつか不可解な点があると言いましたね」
「だから、私は全然」
「本当にご存じないんですか?――どうして郁子さんの身体が痣だらけだったのか」
奈緒子は、全身から汗が噴き出るのがわかった。
唇を
「は……母は認知症でしたから。暴れたり、ふらついたりして、その、家の中で身体をぶつけることがよくありました。だからだと思います」
淡々と答えるつもりだったが、本物の刑事を目の前にして、動揺を隠せなかった。
「そうですか。じゃあ、
刑事は、
「そ、それは……」
「手首と足首にはきつく縛られたような痕がありましたし、爪は無理やり
「だからそれは!」思わず声が大きくなる。「……だから、あ、暴れるんですって。動物を相手にしているようなものなんです。うちには小さい娘もいて、だから、そう、それに、本人のためでもあったんです。ベッドから落ちたら危ないから。だから、だから……止むを得ない場合もあるでしょう?」
まるで懇願するような口調になる。
安全圏から
こんな、本当の意味での人生の苦労を知らない若造に。仕事さえしていればいいような奴に――どうして私が見下されないといけないのか。
「こっちだって、必死だったんです。あなたにはわからないでしょうけど」
刑事は、手帳をぱたんと閉じた。
「――最低だな、あんた」
プッと短いクラクションが鳴った。いつの間にか信号が青に変わっている。
緩やかにアクセルを踏むと、車は動き出した。
……初めて母に手をあげたのは、村に引っ越して一か月が経ったある日のことだ。
離婚の解放感と帰郷の喜びはすっかり消え
晩ご飯のシチューを、郁子がひっくり返したのだ。熱々のシチューを腕にかけられて、怒りが一瞬で沸点に達した。ほとんど反射的に、彼女の頭を思い切り
幼子のように泣く母を見て、ほんの少しだけ気分が晴れた気がした。
だが、すぐに罪悪感で胸がいっぱいになる。
もう二度としない。
そう誓ったのに、一度してしまうと歯止めが利かなくなった。
それから、気に入らないことがあるたびに体罰を与えた。殴る、
言葉で通じないなら身体で覚えさせるしかない。これは、母と私の新たなコミュニケーションだ。
そう自分に言い聞かせて、どれだけ母を傷つけただろう。
オムツをせずにベッドで漏らしたときは、後頭部を
お
ろくに散歩に行かなかったのは、村人たちに痣を見られるのが怖かったからだ。
一人で“窒息の家”に行った翌日からは、ビニール
唯奈がいなくなったとき、こっちは居場所を尋ねているのに、足が痛いの何だのと無関係なことを言い始めたときは、本当にどうにかしてやりたいと思ったものだ。
今思えばおかしくなっていたと思う。離婚、環境の変化、シングルマザーとして子育てをする重圧、そして介護のストレス……それらが自分をおかしくしたのだ。
そうでなければ、実の親に暴力なんて。
母が最期に見せた笑みを思い出す。あれはもしかしたら、奈緒子を解放できることへの喜びではなかったのかもしれない。
むしろ逆――娘の暴力から解放されることを喜んでいたのではないだろうか。
マンションの駐車場に着いた。
エンジンを切って、深い溜め息と共にシートにもたれる。
……こっちに戻ってきてから、あの刑事は姿を見せていない。どこの所属か知らないけれど、所轄が違うのか、
被害者である母はもういない。窒息死の件でも、奈緒子を裁くことなどできないはずだ。あれは、あかずめがやったことなのだから。
あかずめ――
“窒息の家”に巣くう、人を閉じ込めて殺すお化け。
笑みがこぼれた。冠村にいた三か月は、まるで長い悪夢を見ていたかのようだ。
そして振り返ってみれば、全てが
悪夢は、眠っているときは恐ろしいけれど、目覚めてしまえば何ということもない。私はもう、あの家からも、あの村からも脱出したのだから。
そしてもう二度と、あの家にも、村にも、近づくつもりはない。
奈緒子は、シートから身を起こした。
これで終わりだ。もう考えないようにしよう。
そろそろパートの仕事を探そう。
唯奈と二人、幸せに暮らしていくためにも。
窓の外には春の陽射しが注いでいる。
奈緒子は助手席に置いてある
(本編では小説ならではの仕掛けもたくさん! 続きは本書でお楽しみください)
作品紹介
書 名:あかずめの匣
著 者:滝川さり
発売日:2025年03月22日
この呪い、回避不可能。あなた自身が「条件」を解き明かす、新感覚ホラー!
その怪異は人を閉じ込めて殺す。すべての真実をあなたは解き明かせるか。
冠村には“窒息の家”と呼ばれる廃墟があり、「あかずめ」という怪異の言い伝えがあった。
離婚を機に地元の冠村に戻った介護と育児に追われる女性、後輩達と“窒息の家”に足を踏み入れた大学院生、
ある目的のために「あかずめ」の呪いを探る高校生、代々呪いを受け継いできた赤頭家の女。
「あかずめ」に関わった4人の物語から、呪いの条件を見破り、死を回避せよ――。
『ゆうずどの結末』が話題を呼んだ滝川さりによる、新たな体験型ホラー誕生!
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000029/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら
著者プロフィール
滝川さり(たきがわ・さり)
1992年生まれ、兵庫県神戸市出身。2019年、「お孵り」で第39回横溝正史ミステリ&ホラー大賞〈読者賞〉を受賞して、デビュー。現在大学職員。