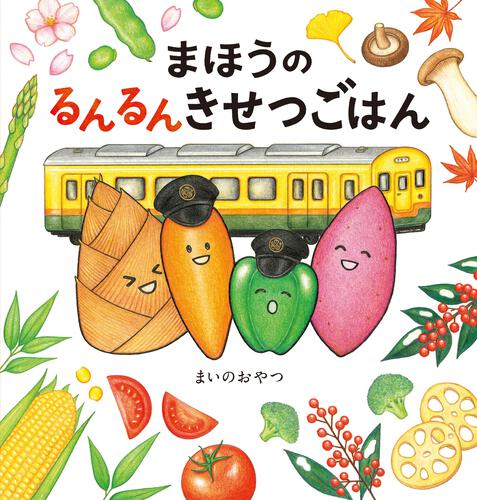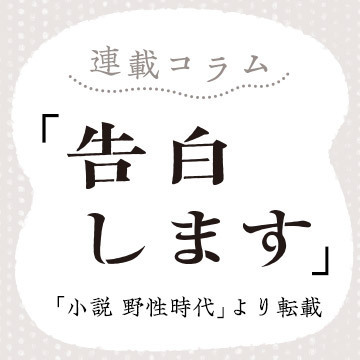7
丹頂の襖絵がある大広間。彼女は襖を開けてすぐのところで泣いていた。
「ママ……」
「唯奈!」
奈緒子は駆け寄ると、娘の身体をひしと抱き締めた。温かい。動いている。心臓の音が聞こえる。当たり前のことが奇跡のように感じられる。ここに来る前にすでに泣いていたが、涙はさらにあふれた。
「ごめんね。もう、大丈夫だから」
「あのね、唯奈ね、プーさんとりにきたの。おばあちゃんが、ここにわすれたって」
「うん、うん。わかってるよ。帰ろう」
奈緒子は唯奈を抱き上げた。唯奈は首に抱き着いてくる。その重さに驚いている場合ではない。きびすを返すと大広間から脱出し、中庭に降りた。雑草にまみれた中庭にも砂利が敷かれていて、じゃっじゃと足音を鳴らしながら内蔵の横を通り抜ける。
振り返ったのは、何かの気配を感じたからだ。
開きっ放しの襖――その奥から、人間が出てきた。
セーラー服の女の子だった。
その子は廊下に立って、じっと奈緒子たちを見ていた。悲しそうな目で。
背筋に冷たいものが走った。あれが……あかずめなのだろうか。
とにかく走った。庭を大回りして、車まで全力で駆ける。
もう大丈夫だ。そう思った矢先、奈緒子の足は止まった。
「……ママ?」
懐中電灯を車に向ける。その後部座席に、郁子の顔が見える。
ガラスに両手を突いて、大きく口を開けている。
娘と孫の無事を喜んでいるようには見えない。何かに
窓を必死に叩いている。車が揺れている。その音もしない。
奇妙なものを感じて、奈緒子の足は進もうとしない。
その顔は、必死に「出してくれ」と訴えているようにも見える。
あるいは、「こっちに来るな」と警告しているようにも。
「……おばあちゃん、何してるの?」
わからない。出たいなら出ればいい。
まるで――閉じ込められているみたいに。
郁子はますます激しく窓ガラスを叩く。その様子は、半狂乱、と言ってよかった。白髪を振り乱し、額を何度もガラスに打ち付けている。両目は完全に上転して白目を
足が動かない。助けなくては。そう思うのに、身体が言うことを聞かない。
「くろい、おうち」
唯奈が言った。
「え?」
「くろいおうちがある。くるまの中。おばあちゃんのうしろ」
黒いおうち――? 奈緒子は目を凝らした。
けれど、そんなものは見えない。
「あるってば。ほら、中から――」
そう言いかけた唯奈の顔を、奈緒子は、自分の胸に押し付けた。
「いいから、ちょっとだけこうしてて」
「でも、おばあちゃんが」
「いいから。ちょっとだけ。もうちょっとだけ」
もうちょっとで――全部終わるから。
見なくていい。祖母が窒息死するところなんて。
母親が、祖母を見殺しにするところなんて。
丸い光の中で暴れる母を、奈緒子はまばたきもせずに見つめる。
それがせめてもの、奈緒子にできる弔いだった。
思い違いをしていた。あかずめに遭遇するのは、あの家の中だけではなかったのだ。
この家の敷地全体が、あかずめのテリトリーなのだ。
母は今、あかずめに襲われている
窒息死させられようとしている。
「ママ」
「もう少しだから」
窓を叩く手が止まった。酸欠の金魚のように、口をぱくぱくと動かしている。あるいは、自分を助けようとしない娘への恨み言を叫んでいるのかもしれない。もしくは、問いかけているのかもしれない。
この罪を背負う覚悟が、お前にあるのかと。
もう少しだから。奈緒子は繰り返す。それは唯奈にではなく、自分自身に言い聞かせていた。もう少しだ。あとちょっとで……私たちは解放される。
この閉じた村から。奴隷のような生活から。
小さな黒目と目が合う。……ねぇ、もういいんでしょ? そう言ってたでしょ? やっぱり土壇場になって「死にたくない」なんて言うの? 娘の人生を踏み
奈緒子は動かない。せめて祈る。――郁子の意識が、虚空を
せめて、死の恐怖をあまり感じずに逝けるように。
そのとき――ガラス越しに見る郁子の表情が、ふっと揺らいだ気がした。
――な、お、こ……
声は聞こえなかった。唇がわずかに動いただけだ。
それが、母の最期の言葉になった。
郁子の頭はずるりと窓の下へ沈んでいった。残された右手がガラスの表面につっかえながら、しかし途中で
奈緒子は、その場にへたり込んだ。
そして、自分がずっと呼吸をしていなかったことに気づいた。
試し読み
紹介した書籍
関連書籍

書籍週間ランキング
2025年10月27日 - 2025年11月2日 紀伊國屋書店調べ
アクセスランキング
新着コンテンツ
-
レビュー
-
文庫解説
-
レビュー
-
連載
-
特集
-
文庫解説
-
試し読み
-
文庫解説
-
試し読み
-
特集