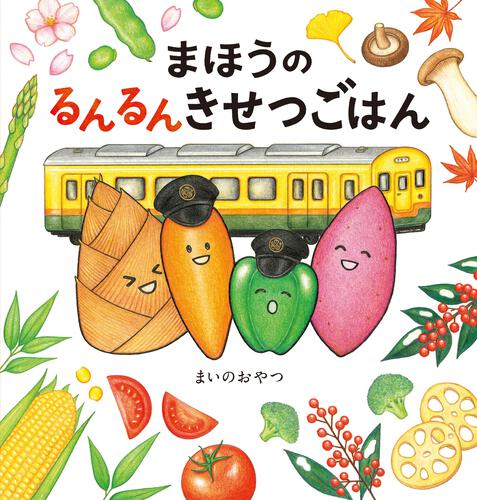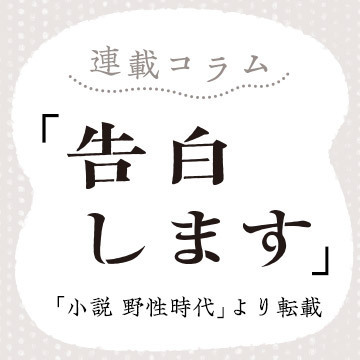3
平成十七年十二月■十一日
村民■位
■■■■で発見■■た窒■死体に■■て
日頃よ■村政の推進に■理解とご協■を賜り厚■■礼■し上げます。
さ■、去る十二月■日、■■■■に不法侵■した不 逞 ■輩 が窒■■す■とい■忌■わ■い事件■発生い■しま■■。村民■皆様■於 か■■しては、■の事件に■する根も■■ない■話に惑わ■■■ことなく、いつ■■おりの日常■過ごし■■ただき■すようお願いいたします。
また、常日頃■■注意■起して■■ますよ■に、■■■■への■近及び「■かずめ」の調■等に■■ては、絶対に■■■■ようお■いいた■ます。
な■、今後も「あか■め」に■する情報■■■す■人物を見■■た場合、そ■内容や■■人物の年齢■■らず、速■かに村■■■■■■■■お願いいたします。
以上
ある日曜日のお昼過ぎ。奈緒子は、郁子と唯奈と、三人で外に出かけた。
散歩に行くのは久しぶりだった。冠村の冬の寒さは厳しい。四方を囲む山の影響で日照時間は短く、特に冬は日中でも薄暗いことが多い。降雪量も多く、今もあぜ道の端には雪が残っている。遠くに見える山も、ところどころ白く覆われていた。――そういう気候の理由もあって、つい出不精になってしまっていた。
今日も陽射しは弱々しい。風はなく、動きのない田んぼや林の景色は空気そのものが凍ってしまったかのようだ。手袋越しにも、車椅子のハンドルは冷たい。肌が露出しないよう毛布にくるまれた郁子はまるで
車椅子の横には、ダッフルコートに身を包んだ唯奈がいる。祖母の手を握って、周りの景色を物珍しそうに眺めていた。プーさんを持っていないと思ったら、郁子の
「ありゃあ、かぁいらしねぇ」
途中、あぜ道に座り込んでいた老婆に話しかけられると、唯奈は「唯奈がかしてあげてるんだよ」と誇らしげに言った。名も知らぬお婆さんは「さよけぇ、さよけぇ」と頷き、可愛らしいと言われたのは自分だと気づいていない七歳に微笑んでいる。
散歩の途中だけどちょっと疲れて休憩中、とお婆さんは言った。見たところ、郁子とそう年齢は変わらないのに。元気そうでうらやましい。
唯奈と握手をしてにこにこしていたお婆さんは、急に真顔になって、言った。
「――“窒息の家”には、行ったらあかんで。あっこには、お化けがおるけぇ」
「……ちっそくって?」
「息ができんくなることや。
お婆さんの鬼気迫る言い方に、唯奈の顔色はもうすでに青くなっていた。
“窒息の家”――村の端にある、大きな日本家屋の
「息が吸えんと、頭もおかしゅうなってくる。死にたない死にたないって、そればっかりになるんや。わけわからんこと叫ぶ。小便も垂らす。目の前のもんをこう爪で」
「寒くなってきたし、もうお婆ちゃんとバイバイしよっか」
奈緒子は、強制終了させた。お婆さんは「ああ、せやなぁ、郁子ちゃん、寒そうにしてるわ。おじょうちゃん、今度お菓子持ってくからねぇ」と
しばらくすると、今度は大量の枯れ枝を抱えたお
「じゃあ、“おいえ”って?」
「……この村のリーダー、かな。学級委員みたいなもの」
ふぅん、と言って、唯奈はそれ以上のことは訊かなかった。奈緒子はほっとした。訊かれても答えられなかったからだ。“御家”について知っているのは、冠村で一番の名家であり、百年くらい前からこの村を仕切っている……ということくらい。苗字はあるけど、昔から村人はみんな“御家”と呼ぶ。恐れられているのだ。かつて村に存在した財閥の資産を大戦のどさくさで奪い取ったとか、黒い噂は絶えない。
すれ違った別のお婆さんがまた、「窒息の家には気ぃつけや」と唯奈に声をかける。
懐かしかった。奈緒子が子供の頃も、今みたいに村人たちが事あるごとに注意をしてきたのを思い出す。禁則事項は自然と胸に刻まれ、何よりも「誰かが見ている」という意識が根付く。都会にはあまりない光景かもしれない。
……唯奈は、ここで大きくなるのだろうか。後ろから見える唯奈の丸い頰が赤く染まっていて、大きくなったと思ってもまだまだ赤ちゃんのような気もしてくる。かつて自分が歩いたあぜ道を、娘が歩いている。
――この村が嫌いだった。薄暗い通学路も、
――なぁなぁ、知っとう?
ふと、懐かしい声が耳によみがえった。
誰だろう? 記憶を手繰る。……そうだ、中学校のときのクラスメイトだ。
夕暮れの教室。掃除当番で、二人だけで残っていたときだ。特に仲がいい子じゃなかったけれど、気まずさに耐えかねて話しかけてきたのだろう。
――あかずめ? なにそれ
――知らんねんな。教えたるわ。おれ、入院しとるひいじいちゃんから聞いてん
――うん、で、なんなん。あかずめって
――へへへ。気になる? あかずめはなぁ、言うたあかんで、あかずめは……
――おい、何しとんや
「な、奈緒子」
呼んだのは郁子だった。名前を呼ぶのは、意識がクリアなときだけだ。
「どうしたの? 寒い?」
「奈緒子、う。奈緒子。奈緒子。……ごえんなぁ」
「奈緒子。ごえんな。かぁ忍やで。おかあちゃん、あかんわ。たえれん。かぁ忍や」
毛布に覆われた小さな肩が、小刻みに震えていた。
「……何言うてん。唯奈もおんねんで」
ごめんな。堪忍や。母なりに罪の意識を抱いているのだ。
介護の負担をかけていることに。娘と孫をこんな村に閉じ込めていることに。
彼女はたまに正気に返る。そうやって殊勝な態度で謝られると、もう少し頑張らなくてはという気持ちになる。母も昔は、ご飯をこぼし、尿を垂れ流していた自分を育ててくれたのだから。……いつまでそう思えるだろうか。
車道に出かけたところで、右手から一台の車が迫ってきた。
白い乗用車で、ナンバーが「8888」だ。奈緒子は、唯奈の肩を
「ねぇ、おばさん、地元の人だよね?」
東京弁だ。東京の人だ。嬉しくなると同時に、恥ずかしかった。二か月前には自分も都会にいたはずなのに、彼女からしたら、自分はもうこんな田舎の「地元の人」に見えるんだ、と。
「訊きたいんだけどさ、あの、ち……チーソー? 何だっけ?」
女性が車内に振り返ると、運転席にいる
「そう、それそれ。ねぇ、チッソクの家、どこにあるか知らない?」
答えるべきか悩んだけれど、どうせ誰かが教えるだろう。そう思い口を開いたとき、
「――あかんで」
真下から声が聞こえた。郁子だった。
「あそこ、は、行ったあかん。近づいても、あかん。そう言われとぉ。せやから……」
絞り出すように言う。久しぶりに聞く、母親らしい厳しい口調だった。
「うわ、すご。マジで言われた!」
しかし、女性は大口を開けて、ケラケラと笑い始めた。
奈緒子がぽかんとしていると、
「だってさぁ、あるあるでしょ? 村人から『あそこに行ってはならぬ〜!』って」
そう言ってまた笑う。運転席の男も唇の端を
男女二人組は「別の人に訊きまーす」と言い残し、車を発進させた。白い排気に、唯奈がけほけほと
車椅子を押して進もうとすると、郁子が唯奈とつないでいた手を
「奈緒子、行きたい……」
「え、どこに?」
「ち……ちそくの、家」
「え?」
「あ、あ、かず、けぇ……」
何を言っているんだろう。今さっき、あいつらに「行くな」と言ったばかりではないか。奈緒子は「そうだね。今度行こうね」と受け流し、車椅子を歩道に移動させると、男女の車とは反対方向に進み始めた。
歩きながら、さっきの記憶の続きを思い出す。
……そうだ、唯奈から聞かされた「あかずめ」というお化け。奈緒子は、その名前だけは知っていた。結局、あの子からそれが何なのかを聞くことはできなかった。途中で担任の先生が教室に入ってきて、うやむやになってしまったのだ。
そして、その後、あの子と話すことはなかった。
数日後に、彼は転校してしまったから。
朝の集会で、先生がそう告げた。理由は、「急に親御さんの仕事の都合で」。
それ以上のことを、大人たちは誰も口にしようとしなかった。