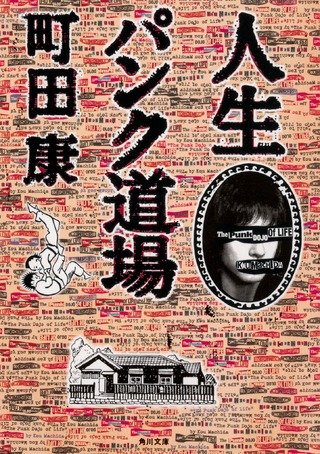夢と現実の才能の狭間でもがく、〝こんなはずじゃなかった〟私たちの人生。こざわたまこ「夢のいる場所」#1-4
こざわたまこ「夢のいる場所」

>>前話を読む
「ごめん、遅れちゃった。店上がる直前にクレーマーに捕まっちゃってさあ」
そう言って座敷に入ってきたのは、今日子だった。こうして顔を合わせるのは何年ぶりだろう。今日子はすぐに私だと気づいたらしく、「え、夢?」と目を見開く。
「久しぶり」
「ちょっと、いるならいるって言ってよ」
反応からして、今日私がここに来ることは知らなかったらしい。今日子は小走りでこちらに近づくと、
「ねえ夢、次の公演出てくれるって本当? 戻って来てくれるの?」
今日子のストレートな物言いに、口ごもってしまう。
「……うん。実は、そうなんだ。なんか、急にごめん」
「謝ることないじゃない。ていうか、また夢の演技が近くで見られるんだ。それ、すっごい嬉しい。夢、お帰り」
今日子はそう言って、右手を差し出してきた。おずおずと、その手を握り返す。
劇団アキレスと兎は、半年後に都内で開かれる演劇祭に参加することが決まっている。なんでも社会人劇団枠というのがあるらしい。前に翔太が言っていたびっくりする企画、というのはこのことだった。そして、その公演に出てみないか、と翔太から持ち掛けられたのが、一ヶ月前のこと。それからというもの、翔太からの熱烈なオファーは毎日のように続いた。
『俺絶対、面白いもの作るからさ。プロの奴らになんて負けないくらい。俺らなら、できると思うんだ。だから、あの頃みたいにもう一回だけ、俺らと一緒にやってみない?』
今日子は続けて、なんで夢が来てるって言わないのよ、と翔太の肩を小突いた。
「芸能人が来るってわかってたらもっといい店予約したのに」
「その方がびっくりするかなと思って」
「当たり前じゃん。あ、ていうかあんた、また酒ばっかり飲んでるんでしょ」
「飲んでねーよ」
「聞いてよ夢、こいつ全然人の話聞かないんだから」
二人の会話が学生時代からあまりに変わっていなくて、笑ってしまった。拓真がここにいないのが不思議なくらいだ。二人は大学でもよくこうして、
今日子と翔太は幼稚園からの幼馴染で、私と出会った時にはもう付き合っていた。それから何度もくっついたり別れたりを繰り返している。いわゆる腐れ縁というやつだ。その関係も会わないうちに少しは進展したらしく、今年から
多分、今日子が演劇畑の人間ではないからこそ続いている関係なのだと思う。今日子はそこに関して、一本線を引いている。いつだったか、今日子も演劇やってみればいいのに、という私の言葉をあっさり否定されたことがある。
『役者なんて頭のネジが一本飛んでる人のやることでしょ』
蔑みでもなんでもなく、心の底からそう思っているらしかった。学生時代も卒業してからも、今日子は演劇に関して、あくまでお手伝いというスタンスを貫いている。それは今も変わらないらしい。
昔話と近況報告に花が咲き、それからしばらくは和やかに時が流れた、ように思えた。雲行きが怪しくなってきたのは、場所を二次会のカラオケボックスに移してからだろうか。夜が更けた頃から、どうも翔太の
「……うちの上司、最悪でさ。なんでも俺に押し付けりゃいいと思ってんだよな。なにかっていうと渡、渡ってさあ。全然仕事しねーし、その癖いいとこばっかもってこうとするし。クレーム対応は渡の方が向いてるから、じゃねえよ。いい年して責任感ないとか、ほんと最悪。しかも子供いるんだぜ、あれで。笑っちゃうよ、ほんと。信じらんねえ」
翔太の話は、時々
次第に、翔太の恨み言は「演劇」や「夢を追う若者」にまで飛び火した。役者気取りのフリーター集団、なんて言葉まで使って、
「あれって親の仕送りだろ、結局。夢破れたところでリスクなんか背負ってないんだよ。ダメなら地元帰ればいいんだし、結局その程度の覚悟なんだよ。そのくせツイッターでは芝居に命懸けてます、みたいな顔してさ。ああいう奴ら見てると、腹立って仕方ないんだけど」
すると、それまで黙って話を聞いていた今日子が、意を決したように口を開いた。
「翔太、さっきから同じこと言い過ぎ。もっと楽しい話しようよ。ほら、今度の演劇祭のこととか。主催者側の人とも会えたんでしょ? なんとかっていう劇団の」
すると翔太が返す刀で、ああ、あの人ね、と吐き捨てた。
「すげえ感じ悪かったよ。お高く止まってるっつーか。俺、ちょっと前にその人の劇観に行ったんだけど。あ、そういえば夢もいたよな、その時」
その言葉に、どきりとした。どう答えていいかわからず、曖昧な笑みを返す。
「全っ然たいしたことなかったんだよな。なんかよくある女の劇団って感じ。あれなら俺達の方が面白いもん作れるし」
言いながらビールを
「つうかチケ代三千八百円ってなんだよ、たけーよ。映画二回観れるじゃん。よくあの内容でそんだけ取れるよな」
「あの劇団の主宰、なんとかっていう映画監督の娘なんだって。それ聞いて納得したわ。だって、劇場のキャパと劇のクオリティ、合ってなくね? 絶対コネだよな」
「ていうか、あそこに書いてあった演出の言葉がもう無理。
夢もそう思うだろ。話を聞いている間、ずっとそう言われている気がした。
翔太はその後も延々とその劇団主宰への
「……渡さんが言ってたのって、あれですよね。半年くらい前に、戯曲の新人コンクールみたいなので賞とった人」
ようやく静かになったカラオケボックスで、田中さんが呟いた。誰かが曲を入れっぱなしにして帰ったらしく、部屋には聞き覚えのある懐メロの伴奏が延々と流れ続けている。奥のソファでは、翔太と劉生君が酔い潰れ、鼾をかいていた。今日子は翔太をタクシーで連れて帰るつもりらしい。
「今日子さん、前からその人のこと知ってました?」
今日子はそれを聞いて、ううん、演劇祭の話聞くまでは全然、と首を振った。
「あたしはみんなほど劇に詳しくないもん。翔太は前から知ってたみたいだけど。でも、結構有名なんでしょ?」
「ですね、最近よく名前聞くんですよ。ネクストブレイクはこいつらだ、みたいな。まあそれも、渡さんの言う通りコネかもしれませんけど」
翔太がそれに同意するように、ふご、と鼻を鳴らす。すると今日子が、でもすごいよね、とぽつりと呟いた。
「実際賞とっちゃうんだもん。たしか、あたし達と同い年なんだっけ? よっぽど才能があるんだろうな。ねえ、夢はどう? その子の名前、知ってた?」
急に話を振られて、咄嗟に、どうだろ、と答えを濁した。すると、それを聞いた今日子がくすくすと笑い出した。どうしたの、と聞いてみると、
「その子ね、名前もすごいんだよ。本名らしいんだけど、ザ・芸能人って感じ」
今日子はそう言って、おかしそうに目尻を拭う。
「宝城莉花、なんて、あたしだったら名前負けしちゃうな」
「長谷川さん、あれ見ました?」
カプチーノを手にドリンクバーから戻った
小柳さんが言っているのは、某有名動画配信サービスで始まったサスペンスドラマのことだ。実際の事件を元にしていることと、テレビなんかではなかなかお目にかかれない攻めた配役、練りに練られた緻密な脚本が話題になり、SNS上ではストーリーの考察が
正直に、見ていない、と答えると、ええ、それはもったいないですよ、と小柳さんが非難めいた声を上げた。
「この世界で仕事するなら絶対に見ておくべきだと思いますよ。勉強にもなるし。小劇場関係の役者が多いみたいだから、長谷川さんなら何人か名前知ってるんじゃないかな。主人公の同僚役の女の子とか、長谷川さんと同年代のはずですし」
その子の存在は、以前から知っていた。昔、一緒にオーディションを受けたこともある。たった三年前のことだ。この三年で相手は着実にキャリアを重ね、最近ではCMなんかでも顔を見かける。たまたま
小柳さんは続けて、出演女優の一人の名前を挙げ、僕は長谷川さんにああいう立ち位置を目指して欲しいんですよ、と力説を始めた。
「あの人も、最近まではまったくの無名だったじゃないですか。それがハマり役に出会って、ちょっとずつ活動の幅を増やして。長谷川さん、今年で何年目でしたっけ。ぶっちゃけ、以前より仕事減っちゃってますよね。ピンチはチャンス。ここが踏ん張りどころだと思うんですよ」
小柳さんの主張はいつも前向きで、一切の淀みがない。だから、聞いていてすごく苦しくなる。どう考えても私が今からあの女優みたいな道を歩めるとは思えないのだ。黙っていると、小柳さんが手を上げ、ちょっと、と店員を呼んだ。
「ここ、汚れてるんだけど。ちゃんと
そう言われて見てみると、たしかにテーブルの端っこが水滴で汚れていた。前の客だろうか。店員は慣れているのか、申し訳ありません、と機械的に頭を下げて、さっとテーブルを掃除した。
「僕、こういうのダメなんですよ。仕事はきちんとやってもらわないと」
小柳さんが、誰に言うでもないトーンで、そう呟いた。
小柳さんは、二年前から私の担当につくようになった。初対面の時の自己紹介によると、私とそう年は変わらないらしい。ミーティングとスケジュール確認を兼ねて、数ヶ月に一度のペースで顔を合わせている。と言っても、私のような売れていない役者の仕事量はたかが知れていて、本題はいつも十分ほどで終わってしまう。あとは世間話がせいぜいだ。なら電話かメールで済ませればいいのに、とも思うけど、これも一応事務所の方針なんだそうだ。
「もちろんその、百人キャパの舞台もいいと思うんですけど。そろそろ次のステージを目指してもらわないと。えーと、なんでしたっけ。長谷川さんが今度出る劇。アキレスと」
「兎、です。アキレスと兎」
そう言って、チラシを渡した。
「実は今回、その劇団が都内の演劇祭に参加することになって。それで誘われたんです。結構すごいことなんですよ、社会人枠とはいえ、この並びに名前が載るのって」
演劇祭の参加リストに名を連ねているのは、主宰が映画の共同脚本に協力したり、所属俳優が深夜のバラエティ番組に出始めているなど、最近知名度が上がった劇団ばかりだ。しかし、小柳さんの目にはそれほど魅力的なメンツには映らなかったらしい。小柳さんは受け取ったチラシにさっと目を通すと、すぐテーブルの上に置いてしまった。小柳さんは元々、小劇場
『正直特殊な世界ですよね、小劇場って。学生時代、何度か誘われて観に行ったことありますけど。アングラっていうんですか。白塗りの人が舞台上で大声出したりとか、なんかよくわからない布持った役者が舞台をぐるぐる走り回ったりとか、そういうイメージですもん。面白くないわけじゃないけど、ちょっと僕には前衛的過ぎました』
炭酸の効き過ぎたカルピスソーダは、口に含むとビリビリ舌が
「長谷川さん。今僕が言ったこと、聞いてました?」
「え」
「え、じゃなくて。こっちが質問してるんですけど」
厳しい口調に、心臓が跳ね上がりそうになる。何を言われていたのか思い出そうとするより先に、すみません、という言葉が口からこぼれた。それを聞いた小柳さんが、呆れたようにため息を
「これも一応仕事ですよ、わかってます? ただお茶飲んでるわけじゃないんです。ミーティングの意味がないじゃないですか。僕だって、無為に時間を潰してるわけじゃないんです」
「この際だから言いますけど。僕、最近の長谷川さんの仕事への姿勢、どうかと思ってます」
「長谷川さんから役者としての熱が伝わってきたこと、一度もないんですよ。そんな人に仕事を任せたいって、誰が思います?」
何も言い返すことができない。席に、重たい沈黙が流れる。呆れたように天を仰いでいた小柳さんが突然立ち上がり、すみませんちょっと、と言って中座した。どうやら、電話がかかってきたらしい。正直、ほっとした。少しして、トイレ前で深々と頭を下げる小柳さんの姿が目に入った。さっきまでとは比べようもないほど朗らかな顔で、電話の受け答えをしている。通話の相手は、別の担当タレントだろうか。
戻ってきた小柳さんは、
小柳さんが置いていったチラシをもう一度手に取り、文面に目を通す。このところよく持ち歩いていたために、所々折れて皺になってしまっている。裏面に書かれた演劇祭の実行委員の名前を上から順に
ほうじょうりか。
その名前を目にする度に、あの日の記憶がまるで昨日のことのように蘇った。呪いみたいだ、と思う。莉花が私に向かって放ったナイフのような言葉。莉花はあの日も、赤いワンピースを身に
『あんたは結局、そこまでの人間なんだね』
莉花はたしかに、そう言った。立ち竦む私に、最後の一太刀を浴びせるように。
『私はこの先の未来で、全部を手に入れるよ。あんたの欲しいものも、私の欲しいものも。根こそぎ奪ってやる。後から欲しいって泣いたって、絶対分けてなんかやらないから。そうでもしなきゃ、自分の夢なんて守れない。欲しいものって、そうやって手に入れるものでしょう?』
莉花はそう言って、私を笑ったのだ。
『だって私には、才能があるんだから』
▶#2-1へつづく
◎第 1 回全文は「カドブンノベル」2020年1月号でお楽しみいただけます!