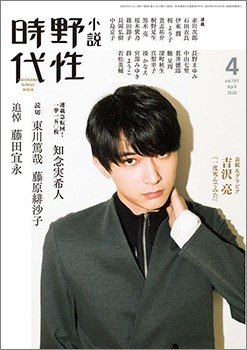【連載コラム 最終回】鉄道ファン必読。内田百閒と宮脇俊三の著作から、酒井順子が鉄道紀行の歴史を振り返る。「鉄道無常 内田百閒と宮脇俊三を読む」#20
酒井順子「鉄道無常 内田百閒と宮脇俊三を読む」

※本記事は連載コラムです。
前回までのあらすじ
鉄道紀行というジャンルを示した内田百閒が「なんにも用事がない」のに汽車で大阪に行っていた時代、普通の人にとっての鉄道は、用事を果たすために乗るものにすぎなかった。その四半世紀後、宮脇俊三は異なるアプローチでそのジャンルを背負うこととなる。子供の頃から鉄道が好きな二人は、心から鉄道旅を楽しみ、多くの紀行文を残した。女子鉄・酒井順子は百間と宮脇を比較しながら、時代とともに発展する鉄道と鉄道紀行を読み解いてゆく。
昭和二十七年(一九五二)の鉄道記念日のイベントで、
「駅長驚クコト
一栄一落コレ春秋」
というもの。
「大鏡」によると、
東京駅の名誉駅長就任を快諾した百閒であったが、しかし国鉄に対して思うところはあった。当時の国鉄総裁は、
「乗客に対するサービスなど不要」
といったことを発言しており、百閒はおおいに不満に思っていた。しかし戦後に長崎が第三代国鉄総裁となると、
「サービス絶対主義」
と、正反対のことを言い出したのが、百閒としては我慢ならない。
時代の変化とともに言うことがガラリと変わった長崎に対する思いが、「時ハ変改ス」だった。一日駅長を務めた日、駅員への訓示においても百閒は、乗客への「サアヴィス」(これは百閒の書き方)などしないでいいのだ、ぐずぐず言うような客は、
「汽車ニ乗セテヤラナクテモヨロシイ」
などと、長崎総裁への嫌味をたっぷりと盛り込んでいる。
時は変改す。
……ということを百閒が感じたのは、しかし長崎総裁の言葉に対してだけではあるまい。戦争が終わって「
百閒は、時の変改を好まない。好きなのはあくまで汽車であり、電車は嫌い。
そんな百閒は、
「肥薩線は私も一二度蒸気機関車で通った事があるが、何だか丸でお手軽になってしまって、これが新しい言葉で言う開発、古くは文明開化の一端かと痛感した」(以上『立腹帖』)
と、百閒は書いている。
「開発」や「文明開化」について、百閒は
そんな百閒にとって、何度も通った八代の
「驚クコト勿レ」
と言っていたのかもしれない。
東京駅の名誉駅長をした時のことを書いた百閒の随筆が「時は変改す」であったことを意識していたかどうかはわからないが、
それは駅長体験の最中、取手駅の本物の駅長に、宮脇が話を聞いている時のこと。駅長が、自らビラを配るなど増収のために様々な努力をしているとの話を聞いて、宮脇は例の漢詩を思い浮かべるのだった。駅長が国鉄に入った頃は「乗せてやる」の時代であったであろうに、わずか一代のうちに逆転するとは、との感慨を抱きつつ。
時は昭和六十年(一九八五)、国鉄分割民営化の二年前。百閒が名誉駅長を務めたのは、国鉄の輸送機能がほぼ戦前並みに回復した頃であり、鉄道はまだ花形の交通手段だった。しかしその後、飛行機や自動車の台頭等の影響で、国鉄は赤字に転落。負債が膨らんでいく。国鉄最後の日々、土地の名士でもある駅長が、少しでも収益を上げるべく汗をかいているという話を聞いて、宮脇は「時は変改す」との感慨を抱いたのだ。
鉄道は、簡単には変わらないイメージがある乗り物である。自動車とは違い、決まったレールを時刻表通りに走るのであり、レールや時刻表に縛られることに、鉄道好き達は喜びを感じている。一度敷いたレール、一度決めたダイヤは、そう簡単に変わるものではないのだ。
鉄道は、変わらないからこそ人を安心させる乗り物でもある。昭和二十年(一九四五)の八月十五日、天皇陛下による終戦の
しかし、どんな時も決められたレールとダイヤを遵守する鉄道にも、変化は訪れる。鉄道を好む人々にとって「変化を受け入れる」ことは、大きな
例えば、ダイヤの改正。『時刻表昭和史』の中で宮脇は、戦前であれば
「趣味の世界にも退屈があり、新鮮な刺激をつねに求めているのだ」
と。
以前も書いたように、新線の開通も、鉄道好き達にとっては新鮮な刺激となる。百閒も岡山にいる時分、新しく開通した宇野線の一番列車に乗りに行ったし、宮脇も〝誕生鉄〟行為はあちこちで行なっている。
そんな中で宮脇が、人生の後半で心待ちにしていたのが、
青函連絡船に強い思い入れを持ち、北海道に行く時は極力、青函連絡船で渡るようにしていた宮脇だったが、しかしだからといって青函トンネルに無関心であったわけではない。トンネル志向の強い宮脇としては、青函トンネルの開通をおおいに楽しみにしていたのであり、開業前に現場を見学に訪れたことも、一度や二度ではない。
また宮脇の両親は香川の出身であるため、四国は
青函トンネルと本四連絡橋は、共に昭和六十三年(一九八八)に開業する。時に宮脇、六十一歳。計画段階から見守り続けていた宮脇としては、自分が生きているうちに通ることができるのかどうかを心配したこともあったトンネルと橋の、待ちに待った開業であった。
宮脇はしばしば、「待つ」ということについて考えている。青函トンネルや本四連絡橋のみならず、計画されながらも年単位で工事が遅れるなどしてなかなか出来上がらない多くの路線や施設の完成を、首を長くして待ちながら、
「鉄道に乗るのが趣味とは運の悪いことだと私は思っている。計画から実現まで歳月がかかりすぎるからである」(『線路のない時刻表』)
と、我が身を嘆く。そんな待ち遠しさを持て余した結果として書かれたのが、この『線路のない時刻表』ではなかったかと、私は思う。なかなか完成しない新線の現場に行き、自分でダイヤを作ってしまうという本書での行為は、鉄道趣味を持って生まれたことを「運が悪い」と思ってしまうほど、延々と待ち続けてきた人だからこそのもの。
そんな宮脇が最も長く待っていたのは、新幹線だった。昭和十五年(一九四〇)、東京~下関間を九時間で走る「弾丸列車」の計画が、帝国議会で承認される。十五年計画ということで、十三歳の宮脇は「早く十五年
しかし戦争で工事は中断し、敗戦で計画は撤回。十五年経っても、弾丸列車は走らなかった。やっと新幹線が新大阪まで走った時に喜び勇んで乗車したが、かつて十三歳だった少年は三十七歳になっていたのであり、博多まで開通した時は四十八歳になっていたのだ。
東海道新幹線が博多まで通った後も、東北新幹線や上越新幹線等の開業を、宮脇は待ち続けている。
「限りある命なのに待ち遠しいことがやたらと多い。まるで死に急いでいるようだ」(『汽車との散歩』)
との文を読むと、一般の人のように「そのうち開業するだろう」くらいの感覚ではなく、まさに一日千秋の思いで真剣に「待つ」身の
「東京─大阪一時間の浮上式鉄道などというのもある。こんなものをつくる必要はないと私は思うが、チラつかす
とも。浮上式鉄道とは、リニアモーターカーのことであろう。
開通まで二十四年も待った新幹線であったが、ではその後の宮脇が新幹線を愛していたかというと、そうではないようだ。新幹線の速さ、便利さが旅を味気ないものにし、「線」ではなく「点」として旅を捉える人が増えてしまったことを、宮脇は嘆く。とはいえ便利であることは事実なので利用はするけれど、そのうちに新幹線に「乗らされている」という感覚になっていくのだった。
新幹線に対してこのような思いを抱くということは、当然ながらリニアモーターカーについては「こんなものをつくる必要はない」と思う。けれど計画をチラつかされればつい、発情してしまう。それが鉄道好きの
古い言葉で言えば「文明開化」、新しい言葉で言えば「開発」に、鉄道を愛する「少年」達がつい発情してしまう一方で、鉄道は反対方向の変化にも見舞われる。特に国鉄が赤字に転落した昭和三十年代以降は、ローカル線の廃線や減便といった、退歩の方向への変化を余儀なくされているのだ。
簡単に変わることができないからこそ、鉄道は一度変化を遂げると、元に戻すことが難しい。しかし何があっても鉄道好き達は、変化を受け止め続けるのだった。何かを愛するということは、愛する対象がどれほど無常の風に吹かれようとも、対象を抱きしめ続けるということ。鉄道は地元の人のためのものなのだから、鉄道ファンは廃線に反対する立場にはないと思っていた宮脇は、廃線を寂しく思いつつも葬式鉄行為はせず、廃線跡を歩くことによって、廃線への愛をつなげていったのだ。
鉄道を愛する人々は、鉄道が醸し出す「常」の空気を享受する一方で、鉄道に乗ることによって、自らもまた無常の風の中にいることを知るのだろう。かつて乗った路線に二度、三度と乗れば、変わらずに走り続けている鉄道に対して、自分がいかに変わってしまったかが、身に
令和二年(二〇二〇)は、新型コロナウィルスの流行によって、世界中の人が大きな変化に直面した。人の移動は制限され、鉄道は今までにない苦境に立たされている。コロナ時代となってからは、人に直接会わなくても、インターネットを利用してかなりのことができるという認識も広まり、もはや東京─大阪間が九時間だ三時間だ一時間だという話ではなく、移動そのものが不要となる時代が到来するかもしれないのだ。
が、しかし。たとえ「移動せずとも、何でもできる」という時代になったとしても、
「なんにも用事がないけれど、汽車に乗って大阪へ行ってこようと思う」
という百閒の文章を思い出せば、鉄道を希求する人々の心は変わらないとの思いが、強まってくる。
阿房列車の旅で百閒は、目的地はあれど、人に会うとか仕事をするとか観光するといった「目的」は持たずに、列車に乗った。目的のために移動する人は、目的がネットで済めば移動する必要はなくなるが、目的を持たないのに鉄道に乗りたい人は、どのような状況でも移動を諦めないだろう。
「なんにも用事がない」のに鉄道に乗っていた百閒について、宮脇は、
「ここには『文明』ではなく『文化』としての鉄道が立ち現れている」(『終着駅は始発駅』)
と書いている。どれだけ速く目的地に着くか、どれだけ効率的に利用できるか、といった観点から乗るものが、「文明」としての鉄道。だからこそ百閒は、肥薩線でバスであるかのようにスムーズに発車するディゼル列車に「文明開化」を感じたのだ。
「文明」は、移動に要する時間を無駄と捉え、その短縮に努めてきた。一方の「文化」としての鉄道は、無駄の中に、目には見えない意味を見ようとする。今、移動はどんどん「しなくてもいいこと」と化してきているが、世界中の「文明」に急ブレーキがかかった時代の転換期の
鉄道には、俗世とは切り離された時間が流れている。より速く移動するのではなく、より深くその地を感じるために鉄道に乗るという鉄道趣味を育てた内田百閒、宮脇俊三の著作を読み返すことによって、実際に乗ることは
了
※本作は小社より、単行本として刊行予定です。