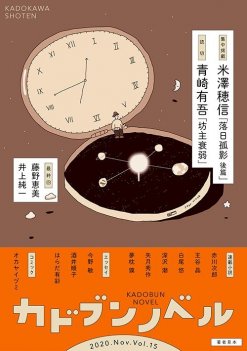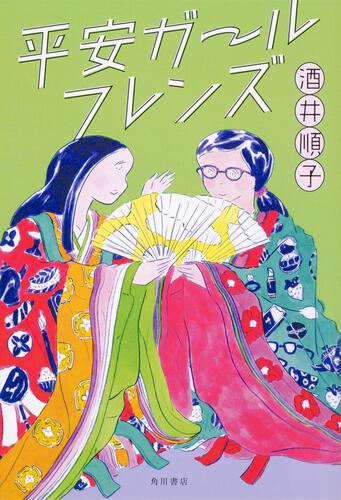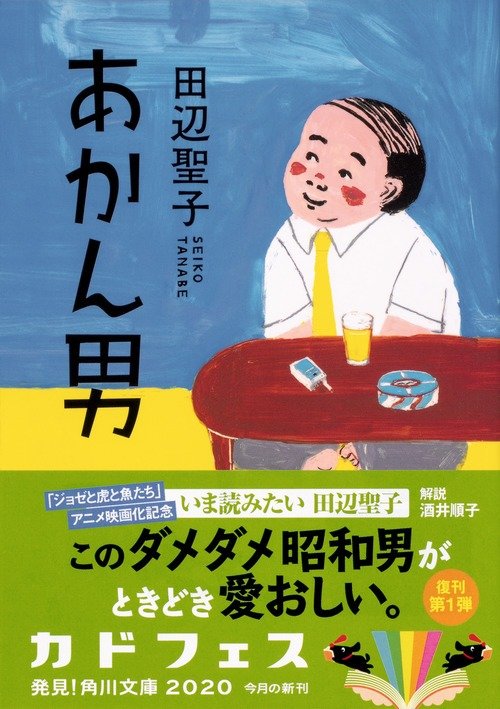【連載コラム】鉄道ファン必読。内田百閒と宮脇俊三の著作から、酒井順子が鉄道紀行の歴史を振り返る。「鉄道無常 内田百閒と宮脇俊三を読む」#19
酒井順子「鉄道無常 内田百閒と宮脇俊三を読む」
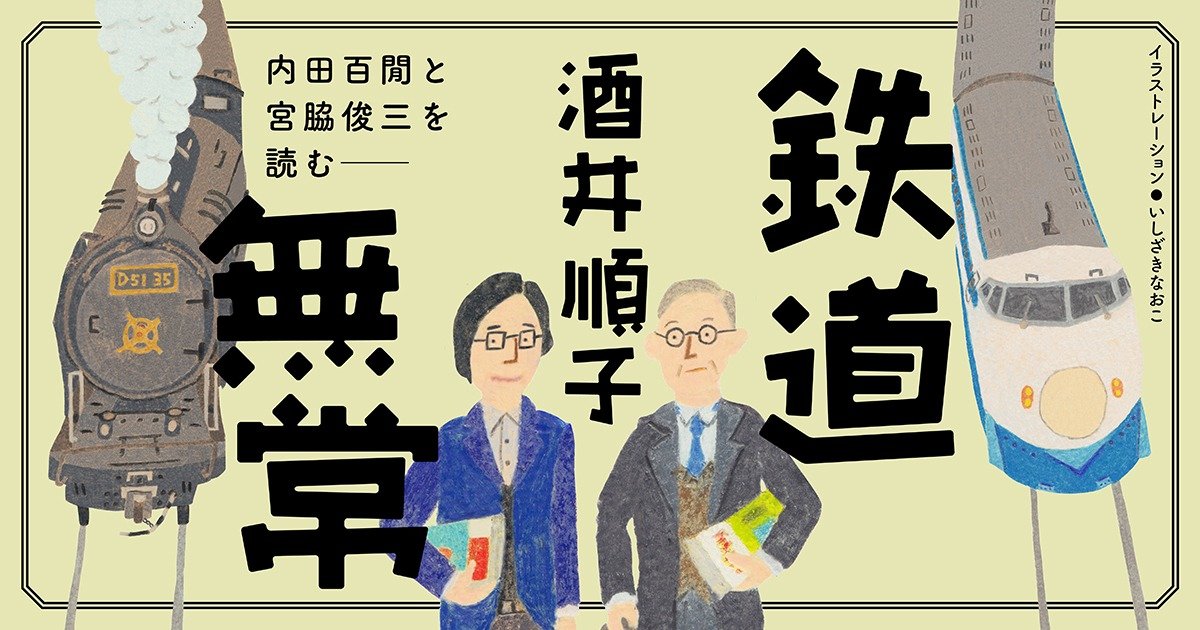
※本記事は連載コラムです。
前回までのあらすじ
鉄道紀行というジャンルを示した内田百閒が「なんにも用事がない」のに汽車で大阪に行っていた時代、普通の人にとっての鉄道は、用事を果たすために乗るものにすぎなかった。その四半世紀後、宮脇俊三は異なるアプローチでそのジャンルを背負うこととなる。多くの紀行文を残した二人は、心から鉄道旅を楽しんでいた。女子鉄・酒井順子が百閒と宮脇を比較しながら時代とともに発展する鉄道と鉄道紀行を読み解いてゆく。
名誉駅長を務めた
当日は制服制帽を着用してほしいという要望も、即座に快諾。あらゆることに難癖をつけがちな百閒が、
「もともと私は詰め襟は好きである」
ということで、自分から進んで帽子のサイズと身長を教えるほどだった。
すなわち百閒は、東京駅の名誉駅長就任という依頼を、おおいに喜んだのだ。名誉駅長の任務の一つとして、当時の花形列車である大阪行きの特急「はと」を発車させることがあったが、もちろんそれも、
話はそこで終わらない。「はと」の「みずみずしい発車」を任されることは嬉しいけれど、大好きな「はと」が発車していくのを、ただ漫然と見送ってしまうことができるものだろうか、と考えた百閒は、
「発車の瞬間に、展望車のデッキに乗り込んで、行ってしまおう、と決心した」
のだ。
「はと」の最後尾には、一等車の乗客用に展望車が連結されていた。展望車にはデッキがついているのであり、発車の時にすっとホームからデッキに乗ってしまえばいい、と考えたのだ。
持病持ちであった百閒は、健康上の不安から、かかりつけの医師にはずっとそばにいてもらいたい。国鉄職員のヒマラヤ山系だけには計画を打ち明けて、事前に医師をこっそりと「はと」に乗せておいてもらう細工もほどこした。
いよいよ当日。駅長の印である二本の金線が輝く制帽と制服を身につけ、百閒は東京駅へと赴く。「はと」の出発に際しては、マスコミやら見物人やらもたくさん集まっている中、首尾よくホームからデッキに乗りうつることができた。
本物の駅長には、
「
と挙手して挨拶。そのまま「はと」と共に去る、というコントのような展開となったのだ。
百閒、その時六十三歳。当時の平均寿命を既に越えている。しかし汽車が好きでたまらず、そして好きな汽車が目の前にいたら乗らずにはいられないという姿は、百閒の仲の良い友人であった
一方の
「国電」とは、首都圏で運転された国鉄の近距離電車のこと。国鉄の分割民営化に伴い、国電に代わり「E電」という名称を使用しようとする動きもあったがそちらは普及せず、現在に至る。国電の終点ということで、深夜に酔って乗り過ごしてきた客を揺り起こすことを宮脇は楽しみにしていたようだ。
駅長体験企画の依頼を受けた時、宮脇もまた喜んで引き受けている。小学生の頃、将来何になりたいかと先生に聞かれた時は、「総理大臣」「陸軍大将」といった答えが目立つ中で「電車の運転士」と答えた宮脇。運転士でなくとも、鉄道関係の何かになりたいという願望はずっと持ち続けていたのであり、
「帽子の金線は二本、白の手袋、カッコいい。『駅長』という名称もいい。社長、組長に匹敵する」
と、ほくほくしている。
宮脇も百閒と同様、制服には敏感に反応している。当日も、
「制服制帽には魔力があって、これらを着用すると、たちまち気分が出てくる」
と、構内の巡回に出かけているのだ。
宮脇駅長は、内田駅長のように珍騒動は起こさない。二人ともターミナル駅の駅長を務めたわけだが、百閒が楽しみにしていたのは「はと」の発車であるのに対して、宮脇が楽しみにしていたのは夜、帰宅の途についた客の到着だった。酔いつぶれた客を揺り起こしたい、という願望を持っていたのは、長年会社勤めをしてきたからという理由もあったのか。
しかし夜になって取手駅に到着する電車を待ち構えていても、その日は酔客が少なく、せいぜい網棚の新聞を回収することしかできない。次第にイライラしてきた宮脇だったが、二十三時を過ぎてようやく一人、眠りこけている乗客を発見した。
「取手ですよ。終点です」
と、乗客を起こす宮脇。降りていく客を眺めつつ達成感を覚えた宮脇は、「胸を張って駅長室へ引揚げた」のだ。
日々、
子供の頃から、鉄道が好き。その精神が大人になってもずっと変わらないところは、二人のみならず多くの鉄道ファン達に共通していよう。しかし宮脇の時代までは、子供の頃の趣味をそのまま維持している大人はまだ、
宮脇は著書の中で、鉄道趣味を「
たとえば宮脇は先頭車両の運転席の後ろに立って前方の景色を眺めるのが好きである。小学校の時に将来の希望として「電車の運転士」を挙げたのも、汽車だと
運転士にはならなかった宮脇は、乗客として列車で運転士の後ろに立つことに、いつも
だからこそ前方が眺めたい時は、列車がガラガラでない方が好ましかった。
「適度に混んでいれば、たまたま先頭部に乗り合わせたような顔で前方を眺めることができる」(『車窓はテレビより面白い』)
のだから。
百閒の場合もまた、自分の鉄道愛が子供の頃から変わっていないことを自覚している。
「子供の頃から汽車が好きで好きで、それから長じて、次に年を取ったが、汽車を崇拝する気持ちは子供の頃から少しも変わらない」(『立腹帖』)
と、気持ち良いほどに断言しているのであり、そこに含羞のようなものは見えない。
が、百閒はいわば「天然」の人である。「天然」などという言葉で表現すると途端に陳腐に聞こえるが、お金が入れば遣ってしまっていつも借金取りに追われ、好物は一年でも二年でも毎日食べ続け、飼い猫がいなくなれば涙を流し続けるというその姿は、岡山の造り酒屋の坊ちゃんのまま。汽車が好きで好きで、駅長なのに「はと」に飛び乗って職場から出奔するのは、そんな百閒だからできたことだろう。
対して宮脇は、「天然」ではない。だからこそ、子供の時のまま変わらない鉄道愛を恥じているという自己認識を示すのだ。
もちろん本当に恥じていたかどうかは、わからない。鉄道の世界は深く、地理や歴史、政治とも密接につながっている。宮脇にとっては一生をかけるにふさわしい趣味であったろうが、宮脇はあえて「汽車ポッポ」と表現して、都会の坊ちゃんらしいテレを示すのだった。
しかし最近は、宮脇のように恥じらいを表明しつつ鉄道に夢中になる、という姿を示す人が減っている気がしてならない。かつて宮脇が遠慮がちに立っていた運転席の後ろに、子供を押しのけてかじりつくように立っている大人の姿を見ることがある。また写真や映像を撮ることが好きな撮り鉄達は、少しでも良い画角のため、必死に場所とりをする姿を隠そうとはしない。
大人が堂々と鉄道愛を露呈させるようになったのは、「おたく」という言葉が人口に
宮脇がいた時代は、まだ「おたく」という言葉は、広まっていない。宮脇も「鉄道マニア」などと表現することが多いのだが、ではマニア達に対して共感を抱いていたのかというと、そうでもなさそうなのだった。
鉄道旅行している時、宮脇はあちこちでマニアに遭遇するが、そこで「おっ、ここにも同好の士が」と温かな気持ちになっているわけではない。ローカル線は地元の人のものだと思っていた宮脇であるから、マニアばかりが乗っているという状態は、望ましいものではなかった。しかし自分もまた同類であることを考えると、ガマの油的な感覚を抱いていたのではないか。
『片道最長切符の旅』では、
「一号車普通車、二号車グリーン車、三号車……」
と、窓から首を出して自分が乗っている列車の編成を確認している老人を宮脇は目撃している。
「鉄道マニアが
と思う宮脇はこの時まだ五十一歳だが、マニアっぷりを自己規制せずに噴出させている他者の姿に対して、同類であるからこそ戸惑う気持ちを持ったのだろう。
『時刻表2万キロ』では、九州で自分が乗っていた車両の運用についてとある予想を立て、それが見事に的中するということがあった。
「この喜びはわかる人にしかわからない」
と、心の中で
「鉄道友の会」とは、昭和二十八年(一九五三)に発足した、
だからこそ宮脇は、一人で旅をした。童子の魂を持つ百閒は、ヒマラヤ山系という秘書のような保護者のような相手と一緒でなければ旅ができなかったが、宮脇は子供の時と同じように鉄道が好きという気持ちを一人、
著書の中で宮脇はしばしば、列車や路線、時には駅を擬人化して見ている。
列車等を擬人化して見る時の宮脇の視線には、しばしば哀しみが混じっている。子供の頃は、常に
また新幹線やトンネル、橋などの開通によって、日の目を見なくなる路線や駅もあった。米原駅は「老大家」だったが、宮脇がそれを感じるのは、新幹線の「ひかり」で米原を通過する時(当時、まだ「のぞみ」は登場していない)。「大きな仕事をしてきた老大家に挨拶もせずに素通りしてしまうような」気持ちを覚えていたのだ。
その視線は、既に子供のものではない。鉄道が弱さを見せるようになって、宮脇は大人の視線を持たざるを得なくなっていた。大人として、いたわるかのように老大家や老兵を見ていたのだ。
はたまた、東北本線と
「小牛田の心中を察すると同情を禁じ得ない」(『終着駅へ行ってきます』)
と、心を寄せる。当時「日本一の豪華列車」であった寝台特急「出雲1号」が東京駅で発車を待っているのを見れば、
「あすの未明には、あの旧態このうえない
と、心配するのであり、それはほとんど親のような視線である。
宮脇が、変わりゆく鉄道をいたわり、
子供の心のままで