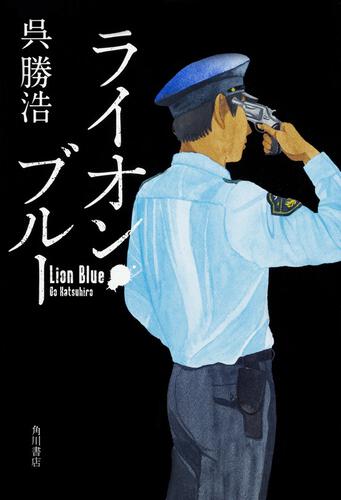「お前、よく生きていられるよな。」連続銃殺事件が生んだ、もう一つの悲劇。呉勝浩「スワン」#16
呉勝浩「スワン」

2
ぎこちなさよりも、いたたまれない空気を、いずみは感じた。
「なんだ、片岡。少し、やせたんじゃないか。ちゃんと、食べてるのか」
職員用玄関で待ち受ける背広の校長と教頭の顔は憶えていたし、眼鏡の女性が保健の先生なのもわかった。けれど気安く話しかけてきた白髪まじりの男性が何者か、とっさにはピンとこなかった。
二年生になってから、これが初めての登校だった。自分が三組になったことも、牛倉というこの男性教諭が担任だということも、真澄から聞かされているだけだ。
「食べなきゃな。ちょっと無理してでも、食べなくちゃ、ちゃんと成長できないぞ」
軽く肩を叩かれ、ここに真澄を連れてこなくて正解だったと確信した。担任の牛倉先生はベテランで学年主任もされている方だから安心よ─。励ますようにいっていた真澄は、たぶん、牛倉がいずみにふれた瞬間に怒りの発作を起こしたにちがいないから。
悪気はないのだろうけど、このご時世、牛倉の振る舞いはデリカシーに欠ける。校長らの、冷や冷やしたつくり笑いがそれを物語っていた。
ただ実のところ、いずみの心が冷めたのは、牛倉の気安さのせいではなかった。変に気をつかわれるくらいなら、ガハハと笑い飛ばしてもらうほうが性には合っているのだ。
でも彼のにこやかさに、いずみはわざとらしさを嗅ぎとってしまった。どうしていいかわからない。どうあつかったらいいのやら……そんな戸惑いを。
そしてわずかな、恐怖。あるいは、嫌悪。
「はい」
ほとんど反射的に、いずみは弱々しくはにかんだ。
「母にもよくいわれます。最近になって食欲は、だいぶマシになりましたけど」
そうか、そりゃあいい、たいへんけっこうだ─。牛倉の陽気さに便乗するように、校長らも声をかけてきた。当たりさわりのない気づかいやねぎらいに、こちらも調子を合わせて返した。
まちがいなく校長は、いずみの様子を真澄に報告するはずだ。へんに心配させてしまっては復学した意味がなくなる。
「じゃあ、とりあえず、いったん校長室へ行こうか」
牛倉に先導され、いずみはひさしぶりに校舎を歩いた。制服もひさしぶりで、少しぶかぶかな感じがした。あまり見られたくないと思ったが、生徒の姿はどこにもない。時刻は二時間目の真ん中あたりで、登校時刻を遅らせたのも職員用玄関を利用したのも学校側の配慮だった。
三階の校長室まで、保健の先生がとなりについて話しかけてきた。おっとりとした中年の女性で、急かすことなく日常のあれこれを尋ねてくる。とはいえ基本的に自宅に引きこもっている生活に、中身のある話などない。
ひまな時間はテレビよりスマホをいじっていると伝えたとき、
「調べものをしたりするの?」
ごく自然な口ぶりで訊かれた。
「─いいえ。猫の動画とか、そういうのを」
「ああ、あれねえ。くせになるよね。観はじめたら止まらなくなるでしょう」
適当に相づちを打つ。怪しまれている雰囲気はない。
校長室に着くと応接セットのソファに座らされ、今後の登校や遅れている学習をどうするかの相談となった。じっさいはおととい、真澄が学校を訪れ話し合いを済ませているから、ほとんど確認作業で終わった。
しばらく授業は個別指導とする。ホームルームや昼休み、体育や音楽といった授業は任意で参加してもいい。慣れてきたら授業にも出るようにしよう。わからなくてもかまわない。遅れているぶんは放課後に埋めていけばいいから。
「あ、でも、片岡はあれだ。放課後は、バレエに通ってたよな」
後ろに立つ牛倉が、ぽんと手を叩きそうないきおいでいった。「だからクラブ活動もしていなかったって、お母さんがおっしゃってたぞ」
「牛倉先生」
さすがに教頭が咎めた。
「え? あっ」という牛倉の間抜けな声が聞こえ、いずみは思わず吹きだしそうになった。ほんとうに、悪気はないのだろう。もしわかって口にしているなら、悪気なんてレベルじゃない。
「大丈夫です」
いずみは、目の前に座る校長と教頭をまっすぐ見た。
「無理をしないように、やっていきます」
うん、という空気になった。それにいずみは満足した。まずは真澄を安心させられそうだ。
クラスにあいさつしていくか訊かれた。昼休みの前にどうだ、と牛倉は前のめりだ。
「……もうちょっと、考えさせてください」
「そうか。そうだな。そうしよう。時間はたっぷりあるしな」
かすかに失望の気配を感じる。考えすぎだろうか。
まずクラスメイトが知りたいと頼むと、じゃあつづきは一階の相談室で、となった。職員室のそばにあるその部屋が、しばらくいずみの個人教室になるらしい。
校長らにお辞儀をして、牛倉と保健の先生といっしょに退室する。ふたりが前を進んだとき、内履きに違和感を覚えた。半年ぶりのせいだろうか。バレエのため、足裏筋を落とさないようにクロックスタイプでなく紐付きシューズを履いていた。それを少し、きつく感じたのだ。
校長室の扉の前でしゃがみ込み、紐をゆるめようとしたとき、
やっかいですな。
中からそんな声がした。教頭だろう。
「片岡?」
ふり返った牛倉に、「あ、大丈夫です」と駆け寄る。
相談室は狭かった。壁はキャビネットで埋まり、自由にできるのは横長のテーブルとパイプ椅子だけ。大きな窓がなければ三分で息がつまりそうな空間だ。
牛倉にお願いし、窓を開けても良いという許可をもらった。一階だから飛び降りの心配はないか─。「少しだけだぞ」とうなずく直前、窓といずみを見比べた瞬間、そんな確認が牛倉の心に生じた気がして、いずみは苦笑をこらえた。
とりあえず初日ということで、受けられなかった一学期の期末テストを解いてみることになった。さすがにこの半年、完全に勉強をサボっていたわけではなく、真澄を安心させるため、そして退屈に堪えかねて、教科書や参考書をパラパラめくったりはしていた。
牛倉が相談室をあとにし、ひとりきりになったいずみはシャーペンを手にテスト用紙に向かった。かたわらには教科書が積んである。わからないところはチェックして、教科書で調べてもよいといわれていた。点数に意味はない。実力が測れればいい。すると負けん気が頭をもたげ、いずみはなるべくたくさん自力で解いてやろうと意気込んだが、英文の三つ目の単語でつまずき、構文のかたちにギブアップした。たしか現在完了形とかいうやつだ。現在なのか過去なのか、はっきりしてほしかった。
十センチくらい開けた窓から風が吹き込んだ。肩にかかった髪がゆれた。外の景色へ目をやるが、ここは裏庭にあたる場所で、それも四時間目の授業中だから、人の姿はもちろん、くしゃみのひとつも聞こえなかった。
いずみの通う学校は共学の公立校で、学力レベルは県内のちょうどまん中くらいだ。受験勉強にギスギスする感じはなく、部活動が強いわけでもなく、取柄はおおらかな校風とゆるい校則だけというのがもっぱらの評判だった。生徒は大まかに、家から近いので選んだというグループと、課外活動に熱心なグループとにわかれる。いずみは後者だ。だからというわけじゃないけれど、いまさら勉強に血道をあげるモチベーションは逆立ちしたって見つかりそうにない。
真澄からうるさくいわれたこともない。我ながら赤面しそうな点数がならぶテスト用紙を見せても、「あなた、ちょっとはやる気をだしなさいよ」と、通りいっぺんのお小言を口にするだけで、真剣味はほとんどない。バレエさえがんばっていれば大丈夫。何を根拠にしているのか知らないが、そんな考えが真澄にはあるらしい。かといってそっちでスパルタというわけでもなく、プロになれるとは彼女も信じちゃいないだろう。するといずみの進路はさえない三流大学か、願書だけで入れるような専門学校か、もしくは就職か。どのみち「勝ち組」から漏れるのは確実で、母親ならもっと心配したほうがいいんじゃない? それもシングルマザーなんだし、一人娘に期待をかけて厳しくしつけるとかしても、ぜんぜん不思議じゃないのに……なんて首をかしげたくなったりもした。同時に、そういう妙に楽天的なところが真澄らしいといえば真澄らしく、喧嘩するときだって、彼女を憎く感じたためしはなかった。
嫌だなと、ふいにいずみは思った。
もう、もどれないのだ。たぶんいずみはもどれないし、真澄ももどれない。いまより心は安定しても、前とおなじとはいかない。もう二度と、わたしたちは朝までカラオケではしゃげないし、仮にそうしたところで、以前にはなかった翳が、狭いカラオケルームの隅っこに、震わせるビブラートの端々に、消えないシミのように存在してしまうのだ。そんな予感が、いずみの胸を重たくする。
テスト用紙の上にシャーペンを転がし、いずみは頬杖をついた。牛倉が残していったクラスの名簿が目に入り、なんとなく引き寄せた。二年三組に、なじみのある名前は少なかった。一年のクラスメイトとは、まるで意図的に引き離されているようだった。それが四月の事件の前から決まっていたことなのか、事件のあと、慌てて調整したものなのか、いずみにはわからなかったし、わかったところで意味はない気がした。
どうせもう、もとにはもどらないのだから。
チャイムが響いた。四時間目が終わり、昼休みがはじまる。
ノックと、「入るよ」の声は同時だった。
「やあ」
サマーセーターに白衣を羽織った男性がこちらを見下ろしてきた。
「おれのこと、憶えてるか」
ぼさっとした髪型と、それに似合わない整った顔つき。すらっとした長身。昔バレーボールの選手だったんだと、クラスの女子がささやいていた。
「はい、憶えてます」
いずみの返事に鮎川快は、そう、と無愛想にこぼし、すっと目をそらした。
身長以外にスポーツマンの面影はなく、熱血の正反対をいく物腰の男だった。年齢が近いせいか熱を上げる女子も多く、体温の低さのわりにここぞという場面で鋭い指導をするところがあって、男子からも一目置かれる存在だという。
けれどこの物理の教師に、授業で教わったことはない。いずみは部活にも入っていない。おそらく牛倉に直訴して、彼はいずみのもとにきたのだろう。その理由は察しがついた。
鮎川の目が、投げだしたテスト用紙に向いた。「あんまり、解けてないみたいだな」
「……やっぱり、ちゃんとやり直さないと駄目みたいです」
そう、と興味なさげに返ってくる。
「お弁当は」
「あります」
そう、と鮎川がいう。
「教室、いってみる気?」
「いいえ」
鮎川は目をそらしたままだった。いずみは、そんな彼を見つめた。
「今日はやめておきます」
「そう」
「もう少し、慣れてから」
「ふうん」
ずっと、目をそらしている。見上げる恰好ではあるけれど、彼の表情がよくわからない。
「慣れるって、どんなふうに?」
特別、棘がある口ぶりには聞こえなかった。ただ、簡単に返してはいけない質問に思えた。
風が吹き込んでくる。薄いカーテンがゆれる。どこからか、男子のはしゃぐ声がした。
「古館も」
彼の口調は平たんなままだった。
「慣れなくちゃ、いけないんだろうな」
いずみは、唇を結んだ。
「古館のおばさんも」
目をそらしそうになったが、心の何かが、それを拒否していた。
「どう思う?」
鮎川がこちらを見た。いずみは、それが決められた振り付けであるかのように、うつむいた。
窓から、にぎわいが届いた。何もかもがすっかり、遠い世界になっていると感じた。
「悪いな。でもおれは、こういうふうにしかいえない」
彼の視線が、それたのがわかった。気だるげな、細く長いため息が聞こえた。
「たまにのぞきにくるから。よろしくな」
そう残し、鮎川は小部屋を出ていった。
いずみは、お腹を押さえる。
鮎川と古館小梢がどんな関係だったのか、正確には知らない。ただ鮎川と古館の家は昔から付き合いがあって、成績でも金銭面でももっと上位のところを狙えたはずの小梢がこの学校を選んだのは、彼の赴任先だったからだと、いずみは聞いている。小梢は鮎川への好意を隠そうとしなかった。公然の秘密とでもいうように、まるで許婚のごとくふるまうことすらあった。
いずみと鮎川のわずかな接点も、ようするに小梢だったのだ。
鮎川は、知っているのだろうか。あの日、小梢がスワンにいずみを呼びだしたこと。その理由。
そして、あの事件のさなか、わたしと彼女がとった行動を。
ふわっと陽光が、室内に満ちた。いずみは、五時間目がはじまったタイミングで帰宅しようと決めた。