この題材は小説になりうるのか? 困惑する作家のミステリー『原因において自由な物語』杉江松恋の新鋭作家ハンティング
杉江松恋の新鋭作家ハンティング
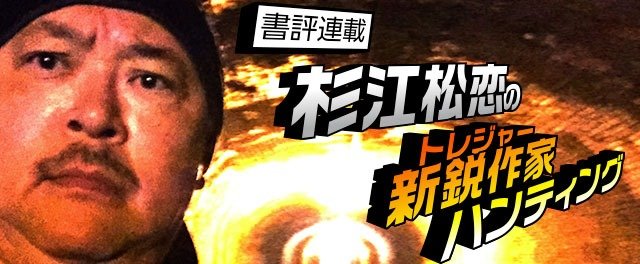
書評家・杉江松恋が新鋭作家の注目作をピックアップ。
今回は、メフィスト賞作家が大きな賭けに出た一冊。
『原因において自由な物語』書評
『原因において自由な物語』(講談社)は、自己言及の小説である。
本作において作者の五十嵐律人は大きな賭けに出たと言える。
自身について語ることが目的に含まれた小説には失敗作になる危険が伴うからだ。
もとより小説とは作者がおのれの内面と向き合い、その中にある何かを文章として表現するものだから、自己言及を多少なりとも含まない作品はありえない。内省を綴ることを主目的とする小説は多数存在する。人気作家が自己を曝け出した自伝的小説を発表すれば、歓迎する読者も多いだろう。
だが、新人作家がそれをしたとして、喜ぶ読者はどのくらい存在するだろうか。
厳しい言い方をしてしまえば、早くも書くことがなくなったのかと、疑いの眼差しで見られる可能性が高いのではないかと思う。縮小再生産は憐れまれることだが、自分の切り売りはさらに痛ましい。小説は虚構を売るものであるから、素材を見つけてくる才能、言い換えれば無から有を作り出す魔術を読者はいつも作家に期待しているのである。
私にもそういう気持ちがあり、デビューして間もない作家が自己言及の小説を書くことには否定的である。もちろん例外もある。綿矢りさ『夢を与える』(河出文庫)は、十代でデビューを果たし、以降しばらくは文壇のアイドル的な扱われ方をした作者が、自身につきまとうそうした虚像を逆手にとって書いた、したたかな小説だった。芸能人を主人公にした、文字通りのアイドル小説だったことにも作者の覚悟が窺える。だが、『夢を与える』ほどの作品はめったにない。無残な失敗例を私は数多く見てきた。
と、ここまで予防線を張っておけばもういいだろう。
『原因において自由な物語』は自己言及の小説だが、稀有な成功例なのである。
失敗を怖れずにこの題材に挑戦した作者の勇気を大いに讃えたいと思う。
極めてあらすじを紹介しにくい作品である。小説を構成する部品の、さらに断片のようなものが冒頭には振り撒かれている。ミステリーにおいてはよく見られる技巧だが、作者が自らの語り口に酔っているだけと見られる場合もあり、私はあまり好みではない。だが、本作の場合はこの技巧が用いられていることに意味がある。『原因において自由な物語』の主人公である〈私〉こと市川紡季は二階堂紡季の筆名を用いる小説家だ。冒頭に置かれた意味の取りづらい部品は、彼女が書かなければならない物語の導入部に当たるのである。それをいかに小説とすべきか、もっと的確に言うならば、それらが本当に小説になりうるものなのか、と訝しみながら〈私〉は読者の前に姿を現す。困惑する作家の小説なのだ。
そうした形式の作品だから、〈私〉の前に置かれているまだ物語になり切れていない素材と、〈私〉自身の人生に関する物語がしばらくは並行して進んでいくことになる。作中の時代は現在よりも少し先の二〇二六年に設定されており、学校に専任の法律家であるスクールロイヤーが置かれていたり、マッチングアプリケーションに進んだ機能が付与されていたりする。素材の中で描かれるのは、そのマッチングアプリケーションが存在したことが事故死の遠因になったと思われる少年に関する話だ。
作中作との二重構成自体はミステリーにおいてはまったく珍しくないが、その扱いが不明なままで進行していくのが本作前半部の特徴である。ある見方が示された後で状況を一変させてしまう出来事が起き、小説はようやく本来の姿を現す。読者によっては頭が重い構成と感じるかもしれない。ここが本作最大の弱点である。〈私〉が断片にすぎない素材の中に分け入り、小説家として格闘するというのが作品の要なので、前半部が茫洋とすることは不可避の事態である。作者はこの弱点をよく自覚しており、断片の中では登場人物の切実な感情を記すことで読者の注意を惹きつけ、〈私〉の物語においては状況の謎を推進力に用いて凪の海のような前半部を乗り切ろうとしている。善戦していると思う。
先に書いたとおり、あらすじを紹介しにくい作品なので、これ以上の内容には触れないほうがいいように思う。前半部では並置されていた断片が、後半部では〈私〉の物語に併合されるような形で進んでいくことになり、そこから真の謎が浮かび上がる仕掛けになっている。全体が〈私〉にとっては最も近い存在である遊佐想護の心中を推し量る物語として書かれており、その意味ではホワイダニットのミステリーである。
ミステリーではあるのだが、ぜひこのジャンルにあまり関心のない方にも読んでもらいたい。これは作家小説であり、小説の小説でもあるからだ。後半で〈私〉がある人物から「けじめなんてその場しのぎの言葉を、作家が使うなよ」と咎められる場面があるが、作家の覚悟を問うということが小説の主題になっている。言うまでもなく、これは五十嵐律人が自分自身に向けたものだろう。作家としての自身の姿勢を問うという行為自体を小説化した作品なのであり、〈私〉の言葉を借りて内面を語ることによって五十嵐は退路を断っている。その潔さが気迫となって表れるか否かが作家としては勝負だったのではあるまいか。私は成功と感じたが、個々の読者に判断は任されている。
五十嵐は二〇二〇年に『法廷遊戯』で第六十二回メフィスト賞を獲得してデビューを果たした。同作は日本では珍しい本格的な法廷ミステリーであり、着想もさることながら、構成の妙によって多くのジャンル読者からの支持を集めた。続く『不可逆少年』は題名からもわかるとおり少年犯罪を題材にした作品である。デビュー時点の五十嵐は司法修習生だったが、最新作の奥付に付された作家紹介を見ると肩書が弁護士になっている。第一作と第二作で法律に関する謎解きを扱ったのでその道を歩むのかと思いきや、第三作となる本作では予想を大きく覆してきた。そのことからも勝負を賭けた一作であったことは間違いない。
『原因において自由な物語』という題名からはやや生硬な印象を受ける。あまり耳慣れないが、実は法律用語なのである。作中人物の言葉を借りながら説明すると、「ワインをがぶ飲みした原因行為のときの自由な意思決定が、殺人という結果行為として実現した」ような場合、「結果行為の時点で責任無能力の状態においても完全な責任を問える」。これを「原因において自由な行為」と呼ぶのだという。この概念がどのように物語に関わっているかは伏せておくことにする。
今回はいろいろ情報を伏せていてもどかしいかと思うが、白紙の状態で読んだほうが感銘を受けるタイプの作品なのだ。収まりのいい売り文句を書けず恐縮である。五十嵐律人が覚悟して書いた小説だという、その一点だけを信じて手に取るしかないのだ。たぶん裏切られないと思う。























