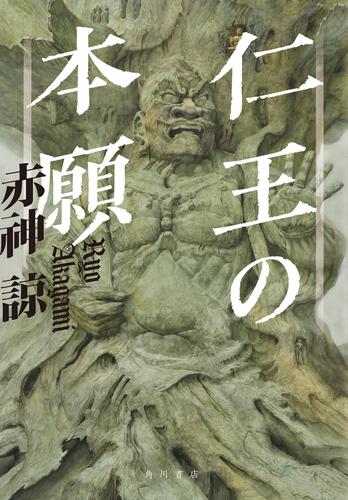加賀一向一揆は、最低の民主主義国家だった? 『仁王の本願』著者・赤神諒が語る#3
『仁王の本願』について著者・赤神諒が語る
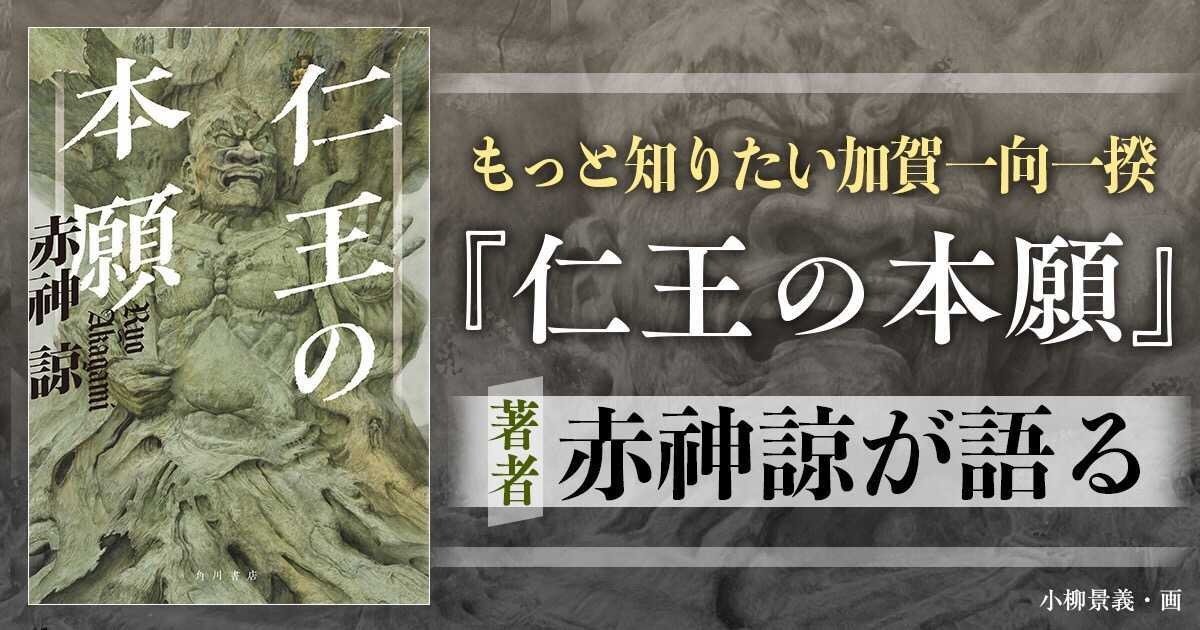
加賀一向一揆を舞台にした歴史小説『仁王の本願』が発売されました。
主人公・杉浦玄任は実在した人物ですが、皆さんご存じですか?
この作品を読めば、謎多き加賀一向一揆の実態に迫る…ことができるかは(信長に資料を焼き尽くされてしまったので)わかりませんが、胸熱くなる戦国エンターテインメント小説です。
刊行を記念して、著者の赤神諒さんが創作の裏話や物語にこめた思いを語ります!
No.3 民主主義への応援歌
本作品のテーマは〈民主主義の価値〉です。
「価値」は「代償」と言ってもいいかも知れません。
私は法律家でもあるのですが、法律を学び始めた頃は、民主主義は人類が到達した当たり前の政治体制だと思い込んでいました。でも、21世紀の世界では、民主主義国家よりも独裁国家の人口のほうが多くなりました。
民主主義はかえって制度疲労を起こし、分断され、疲弊し、弱体化してゆく。
そんな中で、やや大げさに言えば、〈民主主義への応援歌〉を書きたいと強く思いました。
歴史小説として考えた時、想起した舞台が〈加賀一向一揆〉でした。
何年か前に〈越前朝倉家〉の滅亡を描いた時、その宿敵たる〈百姓の持ちたる国〉加賀を、同時代における異質な国として強く意識していました。
得体の知れない、恐るべき集団です。
興味は感じましたが、まさか書くことになるとは思っていませんでした。
まだその時が来ていなかったのでしょう。
今回調べてゆくうち、玄任のわずかに残した足跡を検証し、特にその死についての伝承を知った時、書けると思いました。
作品では<民の国>の腐敗と堕落、再生と滅亡の過程を描きました。
加賀一向一揆は1580年、信長により滅ぼされます。
金沢御堂はもちろん、あらゆるものが佐久間盛政によって破壊されたらしく、どのように滅んだのか、内部事情はほとんど分かりません。400年以上前に完膚なきまでに滅ぼされた国ですので、実は歴史家でも不明な点が多いのです。
実際の政治体制は時期により変遷があったでしょうし、もっと複雑で、多くの人間が関与していたはずですが、私なりに単純化した上で、推測も交えて設定しました。
民主主義とは、治める者と治められる者が一致する政治制度です。
シンプルに言えば、誰かによって支配されるのでなく、〈自分のことは自分で決める〉という政治ですね。
戦国時代に、西洋的な意味での民主主義などなかったでしょう。
でも、民主主義の本質部分は、不完全であれ、加賀一向一揆にあったと思うのです。
現代と同じく貧富の差や格差、差別やありとあらゆる難題に苦しんではいても、阿弥陀の前には皆平等であるという思想のもと、近代民主主義の萌芽のような政治がそこにはあったのではないか。
理想化しすぎかも知れませんが、当時の封建国家に比べれば、加賀ははるかに民主的な国家だったはずです。
――民主主義は最悪の政治体制だ。これまで時おり試みられてきた、他のあらゆる体制を除けば、だが。
この、陳腐と言えるほどに著名なチャーチルの至言を、頭の隅でリフレインしながら、執筆しました。
決して、民主主義を美化しない。
玄任が登場した頃の加賀一向一揆は、最低の民主主義国家です。
問題だらけで、誰も責任を取らず、不合理で、面倒くさくて、投げ出したくなることばかり。
人が誰しも持つ汚い欲望や保身が噴出し、弱点となり、敵につけ込まれる。
これでもかと、民主主義の弱さ、醜さを描きました。
それでも、たった一人の人間が私を捨てて生涯をかけることで、滅びかけた民の国が蘇ってゆく。
ですが、民の愚昧の行きつく先は、民の国の守護神たる杉浦玄任の死です。
玄任は蘇りませんが、皮肉にも彼の死によって、民主主義が復活する。
ところが、時すでに遅し。滅亡の流れは変えられません。
それでもなお民主主義は、他の最悪の政治体制に比べれば、それ自体かけがえのない価値を持っているというメッセージを、逆説的に込めたつもりです。