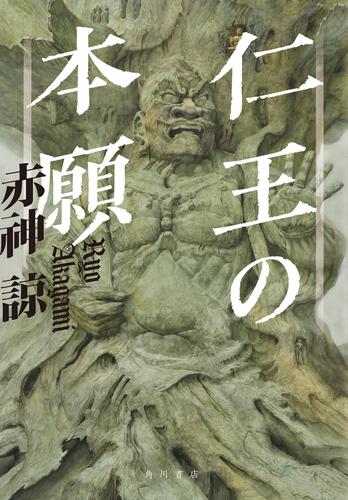時は戦国。宗教者なのに戦をしなくてはならないという悲劇。 『仁王の本願』著者・赤神諒が語る#2
『仁王の本願』について著者・赤神諒が語る
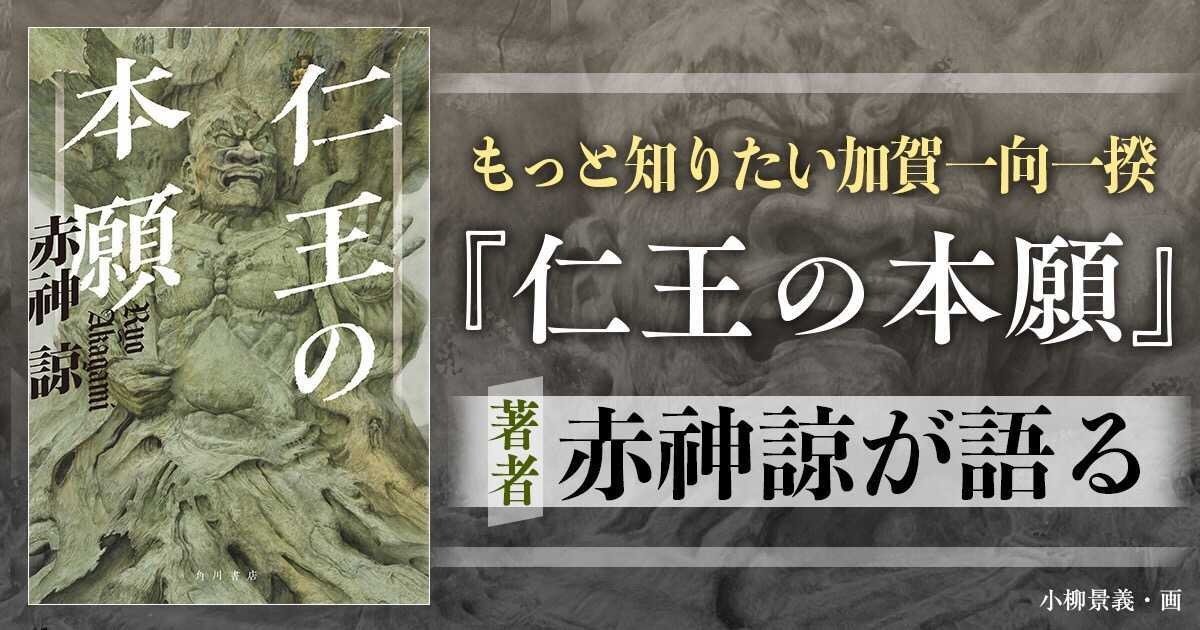
加賀一向一揆を舞台にした歴史小説『仁王の本願』が発売されました。
主人公・杉浦玄任は実在した人物ですが、皆さんご存じですか?
この作品を読めば、謎多き加賀一向一揆の実態に迫る…ことができるかは(信長に資料を焼き尽くされてしまったので)わかりませんが、胸熱くなる戦国エンターテインメント小説です。
刊行を記念して、著者の赤神諒さんが創作の裏話や物語にこめた思いを語ります!
No.2 乱世において、宗教とは
ひとつの宗教国がなぜ、祈りも虚しく、滅びるのか。
信ずる者がなぜ、救われないのか。
人はなぜ、信仰のために死ぬのか。
最初に告白しておきますが、私の手に負えないテーマです。
でも、加賀一向一揆とその滅亡を描くにあたり、避けては通れませんでした。
血で血を洗う乱世を、宗教者はいかに生きるべきなのか。
「心頭滅却すれば火も自ずから涼し」で有名な快川紹喜のごとく、不殺生戒を貫いた傑僧も現にいました。
確固たる生き方は筋が通っているし、世に残すメッセージもありそうです。でも、同時代の滅びゆく国の民にとって、殉教は自己満足に過ぎないようにも思えるのです。
宗教者は信仰を貫き、信者と共に死ぬ以外に道はないのか。
逆に、洋の東西を問わずいつの世も、生き延びるために信仰を捨てる宗教者はいました。
一向一揆でも、織田軍の侵攻に当たり、改宗した信徒たちもいました。
他方、信仰を守るために抗い、戦った僧侶もいた。
顕如に打倒信長を進言したとされる杉浦玄任は、武闘派だったようです。
傍目から見れば、玄任がやっていることは結局、戦国武将と何も変わらない。
坊主がひたすら戦に明け暮れ、不殺生戒を破り続けている。
でも、玄任が戦う目的と動機は、普通の戦国武将と決定的に違います。
出世欲でも、名誉欲でも、意地でも、主君への忠誠でもない。
ただ、同じ信仰を持つ者たちが作った民の国を守るために、彼は戦い続けます。
人間の作る社会が不完全である以上、不可避的に悪が生じます。
その最たるものが戦争です。
世界が弱肉強食である以上、民主国家でもそれは避けられない。
人を救うのが宗教者の役目なら、殺生を繰り返すなんて語義矛盾も甚だしいし、疑いなく失格でしょう。
あえてその最悪の役回りを引き受けて、民を守ろうとする宗教者。
本作では、私を捨て去り、民を守るために、本来許されぬ殺生を引き受けた僧侶の尊い姿を描きました。
この作品の難所は、人間離れした聖者になってゆく玄任の描き方でした。
最初の方こそ波瀾はありますが、主人公が「仁王」として復活した後は、ほぼ完全無欠の人間なので、読者が感情移入しにくい。
(ちなみに玄任は、民主国家に実在する、複数の奇跡の政治家をモデルにしています)
これは物語の設定上、変更できないので、できるだけ周りの登場人物の視点から主人公を描くようにしたのはそのためです。
「本願寺の仁王」というのは創作ですが、戦場を駆け巡った坊官にこそ、乱世の高僧がいたのだという悲劇を描いたつもりです。
玄任がそうだったという証拠はありませんが、たとえ歴史に名を残さずとも、そんな宗教者がきっといたと私は思っています。