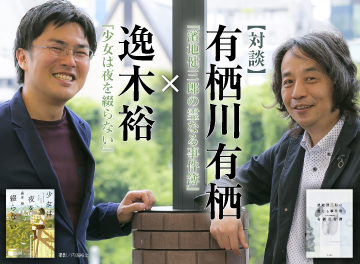【連載小説】死んだはずの真夜が、僕だけに見える――。少女の死の真相とは? 青春ミステリの最新型! 逸木裕「空想クラブ」#5
逸木 裕「空想クラブ」

※本記事は連載小説です。
>>前話を読む
第二章 エスキモーの服を着た少年
1
「それで……どうしたんだよ」
翌日の昼休み。ぼくは
こんなことを相談できる相手は、隼人しかいない。彼は空想クラブのメンバーで、
「どういう状況だったんだよ。きちんと、詳しく、説明しろ」
その上、ぼくがいくら突飛なことを言っても、馬鹿にせず話を聞いてくれる。こんな柔軟な心を持っている人は、隼人しかいない。
ぼくは、家でプリントしてきた、
「真夜と会ったのは、大体この位置だ」
「
「昨日、ぼくは真夜の告別式に参加したあと、このあたりを歩いてたんだ」
「真夜が死んだ現場を、見ときたかったのか?」
「考えごとをしながら、ぼくはサイクリングロードを歩いてた。そうしたら、突然真夜の声が聞こえたんだ。河原のほうを見たら──真夜がいた」
ぼくは×印を指で示す。
「少し質問させてくれ。お前、死んだ人とか見えるんだっけ?」
隼人の声に、慎重な色が混ざる。ぼくは首を振った。
「ぼくの〈力〉は、世界のどこかの光景を見ることだけだ。死んだ人が見えたことはない」
「じゃあ、なんで真夜が見える?」
判らない、と答えた。ぼくにも初めての経験だ。
誰かに能力を説明するとき、ぼくは小さな部屋にいるところをイメージしてもらう。部屋の中には棚や机があって、動いて手を伸ばせば、好きなものを手に取ることができる。
ぼくの〈力〉は、それをもっと拡大したようなものだ。目を閉じると、ぼくの前に空間が現れる。それは
〈力〉を使うとき、ぼくはその対象を見たいと強く願う。そうすると、ぼくの願いに共鳴するように、空間のどこかにあるひとつの〈窓〉が、じわじわと反応をはじめる。音が聞こえるわけでも、光が見えるわけでもないけれど、なんだか〈窓〉に引き寄せられるような感じがするのだ。だんだんと強くなる反応を感じて、いまだというときに手を伸ばしてそれに触ると、見たかった光景が目の前に広がる。その場にいるみたいに、とてもリアルに。
すごい〈力〉だ。宮おじぃーはこの能力を使って、毎日のように世界旅行を楽しんでいた。
でも、ぼくはそれほど、
たぶん、ぼくは「見たい」人じゃないんだと思う。世界中のあちこちにあるものを見るよりも、勝手気ままに空想をして、好きなことを思い描いているほうが好きなのだ。実際にもらってすぐに見たいものは尽きてしまって、ぼくは〈力〉を使わなくなってしまった。
〈力〉は使っていないと、
〈力〉がぼくに干渉するようになったのは、そのあとのことだ。
器にたまった雨水が漏れるみたいに、空想がぼくの世界に漏れるようになってきたのだ。最近見たアンコールワットや飛行船のビジョンが、まさにそれだった。〈力〉を使え、解放しろと抗議するように、ランダムに〈窓〉が開いて、向こうから空想がやってくる。特に困ることはないので放置しているけれど、自転車を飛ばしているときに空想に襲われることもあって、そういうときはちょっと怖い。
「真夜が見える理由は、自分でもよく判らない。ただ、見えるとしか言えない」
「そう言われてもな。誰か〈力〉について、もっと詳しい人はいないのか?」
ぼくは首を横に振った。宮おじぃーは「死んだ人が見える」などとは一言も言っていなかったし、聞きたくても、宮おばぁーが死んでから半年後、あとを追うみたいに亡くなってしまった。
隼人が眉をひそめる。信じてもらえなくて当然だ。そんな都合のいい話、ぼくなら信じるのは難しいだろう。
「本当に真夜が、河原にいるんだな?」
「うん。ぼくには見えた」
「なら、信じるよ」
あっさりと言った。
「お前は、こんな噓はつかない。お前は本当に真夜が見えてるんだと思う」
「隼人、ありがとう」
「ただ、半分だけな。真夜が本当にそこにいるかは、判断保留にさせてくれ。お前は噓を言ってない。でも、何かを勘違いしてる可能性だってある」
それで充分だった。いきなりこんな話を聞かせて、ドン引きされたり怒られたりしても仕方ないと思っていた。半分信じてもらえるだけでも、いまのぼくにはありがたい。
「それで……真夜はなんでそんなところにいるんだ?」
当然そのことは、真夜から聞いている。
真夜が打ち明けてくれた話は、こういうものだった。
五日前の水曜日、二十一時ごろ、真夜は川沿いのサイクリングロードを自転車で走っていた。塾から自宅に帰るのに、いつもその道を使っていたらしい。
夜中から雨になるという予報で、天気が崩れそうな気配がしていた。まとわりつく湿気の中、真夜は自転車を飛ばしていた。
〈助けて!〉
突然、子供の声が聞こえた。
声は、川のほうから聞こえてきた。真夜は、自転車を停めた。
ここ何年かで川沿いにはマンションが新しくでき、サイクリングロードのあたりはほのかに明るい。でも、川までは距離があって、河原のあたりは暗くてよく見えなかった。子供の声は、闇の向こうから響いていた。
真夜は、迷った末に川に向かって歩きだした。警察を呼ぶことも考えたけれど、急を要する事態だったらいけないと思ったらしい。正義感の強い、真夜らしい行動だった。
悲鳴の主の正体は、川まで半分くらいの距離を歩いたところで判った。
川で、女の子が
薄闇の向こうに、川の中でバタバタとあがく小さなシルエットが見えた。幸い、女の子がいるのは、岸の近くだった。いまなら助けられる。真夜は突き動かされるように、全力で走った。
そして、川岸まできたところで──真夜は、バランスを崩した。
〈たぶんあのとき、木の枝を踏んだんだと思う。バチッと枝が折れるような音がして、その瞬間に私はバランスを崩した〉
次の瞬間、黒い
そこから先は、あまり記憶がない。自分が川に
そして、ものすごい勢いで、闇の中に引きずり込まれていった。
「それで、気がついたら、河原にいた……か」
隼人は
放課後。ぼくたちは
川に落ち、しばらく闇の中に引きずり込まれていったあと、真夜はまた別の何かに引っ張られるのを感じたらしい。そして気がつくと、自分が転落したあたりの河原にいた。
誰とも話せなかった、と真夜は言っていた。河原には、現場を調べにきた警察官や、花を供えにきた同級生、先生、地元の人たちなんかがやってきたけれど、声をかけても、触ろうとしても、相手とコミュニケーションを取るのは無理だったそうだ。
四日間ずっとそのままで、焦りと孤独感でおかしくなりそうだったところに、ぼくが通りかかった。意思疎通ができて、真夜は腰が抜けるくらい安心したらしい。出会ったとき、へたりこんでいた真夜は〈よかった……〉と涙ぐんだ声で言っていた。
なぜ真夜と話せるのかは判らない。そして、もうひとつ判らないことがある。
〈真夜は、事故で死んだんじゃない。去年もう、なくなってたのに。噓なんだよ〉
真夜が川に落ちたのは、間違いなく先週の水曜日だ。〈去年もう、なくなってた〉というのは何のことなんだろう。
真夜に直接聞いてみたけれど、見当がつかないと言っていた。涼子も言っていたが、そもそも最近ふたりはあまり会ってもいなかったようだ。ぼくの聞き間違えか、全然脈絡のないことを涼子が呟いたのか。とにかく、真夜が事故で五日前に死んだのは、間違いない。
川のそばにつき、ぼくたちは土手を上がりはじめる。
──真夜は、いるだろうか。
少し不安になってくる。昨日見えた真夜はぼくが作りだした幻覚で、河原には誰もいないんじゃないか。一歩歩くごとに、不安が少しずつ高まってくる。
「あっ!
いらない心配だった。土手を登ると、昨日と同じ場所で、真夜が手を振っていた。
真夜がいる場所は一面の芝生で、川沿いに背の高い草むらがあるくらいでほかには何もない。黄緑の芝生に、真夜の赤いパーカーはよく目立つ。ぼくは手を振り返した。
「真夜が、あそこに見えるのか?」
「うん」
「そうか」
隼人はそう言って、軽く雑草を
「俺には、川しか見えねえ」
河原まで下り、真夜に近づく。真夜の姿は、幽霊みたいに透けているわけではなく、本当にそこにいるみたいにリアルだ。
「やっ、今日もきてくれてありがとう」
全体的な印象は、小学生のころとあまり変わっていない。中学に入ってもイメチェンをするでもなく、大きな丸い眼鏡も、赤いパーカーにジーンズというさっぱりとした
「うえー、
真夜が隼人をじろじろ見る。
「背も伸びたし、すっごい恰好よくなったね。
「隼人、真夜が恰好よくなったって。西中にこんな子はいないってさ」
隼人は少し
「まあ、信じられないのも無理はないよねえ……」
真夜は、隼人にパンチを入れるみたいに
「こんなことも、あろうかと……」
真夜は、ぼくのほうを向いた。
「吉見くん。小瀬くんに、伝えてほしいことがあるんだ」
「何?」
「六年生のとき、クラスの女子たちと、
笹塚リトルは、小学生のころに隼人が入っていた地域チームだ。
「そのとき、私はあるものを差し入れに持っていったんだけど、小瀬くんは〈おばあちゃんかよ〉って馬鹿にしたように笑った。あれ、ショックだったんだよねー。クエン酸がたっぷり入ってて乳酸を分解してくれるから、いいプレゼントだと思ったのに。あのときのこと、恨んでるよって、伝えて」
全然恨んでないような口調で言う。ぼくはそのまま隼人に伝えた。
「お前……その話、なんで知ってる?」
隼人は目を丸くした。
「いま、真夜に聞いたからだよ」
「本当か? 前に真夜から聞いてたとか、そんな話じゃないよな。もしそうだったら怒るぜ?」
「いま初めて聞いたよ。だいたい、真夜は陰口なんか言わないだろ」
「まさか。でも、そんな……」
隼人は頭を抱え、ぼりぼりとかいた。その姿勢のまま、真夜がいるあたりをじっと見つめる。
「信じる」
しばらくして隼人は、答えを出した。
「疑って悪かった。
「本当に?」
「だってそうとしか考えられない。お前は噓を言わないし、差し入れのときに、真夜の周りには誰もいなかった。俺には見えないけど、本当に真夜はそこにいる。間違いない」
あっさりと認めた隼人の柔軟さに、ぼくは感心した。隼人は手を合わせ、軽く頭を下げる。
「真夜に伝えてくれ。あのときはごめんって。試合前で、ちょっとハイになってて、心ないことを言っちまった。許してくれって。
「聞こえてるし」
作戦成功という感じで、にしししと笑い、ぼくにピースを送ってくる。あっという間に隼人を信じさせてしまった真夜も、同じくらいすごい。
「ちなみに、その差し入れってなんだったの?」
「……梅干し。
まあ……それは確かに、おばあちゃんっぽい。
「でも、やっぱりよく判んないんだよな」
隼人が腕組みをして言う。
「どうして真夜が見えるんだ? いままで、死んだ人が見えたことなんか、なかったんだろ?」
「うん。でも、ぼくの〈力〉は、見たいと思ったものを見る〈力〉だから──真夜に会いたいと思ったから会えたのかもしれない」
「それなら、学校でも家でも真夜の姿が見えるはずだろ。なんでこの場所にこないといけない?」
「それは……判らないけど……」
そもそも自分の〈力〉がなんなのかも判っていないのに、答えられるわけがない。
「私なりの仮説があるんだけど、いい?」
口ごもっていると、横から真夜が手を挙げた。
▶#6へつづく
◎前編の全文は「カドブンノベル」2020年8月号でお楽しみいただけます!