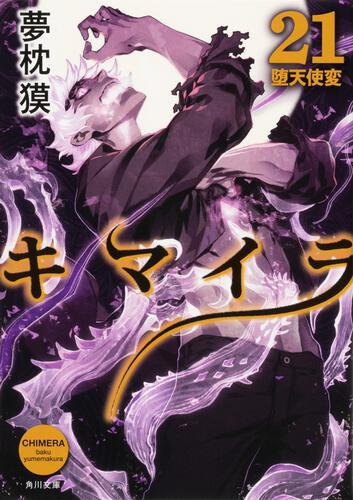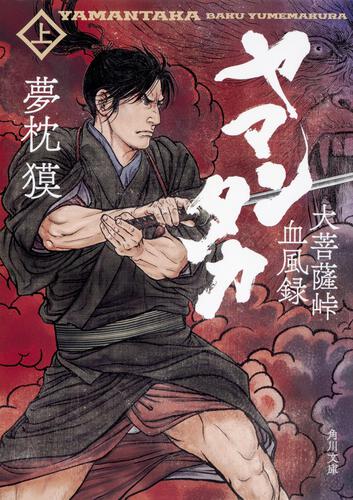遣唐使・井真成に降りかかる数々の試練。 旅に出た真成一行の行く手にあるものは? 夢枕獏「蠱毒の城――⽉の船――」#105〈後編〉
夢枕 獏「蠱毒の城――月の船――」

※本記事は連載小説です。
>>前編を読む
始皇帝を見てみたい──
項羽の一番の興味はそこであった。
負けたら、滅ぶ──それが、この世の
敗れたら滅ぶ、勝ったら滅ぼさねばならない。
だから、略奪し、咸陽も焼いた。
その炎は、まだ消えない。
滅びには、どこか美しさがある──
項羽はそう思っている。
しかし、略奪し、焼く前に、始皇帝という人物を眺めてみたい。
それが、項羽の思いであった。
墓を覗くというのは、始皇帝の心の中を覗く行為と同じだ。
だが、思わぬことがおこった。
それが、外羨門の左右が崩れてきたことだ。
噂は、耳にしていた。
この陵の建設に携わった者、七十万人余。
この
冢をあばこうとする者があれば、その者を、からくり仕掛けの弓と矢で射殺すようにもしたという。
地下の水脈を、三つも掘り下げ、周囲を岩で囲み、さらに銅板を下に敷いた。
この作業に関わった者、つまり、内部の様子を知る者のことごとくを、陵墓に残したまま門を閉じ、始皇帝は殺してしまった。
そういう仕掛けの奥で、死してなお始皇帝は、
できることなら、その棺を剣で叩き割り、始皇帝を揺すり起こして、
「次の王はこのおれだ」
この言葉を、その耳に注ぎ込んでやろうと思っていたのだ。
それが、このありさまだ。
人を増やして、作業をさせれば、いずれ、
羨というのは、陵墓、つまり冢の通路のことだ。
内部に入るための外にある羨が外羨で、内部にある羨が中羨である。
その中羨を、この自分の二本の足で踏まねばならない。
しかし、人の作業では、時間がかかりすぎる。
今すぐ、見たいのだ。
そこへ、不思議な人物が、范增に声をかけてきたのだという。
「おれが、ひと息に、陵墓への道を通してやろう」
その人物がそう言ったというのである。
その人物を、范增の部下が、今、連れに行っているのである。
「きましたぞ」
范增の声で、ようやく項羽は振り返った。
そこに、ひとりの老人が立っていた。
范增よりも歳が上、八〇歳は越えているだろうと思われた。
古い、ぼろぼろの道服を着ている。
「おまえか」
項羽は、その老人に声をかけた。
「来い」
老人は、范增の後ろに立っていたのだが、項羽に呼ばれて前に出ようとしたところを、范增と、囲んでいた三人の兵に止められた。
理由はわかる。
それは、その老人が、背に剣を負っていたからだ。
噓を言って項羽に近づき、殺そうと考えている人間かもしれないと、范增や兵たちが考えるのは、自然なことである。
「かまわん」
項羽の声で、老人を押さえていた手が離れた。
項羽の前に、その老人が立った。
「名は?」
項羽が訊ねる。
「
老人は、真っ直ぐに項羽を見ながら言った。
奇妙な名だ。
しかし──
青壺?
とは、項羽は訊き返さない。
男は、左手に握った縄に、三頭の羊を繫いでいた。
妙な光景であったが、その羊はなんだとも項羽は問わなかった。
「青壺とやら、おまえ、この冢の羨を、ひと息に通すと言ったそうだな」
「言った」
「試せ」
項羽の言葉は短い。
「できねば、おまえを首にする」
「好きにせよ」
老人──青壺は言いながら前に出て、項羽を越して、崩れた岩の前に立った。
「これを──」
左手に握っていた羊を繫いだ縄を青壺が持ちあげると、兵士のひとりが飛んできて、それを受けとった。
青壺は、両足を軽く前後に開き、右手で、背の剣を抜いた。
柄を両手で握り、頭上に振りかぶって、
「むん」
岩に向かって剣を斬り下げた。
ごう、
と、音をたて、光のような剣風が、
その光が、青壺の眼前の岩に向かって
ごきゃっ、
という音がした。
剣先が、岩に触れていないのに、青壺の前にあった幾つもの岩のことごとくが割れて、裂けていた。
人ひとりが充分通れるほどの羨──通路がそこにできていた。
「開いたよ」
青壺は言った。
(つづく)