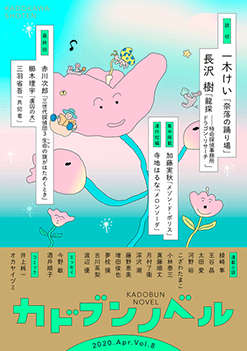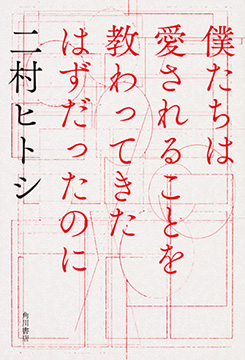仕事はデキるが女には弱い名探偵。今回の依頼は女性AV監督の護衛なのだが――。長沢 樹「龍探――特命探偵事務所 ドラゴン・リサーチ」#1-1
長沢 樹「龍探――特命探偵事務所 ドラゴン・リサーチ」

元敏腕刑事の遊佐龍太が営む探偵事務所「ドラゴン・リサーチ」は、警察の手に余る厄介な依頼が持ち込まれる特殊な探偵事務所。この遊佐龍太が活躍する『龍探―特命探偵事務所ドラゴン・リサーチ』が3月24日に角川文庫より発売。刊行に先駆けて、第一話をカドブンで特別公開します!
新刊はこちらから
◆ILLOGICAL 非論理的◆
十一月九日 金曜 川崎市川崎区某所 11:33pm
眼前の壁で火花が
「ほんとに撃ってきた」
背後に隠れていたマコも通りをのぞこうと、背中に胸を押しつけてきた。「大陸の人は自由で大胆だね」
「くっつくな」
遊佐は再び身を隠すと、マコを押し返した。「自由で大胆な人が撃ってくるなんて、聞いていないんだけどな」
「わたしも知らなかった」
「ほんとにというのはどういう意味だ」
「鉛弾
「ならなぜ大陸の人とわかる」
「だって借りるとき、それぞれと顔つき合わせてますもん」
多重債務。それも複数の脱法上等金利自由の金融業者から。それが彼女が抱えている事情だ。
「一番やばそうなとこの、
マコと合流した駐車場には、すでに不穏な空気をまとった人影が複数いて、挨拶もそこそこに車を諦め、駐車場から連れ出した。
途端に、これだ。
「走るぞ」
壁と壁の間を、路面にはみ出した雑多な機械片や鉄片を
川崎の重工業地帯の一角だ。大規模工場、産業用道路、貨物線が入り組む中に、昔ながらの中小の工場、倉庫が密集している。
移動に合わせて、時折複数の足音や
背後でまた乾いた破裂音。
「向こうはサプレッサー付きか。音とマズルフラッシュで位置を特定するのは難しいね」
「そんな知識、どこで仕入れた」
「マンガと小説と映画」
「この日本で一般人が銃撃されるのは、マンガと小説と映画の中くらいなんだが」
「探偵さんは道具持ってないの?」
ここで言う〝道具〟とは拳銃のことだ。
「日本に拳銃を所持した探偵はいない」
「元警官なのに?」
一応、信用商売だから、プロフィールには記述してある。
「元警官だろうと拳銃は持てない。マンガと小説と映画は教えてくれなかったのか」
「人を撃ったことある?」
「ノーコメント!」
「それ肯定と同じじゃん。ちょっと安心」
見た目は二十三、四歳くらいだが、二十九歳と聞いていた。黒髪ショート。上下カジュアルジャージで、胸元は開きがち。厚めの唇と潤みがちの瞳が、ともすれば保護欲と性欲を
「でも、わたし殺したらお金返ってこないのにね」
「あとで危険手当も別途請求しておく」
息子が来年高校受験で、何かと入り用だった。破格の依頼だったが、構わないだろう。
「日本に拳銃を持った探偵がどうとか、もう一回言ってくれない?」
マコが肩にかけたトートバッグから小型のムービーカメラを取りだし、RECボタンを押した。
「何してる」
「ドキュメントの撮影」
カメラを向けてくる。「ほらいい男。ハットとヨレヨレのシャツがちょっと渋めで退廃的で、
彼女は有名な映像作家らしく、バッグからはシナリオらしき紙束やノートパソコンが顔をのぞかせている。
「怖くないのか」
「これが最後かもしれないし。生と死の記録」
「悲壮だな」
「探偵さんにとってもだよ」
「聞き捨てならんな」
「ムラッとこない?」
「なに言ってんの」
「男って命の危険が迫ると、本能的に子孫を残したくなるんでしょ」
「だとしても原因を作ったのは君なんだが」
「じゃあ、責任取ってエッチさせて頂きます」
「言ってる場合か」
「確かに生き残らないと子孫残せないものね」
「残す前提か」
連中の目的は彼女の殺害ではなく拉致だろう。射撃は心を折るための手段。ここは──「こんな零細探偵でも、いくつか隠れ家を用意しているんだが、そこに行く」
問題は、どう逃げるか。この辺りは貨物線の線路と運河に挟まれた細長い土地で、複数の追跡者から長時間逃げることは難しい。北に行けば
陸橋が見える位置まで近づくと、また路上で火花が弾けた。やはり、警戒していた。マコを促し、来た道を戻る。
「事情は
「却下。それより家に帰りたい」
「
四発目が近くのブロック塀で
「借りる時に記入したのは、個人事務所の住所。自宅は教えてない」
「連中の情報収集能力を甘く見ないほうがいい。自宅は割れている前提で行動すべきだ」
「でも、今のうちに大事なものを持ちだしておきたいの」
「だったら俺が行こう。住所を言ってくれ」
「言えない。わたしが行く」
「じゃあ俺を雇った意味がないだろう」
マコがカメラをおろし、人差し指を遊佐に向ける。
「とにかく今を切り抜けて」
最初から違和感が付きまとう依頼だった。
十時間前 十一月九日 金曜 川崎市中原区 1:17pm
駐車場に愛車シトロエンBXを入れ、食材が詰まった紙袋を手に通りを渡る。
遊佐は紙袋を抱え直すと、住居兼事務所の鍵を開け、
「こちらの事務所の方ですか」という声に振り返り、肝を冷やしかけたことを伏し目で誤魔化しつつ、「御用ですか」と視線を上げたところで電流に撃たれた。
艶のある長い黒髪で、目鼻立ちのスッキリとした美しき女性! 二十代半ばか。白のパンツにベージュ系のニットと薄いカーディガン。雰囲気は透明感の塊だ。
「こちらはドラゴン探偵社さんですか?」
思い切り社名を間違えているが、その所作と口調は実に自然で品がよく、不快感は覚えない。看板は出さず、広告も打っていないのだ。社名違いは許そう──
「ドラゴン・リサーチの遊佐と申しますが」
キリリと表情を作り直し、応える。
「すみません、そううかがっていたもので」
彼女は丁寧に頭を下げた。「タカラダアカリと申します。
アカリと名乗った女性は、濁りのない真摯な瞳の持ち主だった。「お仕事を依頼したいのですが」
「寒いので中へ」
遊佐はアカリを事務所に招き入れた。
祖父の代から営んでいた木造平屋建ての自転車店をリフォームし、作業場を事務所兼応接室にした。床のタイルはモノトーンのチェック、壁もグレーやブラウンの落ち着いた色で
アカリを窓際の応接テーブルに案内した。
「かけて待っていてください」
ソファはフランス製で、十七軒の輸入家具店を回り、厳選したものだ。
ジャケットとハットを脱ぎ、執務デスク脇のコートハンガーに掛け、隣接するダイニングの冷蔵庫に食材を入れると、事務所に戻る。よくできた息子=中学三年生のお陰で、隅のコーヒーメーカーは、香ばしい匂いを漂わせていた。律儀に
ちらりと時計を見ると、午後一時を過ぎていた。
「コーヒー飲みます? ちょっと時間が経ってるけど」
「頂きます。ありがとうございます」
アカリは遠慮することなく、とはいえ
「看板が出ていないので、少し不安でした」
改めて見ると肌は白くきめ細かいが、どこかエキゾチックさも感じさせる。その微妙なアンバランスさが、美しさにアクセントをつけている、などと分析しながら遊佐はビジネスフェイスを貫く。
「調査員が俺一人でね、今は紹介の仕事しかしていない」
一時間前、昼食兼夕食の食材を買いに出た時にはいなかった。「待ちました?」
「短時間です。お気遣いありがとうございます」
「織原のヤツ、どんな紹介の仕方をしたんでしょうね、申し訳ありませんね」
いい加減な社名を伝えた、元同僚の仲介人だ。
「住所と電話番号を聞いたのですが、電話番号をメモするときに間違えてしまったようで……。織原さんにはすぐ電話を返したのですが、つながらないので、直接おうかがいしました。あらためまして、タカラダと申します」
名刺交換をした。
『Tプランニング 代表取締役社長 宝田灯梨』
「どういったお仕事ですか」
「映像作品の制作をしています」
DVDのようで、パッケージには、微笑み、胸を強調したメイド服の美少女。
タイトルは汗と涙とヘドロとアリス。『貴石乃アリスが奇跡の痴態』とキャッチコピーがついている。
手に取り裏を見ると、メイド服をオイルで汚され、汚泥の中でブルーカラー風の男たちに
「アダルトDVDですか」
パッケージの背を確認すると『Tプランニング』と印字されていた。出演女優の
「あ、それはわたしではありません」
何を勘違いしたのか、灯梨は両手を振る。「会社の危機に当たり、わたしも出演陣に加わると言ったのですが、専務にAV女優なめるなと言われまして、今はまだ制作に専心しています」
勘違いの上塗りに加え、中間の説明をすっ飛ばしているようだ。
「会社は規模を縮小して、なんとか続けている状態です。あ、それはさし上げます」
灯梨の
「会社は、もしかしてご親族からうけ継いだとか?」
でなければ、
「父からです。
くも膜下出血だったという。「それで、専務以外の人たちはいなくなったので、わたしが立ちました」
灯梨は現在二十七歳。大学卒業後、ハワイの撮影コーディネーター会社で営業事務をしていたが、去年帰国し、Tプランニングの代表取締役に就任したという。社員は灯梨のほか、
「社長になったのはいいですが、制作は外注で、なかなか人材が揃わず、あらためて先代の偉大さを感じています」
灯梨は苦笑のあと、表情を引き締め、居住まいを正す。「それで依頼なのですが、我が社の主力監督を撮影現場から無事逃がして頂けませんでしょうか。期日は今日から」
出演女優か、モデルプロダクションとのトラブルは時折聞く。プロダクションの背後には、暴力団や半グレ集団など反社会組織がついていることも多い。
「どのような理由で、誰から守ればいいのですか」
「いわゆる反社勢力と呼ばれる方たちです。理由は債務の延滞です」
借金──恐らく街金からか。
「法的に問題は」
「ないと思います。向こうは不法な高利で貸し付けたわけですから、あくまでも当事者同士の問題です」
灯梨はくもりのない瞳でうなずいた。
「まずはその監督のプロフィールを」
「名前はバーゴン・マコです」
「バ……バーゴン?」
灯梨は生真面目な表情でうなずいた。パッケージに書かれていたのは監督名だった?
「彼女は根強いマニアが一定数ついている、我が社の稼ぎ頭です。いなくなったら大損害です。業界的にも損失は大きいと思います」
「……彼女?」
灯梨は写真を遊佐の前に置いた。二十代半ばに見える女性。証明写真だが、その目は自信に満ち、行動的で野心家のようなパーソナリティーが
「我が社が把握しているだけで、七つの金融機関からお金を借りています」
灯梨は、メモを遊佐の前に置いた。どれも街金融で知らない名もいくつかあった。
「本人は自分の責任で借りているので、心配するなと言っていますが、我が社にも問い合わせがありまして……」
「それぞれの金額は」
「確認はできていませんが、それぞれ数十万円かと」
全て合わせると、三ケタ万円になるだろう。「大事なスタッフです。守りたいんです」
灯梨は両の拳を握り、力を込める。先代の会社を懸命に守ろうとする、若き美人社長。実にいい物語だ。遊佐は執務デスクからノートパソコンを持ってくると、開いた。
「ほかにトラブルや特記事項は」
「今朝、彼女の個人事務所に何者かが侵入して、荒らされました」
タイピングの手が止まった。徹夜仕事のバーゴン・マコのため、着替えを取りに行ったアシスタントディレクターが異変に気づき、その場で警察に通報したという。
「通報はしたのですね」と念を押す。
「事務所荒らしに関してのみです。久和の指示で、それ以上の事は伝えていません」
思えば最初の違和感は、ここだった。
「マコさんの身辺は警察以外のプロに任せると、専務が」
織原は現役の警察官だが、灯梨はそれを知らないようだ。「織原さんからは、遊佐さんが腕利きの警察官だったと聞きました。弱きを助け強きを
また織原がいい加減なことを吹き込んだようだ。「ハマーさんという方のことは、よく存じ上げませんが……」
「シロナガスクジラなみの尾ひれがついているようですが、どこで知りました?」
「ハマーさんですか?」
「いえ、織原のことを」
「久和が連絡先を知っていまして、相談するようにと」
事務所荒らしと身辺警護を別立にする辺り、久和という専務はそれなりにくせ者であることは想像できた。
「それで、バーゴンさんとはどこで合流を?」
「いまは川崎のスタジオで撮影中です。午後十一時に終了の予定です」
川崎区
「……それで経費を節約しているわけです。出演女優は四人。男優は十二人。監督、撮影スタッフ、制作スタッフ、メイクさんなどはいろいろ兼任してもらっています」
撮影終了予定の午後十一時にその休眠工場に行き、バーゴン・マコと合流する。そして、マコと相談の上、入金まで逃げ切る。詳細は直接マコと打ち合わせると話が決まった。
▶#1-2へつづく
◎第 1 回全文は「カドブンノベル」2020年4月号でお楽しみいただけます!