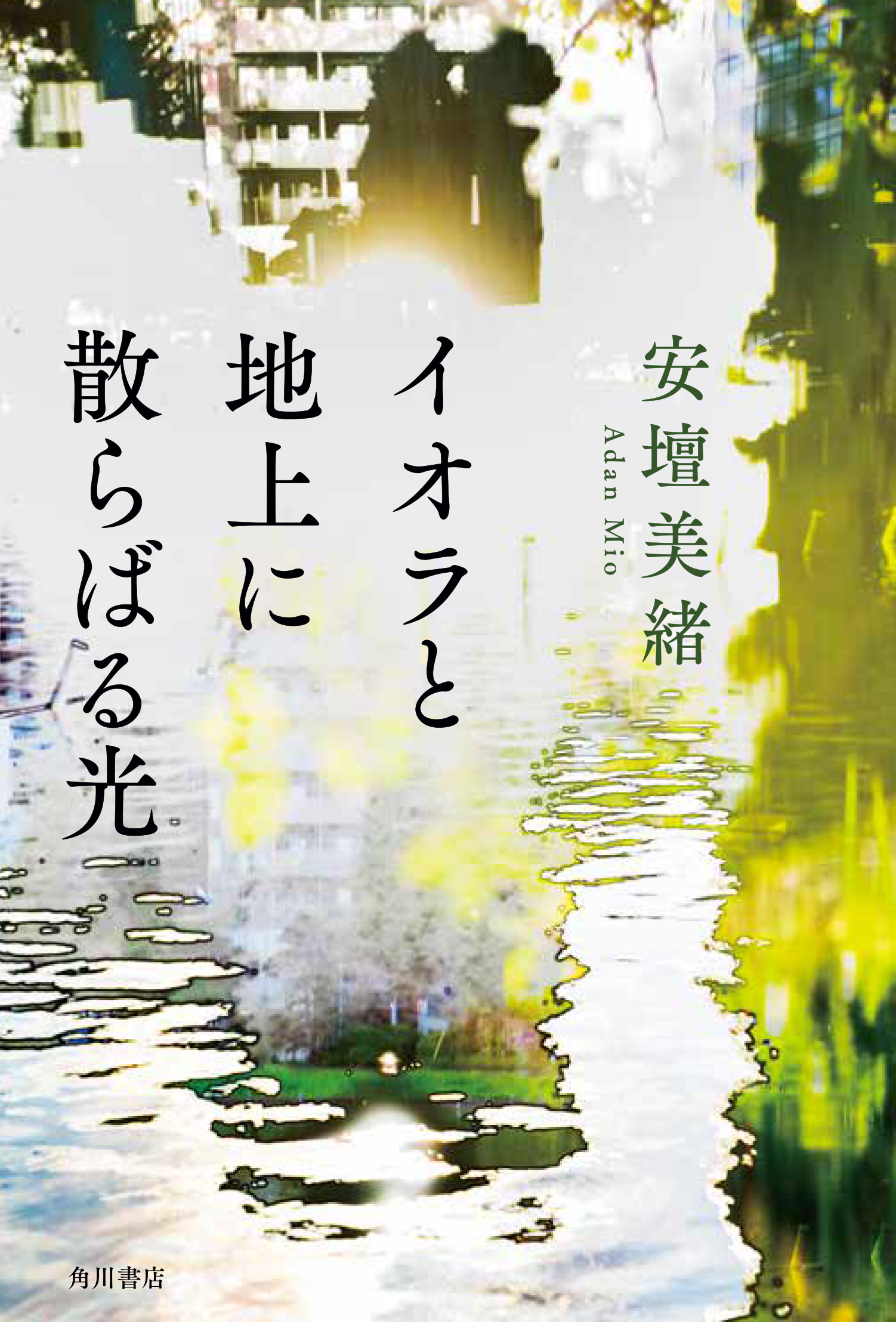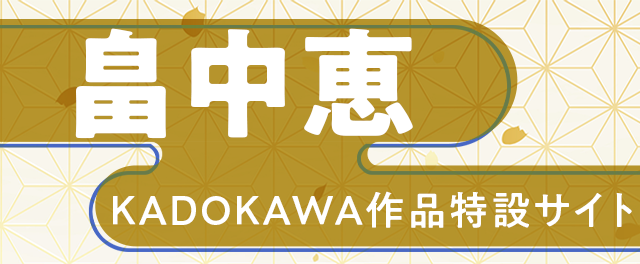澤村伊智の快進撃が続いている。
ぼぎわんという化け物の恐怖をめぐる『ぼぎわんが、来る』で第二十二回日本ホラー小説大賞を受賞したあと、都市伝説的ミステリ『ずうのめ人形』、怪談『ししりばの家』、サイコ・サスペンス『恐怖小説 キリカ』、さらに短篇集『などらきの首』など次々に世に送り出している。とりわけ『ぼぎわんが、来る』が『来る』というタイトルで中島哲也監督によって映画化されてから、人気に拍車がかかり、いまや若手ナンバーワンのホラー作家になったといっていいだろう。
そんな澤村伊智の最新作が『予言の島』である。澤村伊智の長所がつまった内容で、出来ばえもいい。
物語はまず、ある島で撮影中の心霊番組の場面から始まる。女性霊能者が山に棲む怨霊の存在に気づき、そこに向かおうとする。村人たちは、取り返しのつかないことになるぞとおそれるのだが、霊能者の孫だけは、全部インチキなのではないかと言い放つ。
それから二十二年後、天宮淳、大原宗作、岬春夫ら高校時代の友人たちが、その霧久井島をめざす。当時、霊能者は撮影中に体調を崩し、二年後に亡くなった。怨霊の祟りをおそれてか、番組はお蔵入りになった。
その霊能者はいまなお語り継がれる宇津木幽子で、彼女は死ぬ直前に謎めいた文言を残していた。ある解釈によれば「今年の八月二十五日から二十六日の未明にかけて、霧久井島で六人死ぬ」という予言だった。淳たちはそれを間近で確認しようという邪な考えで島を訪れたのだが、観光客は彼らばかりではなく、中年の母と青年の息子、派手な装いの中年女性、そして童顔で小柄な若い女性などもいた。
もちろん島の住民たちは彼らを歓迎するはずもなく、不穏な空気のまま時間が過ぎ、やがて予言通りに、一人ずつ死んでいくのだった。
いやあ驚いた。終盤に大きなどんでん返しがある。それまで細かい違和感があり、ネタバレになるので詳しくは書けないが、ある種の揺らぎというか、不確かさのようなものが小骨のように喉にひっかかっていたのだが、なるほどこれだったのか! と合点した。
澤村伊智のいいところは、『ずうのめ人形』がいい例だが、ホラー的要素とミステリ的な謎解きの要素を組み込んで、なかなかスリリングな作品に仕上げている点だろう。現代人らしい冷静な(ときに白けた)視点から怪異現象を分析しながら(つまり合理的な視点を忘れずにのぞみながら)、それでいて必ずしもオカルトを否定するわけではなく、どこかネタとして愉しむ余裕がある。シニカルでありながら真摯、それでもコミカルの部分は残っていて、苦笑しながらも恐ろしく不安を覚えつつ緊迫感のただなかに入っていく。
それは本書も同じで、「推理小説が作者の都合の御伽噺なら、予言はさしずめ読者都合の暗号ね」と、まさにいまあなたの読んでいる小説を冷やかしながら(このあたりは『恐怖小説 キリカ』を思い出させる)、どうみても予言通りの展開をたどり、主要人物たちは自分が死者になるのかと、呪いの真実に戦慄を覚えるようになる。
本書が優れているのは、横溝正史の小説の言葉を冒頭に配して、いかにも伝奇的なホラーを意図していながら、たとえば呪いといったものを日常的なレベルにおきかえて、言葉による暴力や洗脳として捉え、「みんな誰かに——誰かの言葉に縛られて、振り回されて生きてる」「お互いがお互いを縛ってる感じがする」と呪縛という概念を現代的な視点で解きあかしている点だろう。そしてこれがそのまま家族という主題を掘り下げ、読者をあっといわせる仕掛けとも繋がっていてなかなか心憎い。また、ホラーで昂奮したいという読者の欲望に充分にこたえながら、ひとつずつ予想外のところへもっていく手練手管も頼もしい。
冷静に考えれば、いくらなんでもあの秘密をあそこまで保てるのかと思わないでもないが、そのあたりもホラーのお約束という愛嬌に変えて愉しませてくれる。澤村伊智の会心作だろう。
書誌情報はこちら>>『予言の島』
紹介した書籍
関連書籍
-
レビュー
-
連載
-
試し読み
-
特集
-
レビュー