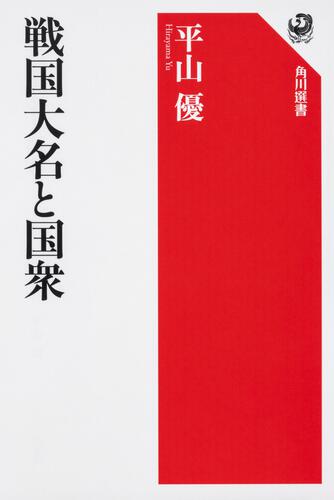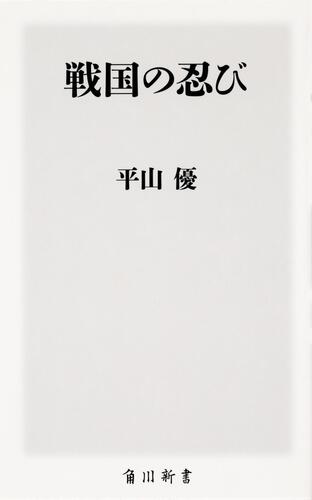戦国時代の地域領主のことを、「国衆」と呼ぶことについては、NHK大河ドラマ「真田丸」「おんな城主 直虎」によりかなり一般にまで浸透してきた。城を持ち、戦国大名に翻弄されつつも、独立を保ち、合戦にも軍勢を率いて参加する存在であることが、かほどに理解される時代が来るとは、正直予想外である。それほどまでに、かつて戦国大名研究では傍流だったのが、国衆研究である。国衆こそ、室町期の国人領主の流れを汲みつつも、一層発展した領主であることが明確になってきたのは、一九九〇年代になってからだ。
では、なぜマイナーな扱いだったかといえば、史料が極めて少ないからという理由に尽きる。発給文書や受給文書、関連史料が豊富な国衆は、中部地方でも指折り数えるほどでしかない。そのため、個別研究にも限界があった。ましてや、室町期から戦国期にかけての成長をたどることができる国衆は、もっと少ないのだ。ある意味で、地域の人々にとって、「おらが殿様」は、ほんらい武田信玄や今川義元などではなく、集落の山で草木に埋もれた小さな古城や、村の寺を創建した国衆であるはずなのに。
本書では、一つひとつの国衆を解説していくのではなく、武田氏の領国をフィールドに、網羅的に紹介しつつ、その特徴を点検、確認する手法を用いた。もちろん、室町期国人領主から、どのような経緯をたどって国衆に成長したのか、その基盤となる国衆領(当時は「〜領」「国」などと呼ばれた」)がどのように形成されたかを、限られた史料をもとに叙述してみた。そこから浮かび上がる成長の秘密は、まさに戦国争乱という混乱を契機に、荘園を自力で切り取り、周辺の領主を押しのけ、村の土豪や百姓を被官に組み込み、新たな一円的領域支配権を確立したことにあった。
キーワードは領域支配権の確立(「領」「国」の確立)である。それまで、なんらの由緒も、関わりも持たなかった村(百姓)、町(商人、職人)、寺社を保護下に置き、治安維持や裁判を機能させて領域内の秩序と安寧を保つ自力による支配、これこそが領域支配権の内実である。
いっぽうで、国衆は単独で自らの領域支配権を安定的に確保することはできなかった。彼らを国人領主から脱皮させた契機が戦国争乱であるならば、同時にまた彼らを存亡の危機に常に陥れたのも同じ理由に他ならない。それゆえに、より強力な実力を持つ勢力に連なり、その保護下に入ることで、領域支配権の安定を図ろうとしたわけだ。こうした動きに、戦国大名の成立や膨張、そして滅亡の秘密が潜んでいるといえるだろう。
戦国初期、各地に複数の中小国衆を統括する広域支配権力が登場し始めていた。例えば、信濃国では、諏方・村上・小笠原・高梨・岩村田大井氏がそれに当たる。彼らは、戦国大名への脱皮を遂げつつあった存在であった。その可能性は断ち切られた。隣国甲斐を統一し、一国支配権を確立した戦国大名武田氏による軍事侵攻にさらされたからである。
それに抵抗し続けた者、抵抗を諦め従属した者、戦ったがすぐに服属した者など、様々な反応を通じて、国衆は武田氏に編成されていき、一円領たる国衆領にも変化がもたらされた。しかし、独立領主たる性格は失われず、戦国大名はそれを包摂する形で領国を編成していった。それゆえに、戦国大名領国は、直轄支配地域(国衆、土豪などを討滅、追放し直接支配を確立した地域)と、国衆領とによるモザイク国家の様相を呈した。それは軍事力編成にも、色濃く反映された。武田氏の軍事力は、譜代、直参による軍事力と、国衆(先方衆)の「家中」による軍事力の混成としての性格を持っていたわけである。そして、戦国大名、国衆双方は、政治的・軍事的に依存しあい、協力しあうことで領国(大名)と国(領)の維持、安定を果たしていた。その詳細は、ぜひ拙著を手に取って確認していただきたいと思う。
レビュー
-
試し読み
-
特集
-
レビュー
-
試し読み
-
特集