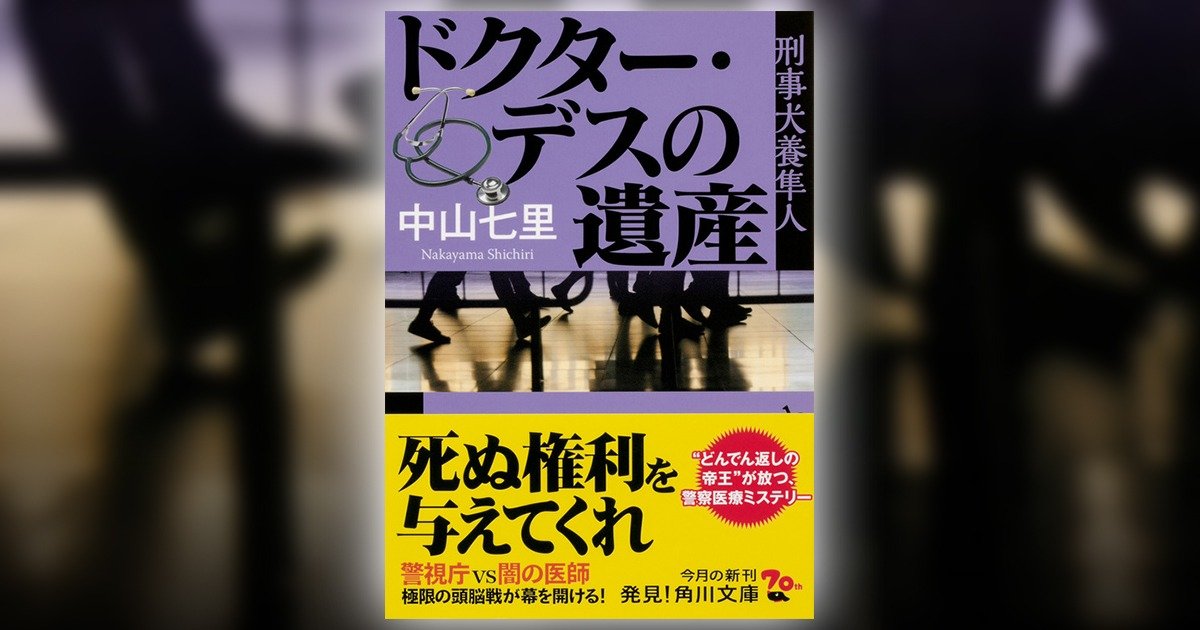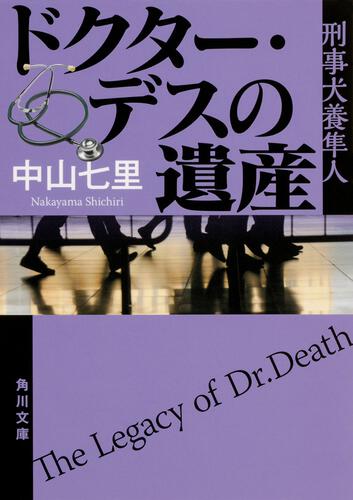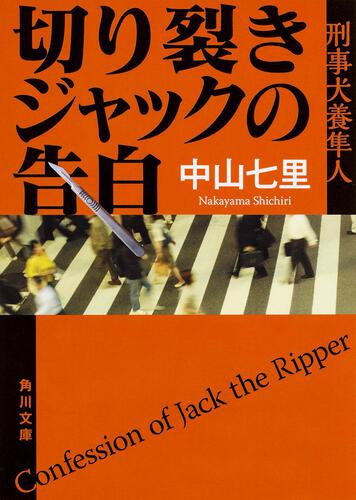『ドクター・デスの遺産』は、難病を抱える娘を持つ捜査一課・犬養隼人刑事が、部下の高千穂明日香とともに、末期患者らの安楽死を二十万円で請け負う「ドクター・デス」の逮捕劇を描いた中山七里氏の「刑事犬養隼人」シリーズ第四弾だ。その闇の人物とは誰なのか。悪魔、それとも聖人か。
犬養は、一人の刑事、そして一人の父親として、死を間近に控える患者の尊厳に立ちはだかり、葛藤する。それと同時に読者も、これまでとは異なる視点で安楽死を見つめ直すに違いない。
中山氏は、警察と安楽死依頼者たちの倫理的ギャップを緻密に映し出し、スリリングな見せ場とともに法を超えた人間の尊厳について、問題提起しているように見える。つまり、「生きる権利」だけに目を向けがちな現代社会で、個人が望む「死ぬ権利」を法が支配できるのか、という問いかけのようでもある。
本作品の中で、全身性エリテマトーデスという難病を背負う娘を安楽死させようと、ドクター・デスに依頼した父親・増渕耕平が取り調べ中に、次のように述べている。
「……痛がって、苦しんで、わたしに向かってお願いだから殺して欲しいとまで懇願したんですよ。だけど、わたしには、そして主治医の先生もどうすることもできなかった。最後の最後まで苦痛と絶望に塗(まみ)れた死でした。あんな目に遭わせるくらいなら、もっともっと早く安楽死させてやればよかった。な、何故もっと早く……」
介護、高額医療、保険金、相続……。昨今、高齢者を取り巻く諸問題が、殺人事件へと進展している。安楽死さえ認められていれば、と願う人たちの声も分からなくはない。登場する事件対象者たちのように、悪意でなく善意として、末期の伴侶を死に導こうとする人や、生かすだけの治療に意味を見出せない人もいる。著者は、現実に起こりうる社会問題を次々と事件化させ、犯行者のグレーゾーンに迫っていく。
もがき苦しむ最期を避け、その姿を家族に見せたくないという思いは、万国共通だ。余命わずかと知る医師たちも、現実の世界では患者を「楽」にすることはできない。現状の日本で、安らかな死を迎えることは難しく、だからこそ安楽死待望論を叫ぶ国民も増えている。ドクター・デスは、このような人々の願いを叶え、恨まれることのない存在として浮かび上がってくる。
正体不明の犯人が特定されてからのクライマックスは、凄まじい。なぜ、その闇の人物が安楽死を繰り返すのか。その背景には、戦地で悶絶する重傷者たちの生死をコントロールしてきた過去に由来した。
国や状況によっては、安楽死を正義と見なしたり、殺人と見なしたりする。戦争という舞台を織り交ぜることで、日本における「死ねない患者」たちこそが、尊厳のない戦傷者たちに等しいことを、著者は揶揄しているのかもしれない。
捜査一課が仕掛けた囮作戦で、犯人はまんまと罠にはまるのだが、末期癌患者を前にした二人は、呆然と立ち尽くし、犯人の言葉に動揺する。凄絶な殺害を実行するドクター・デスを前に、犬養は力なく肩を落としてしまう。刑事としての正義感に揺らぎが生まれるという、事件小説には稀に見る展開だ。
究極の選択を迫られた状況下で、法がいかに無意味であるか、読者が理解に苦しむことはないだろう。だが、医師であっても、死を早める行為は常に犯罪であることを忘れてはならない。
日本において安楽死は殺人罪に当たる。医師が薬物を投与し、患者を死に至らす「積極的安楽死」だけでなく、医師が処方した薬物で患者自らが自死する「自殺(自死)幇助」も認められていない。一九九一年に起きた東海大学付属病院事件を始め、二〇〇二年の川崎協同病院事件などは、医師が担当していた末期患者に筋弛緩剤を投入し、有罪判決を受けている。医師免許剥奪には至らなかったものの、彼らの現場復帰は不可能となった。
海外で安楽死が許されているのは、スイス、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、カナダや米国の一部にすぎない。中でも、スイスは外国人が安楽死できる、世界でたったひとつの国で、海外からの患者たちが「理想的な死」を求めて渡航する。実際の費用は約百万円で、ドクター・デスが受け取る二十万円では実現が難しい。だが、致死薬を使えば、患者が苦しまずに一瞬で息を引き取るというのは間違いない。
本作品でも触れられているが、安楽死が認められるためには、主に以下の四条件が満たされていなくてはならない。
- 回復の見込みがない
- 耐え難い苦痛がある
- 代替治療がない
- 本人の明確な意思がある
昨今、日本では、多くの著名人が安楽死を望んだり、自殺希望者が容認論を叫んだりと、以前に増して「死期を早める行為」に正当性を見出そうとする風潮が高まっている。まもなく高齢者人口が三五〇〇万人に達する中、われわれは「死にたくても死ねない現実」とどう向き合うべきか、議論を積み重ねていかなくてはならない。
胃瘻による延命や高額な医療費を払ってまでの治療など、人間はどこまで生かされるべきなのか。とりわけ、高齢者でなくとも、末期や難病患者が「本人の明確な意思」の下で安楽死を選択できるのかは、国の価値観によって大きく異なるところだ。
犬養は、犯人逮捕には手段を選ばない上司・麻生に対し、こう語っている。
「医療現場では医師の多くが法的責任を怖れて、積極的に終末期医療に取り組もうとしない。それに日本人独自の倫理観からすれば、どうしても患者の延命を第一に考えてしまいます。個人の死ぬ権利、終末期医療について一般的なコンセンサスが得られていないのも理由の一つでしょう」
「日本人独自の倫理観」で安楽死を考えた場合、欧米諸国との大きな違いは「周りに迷惑をかけたくない」という文化に尽きるかもしれない。キリスト教文化圏では、死はあくまでも「個人の死」であると考えられ、文中にもあるように「教義で自殺を禁じる一方、無意味な治療で本人を苦しませるのは形を変えた虐待や拷問に過ぎない」との認識もある。だが、日本では、家族や社会を巻き込む「集団の死」という意識の強さから、死がタブー視されてきた閉鎖性も否めない。
ドクター・デスは、犯行を認めた上で、犬養に説得力のある口調で、こう放つ。
『犯罪犯罪と言うけれど、それはまだこの国が安楽死の問題をタブー視しているから』
『安楽死の案件が多くなり、現状の規範では捌(さば)ききれないと知れた瞬間、安楽死は違法ではなくなる』
安楽死が世に認められるべき行為か否かを、中山氏独特の警察医療ミステリーとして扱ったのが本作品であるが、読後は、いかなる生命倫理や医療系書籍よりも刺激的に考える材料を読者に与えている。
この安楽死にまつわる『ドクター・デスの遺産』が出版されたのは二〇一七年五月だが、その約半年後には、私が世界六カ国で取材した『安楽死を遂げるまで』(小学館)が刊行された。前者は空想のフィクションで、後者は現実に基づいたノンフィクションだ。
私は、皮膚癌を患う英国人老婦や、多発性硬化症という難病に苦しむ元米大学研究者らの安楽死に立ち会ったほか、初期の認知症で致死薬を飲み干したオランダ人男性の家族や、重度の欝病を抱え安楽死を待つベルギー人女性の心境にも迫った。病状は異なるものの、誰もが同じ台詞を吐いていた。
「私には私の生き方や死に方がある。誰も口出しはできない」
個の生き方を尊重する欧米だからこそ受け入れられる最期であって、自己決定を憚られる日本社会ではなかなか難しい。それを知る私は、中山氏の作品を読み進めるうちに、不吉な予感がしてきた。
――この事件が実際に、日本で起こるのは時間の問題かもしれない……
日本人は今、死を前にして自由がきかないことを嘆く一方で、たとえ医療行為であろうとも、死は遂行されるべきでないとの期待もある。安楽死は、裕福で高学歴者が選択する先進国の社会現象であることも事実で、発展途上国では起きない理由を、われわれは考えてみる必要があるだろう。
安楽死が法として確立されなければ、ドクター・デスが世に出没する可能性もあるが、国が人間の死をルール化することも何か違う。日本では、「個人の死」というよりはむしろ、「他人に迷惑をかけないための死」に逃れる危険性を孕んでいるからだ。日本人が安楽死をしたいと言えば、それは必ずしも本人の意思によるものではなく、周囲の空気を読んでの意思表示になりかねない。安楽死がこの国で認められることは、しばらくはなさそうだ。
スイスで、年間八十人の患者を安楽死させる実存のドクター・デスは、こう言った。
「安楽死のほうが、患者も家族も納得できて良い別れになる。いつか、私が外国人を助けなくていい日が来てほしい。それには、世界の国々が死に対する考え方や対処法を変えなければならないのよ」
日本は今、死に方の切実な問題に迫られている。