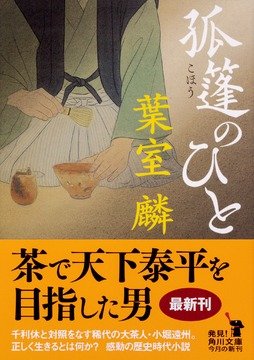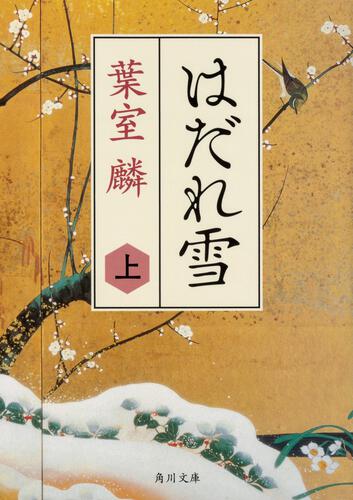文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
(解説者:東えりか / 書評家)
──人間五十年 下天の内をくらぶれば、夢幻のごとくなり──
桶狭間の戦い前夜、信長は「敦盛」のこの一節を謡い舞ったという。だがわずか五十年のうちに、信長は本能寺で果て、豊臣家が栄えたのも束の間、天下分け目の関ヶ原で徳川家康が勝利して徳川幕府が開かれる。まさに人間の一生分の年月で、世の為政者は夢幻のごとく浮かんでは沈んでいった。
『孤篷のひと』は小堀遠州の人生を描いている。幼名は作介、名は政一といい、天正七年(一五七九)に羽柴筑前守秀吉に仕える小堀新介正次の長男として生まれた。後に父に従い秀吉の弟、秀長の小姓として仕えたが、秀長が病没し遺領を継いだ秀保も亡くなった後、秀吉の直臣となる。その秀吉の死後は父とともに関ヶ原の戦いで徳川方に付く。
徳川が勝利し、備中国松山で一万石の加増を受けた父・新介が急逝すると、作介(遠州)がその遺領を継ぎ、作事奉行として駿府城や禁裏、二条城など多くの普請に携わり、建築と造園の才能を発揮し六十九歳の人生を全うした。本能寺の変ではまだ幼児であったにせよ、その後の豊臣家の隆盛から関ヶ原の戦いを経験し、家康によって世の中が平定される流れを具に見てきたのが小堀遠州なのだ。
作介が生まれたのは秀吉の茶の湯への執着が次第に熱を帯びてきたころだ。幼いころより新介について茶に親しみ、わび茶の大成者、千利休にも出会った。
才能もあったのだろう、利休七哲のひとり古田織部に師事して茶の道を極めた。遠州の茶は「綺麗寂び」と呼ばれ、巷間では利休、織部に次ぐ大茶人と称される。織部亡き後は大名茶の総帥となり多くの大名茶人を指導したという。遠州という名は慶長十三年(一六〇八)に従五位下遠江守に叙せられたところから、そう呼ばれるようになった。
「綺麗寂び」とは何か。後に葉室麟のインタビューをまとめた『葉室麟 洛中洛外をゆく。』(KKベストセラーズ)では利休、織部と比較してこう説明されている。
余分なものを徹底的に削ぎ落とした暗い茶室で、黒い楽茶碗を用いることで、客人と深く濃い交わりを求めた利休、大きく歪んだ茶碗で自身の感性を表現しようとした織部。一方、遠州は、均整のとれた白い茶碗を好み、茶室は、窓が多く、柔らかに光が届く明るい空間だった。
戦国時代を生き抜き、独自の茶道を見出した遠州の処世には、司馬遼太郎も興味を持っていたようで、『街道をゆく34』(朝日文庫)の「大徳寺散歩」のなかにも「小堀遠州」という一章がある。徳川家の重臣でもないのに、譜代並の扱いを受け、将軍の直接の命令によって五畿内を検地する仕事を成した遠州は、江戸時代の幕藩体制の中で、門閥にさえ生まれれば生涯遊んで食べられたのに、彼ほど働かされた大名は、江戸時代を通じていなかっただろうと綴っている。
『孤篷のひと』の遠州は六十八歳。徳川幕府の伏見奉行を務める遠州のもとをさまざまな人物が訪れる。客は長き人生のなかで、茶の湯を共に親しんだ誰よりも語り合える相手である。
訪うのは奈良の豪商で塗師屋の松屋久重、作庭を手伝ってきた得難い家臣の村瀬佐助、「綺麗寂び」の茶と並んで華やかな「姫宗和」の茶人として名高い金森宗和、義理の弟で作庭の右腕となった中沼左京、弟子の五十嵐宗林、医師の宗由、絵師の狩野采女、鹿苑寺の鳳林和尚。
語り合うのは、嘗て遠州が関わった戦国の世の荒々しい歴史の裏で、ひっそりと行われた交渉事。遠州は大名茶の総帥として、禁裏や名刹の作庭を行った作事奉行として、何よりも千利休の流れを引く、古田織部の弟子として、争い事を丸く収める画策をしてきたのであった。
思い出は次々甦る。一緒に関わりのあった茶道具の姿もまた思い出される。各章に付けられた題名はそれらの銘である。
「白炭」は湯を沸かす折に使う特別な炭。遠州は自ら炭焼き窯を造り焼いていた。そこには利休とも織部とも一線を画する、遠州のこだわりがあった。
「肩衝」は茶入れの壺で肩が張った形のもの。織田信長が所有していたという勢高肩衝が石田三成と似ていた、と遠州は語る。肩肘を張り、背筋のすっきり伸びた後ろ姿には孤独な翳りがあった。
「投頭巾」も茶入れの銘。「此世」は香炉。「雨雲」は楽茶碗。「夢」は掛け軸。「泪」は茶杓。「埋火」は灰被天目茶碗。「桜ちるの文」は掛け軸。そして「忘筌」は遠州が普請した茶室の名。
茶の湯はいつも密室で行われた。天下が覆るような争い事もあれば、男と女の濃やかな秘め事もあった。人に恨まれることも疎んじられることも、反対に慕われることもあった。
各章のタイトルに茶道具の名称を連ねたわけを葉室麟はこう語る。
茶道具には、基本的に銘があり、名付けられた謂れがあります。多くの場合、背景に何かしら物語が隠されています。遠州を主人公にした小説を書くことにしたとき、その物語を小説のストーリーと重ね合わせることで、二重構造的な世界観が生まれるのではないかと考えました。『葉室麟 洛中洛外をゆく。』
関わった人たちは、みな彼岸に旅立った。それぞれの茶道具に秘められた思いが戦国時代の激動と呼応し、静かな物語にもかかわらず内側にはマグマのような熱量を孕んでいる。戦いのはざまにあったしばしの静謐である茶席の場が、その熱さをさらに際立たせる。
権謀術数の限りを尽くした遠州の、晩年の心の動きだけを描いた作品なのに、読み手はなぜか胸が躍る。あの日あの時の謎解きを、手に汗握り読みふけってしまうのだ。
やがて来る最期の時。利休とも織部とも違う安寧の瞬間を著者はこう思っていた。
人は、それなりに働いて、最期に成仏していきます。つまり、ある種の役割を果たして、何者かになっていく過程の果てが〝死〟だったと僕は思います。(中略)
死ぬということは、生きてきたという証。だから、自分自身が『ちゃんと生きてきた』と言えるのであれば、『死もまた、良し』です。『葉室麟 洛中洛外をゆく。』
本書を上梓した一年三か月後、葉室麟は二〇一七年十二月に急逝された。享年六十六。早すぎる死である。多くの後輩作家に慕われた葉室麟へ、さまざまな追悼がなされ、特に同じ京都に住んだ歴史小説家、澤田瞳子の文章が哀切であった。一部、澤田さんの了承を得て紹介する。
葉室麟さんはお話好きな方だった。酒を愛し、酔えば酔うほど饒舌になり、活発な意見の応酬を好まれた。(中略)
我々後進作家の成長を心の底から喜ぶ一方で、作品はもちろん随想にも目を通し、常に丁寧な意見を下さった。「この人に会っておくといいよ」と様々な方を引き合わせ、よりよい活躍の場を、惜しまず人に与えられた。それでいて決しておごらず、親しい友のようにお付き合い下さりながら、常に「正しく生きる」とは何かという問いを、我々に──そしてご自身に投げかけ続けられた。「波」二〇一八年二月号
『孤篷のひと』はこの澤田さんの言葉どおり、何が正しい生き方であったのかを、終始、問い続ける作品だ。人生を全うした天下一の茶人の人生に酔いしれてほしい。
ご購入&試し読みはこちら▷葉室麟『孤篷のひと』| KADOKAWA