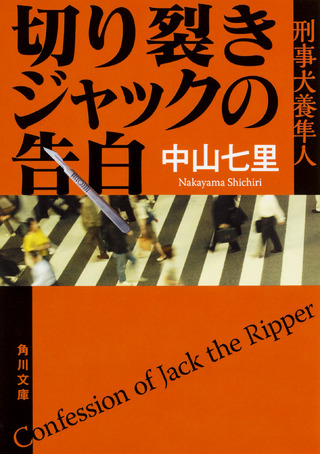ラストのどんでん返しで驚く前に、私は驚いていた。
政治、震災、テロ、寃罪。どうしたって現実社会とリンクしてしまう取り扱い厳重注意のテーマで、見事などんでん返しミステリを成功させてきたのは、作者のフラットな視点があったからだ。己の主義主張を主人公に代弁させたいだけの小説では、あれほどのインパクトを読者に与えることはできない。
しかし本作は、いささか偏りがあると感じた。
子宮頚がんワクチンについて、冷静に考えてみてほしい。ワクチンは何のためのものか。
実際、私は身近な人をがんで失くしている。せめてそれがワクチンで避けられるがんだったら、とやりきれない思いだった。忘れてはいけない。子宮頚がんワクチンは、多くの人を救ってきたのだ。
しかし物語の中には、利権以外でワクチンの恩恵を受けた人が出てこない。当たり前だ。子宮頚がんにならなかったことを、わざわざワクチンのお陰だと言って感謝する人などいない。そもそもフェアではないのだ。
それぞれの立場と利益を基盤にした理屈があり、どうやったって正解は出ない。
だが、ただ惑わされ流され、仕方がないと考えるのをあきらめてしまってもいいのか。その中にも、絶対に揺るぎないものがあるのではないか。
どこまで意図したものかはわからないが、この中山七里らしからぬ偏った論調が、逆に私を冷静にさせた。熟考して、もっと判断に迷えと言われているように思えた。
だから私は、物語のその後を妄想することにした。
飯田橋駅から早足で三分のホテルは、平日の二十時過ぎとあって、人影はまばらだ。学生のような服装の美鳥を呼び止める者もなかった。
吹き抜けの二階から、眩しい光と賑やかな声が降ってくる。目指す場所はあそこだ。
エスカレーターに足を掛けたところで、美鳥は唐突に、今日が三月十三日であると気付いた。あれからちょうど、十年だ。
亜美が連絡をして来ないだろうことを、美鳥はどこかでわかっていた。伊達にいちばんの親友をやっていたわけではないのだ。
頭が良く、冷静に正しさを選び取るが、決して冷淡なわけではない。そこに懊悩がないわけでもない。カバンを持って立ち尽くす美鳥の気持ちが、わからなかったわけがないのだ。
だから、無理に捜し出すようなことはしなかった。
親友がいなくなった後、いつまでも落ち込んでいたかといえば、そんなこともない。
なにしろ「感情の赴くままに動けばいい」と言ったのは自分だ。
美鳥は自分なりの人生を、心の赴くままに進むことにした。
今は神保町の書店で働いている。亜美の事件がなければ、本を読むことなどなかった。子宮頚がんワクチンや、医療に関する事件や訴訟についての本を読んだことが、美鳥の人生を変えた。何が正解か、何をすべきなのかを考え続けた十年だった。
美鳥は子宮頚がんワクチンを接種していたが、副反応はなかった。しかしそう言えるのは、もともと丈夫な体で、ここ十年、病気らしい病気もしなかったからだ。もしワクチンを接種していなかったら、今頃子宮頚がんを患っていたかもしれない。その可能性は、誰にも否定できないのだ。
実際、ワクチンのおかげで、世界の子宮頚がん患者は激減した。副反応に苦しむ少女と、後にワクチンのおかげで子宮頚がんを回避できる少女の人数は、どうしたって比べることができない。そして、そのために誰かが犠牲になってもよいなんてことは、絶対にない。
会場に足を踏み入れると、正面に座ってボロボロ泣く新郎新婦の横で、もらい泣きした司会者が披露宴のお開きを告げるところだった。やたらと泣いている人が多い会場だ。きっと直前に、新郎か新婦が手紙でも読み上げたのだろう。美鳥もなんだか泣けてきた。いい会だったようだ。
タキシードを着た新郎の横に座る、しあわせそうな新婦の名前は、香苗。
ホテルの車寄せに出ると、雨が本降りだった。
十年経っても人は変わらない。夜からの降水確率は百パーセントだと予報が出ていたのに、傘を持って出るのを忘れてしまった。うっかりにも程がある。
この寒さで雨に濡れたら、さすがの美鳥も風邪をひいてしまう。
『帰り道、途中まで一緒だったよね。入っていかない?』
その声を聞くのは十年ぶり。
人を待たせても決して慌てる素振りなど見せないのが彼女らしい。
そして、待たされても憎めないのが彼女らしい。
美鳥は振り返る。
『お待たせ』
本当はまだまだ続くが、ここまでにしておく。
どうしたら亜美にまた会えるだろう。笑顔で美鳥と会わせてあげられるだろう。
それを考えることで、私なりの「揺るぎないもの」を追い求めた。
中山七里さんとの出会いは、デビュー作の『さよならドビュッシー』だ。過酷な運命を辿るピアニストの少女にすっかり心を奪われてしまい、七年経ってもまだ私の中にいる。亜美は少し、あの子に似たところがあるのかもしれない。
最後になるが、この小説のラストで大活躍をする刑事、犬養隼人のことにも触れておく。彼がどこまでも刑事としての信念を失わなかったからこそ、この異色な物語が中山七里作品として成立しているのである。病と闘う娘を持つ父親として、今回の事件では苦しい面もあっただろう。しかし彼は、ぶれなかった。女性の気持ちが読めない男だが、私の理想の上司ナンバーワンである。
もしこの作品で初めて犬養隼人に出会ったなら『切り裂きジャックの告白』と『七色の毒』で、彼のことをもっと好きになって、ここに帰ってきて欲しいと思う。
作者の筆が異様に速いため、その後の犬養刑事には、妄想せずともそう遠くないうちに会うことができるだろう。
紹介した書籍
関連書籍
-
レビュー
-
レビュー
-
特集
-
レビュー
-
レビュー