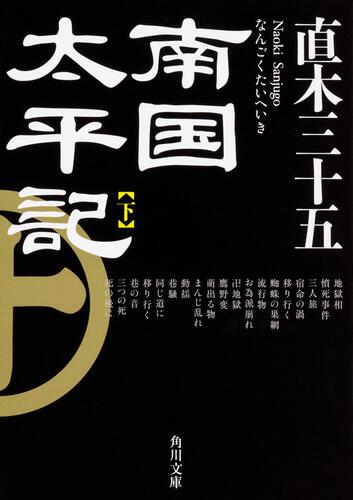いやはや、面白い。いま読んでも面白いのか、と驚いてしまった。直木三十五『南国太平記』は昭和5年6月12日から6年10月16日まで「東京日日新聞」・「大阪毎日新聞」に連載され、昭和6年4月に前篇、7月に中篇、11月に後篇が刊行された長編小説である。つまり2017年の現在からすると、なんと86年前に上梓された書なのだ。にもかかわらず、いま読んでも面白いのは驚異といっていい。
たとえば、冒頭近くに、印籠を盗ろうとしたスリの庄吉が小太郎に捕まるシーンがある。それはこのように描かれている。
庄吉は、口惜しさに逆上した。左手を、小太郎の頬へ叩きつけようとした時、何かが、胸へ当ってよろめいた。踏み止まろうと、手を振って、足へ力を入れた刹那、足へ、大きい、強い力が、ぶっつかって――青空が、広々と見えると、背中を、大地へぶちつけていた。
ようするに、小太郎に倒されて地面に横になるというシーンだが、それを「外」から説明として描くのではなく、庄吉の感覚として「内」から描くのである。すなわち、足に大きな力がぶつかって、次に気がつくと青空が見えていた――つまり地面に倒されていた、というわけだ。すごくリアルで肉感的といっていい。
もう一つ引く。これも冒頭近くのシーンだが、山内が青年を切るシーン。
山内は、強く、短く、唸った。二つの刀が白くきらっと人々の眼に閃いた瞬間、血が三、四尺も、ポンプから噴出する水のような勢いで、真直ぐに奔騰した。そして、雨のように砕けて降りかかった。
あの有名な黒澤明「椿三十郎」のラストシーンを彷彿とさせる強烈な場面といっていい。この血の噴出があまりにショッキングであったため、以降類似シーンが日本映画で増えてしまったというのは有名な話だが、その30年以上前に(「椿三十郎」は1962年の公開)小説の世界では描かれていた。ちなみに「椿三十郎」は山本周五郎「日日平安」を映画化するために用意していたシナリオを大幅に書き直したもので、『南国太平記』と関係はないし、黒澤明が『南国太平記』を読んでいたかどうかも定かではない。リアルさを追求すると同じ地点にたどりつく、ということなのかもしれない。一つだけ言えることは、30年先のことを読んでいたという意味で、現代的だということだ。
庄吉が倒されるシーン、そして山内が青年を切るシーン。この二つのシーンに共通するのは、句点を多用して独特のリズムをつくり、そのために読みやすいこと。刊行から86年たっても面白いのは、そういうふうに本書が、現代的で、リアルで、読みやすい、ということも原因としてあるのかもしれない。
直木三十五という作家についての基礎知識を少しだけ書いておく。植村鞆音(直木三十五の弟の長男)が書いた『直木三十五伝』という大変興味深い書がある。その中に、文藝春秋創業3周年の大正14年と、10周年の昭和7年に、勧進元菊池寛の名で「文藝春秋執筆回数番付」が作られ、直木三十五はともに西の正横綱であったという。ちなみに芥川龍之介は、前者では東の正横綱、後者では張出横綱。つまりその後、「芥川賞」と「直木賞」を創設したのは、単なる思いつきや気まぐれではなく、「二人の貢献度を数値として頭に刻みこんでいたに違いない」と植村鞆音は書いている。
また直木三十五が、事業欲が旺盛だったことも興味深い。大阪で出版社を興して日本初の「トルストイ全集」を発刊したり、マキノ省三と組んで映画制作に乗り出したりと大活躍。たとえば、大正13年封切りの「籠の鳥」という映画は、制作費わずか1500円(通常は5000円)。ロケ中心で4日半で仕上げ、制作費の100倍以上、17万円という純益をあげたという。事業家としてもなかなかのやり手だったようだ。そういえば、大村彦次郎『時代小説盛衰史』には「カツドウ屋直木三十五」という見出しがある。日本文壇には時折こういう事業欲の旺盛な作家がいるが(缶詰工場などの事業に熱心だった岩野泡鳴は有名だ)、直木三十五もそういう典型的な作家であった。
さらに植村鞆音の前掲書によれば、直木三十五は毀誉褒貶の激しい人でもあったようだ。金を使いまくるから一緒に事業をやった人にはたまったものではない。関西の出版社時代について、植村鞆音は次のように書いている。
人間社のほうも自転車操業であった。書店や読者から振替の為替が届くとそれで質入れしてあった出版物を引き出し、別の為替が届くと注文のあった本を出版し、出版した本をまた質入れして遊びにいく、といった調子だった
ようするに、計画性のない人間なのである。興味深いのは次の一文だ。
つまり、借金取りがみんな直木に惚れたのである。やっと午過ぎになって起き出した彼と、無言の睨めっこをしているうちに、同情と尊敬とがまじり合ったような気持ちになるらしかった。その結果、彼の腹心の参謀になって、債鬼撃退の役をひとりで引き受けるような男も出てきたほどであった
その直木三十五は本書『南国太平記』の成功で売れっ子作家になり、死の前年(昭和8年)には「直木三十五書き下ろし全集」全12巻を改造社から刊行。これは毎月1巻、書き下ろしで刊行するという無茶な企画で(他にもたくさんの連載や短編を書いているのだ。よくもまあ、こんな企画がスタートしたものだ)、さすがに実際に書き下ろされたのは4巻だけだったが。昭和9年、43歳で永眠。昔の作家はみんな、若くして死んだもので、芥川龍之介35歳、太宰治38歳と、みんな若い。
順序が逆になったが、本書の内容紹介を最後に少しだけ書いておく。中心になるのは、薩摩藩の内紛である。いわゆる「お由羅騒動」だ。島津氏の第27代当主(薩摩藩の第10代藩主)島津斉興の愛妾お由羅の方は、実子久光への家督相続を画策。斉興の長子斉彬の子どもたちを次々と呪殺する。それに対抗するのが、仙波八郎太に小太郎の親子、さらに維新の風雲児益満休之助らの改革派。これがメイン・ストーリーだが、面白いのは、騒いでいるのは周囲だけで、久光は兄の斉彬を慕っているという構図だろう。当の二人は仲がいいのだ。兄をさしおいて家督相続する気など、久光には微塵もない。
この構図がなかなかにいいが、背景にあるのは、もちろん幕末維新の激動史。そういう波瀾万丈の背景が、前面のドラマをリアルにしていることは見逃せない。そしてわき役たちの造形も秀逸だ。スリの庄吉、講釈師の南玉、常磐津の女師匠富士春など、個性的なわき役が次々に登場するが、特にスリの庄吉がいい。この男は小太郎に腕を折られるのだが、それでも小太郎の妹深雪に惚れて(というよりも、崇めて、といったほうがいいか)小太郎たちの味方をするという関係がいい。このように、本書は86年前に書かれた長編ながらも、アクションの切れがよく、文体のリズムがよく、わき役たちの造形もいいという傑作である。
直木賞にその名を残しながらも、大半の作品は絶版で読むことが出来ないので、本書は直木三十五の作品に触れるいい機会になるだろう。1997年に講談社の大衆文学館から上下2分冊として刊行されて以来、これが20年ぶりの復刊になる。この機会にぜひお読みになることをおすすめしたい。