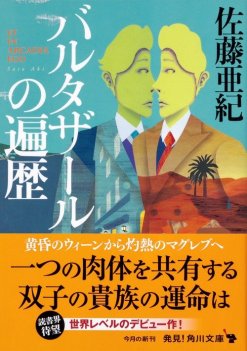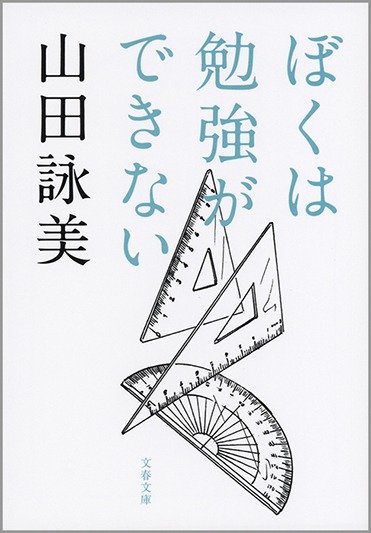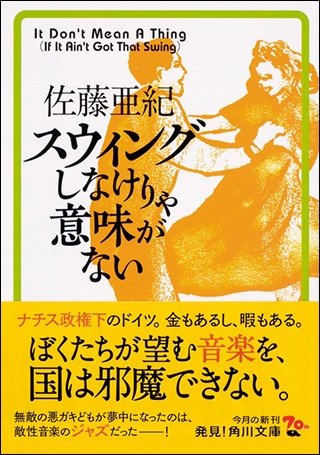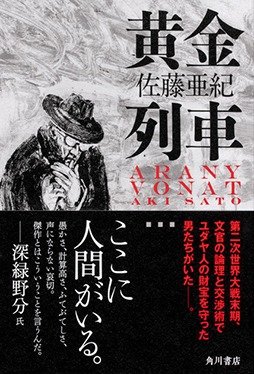文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!
本選びにお役立てください。
(解説:
『バルタザールの遍歴』を初めて読んだとき、強烈に
〈私たち〉とは、メルヒオールとバルタザールのことだ。一九〇六年のウィーンで、カスパール・フォン・ヴィスコフスキー=エネスコ公爵の長子として生まれた。本書のあらすじを乱暴に説明してしまえば、貴族のドラ息子の転落物語だ。ただし、そのドラ息子は一つの肉体を共有する双子なのである。
父が息子につけた名前はメルヒオールのみで、バルタザールの存在はないことにされていた。メルヒオールによれば〈私たちが二人であることを認めさせようとすると、人々は一様にぎょっとし、無視しようとし、ついには狂人扱いし始めた〉という。
ウィーンは精神分析学の創始者フロイトが活躍した街だ。一八八〇年代にはすでに二重人格(現在は解離性同一性障害と呼ばれる)の症例も発見されていた。しかし、メルヒオールとバルタザールは、もともと一つの人格が、何らかのストレスによって二つに分裂したわけではない。物質的身体は一つしか持っていなくとも、生まれながらに二人なのだという自覚がある。また、本書のエピグラフには、ボードレールの「どこへでも此世の外へ」という詩の一節が引用されている。この詩に出てくる〈私〉と〈私の魂〉と同じように、二人も対等な関係なのだ。
メルヒオールとバルタザールは、なぜこんな奇妙な双子に造形されたのだろう。作中の「手記」は主にメルヒオールが書いているのに、どうして〈バルタザールの〉遍歴なのだろう。本書を読んでいるとそんな疑問が浮かぶ。
〈私たち〉の肖像画を描いたのは、
「肖像画はモデルの外見だけじゃなくて、内面も描こうとするものだろう」
「それは完全に誤った理屈ね。モデルに内面なんてないわ」
「僕らにはあるぜ、悪いけど」
「あるかもしれないけど、関係ないのよ」と彼女は苛ついた口調で言った。「一体どうやって、ある色彩で塗られた表面と別な色彩で塗られた表面の組合せが、内面を表現したり出来るのかしら。表現なんて言葉がそもそも間違ってるわ。私はある色彩、ある線を一定の面積内に美的に構成するだけなの」
マグダの絵画論は、
ビリジャンは青みをおびた鮮やかな緑だ。一八五九年にフランスで作られた顔料の色で、非常に流行したという。今でも基本の絵の具セットに入っている。
マグダはビリジャンを顔に使ったのだろう。〈立体派の構図に野獣派の色彩を載せたような絵〉という記述があるから。ぼんやりとイメージしたのは、立体派を代表する画家パブロ・ピカソの「泣く女」だ。黄色と緑をメインに塗り分けられた肌に、失敗した福笑いみたいに目鼻口が置いてある。真ん中から顔がぱっくり割れているようにも見える。ヘンテコな双子にはぴったりの構図かもしれない。野獣派のアンリ・マティスにも「帽子の女」とか「緑の筋のある女」とか、緑色の顔の人を描いた作品がある。現実の人間にはありえない肌色なのに、不思議としっくりくる。
ピカソは愛人を、マティスは妻を、マグダは従兄を緑色で塗った。絵のモデルになる前に、メルヒオールはマグダに本気とも冗談ともつかない求婚をしていた。マグダの内面は描かれない。誰も自分が思っていることをくどくど説明しない。けれども、メルヒオールとバルタザールはビリジャンを費やしたくなる相手だったのだ、ということはわかる。この場面の語り手であるメルヒオールもまた、マグダの描いた絵を鮮明に覚えている。言葉と言葉のつながり、細部を吟味することによってもたらされる発見が、読み手の感情を動かす。
言語芸術の真髄は、どの言葉をどう並べるかに尽きる。構成された言葉からどんな世界が立ち上がるかは自分次第だと佐藤亜紀の小説は実感させてくれる。読者として試されるのは恐ろしいが、信頼されているとも思う。知りたいことが出てきたら調べればいい。能動的に読めば読むほど面白い。
遅ればせながら、この作品が生まれた背景に触れておこう。『バルタザールの遍歴』の初版は、一九九一年に刊行された。佐藤亜紀のデビュー作だ。「ウィーンに還る」(『外人術』に収録)というエッセイで、佐藤亜紀は執筆の経緯を回想している。ウィーンの美術学校の画廊で〈白い孔雀を逆さに吊って装飾的に配置した静物画〉を眺めていたとき、ふいに
これほどウィーン的な場所を今まで見過ごして来たのは失策だった。このさかしま。この無意味。一箇所硝子が破れれば死に絶えてしまう蝶たちを閉じ込めて、楽園の生きもののように無心に繁殖させるという行為の、何とも言えない淫靡さ。しかも温室自体はごく古びていて、あり得べからざる場所で彼らを生き延びさせているのはどうやら旧式の石油暖房らしい。ウィーンの魅惑──初めて訪れた時に私を虜にした、記憶の影で溢れる廃屋めいた魅惑を、殆ど十年の後に、奇妙なところで見い出したものだ。
その魅惑をどうにか形にしたい、と当時の私は考えたのだった。いや、考えたというよりは、漠然と感じた、と言ったほうがいいだろう。ウィーンのことを思い出す度、何とも言えない焦燥感のようなものを覚えて、いても立ってもいられなくなったのである。(「ウィーンに還る」より)
〈記憶の影で溢れる廃屋めいた魅惑〉を形にするために選ばれたのが、一つの肉体を共有する双子〈私たち〉の語りなのだ。
何の記憶か。まずはおよそ六五〇年にわたってウィーンを支配していたハプスブルク家。ハプスブルク家は「双頭の
かつてヨーロッパで栄華を誇った一族が
『バルタザールの遍歴』は、一九三九年九月一日という日付で締めくくられている。ナチス・ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦の
エピグラフに引用されたボードレールの詩を思い出す。人生は病院のようなものだという〈私〉が、どこに居場所を移すべきか〈私の魂〉に問いかける。あれこれ候補を挙げる〈私〉に、〈私の魂〉はなかなか返答しない。ところが、最後にこう叫ぶのだ。
「どこでもいい、どこでもいい……、ただ、この世界の外でさえあるならば!」(三好達治訳『巴里の憂鬱』所収「どこへでも此世の外へ」より)
▼佐藤亜紀『バルタザールの遍歴』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000255/