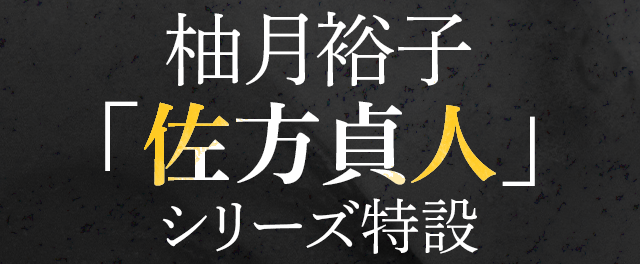社会人になって働きはじめた頃は、何もかもが初めてで、分からないことだらけだった。でも、年数が経過し、経験を積んでいくうちに、仕事を覚えて、確実に上達していく。人間にとって、学習能力は大きな武器だ。
しかし、経験が武器にならないこともある。例えば、「死」にまつわることだ。「死」は一度きりであり、学習することはできない。時に、身近な人に死がやってくると、戸惑うばかりで、自分の無知を思い知ることになる。
『勿忘草の咲く町で』は二人の主人公が医療の仕事を通じて、「死」、そして「生」に正面から向き合い、悩みぬきながら力強く成長していく物語である。
舞台は長野県松本市。安曇野の広がる自然豊かな町の、上高地の入口にある「梓川病院」は、常にフル回転で地域の人々を支えている。3年目の看護師として働く「月岡美琴」は、ちょっとした処置の介助や急変時の対応などは身につけた一方で、徐々に視野が広がり、周囲への働きかけ方や自分がどうなりたいかについて、悩み始めていた。そんな中、研修医として信州大学から「桂正太郎」が赴任してくる。医療に対する情熱と理想を迷いながらも追求していく二人は、互いに惹かれていくと同時に、職場では触発し合い、それぞれ自分なりの答えを見つけ出していく。
二人が奮闘する地方医療の実情は、深刻そのものである。高齢化が進んだ町から治療を求めてくる患者は、病院で看取られることも少なくない。さらに、全ての人に身寄りがあるわけではなく、家族がいても疎遠になっている場合や、退院後の戻り先が施設であったりもする。だからこそ、研修医である桂は、限られた人員や医療資源の中で、患者や病自体だけでなく、患者の家族の心の問題も扱うことになる。最も印象に残ったのが、「インフォームド・コンセント(医師と患者や家族との、十分な情報と理解を得た上での合意)」を行うシーンである。とりわけ、自らが意思表示できない患者への治療を家族に説明する場面は、桂と一緒になって、どうしたらいいのか考えずにはいられなかった。
「肺炎なら肺炎でいいです。治療もお任せします。治ったら胃瘻(いろう)で構いません。病院に任せるとお伝えしたはずです。私たちも忙しいんですよ」
段々語気を荒らげてくる昭(あきら)に対して、桂は忍耐強く応じていた。(p.245より)
「死」に関する問題を自らの日常と遮断し、医師に押し付けて見て見ぬふりをしようとするこの家族に、桂は自身の考えを誠実に伝えていく。実家が花屋を営む桂だからこそ紡げる言葉で、「生」は人と人とがつながって保たれていることを伝えていく。正解のない問題を前にして、真剣に悩んで、もがいて、答えを出そうとする姿勢に胸が震える。
サンダーソニア、秋海棠、ダリア、山茶花、カタクリ、勿忘草。各章のタイトルを飾る花たちのように根をしっかりと張り、大きく咲いていく二人の姿は、ずっと見ていたくなるくらいに、とても生き生きとしている。