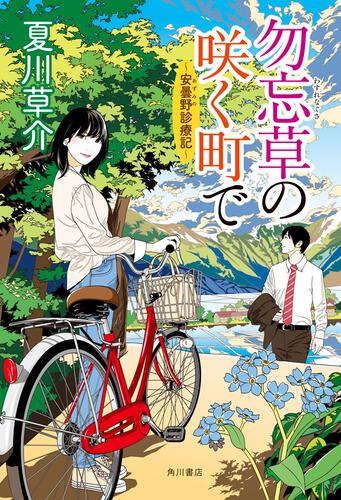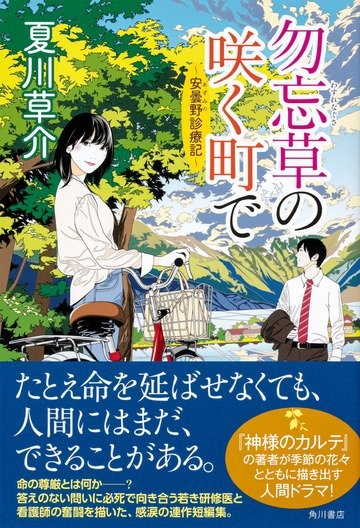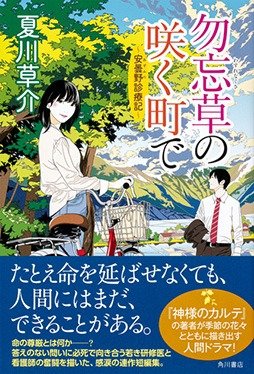インタビュー 小説 野性時代 第194号 2020年1月号より

現役医師から見た「人の死」とは。夏川草介『勿忘草の咲く町で~安曇野診療記~』刊行記念インタビュー
撮影:川口 宗道 撮影協力:ホテルブエナビスタ 取材・文:門賀 美央子
新刊『勿忘草の咲く町で ~安曇野診療記~』は夏川さんの代表作〈神様のカルテ〉シリーズ同様、病院を舞台に繰り広げられる人間模様を描く作品だ。
命が尽きる前、患者とその家族は何を考え、どうふるまうのか……。
現役の医師でもある夏川さんから見た「人の死」とは。
――本作では「高齢者医療」という現代日本が直面する大きな問題に真正面から向き合い、「命」についても従来作よりかなり思い切った踏み込み方をされているように感じました。
夏川:ええ。雑誌での連載開始当時から、私が携わっている地域医療、とりわけ高齢者医療において、医療現場の外からはなかなか見えない隠された部分を書こうというイメージがありましたので。
――なぜ、そこについて書こうと考えられたのですか?
夏川:私は医師になってもう15~6年が経つのですが、その間ずっと感じてきたのが、今の社会は「死」と正面から向き合っていないのではないかということでした。
――作中、三島というベテラン医師が「今の社会は、死や病を日常から完全に切り離し、病院や施設に投げ込んで、考えることそのものを放棄している」と話すシーンがありますが、まさにそういったことでしょうか。
夏川:そうですね。現役の医師として日常的に患者さんの死に立ち会う中、医療外のトラブルが発生することがしばしばあります。そして、そのせいで患者さんの最期がよくない形になってしまうことも。原因は様々ありますが、医者の目から見ると、それまでの人生の中で病気や死から目をそらし続けてきた結果ではないかと感じる瞬間が少なくないのです。普段から「自分の死」や「家族の死」について考えておけば、もっと違う展開になったのではないか、と痛感するんですよ。これは、私が医師になって以来ずっと悩んでいることであり、いつかは明確に書きたかった。ただ、〈神様のカルテ〉シリーズに入れ込むには少々重すぎるので、書くとしたら別の物語でと考えていました。
――確かに、人の死に対してかなりドライな考え方をする登場人物も出てきます。
夏川:内科医の谷崎ですね。正直な話をしますと、この作品は雑誌連載用に書いたものだったので、書籍になるとは思っていなかったんです(笑)。雑誌なら本に比べると読む人も少ないだろうから多少毒を吐いても大丈夫だろうし、書くことで自分の気持ちの整理がつけばいいかな、と軽く考えていました。ところが、書籍化されるということになって、さてどうしよう、と(笑)。登場人物はあくまで架空の存在であり、決して私そのものではありません。谷崎の考え方はちょっと極端で、私は彼に百パーセント賛同するわけではないけれども、こうして本になってしまった手前、今後はちょっと気をつけないといけないなとは思っています。これを読んだ患者さんが「自分がかかっている医者はあんなことを考えているのか」と思ってしまうと不幸なことになりかねませんから。とは言いつつ、自分が考え続けてきたことの一側面ではあり、今となってはこのように作品化できてよかったと思っています。
――本作では第一話から第四話まで様々な「死」が描かれています。一般的な医療系ドラマでは、難病の人が山あり谷ありの闘病生活を送りながらも、医療者の尽力と最先端技術によって最終的には回復するパターンが多いようですが、本作ではかなりリアルな「命の終わり」が描かれていますね。
夏川:第一話で書いた通り、死に際して医療にできることは実はとても限られています。ところが、最近は医療がすごく理想化されて、どんな死病や致命傷でも力を尽くせば治せるという幻想が社会に広がってしまっている。スーパードクターが登場するテレビドラマなんかの影響かもしれませんが、患者さんの要求度がすごく高くなっている面があるのです。しかし、人というのはいつか必ず死ぬ存在です。たとえば、九十代の高齢者が末期の悪性腫瘍で余命いくばくもないと判明した場合、果たして「治す」だけが医療なのか。そうではないことは、もうわかっているのですが。
――真剣に仕事に取り組む登場人物たちが力を尽くしても結末は変えられないし、何らかの問題は必ず出てくるという現実を前面に押し出したのが本作のすごみである一方、随所にちりばめられた安曇野の豊かな自然や若い医師と看護師の微笑ましい恋愛模様などによって読後感はどこまでも爽やかで、澱のようなものは残りません。
夏川:それは意図してそう書いています。私は、読者にかっこいい人たちが登場する美しい物語を届けたいのです。もちろん人のドロドロとした部分を描くのは文学の役割ですし、僕も年をとったらそういうものに挑戦するかもしれません。ですが今は、特に若い人たちに「美しいもの」を見てもらいたいという気持ちの方が強いのです。地域医療の現実にしたって、ありのままを書いたら重くて暗くて、とてもじゃないですが読めたものにならないでしょう。でも、明るい二人の若者を中心に、彼らの恋も交えることで、モノクロの物語をカラーリングすることができます。僕自身、仕事をしていてつらいこともある中で、安曇野の自然や花の美しさに助けられている部分がかなりあるので、そういう気持ちが自然と反映されたのでしょう。
――出てくるのは良い人たちばかりだけれども、「答えの出ない問題」は常に存在し、重石としてのしかかってくる。それでも逃げずに向き合おうとする登場人物たちの姿勢に、人としての誠実さというか、夏川さんが一連の作品の中で訴えようとしている真実が垣間見えるように思いました。
夏川:今の社会ってとてもアンバランスで、何が正しくて何が間違っているのかとか、なにがかっこよくてなにがかっこ悪いのかといった、人としての基本的な部分がとても見えづらくなっているように感じるんです。みんな自己主張はするけれども、周囲との協調や相互の思いやりが疎かになってしまい、その結果、露骨で毒のある表現ばかりが増えています。それはそれでいいんですけど、まだ若い人たちにはまずは「理想」や「人としての美しさ」をきちんと見ておいてほしい。そうしないと、醜いものに触れてもそれが醜いとはわからなくなるのではないでしょうか。さらに言えば、たとえ悪人は誰一人いなくても問題は起こるし、いい人ばかりの集団でもどうにもならない出来事にぶつかることもある。そんな時、人は本当の苦しみを知るのだと思います。だから、本作でも登場人物には理想的な言動をしてもらいつつ、問題は極力リアルにして、最後の「悪」というのはこういう形で表れるんですよというのを書いたつもりです。「悪」は単純なものではありませんから。私は、今の社会に失われつつある、人の人に対する信頼感を取り戻したいと常に思っています。最近は医療不信もすごく過激になってきていて、診察室に入ってくるなり「先生は何年目ですか? 専門医なんですか?」というような質問をしてくる患者さんもいるんですよ。「もう四十は越えていますし、専門医資格も持っていますよ」と返事をして相手が途端に大人しくなったとしても、そういうやり取りをした瞬間から壊れていくものは確実にある。そんな風に相手を頭から疑ってかかるのではなく、みんな自分のできることを一生懸命やって真面目に生きていますよ、という前提で動く社会の方が幸せですよね。
――同時に、本作の端々から、一人ひとりが「死」を直視し、いつか来るその時について予め考えておこうという強いメッセージを感じました。
夏川:その通りです。今元気で過ごしている人たちが、この作品をきっかけに自分や家族の死について少しでも考えてくれれば、これ以上のことはありません。すぐに答えが出てくるものではありませんが、それでも考え続けてほしいと思っています。
書籍紹介
『勿忘草の咲く町で ~安曇野診療記~』
夏川草介
松本市郊外にある梓川病院は小規模ながらも地域医療を支える要だ。そこで活躍する若き医療者たちは時には苦悩しつつ、それでもタフに歩んでいく。「小説 野性時代」に掲載された全四話に、「プロローグ 窓辺のサンダーソニア」と「エピローグ 勿忘草の咲く町で」を書き下ろしで加えた、終末期医療の現実を赤裸々に描く著者の新境地。
https://www.kadokawa.co.jp/product/321903000372/
[主な登場人物]
月岡美琴(つきおか・みこと)
梓川病院に勤める三年目の看護師。明朗快活。病棟の重要な戦力だが、まだまだ未熟な面も。正太郎を励ますうち心が通じ合うように。
桂 正太郎(かつら・しょうたろう)
梓川病院に研修医としてやってきた青年。真面目だがどこか茫洋としていて周囲から変人扱いされる中、美琴の強さに惹かれていく。
[各話紹介]
「秋海棠の季節」
内科病棟にやってきたばかりの正太郎が担当することになったのは膵臓癌で余命わずかな四十代の男性。家族を遺して逝かなければならない患者にまっすぐ向き合おうとする真摯な姿に、美琴は心打たれる。
1話まるごと公開▶「神様のカルテ」では書けなかったこと――。夏川草介最新刊、第一話試し読み!
「ダリア・ダイアリー」
正太郎の新たな指導医・谷崎は、八十代以上の患者は看取りに持っていくため「死神」とあだ名されていた。正太郎はそんな方針に異を唱えるも、谷崎の経験に裏打ちされた信念には反論できず……。
「山茶花の咲く道」
院内で患者が誤嚥による窒息で死亡。防ぎようのない事態ではあったが、遺族は医療事故を疑っているという。訴訟沙汰を避けるため責任を認めようとする上層部に、美琴はひとり敢然と異を唱えるが。
「カタクリ賛歌」
寝たきりで意識もほぼない高齢患者が予定する胃瘻手術、急性胆管炎で救急搬送されるも「ただお迎えを待ちたい」と望む九十五歳の女性。自然に消えゆく命の前に、正太郎は日々苦しい判断を迫られる。