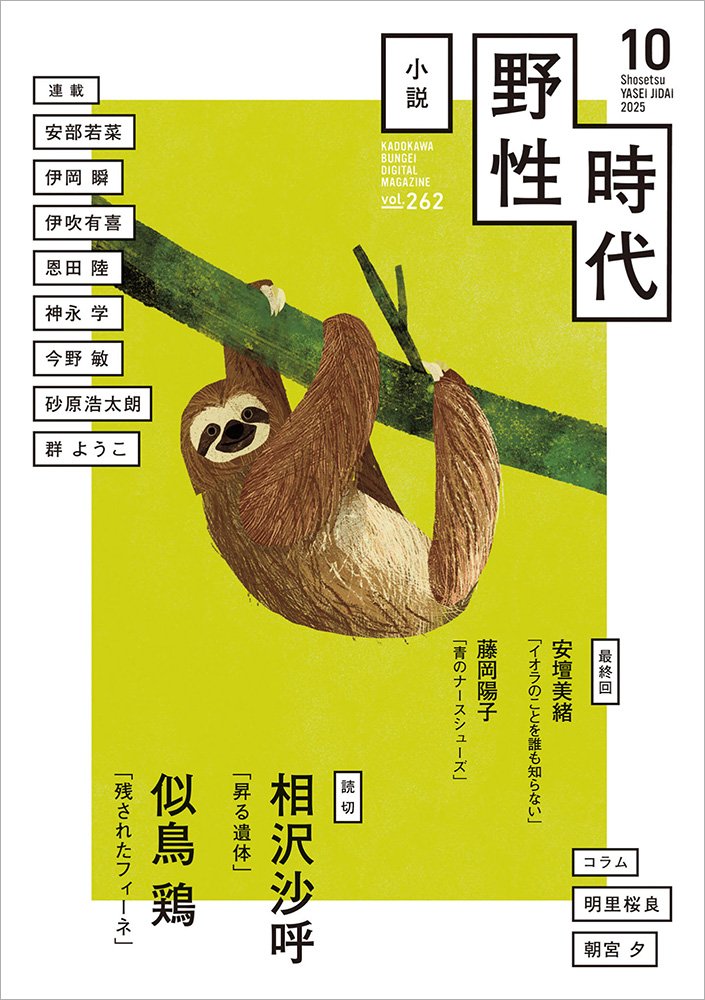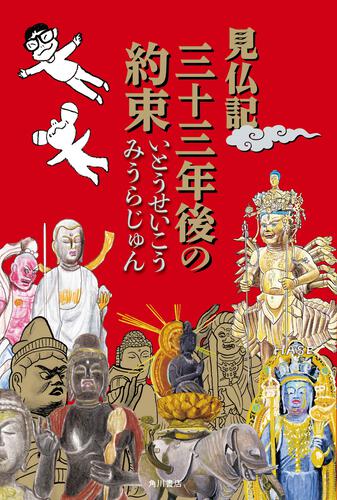『君の顔では泣けない』著者・君嶋彼方さん待望の新刊! 小説野性時代新人賞受賞第一作『夜がうたた寝してる間に』
新人ばなれしたデビュー作として話題となった『君の顔では泣けない』の著者・君嶋彼方さんの待望の第2作となる長篇小説『夜がうたた寝してる間に』が8/26に発売となります。
生まれつきある「力」を持ったことで、周囲との違いや関係性に悩みを抱える高校生の葛藤と成長を描いた作品です。
本作の冒頭50ページを特別公開。書き出しの一文から息を呑むほど美しい、珠玉の物語をお楽しみください。
▼君嶋彼方特設サイトはこちら
https://kadobun.jp/special/kimijima-kanata/
『夜がうたた寝してる間に』試し読み#3
「あー、おっかなかった」
「センセー、ありがとー。めっちゃ助かった」
俺が手を合わせて礼を言うと、隣から篠宮が口を挟む。
「大丈夫なんですか、先生。あんなふうに
「うーん」と、岡先生が
あの言葉は果たして本音なのだろうか、とふと思う。本当は俺たちのことを疑っているが、立場上ああ言っているだけなのではないだろうか。その真実は、篠宮にすら分からない。
「とりあえず、しばらくは国城先生も目光らせてるだろうから、お前ら大人しくしとけよ。じゃあな」
そう言うと岡先生は教室を去っていく。なんでこんな思いをしなければならないんだ、と俺は
他の二人はコートを着込み、帰り支度をしている。俺はマスクを着けると、慌てて声をかける。
「あー、ちょ、ちょっと、ちょっと待って」
篠宮と我妻がぴたりと動きを止め、同時に視線をこちらに向ける。少したじろぎそうになりながらも続ける。
「てかさあ、普通にむかつかない? 国城もだけどさ、他の奴らもめっちゃ犯人扱いしてくるじゃん。腹立たない?」
きっとこいつらだって、能力者に生まれてしまったというだけで、つらい思いを何度もしてきたはずだ。それこそ今回のように、何かある度に
けれど、返ってきた反応は思った以上に芳しくないものだった。我妻は興味なさそうにあくびをし、篠宮は何故か鋭く俺を睨みつけていた。
「べつに。全然むかつかないけど」
「まじかよ! お前もむかつかないの?」
我妻を見る。我妻がやっとそれに気が付いたように、後頭部の寝癖を指でいじった。
「っていうか、あんま興味ない」
だるそうに言うその姿は、ポーズではなく本当に関心がないように見えた。俺は衝撃を受ける。
「興味ない、って……我妻はクラスの奴らになんか言われたりしないの?」
「してるよ。こそこそ言ってる、わざわざ俺に聞こえるようにして」
「なんだよそれ、めっちゃむかつくじゃん!」
「でも、俺には関係ないし」癖っ毛を混ぜるように頭を搔く。「事件のことについてとか、本当に何も知らないし。だからどうでもいい」
「えー、まじかよ。みんなで犯人見つけてさ、身の潔白を証明してやろうぜ!」
「何それ、やだよ。めんどくさい」
我妻に鼻で笑うように言われ、むっとする。当の本人はもう話は終わったと言わんばかりに教室を出ていく。「あ、待てよ」と廊下に顔を出すが、既にその姿はなかった。
「じゃ、私も帰るね。バイバイ」
「あー待って、ちょっと待って待って」
帰ろうとする篠宮のマフラーを思わず引っ張る。
「なぁまじでむかつかないわけ? 犯人捜し協力してよ」
「あのさあ、そんなに簡単に見つかるわけないでしょ。何言ってんの」
「いやいや。篠宮の能力さえあれば、そんなの簡単じゃーん!」
おどけて言ってみせたつもりだったが、その顔にすっと不愉快さが張り付いた。しまった、と思い慌てて続ける。
「さすがにさ、学校中の奴らの心読んでくれとは言わないからさ! ちゃんと俺も協力するし。なっ?」
「悪いけど、学校の人の心は読まないことにしてるの」
そう言いながらも、悪びれた様子は一切ない。夜のように暗い黒目に自分の姿が映っているのが見えて、俺は視線を逸らしたくなる。マスクのお陰で、心を読まれることはない。けれど篠宮にじっと
「でもなんか、浮気見破ったりしてるって聞いてるけど」
「あれは全部、学外の人だから。学校内ではそういうことしない」
「なんだよ、中も外も変わんないだろー」
そのとき初めて、篠宮が視線を逸らした。俯くと前髪に隠れて、見下ろしている俺からは彼女の表情が見えなくなる。少しの沈黙の後、口を開いた。
「私が、好きで人の心の中読んでるとでも思ってるの?」
さっきよりもずっと低い声に、俺は「え」と言葉を失う。篠宮の前髪が横に垂れて、彼女が俺を見上げる。さっきと変わらない暗い色が目の奥にある。
「あんたがマスク外してくれたら、協力してあげてもいいよ」
「えっ?」自分でも驚くほど間の抜けた声が出る。
「岡先生が言ってたでしょ。この学校の人間、全員平等に犯人の可能性はあるって。逆に言えば、私たちの誰かが犯人だって可能性ももちろんある。それは、あんたも一緒でしょ」
「いやいやいや。犯人が、わざわざ犯人捜ししようって言わないっしょ!」
「そんなのなんの証拠にもなんない。マスク外して、自分は犯人じゃないってちゃんと証明してよ」
篠宮がゆっくりとマスクを
その途端、背筋がぞわりと震える。恐怖だった。今自分が思っていること、考えていること、隠していること、全部すべてこの女に読み取られてしまう。その事実がとてつもなく怖かった。やましいことがあるわけではない。当然、俺は犯人ではないし、犯人を見つけ出したいという思いは本物だ。本物のはずなのに。
篠宮は表情をぴくりとも変えず俺を見つめてくる。どうにか笑顔を作る。
「外す、外す。ちゃんと外すからさ、外しゃいいんだろ。でもちょっと待って、あの、えーっと、心の準備が」
顔の下半分がじっとりと湿っている。マスクにかけた指は、まるで凍りついたかのように動かない。篠宮が、はぁと大きく息を吐いた。
「自分の心は読まれたくないくせに、他の人のを読んでくれだなんて、ほんと都合がいいよね」
まあ、結局みんなそうなんだけどね。そう吐き捨てるように言うと、マスクを着け、くるりと
高い笑い声が遠ざかって、俺はようやく平静を取り戻す。マスクを外すと、口元が汗で
「アーサー」
声をかけられて振り向く。ドアの外から、毛利と榎本が顔を
「なんだよ、お前ら。部活は?」
「いや、行くけど。様子気になっちゃって」
出入口の方まで歩くと、その隣には天の姿もあった。
「天ちゃんまで来てくれたの」
「うん、なんか心配で」
「まじか。ありがと」
「ううん、いいんだけど」寒いのか、天は右手で左腕を頻りにさすっている。「大丈夫だった?」
まるで自分が傷付けられたかのような表情で、天は俺を見つめる。なんだか昔を思い出してしまう。天はよくこうやって、悲しそうな顔で俺を気にかけてくれていた。大丈夫だよ、と笑って肩を叩くと、いてっ、と苦笑いを返してくる。毛利と榎本もどことなく心配そうだ。
「なんかすごい長かったな。
「うんまぁ、そんなところ。てかまじ疲れたわぁ」
「国城が結構ぎゃーぎゃー言ってる感じ?」
「そ。いつ火ぃ吹くのかひやひやしてたわ」
そう言って笑う。三人も笑う。稚拙な会話、幼稚な話題。つまらなくても笑って、思ってなくても同意して。周りから浮かないよう、疎まれないよう、どうにかやってきた。自分を偽って溶け込むことは、慣れてしまえばどうということはなかった。相手の欲しがる反応や言葉さえ分かれば、それを与えてあげるだけで、相手は喜ぶ。たとえそれがちっとも思っていないことだったとしても。
そうやって、俺はやってきたのだ。それが偽りだと、心の中を見透かされてしまうことは怖かった。俺が楽しいと思って過ごしている日々が、全部偽物だとつきつけられてしまうことになりそうで。