蘇った刑事 デッドマンズサイド
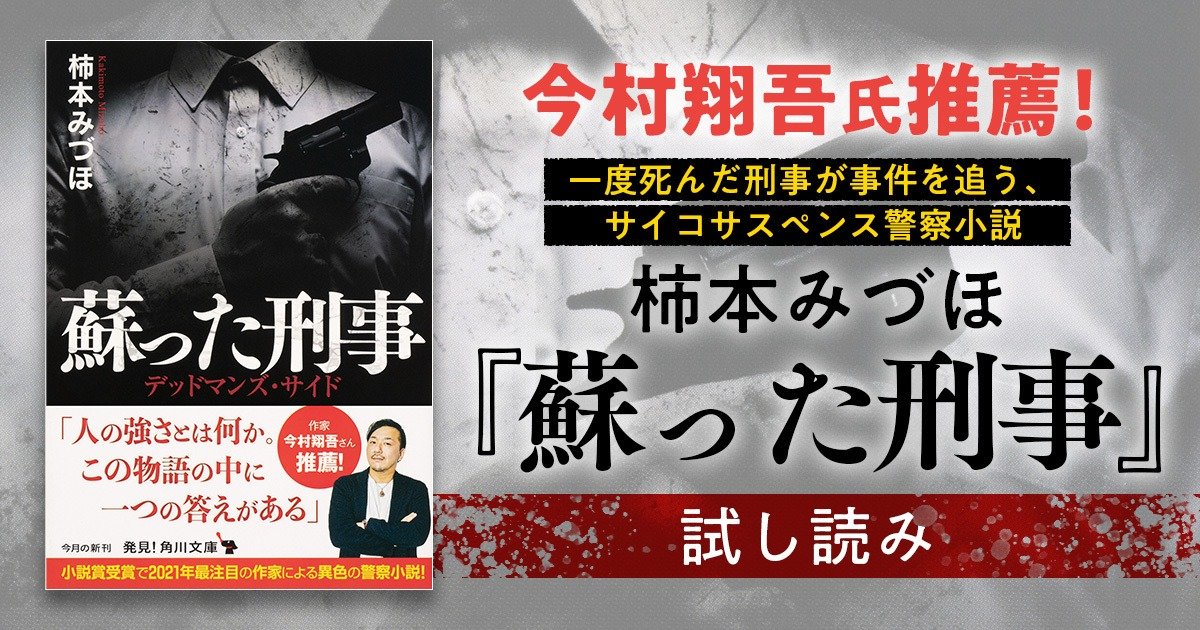
一度死んだ者にしか嗅げない事件の”におい”がある 『蘇った刑事 デッドマンズサイド』試し読み #4
「あなたは死人なんです。言わばゾンビです。一度死んだけれど、とある理由で生きながらえている」
頭を撃たれながら奇跡的に蘇った刑事の入尾は、覚醒後、元部下の波多野にそう告げられた。そして、波多野もまた、一度死んだのだという――。
柿本みづほさんの書き下ろし最新作『蘇った刑事 デッドマンズサイド』は、札幌が舞台のサイコサスペンス警察小説です。九死に一生を得たのと引き換えにある衝動を抑えきれなくなった主人公は、刑事として正義を貫けるのか――。根源的な問いが詰まったスリル満点の本書。その冒頭部分を特別に公開いたします。
『蘇った刑事 デッドマンズサイド』試し読み #4
□
約一ヶ月後──十月二十八日。
病室には沢村と、西署長の
目を覚ましてから二ヶ月ほどが経過し、入尾は問題なく日常生活を送れるまでに運動能力が回復していた。今はもう松葉
このタイミングで和田署長が病室を訪れたのは、おそらく〝進退〟の話をするためだろう。
入尾は布団の上で軽く
再び刑事課に復帰できるとは思えない。地方警察署の生活安全課か、警務課あたりが妥当なところだ。
二十九歳の時に刑事課へ配属になって以降、刑事畑から出たことは一度もなかった。しかしこればかりはどうしようもない。
「沢村君から話は聞いている。元気そうでなによりだ。……さっそく本題に入ろうと思うのだが、問題ないかな」
入尾は
「構いません」
和田署長は一度
「君は現在道警に籍を置いてはいるものの、西署の強行犯係長という任は解かれている。これは分かってくれるね」
「半年も寝ていたのですから当然でしょう」
「理解してくれて助かるよ。君の処遇について本部とも協議したが、復帰してもらうにしても、万全ではない君を再び強行犯係に配属するのは忍びないという話になった」
なので警務課に、と続くのだろう。仕方のないことだ。警察組織に籍を置けるだけありがたいと思わなければ。
「しかしだね、元係長で、なおかつ実績も申し分なかった君を他の課へ異動させるのは筋が違うという話にもなった。そこでだ」
和田署長は仮面のような笑みを張り付けて身を乗り出した。
「ちょうど半年前、中央署の刑事課に新しい部署が設置された。近年増えている異常犯罪に対し、より専門的な捜査が行える部署を設立せよ。そういった上のご意向でね。ここ数年、異常犯罪が増加傾向にあることは君も承知しているだろう」
和田署長の言うとおり、二〇一七年以降、北海道──特に札幌での異常犯罪発生件数は増加傾向にある。同様に変死体の発見件数も増加しており、道警本部は警戒を強化していた。
「それがどうかしましたか」
「君に、その新部署──特異犯罪捜査係の係長を務めてもらいたい」
「……はい?」
「悪い話ではないはずだ。多少違いはあるだろうが、刑事課の一係長であることに変わりはない。どうだろうか」
──どうだろうか、と言われても。
「特異犯罪捜査係というのは、一体どういう」
「異常犯罪の捜査を専門とした部署だ。経験を積んだベテランが集められている。少数精鋭部隊、と言えばいいかな。君のような優秀な刑事にぴったりの部署だと思うが」
「専門的とのことですが、まさかプロファイリング捜査などをするんですか」
「必要であれば科捜研の犯罪者プロファイリング係と連携して捜査を行うことにもなるだろうが……まあ、あまり難しく考えなくてもいい。まだ設置されたばかりだからな、運用方針を模索している最中なんだ」
つまりまだ実験段階にあるということか。何故本部ではなく所轄の中央署に設置されたのかが気になるが、上層部の意向についてあれこれ考えても仕方がない。
「特異犯罪捜査係の現在の係長は?」
「ちょうど先月から体調不良で休職していてね。今は刑事課長が代理を務めている。君が異動してきてくれるのなら、喜んで席を明け渡すと言っていた」
随分とお
刑事で居続けられるかどうかすら怪しかったのだ。再び刑事課に配属され、役職も係長のままでいられるなど願ってもない話である。
ただ、妙に引っかかる。
頭の奥底にこびりついた刑事としての勘が、何かを叫んでいるような気がする。
「どうかな。特異犯罪捜査係長の件、受けてくれるだろうか」
一瞬、返事をするのに
横目で沢村を見る。沢村は下を向いているので視線が合うことはない。
──迷っていても仕方がないか。
「
和田署長は分かりやすく
「そうか。これで一安心だ。君のように優秀な刑事が係長を務めるのだ、本部もますます特異犯罪捜査係に期待を寄せることだろうね」
とりあえずうなずいておいた。
和田署長の隣で悔しげに拳を握る沢村の姿が目に焼き付いて離れなかった。
□
十二月二日。
入尾は荷物を詰めた段ボールを抱え、中央署の廊下を歩いていた。
目を覚ましてからおおよそ三ヶ月が経過したが、身体や脳機能に異常が生じることは一切なかった。むしろ煙草を吸わなくなったので以前よりも調子が良い。これを機に酒もやめた。
和田署長から異動の話を受けた翌週、入尾は八ヶ月ほど居続けた病院を後にした。スタッフから盛大に見送られたのが少し気恥ずかしかった。
以前住んでいたアパートは解約されていたため、今は北大近くの単身者向けアパートで暮らしている。本当は
即日入居可の物件を探したもののあれこれと手続きがあり、あらかたの引っ越し作業が完了したのが一週間前。ようやく一息ついたと思ったらすぐに職場復帰である。
半年の間にどんな事件があり、どんな出来事があったのかは
あとはブランクをどれだけ早く埋められるかだが──。
「ここか……?」
入尾は教えられた部屋の前で足を止めた。
目の前にはスチール扉がある。「特異犯罪捜査係」というテープが貼ってあるので、ここで間違いないだろう。テープの端がめくれているのが若干気になる。
特異犯罪捜査係の部屋は刑事課のオフィスと別になっていると聞いた時、「さすが本部肝いりの新部署は違うな」と素直に感心した。だが、どうも様子がおかしい。丸ゴシック体で書かれた「特異犯罪捜査係」の七文字が嫌な予感を助長させている。
入尾は段ボールを片手で抱えて扉を押し開いた。立て付けが悪いのか、化け物じみた音が響き渡った。
部屋──いや、小部屋の中にはデスクが四台向かい合わせで置かれている。そのうちの一席には若い女が座っていた。おかっぱ頭に丸眼鏡という何とも言えない
入尾は女の向かいの席に段ボールを置いた。荷物の重みでデスクがギィと嫌な音を立てた。
部屋は壁が黄ばみ、天井は
嫌な予感が確信に変わりつつある。端のめくれたテープと丸ゴシック体が頭の中にちらついて仕方がない。
これは個室というより──。
(この続きは本編でお楽しみください)
作品紹介
蘇った刑事 デッドマンズ・サイド
著者 柿本 みづほ
定価: 792円(本体720円+税)
一度死んだ者にしか嗅げない事件の”におい”がある――
頭を撃たれながら奇跡的に蘇った刑事の入尾は、覚醒後、“ある衝動”を伴って現れる元妻の幻覚に悩まされていた。ある日、突然入尾の前に姿を見せた元部下の波多野は、その原因を「頭にいる女王のせいだ」と説明。自分は仲間だとも言う。女王とは一体? そもそも撃たれたのは何故? 一方、周囲では熊害が頻発していた。当面の利害が一致し、行動を共にすることにした2人が辿りついた真実は? 型破りな書き下ろし警察小説!
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322011000415/
amazonページはこちら































