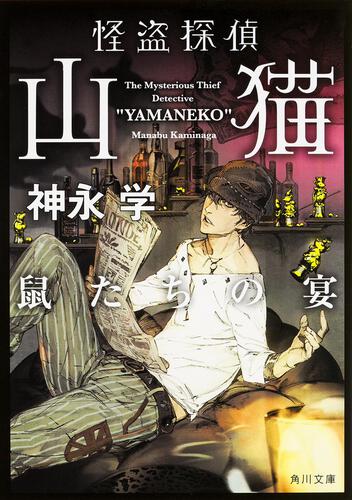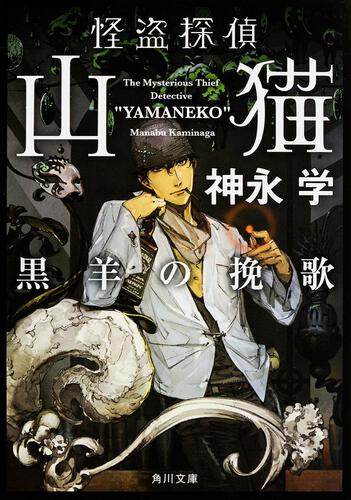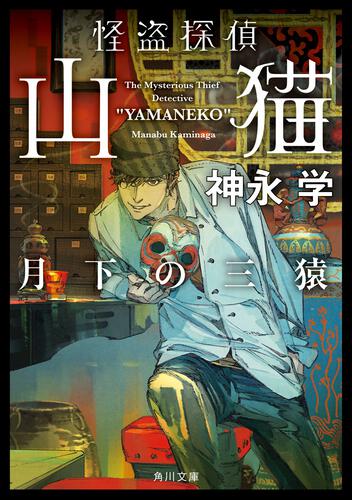さらば、山猫――!?
最強の敵が現代の義賊に襲いかかる。累計90万部の話題シリーズ、堂々完結!
ドラマ化もされ、話題になった「怪盗探偵山猫」シリーズ完結巻、
『怪盗探偵山猫 深紅の虎』がいよいよ刊行。
シリーズ完結を記念し、カドブンでは、シリーズ1冊目の『怪盗探偵山猫』の
試し読みを公開します。
希代の名盗賊の活躍をぜひお楽しみください。
>>前話を読む
10
署に戻って来たさくらは、崩れ落ちるように自席に座った。
三軒茶屋の現場を見たあと、関本が本庁に用事があると言いだし、車で送るはめになった。
──これでは、本当にただの運転手だ。
「お疲れのようだね」
冷やかし半分の声を上げながら、福原がさくらの隣に座った。
疲れているときに福原のニヤケ顔を見ると、いつも以上に腹が立つ。
「そっちは、どうなの?」
さくらは、捜査状況が気になり、
「またすぐに、聞き込みに行かなきゃならない。お守りをしている霧島が
「いつでも代わってあげるわよ」
「俺は、子どもが嫌いなんだ」
福原は、おどけた調子で答えると席を立った。「ねぇ」さくらは、立ち去ろうとする福原を呼び止める。
「何だ?」
「関本警部補が、盗まれた金額を知りたがってたわよ」
関本を引き合いに出したが、さくらも、それを知りたかった。
「口座には、金はほとんど無かった」
福原は、椅子に座り直してから言う。
「そうなんだ……」
「銀行からの借金は、返済が滞っていたらしい。廃業届も出ていたくらいだからな」
「それじゃ、山猫が盗む金はなかったってことね」
さくらは、
山猫は、入る場所を間違えたようだ。その上、犯行を目撃され、殺人まで犯すことになった。
「俺たちも、最初はそう思ってたんだが、従業員から面白い証言がとれた」
「何?」
「金庫の中には、こんな札束が十はあったらしい」
福原が、厚さを指で示しながら言う。
札束一つが百万円だったとして、一千万円の現金があったということになる。
「それだけの現金があって、なんで廃業届なんか……」
それで、借金全額を返済できなくても、事業を立て直すことに使うこともできたはずだ。
「そりゃ、あれだよ」
「
さくらの言葉に、福原が
「山猫にターゲットにされたくらいだから、
「目星はついてるの?」
「さっぱりだよ。何で山猫は、今回に限ってそのへんを書いてくれなかったのかねぇ」
福原は、両手を広げて大げさにジェスチャーすると、今度こそ席を立って出ていった。
「窃盗犯に、何を期待してるんだか……」
さくらは、ぼやくように言いながらも、疑問は感じていた。
今まで、山猫の残した貼り紙には、窃盗に入った会社が行っていた悪事の詳細が書き記されていた。
だが、今回に限り、その部分は書かれていなかった。
「なぜ?」
口にしたことで、新たな疑問が浮かんできた。
──いつから、山猫が出没するようになったのか?
さくらは、携帯電話を取りだし、聞いたばかりの関本の携帯電話の番号をプッシュする。
しばらくのコール音のあと、電話がつながった。
〈関本だ〉
低いトーンの関本の声が返ってきた。
「霧島です」
〈何の用だ?〉
「今井の事務所の金庫には、一千万円相当の現金が保管してあったそうです」
さくらは、相手の警戒を解く意味も込めて、最初に福原から仕入れた情報を伝えた。
〈一千万……はした金だな〉
関本が、鼻を鳴らして笑った。
「はした金……ですか?」
〈山猫にとって、一千万は、はした金だ。あいつは、一億以下の仕事をしたことがない〉
関本の言う通りであれば、確かにはした金だ。だが──。
「山猫は、最初から、そんな大金を?」
さくらは、疑問をぶつけた。
通常の犯罪者の心理から考えれば、まずは、小さい仕事から行い、慣れてくるにつれて、大きな仕事に移行していくのが自然だ。
〈最初からだ〉
「最初は、いつなんですか?」
〈五年前。場所は、
「三億!」
さくらは、目を
最初の仕事で、いきなり三億──。
〈奴は、特別なんだ〉
確かに特別だ。いきなり、三億の現金を盗もうとするなど、余程の自信があるか、ただのバカのどちらかだ。
「そのときも、犯行現場には、何の
〈貼り紙以外に、物的証拠は何もない。いつもと同じだ〉
関本が断言した。
もし、その話が本当なら、山猫は、最初の犯行のときから、今のやり方を確立していたことになる。
それは、
「そうですか。ありがとうございます」
電話を切ろうとしたさくらを、関本が呼び止めた。
〈がんばるのはいいが、これ以上、首を突っ込むのは止めておけ〉
関本は、この上ないくらいに冷淡な口調だった。
「どういう意味です?」
〈お前は、刑事には向いてない。残念だが、親父さんにはなれない〉
「あたしは……」
〈親父さんを思うなら、警察なんか辞めて、普通の生活を送れ〉
関本は、一方的に言うと、電話を切ってしまった。
さくらは、携帯電話を握り締め、きつく唇を
かつて、母親にも同じことを言われた。
さくらが、警察官になったきっかけは、父親の殉職が大きく関係していたのは確かだ。だが、今はそれだけではない。
仕事の中に、自分の存在意義を感じている。だから──。
「辞めるもんですか」
さくらは、キッと表情を引き締めて顔を上げた。
11
アスファルトから、熱気が立ち上ってくる。
勝村は、額からあふれ出るタマのような汗を
渋谷の駅に戻るより、井の頭線の
狭い路地を選んで歩いてきたので、すれ違う人もほとんど無い。
──ごめんなさい。
サキが、最後に言った言葉が頭を
──なぜ、彼女は別れ際に「さよなら」でも「またね」でもなく「ごめんなさい」と口にしたのかだ──。
あれは、誰に対する、どういう意味の「ごめんなさい」だったのか?
今になって思えば、サキは肉食動物に
──サキには、ぼくが血に飢えた狼に見えたのだろうか?
もしそうだとしたら勘違いだ。勝村は、自分のことを
スキを見て飛び掛かるだけの
勝村は、公園の前まで来たところで、ふと足を止めた。
ジャケットのポケットに手を突っ込み、サキから受け取ったネックレスを取り出す。
チェーンの先に付けられた装飾の花びらは、おそらく桜だろう。
花自体をモチーフにした装飾品ならよく見るが、花びら一枚だと、どこか味気ない気がする。
不意に、背後から強い光を浴びせられた。
──何だろう?
勝村は、手をかざし、目を細めながら振り返る。
黒いハイエースが、ライトをハイビームにしてすぐ後ろに迫っていた。
車が一台やっと通れるほどの狭い路地だ。勝村は、公園の敷地に身体を寄せ、通過するのを待つことにした。
ハイエースは、人間が歩くのよりゆっくりした速度で進み、勝村の真横で停車した。
ゴォ!
獣の
「え?」
勝村が戸惑っている間に、中から覆面を
海外のテロリストがしているような、目と口の部分に穴が空いた、ニット地のバラクラバという覆面だ。
だが、覆面をしていても、勝村は相手が誰であるかはすぐに分かってしまった。
白シャツにグレイのパンツの男と、アロハシャツにジーンズの男。服装は、さっきクラブにいたときと全く同じだ。
「勝村英男だな」
覆面の奥で目を光らせながら、白シャツの男が言った。
どう見積もっても、友好的な態度には見えない。
「は、はい……」
──なぜ、ぼくの名を?
勝村は、戸惑いながらも返事をする。
嫌な予感がして、みるみる
白シャツの男が、
それを受けたアロハシャツの男が、勝村の背後に回り込み、後ろから抱きしめるように身体を押さえつける。
「な、何をするんですか!」
勝村は、軽いパニックに陥りながらも、身体をよじって必死に抵抗を試みる。
「黙れ」
声と同時に、白シャツの男の右の
とっさのことに、かわすこともできず、勝村は鼻でそれを受け止めた。
肉を打つ鈍い音とともに、熱をもった痛みが、鼻を中心に顔全体に広がっていく。
鼻から、ぬるりとした液体が流れ出てくる。
──血だ。
真っ赤な血が、アスファルトにポタポタと滴り落ちる。
後ろから押さえつけられていて、顔を押さえることも、うずくまることもできなかった。
白シャツの男は、勝村の手から強引にネックレスを奪い取る。
「返せ!」
勝村は、腹から声を絞り出すようにして叫んだ。
「騒ぐんじゃねえよ」
白シャツの男は、勝村に顔を近づけ、静かに言う。
他人を傷つけることを、何とも思っていない──覆面の奥で鋭く光る目が、そう言っているようだった。
「連れてくぞ」
白シャツの男の指示に従い、アロハシャツの男が、強引に勝村を車の中に押し込もうとする。
さっきのパンチで顔には痛みが残っているし、再び殴られることに対する恐怖もある。
だが、事情も説明せず、いきなり人を殴りつけるような奴らの車に乗ることは、自殺行為でしかない。
──逃げなきゃ!
「うあぁ!」
勝村は、声を上げながら最後の抵抗を試みる。
アロハシャツの男から逃れようと、足をバタつかせながら、身体をよじる。
暴れた拍子に、運良く勝村の頭が、アロハシャツの男の顎先に当たった。「うっ」と短い
──今がチャンスだ。
勝村が、身を翻そうとした
呼吸が止まり、下半身に力が入らず、そのまま前のめりにアスファルトに倒れた。
血の気がどんどん引いていき、冷や汗が流れ出す。
「騒ぐなと言ったろ! ボケが!」
白シャツの男が、革のブーツを倒れた勝村の頭に載せ、体重をかける。アスファルトと靴底に挟まれ、
──クソッ。
勝村は、痛みを
悲嘆に暮れる勝村の耳に、突然歌声が聞こえてきた。最初は、白シャツの男が歌っているのかと思ったが、違うらしい。
歌声が、どんどん近づいてくる。
「男はぁ~いつもぉ~、待たせるぅだけでぇ~。女はぁ~いつもぉ~、待ちくたぁ~びれてぇ~」
歌詞からして、
白シャツの男は、勝村の頭に載せた足をどけ、必死に辺りを見回している。
おそらく、酔っ払いだろう──。
偶然にも、この路地を通りかかってくれたのはラッキーだった。不条理な状態から抜け出せるかもしれない。
勝村も、身体を起こして声の主を捜す。
暗闇の中から、ぬうっと浮かび上がるように男が姿を現した。
「いやあぁ。恋ってのは
男は、そこで起きている騒動などお構い無しに、
初夏だというのに、黒のロングレザーコートを着て、ニット帽をかぶっている。
だが、その顔はもっと異様だった。男は、なぜか、ひょっとこのお面をつけていた。
「さっさと
白シャツの男が、
「やだなぁ、お兄さん。怖い顔しちゃって。そんなんじゃ、女にモテないよぉ」
お面の男は、間延びした口調で言うと、肩を震わせながら笑った。
「てめぇ、何者だ?」
「見て分からない? ただの酔っ払いだよぉ~ん」
白シャツの男の脅しは通用しなかった。お面の男は、両手を広げ、腰を振るようにして奇妙な踊りを披露する。
「調子に乗りやがって」
我慢の限界を超えたのだろう。白シャツの男は、ボクサースタイルの構えから、体重を乗せた右のパンチを打ち出す。
──危ない。
勝村が思うのより早く、お面の男は身体を左に振ってパンチをかわす。
「残念でしたぁ」
お面の男が、陽気に身体をゆする。
すっかりプライドを傷つけられた白シャツの男は、右、左と連続して大振りのパンチを繰り出す。
だが、お面の男は、そのパンチを全てダッキングだけでかわしていく。
息の上がった白シャツの男が、動きを止めてお面の男を睨む。
「次は、こっちの番だね」
お面の男は、言うなりコートのポケットから筒のような物を取りだし、白シャツの男に向かって放り投げた。
白シャツの男は、訳も分からず、反射的にそれを受け取る。
それと同時に、その筒から勢いよく煙が噴き出した。
動揺した白シャツの男は、その筒をアスファルトの上に落とした。それでも、煙は勢いよく噴出し、視界が白い煙におおわれていく。
──あれは、発煙筒だ。
「クソ!」
「何だ、この煙!」
「わ、分かりません!」
「何とかしろ!」
白シャツの男と、アロハシャツの男が、次々と声を上げる。
ジャケットの
視線を向けると、煙で
「走れるか?」
お面の男が言う。
「なんとか……」
勝村は、むせ返りながら答える。
「来い」
お面の男が、言いながら勝村の腕を強く引っ張った。
──お面の男は何者で、何を考えているのか?
疑問はたくさんあったが、このままここにいるよりマシだ。勝村は、お面の男に従うことにした。
「乗れ」
そのまま、遠くに逃げるのかと思っていたが、お面の男はハイエースの後部座席に乗るように促す。
「この車に?」
「早くしろ」
お面の男に
──どうするつもりだ?
勝村の疑問をよそに、お面の男はハイエースの運転席に乗り込み、エンジンを吹かす。
「ドアを閉めろ」
お面の男に指示され、勝村はスライド式のドアを勢いよく閉めた。
それと同時に、こちらの動きに気づいたらしい白シャツの男が、ドアに張り付いてきた。
ホラー映画のゾンビのようだ。
白シャツの男が、ドアを開けようと手を伸ばす。勝村は、急いで
「出て来い!」
ドンドンとドアを
この状況で、「出ろ」と言われて、素直に出ていく奴はいない。
「ぶっ殺してやる!」
白シャツの男は、怒声を響かせるのと同時に、腰とベルトの間に挟んであった
ロシア製の軍用拳銃、トカレフだ──。
七・六二ミリの弾丸は、車のガラスなど簡単に貫通する。
──殺される。
勝村は、身を硬くすることしかできなかった。
白シャツの男が引き金を引いた瞬間、ハイエースが勢い良く走り出した。
ガラスが砕け散ったものの、運良く弾丸は勝村を
車は、ぐんぐんスピードを上げ、すぐに二人組の姿は見えなくなった。
──助かった。
相手が違うだけで、正体不明の人間に
「ひ、一つ質問してもいいですか?」
勝村は、おそるおそる運転しているお面の男に声をかけてみた。
「一つならいいぞ」
あれだけの騒ぎのあとなのにもかかわらず、お面の男はのんびりとした口調だった。
「あなたは、誰ですか? ぼくを、どうするつもりですか?」
「一つって言いながら、二つ質問してるじゃねぇか」
「あ、いや……」
「まぁ、俺は優しいから、答えてやってもいいぞ」
「お、お願いします」
──妙な感じになっている。
勝村には、お面の男の言動がまるで読めない。
「俺は、正義の味方で、君を助けにやってきたんだよ。勝村英男君」
お面の男は、いかにも得意そうに言う。
──正義の味方? 助ける?
勝村は、ますます混乱してしまった。
そんな説明で喜ぶのは、三歳児くらいまでだ。だいたい、ひょっとこのお面をつけた正義の味方なんて、聞いたことがない。
「答えになっていません。それに、なぜぼくの名前を知ってるんですか?」
「一度にいろいろ言うな。見かけによらず、せっかちな奴だな。人生には、ゆとりが大事だ。分かるか?」
お面の男は、相変わらずおどけた調子だ。
これ以上、お面の男と話していても、まともな返答は得られそうにない。
「あの……車を停めてもらえますか?」
勝村は、運転席の方に身を乗り出しながら言う。
「なぜだ?」
「警察に行きます」
「嫌だね」
お面の男は、即答だった。
「え?」
「警察は、俺が世の中で三番目に嫌いなものだ。いや、違うな。警察より、ギャル男の方が嫌いだから四番目か……」
また、話を
この際、そんなの何番目だって構わない。
「嫌いとかの問題じゃありません。ぼくは襲われて、殺されかけたんです」
「うん。優等生の答えだな。だけど、今回の問題は、受験用の問題じゃない。なぞなぞなんだよ。よって、その答えは不正解」
お面の男は「プップー」とクラクションを二回鳴らした。
勝村には、お面の男が、この状況において、なぜここまでふざけていられるのか、その精神構造が理解できなかった。
「間違ってなんかないです。警察に行って、彼らを捕まえてもらう。それで終わりです」
勝村は、むきになって反論する。
「俺はそうは思わないなぁ。勝村君」
「どうしてです?」
「警察に行ったら、あの男たちは逮捕されるかも知れない。傷害罪に銃刀法違反ってとこだ。あと、これ盗難車っぽいから窃盗もつくな」
お面の男は、ハンドル脇から飛び出たコードを
イグニッションの下にあるカバーも
「それで充分でしょ」
「いいや。それが充分じゃないんだよ」
「どういう意味です?」
「あいつら、筋者だよ。意味分かる?」
「ええ」
勝村は
彼らが、まっとうな社会人とは到底思えない。お面の男が言う通り、暴力団関連の人間だろう。
「もしそうなったら、多分、逮捕されるのは一人だけだろうな。トカゲの
お面の男は、手を叩いて楽しそうに笑った。
──笑いながら言う話じゃないだろう。
勝村は、
「だいたい、何でぼくが、あんな目に遭わなくちゃいけないんですか? 何もやってないです」
勝村は、言いながらルームミラーに映るお面の男の顔を見た。
当然なのだが、お面をつけているので、その表情は分からない。
「そう。そこが問題なんだよ。君は、何もやってないと思ってる」
「事実です」
「残念だが、その考えは外れだ」
お面の男が、再びクラクションを二回鳴らした。
「なぜです?」
「何もしていないのに、狙われるはずがない。残念だが、君には狙われる理由がある。そして、君がその原因を解明し、改善するまで狙われ続ける」
「ぼくが何かしたと?」
思い返してみたが、誰かに恨みを買うようなことをした覚えはない。
多少、恨みや反感を買うことはあるかもしれないが、拳銃を向けられるほどのことではない。
「正確には、少し違う。君は知ってはならないことを、知ってしまっている」
──知っては、ならないこと?
「それは何ですか?」
「おそらくは、今井洋介殺害の真相につながる何かだ──」
お面の男の一言が、勝村の心臓を貫いた。
呼吸が乱れ、鼓動が速くなる。
「今井さんの死の真相?」
勝村は、震える声で、かろうじてそれだけ口にした。
「本当に、今井は窃盗犯を目撃したために殺害されたのかな?」
「別に理由があると?」
お面の男は、大きく頷いた。
素顔を隠していても、自信に満ちた表情をしているのが伝わってきた。
「俺は、この事件は山猫という窃盗犯の仕業ではないと確信している。裏にもっと大きな何かがある」
「大きな何か……」
勝村は、オウム返しする。
事件の取材を始めてから、勝村もそれを薄々感じていた。
窃盗犯の場当たり的な犯行だとした場合、不自然なことが幾つもある。
「君はどうだ勝村君。今回の事件に、疑問を持ち始めているんじゃないのか? 本当に今井洋介は居直り強盗に殺されたのか?」
図星を指され、勝村は目を剝いた。
今井が死んでから、立て続けに奇妙な出来事が起きている。
サキからの電話。渡されたネックレス。それに、サキの話では、今井は自分が死ぬかもしれないと予見していたとも考えられる。
極めつけは、さっきの二人組からの襲撃──。
「でも、警察がちゃんと捜査しているわけだし……」
勝村は、苦し紛れに言う。
お面の男は、それを鼻で笑い飛ばすと、路肩に車を停め、ひょっとこのお面を外した。
彼の素顔が見られると思ったが、大きな間違いだった。
念入りに、ひょっとこのお面の下に、さっきの暴漢と同じ、ニット地の覆面をかぶっていた。
「警察がやっているのは、窃盗犯の追跡捜査だよ」
男は、さっきまでとは明らかに違うトーンで切り出した。
「そうでしょうね」
「もし、今井という男の死に、別の真相があるのだとすれば、目指す方向が違う。東北新幹線に乗っても、京都にはたどり着けない」
言っていることは理解できる。
だが、素顔を隠すような人間の言うことを、素直に聞くわけにはいかない。
「今回のことをちゃんと説明すれば、警察だって事件の関連を……」
「本気で言ってるわけじゃないだろ。警察はすでに、居直り強盗の犯行だと断定しているんだ。その状態で、状況証拠を並べたところで捜査方針は変わりっこない」
勝村に口を挟む隙を与えず、男がさらに続ける。
「仮に、窃盗犯を捕らえることができれば、警察は自分たちの過ちに気付くかも知れない。だが、それでは遅い。初動捜査を誤った警察が、犯人を逮捕できると思うか?」
勝村の頭に、名古屋で起きた妊婦殺害事件が思い起こされた。
警察は初動捜査の際、第一発見者の夫を犯人だと決めつけて捜査にかかった。それが誤りであったと気付いたときには、すでに遅かった。
情報は風化し、目的を失った捜査官たちが、犯人を捕らえることなく時効を迎えてしまった。
居直り強盗でないとすれば、警察はすでに致命的なミスを犯していることになる。
答えを迫るように、覆面の下から男の鋭い視線が向けられた。
──あ!
勝村は、そこで思わぬことに気づいた。
「ぼくは、あなたを知っている」
勝村は、男を指差して声を上げた。
男の目にぐっと力が入る。目の下に、小さな傷があるのを見つけた。勝村は、昨晩、同じ箇所に傷のある男に会っている。
「あなたは、あの時のカメラマンでしょ」
口に出したことで、勝村のイメージが、より確かなものに変わっていく。
──間違いない。
覆面を
「どうしてそう言いきれる?」
「右の目の下にある傷。それに、特徴的な鼻」
「おいおい。冗談はやめてくれ」
「ぼくは、記憶力だけは自信があるんだ。覆面の上からでも、鼻の形はイメージできる。時計だって同じGショックだ。それに、靴は……」
「分かった。もういい。恐ろしい記憶力と観察力だな。応用はできていないようだが」
男は観念したのか、覆面を外した。
その顔は、予想通り、昨晩一緒に飲んだ、カメラマンの山根だった。
相手の素顔が分かったことで、精神的に少しだけ優位に立ったような気がする。
山根とは、居酒屋で再び顔を合わせたが、今になってみると、それも偶然ではないかも知れない。
今井と仕事をしたことがあると言っていたが、それだって怪しい。
「あなたは何者ですか。ただのカメラマンじゃないはずだ」
男は隠していた素顔がバレたというのに、全く動じた様子がない。
マッチを擦って煙草に火を
目を閉じ、ゆっくりと煙を吐き出す。
「俺が何者かなんて、この際どうでもいい。お前は知りたくないのか? 今井という男がなぜ死んだのか」
──もし、他に真相があるなら何としても知りたい。
勝村は、ぐっと山根の方に身を乗り出した。
「あなたはその答えを知ってるとでも?」
「知らねぇよ」
山根は、あっさり質問を突き放す。
「そんな無責任な。なら、どうして今井さんの事件に裏があると?」
「今井という男の会社に、山猫は窃盗に入っていない。それなのに〈山猫〉と書かれた貼り紙が残された。誰かが山猫に罪を被せようとした。ということは、これは間違いなく計画殺人なんだよ」
山根の理論は分かる。だが、それは山猫が窃盗に入っていないという大前提の下で、初めて成立するものだ。
「どうして、山猫の仕業ではないと断言できるんです?」
勝村は、自分で口にしながら、不意にその答えが頭に浮かんでしまった。
現在の捜査状況の中で、山猫が犯人ではないと言い切れる人間は、世界中でただ一人しかいない──。
「それはな……」
山根が運転席から身を乗り出して、尖った鼻先が付くほどに顔を近づけた。
「俺が山猫だからだよ」
〈第8回へつづく〉
ご購入はこちら▶神永学『怪盗探偵山猫』| KADOKAWA
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
▶神永学シリーズ特設サイト