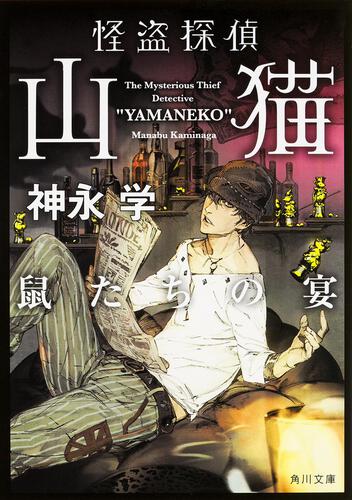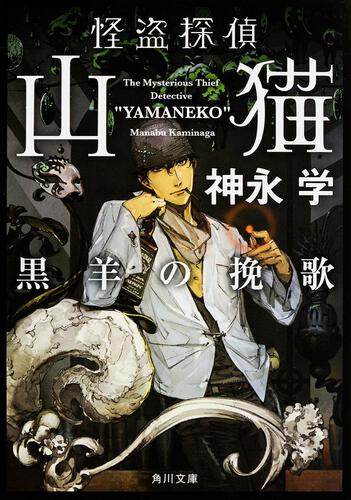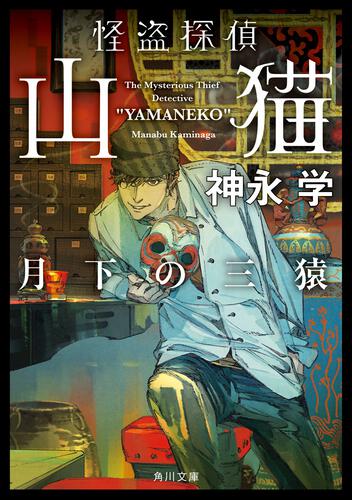The first day
一日目 こうして事件は始まった
1
「山猫って知ってるか?」
質問の主は、雑誌の副編集長、
明日、納品分の原稿を書き上げ、帰り支度をしていた勝村は、カバンを肩にかけて水上のデスクに歩み寄った。
「絶滅の危機にある猫ですよね。ツシマとかイリオモテとか」
勝村は、おどけた調子で答えた。
環境問題をテーマにした記事を、担当させられるのかもしれない。
「やっぱり、そうきたか」
水上は、乾いた笑い声を上げた。
「違うんですか?」
「うん、全然違う」
「じゃあ、ヴィスコンティですか?」
一九六三年に公開されたイタリア映画──。
芸術とまで言われる名作だが、勝村は、最後まで集中力がもたず、途中から眠ってしまった。
「あれ、いい映画だよね」
「はぁ……」
勝村は、
「だが、残念だけど、ヴィスコンティでもない」
「じゃあ、何です?」
勝村は、黒ぶちメガネのフレームを指先で直しながら
「三日前、
「はい」
ニュースでしきりに報道されているので、勝村もある程度の情報は持っている。
三軒茶屋のオフィスビルに入っている、システム開発会社の金庫から、一億円の現金が、ごっそり盗まれた。
荒らされた形跡はなく、社長が金庫を開けるまで、誰も被害にあっていることに気づかなかったらしい。
間違いなくプロの仕事だ──。
「あの事件の犯人が、山猫というらしいんだ」
「そうなんすか」
勝村は、納得して
「実はな、まだ記事になってないんだが、その事件には後日談があるんだ」
水上は、ヤニで黄色くなった歯を見せて、ニヤリと笑った。
「後日談?」
「そう。今日になって、社長が逮捕されたんだよ」
「被害者なのに?」
勝村は、
「そう。被害者なのに……」
水上は、じらすように間を置くと、煙草に火を
「どういうことです?」
勝村は、身体を反らして煙を
「被害にあった会社には、副業があったんだよ」
「副業?」
「その会社は、顧客情報の管理システムに携わっていたんだが、その業務の中で入手した個人情報を使い、振り込め詐欺をやっていたんだ」
「それは、不運でしたね」
勝村は、肩をすくめるようにして笑った。
金を盗まれたうえに、自らの犯罪が明るみに出て、警察に逮捕される。
──いい気味だ。
勝村は、内心
「いやいや違うんだよ。あの事件は、ただの不運じゃないんだ」
水上は、ウィンナーのように、たっぷり肉のついた指を、勝村の鼻先に突きつけた。
勝村は、逃げるように身体を
「不運じゃない……」
──どういうことだろう?
勝村は、考えをめぐらせてみたが、これといっていいアイデアは出て来ない。両手を広げて、降参のポーズをとった。
「金庫に、貼り紙が残されていたんだ」
水上が、得意そうに言う。
「貼り紙……ですか?」
「そう貼り紙だ。犯人から警察に向けた、メッセージが書かれた貼り紙」
──そういうことか。
勝村にも、話の筋が見えてきた。
「つまり……」
「窃盗犯である山猫が、警察に貼り紙というかたちで密告していたらしいんだ」
水上が、勝村を遮るように言った。
──なかなか
だが、勝村はもうひとつ信じられなかった。
現代の世の中に、
「それって都市伝説みたいな話ですね」
「噓ついてるように見える?」
素直に頷きそうになった勝村だったが、慌てて首を左右に振り、鼻の頭をかいた。
「何か証拠はあるんですか?」
「だからさ、それを勝村君に調べてもらって、追跡記事を書いてもらいたいわけ」
「ぼくに?」
「そう。うちって芸能記事メインだけどさ、この事件はいけると思うんだよね」
水上は、煙草を灰皿に押しつけ、続けざまに新しい煙草に火を点けた。
水上が副編集長を務めるのは、芸能スキャンダルやファッション、映画などのネタをメインにしている大衆向けの週刊誌だ。
かつては事件記事も追いかけていたのだが、編集長が代わり、大幅に方向転換した。
今の時代、暗い事件記事よりゴシップをメインに持ってきた方が雑誌の売り上げが伸びるというのが、現編集長の考えだ。
山猫と名乗る窃盗犯のネタは、事件記事ではあるが、どこか現実離れしている。
水上は、現編集長の意向とも合うと踏んだのだろう。
「勝村君は、
「あ、はい」
水上の言う通り、前任の編集長である今井のとき、勝村は主に事件記事を追いかけていた。
勝村が、出版社で働きだして、すぐについた上司が今井だった。
取材のイロハを徹底的にたたき込まれた。勝村にとって、今井は師匠と呼ぶに値する人物だ。
二年前に、独立するために退職したが、今でも月に一度は飲みに行く間柄だ。
「適任かなって思ったんだ」
「いいっすよ。やらせて下さい」
勝村は快諾した。
久しぶりの事件記事ということで、気持ちが
「じゃあ、頼むね」
水上は、煙草をくわえたまま、椅子の背もたれに身体を預けた。
「期限はどれくらいあるんですか?」
勝村は、カバンの中からスケジュール帳を取りだしながら訊ねた。
「次号に、追跡記事の第一弾を載せたいんだよね」
「と、いうことは、五日くらいですかね」
勝村は、スケジュールを目で追いながら言う。
「三日で頼むよ」
「三日?」
──期間が短すぎる。
「全部、まとめろとは言わないよ。ただ、記事がモノになるか、確認したいんだ」
今から、事件の概要を調べ、取材対象を捜し、インタビューをする。現場の写真も必要だし、捜査状況の情報も欲しいところだ。
勝村が、今からやるべきことを、頭の中で整理しているところで、水上の携帯電話に着信があった。
「久しぶりだね。あ、うん。大丈夫よ……」
水上は、煙草を灰皿に押しつけ、勝村がいることを忘れているかのように、携帯電話で話を始めた。
一度、席に戻るべきか悩んだが、勝村は、立ったまま水上の電話が終わるのを待った。
「え? それってマジ? 今回、タイミング早いね。あ、本当……うん。今さ、丁度ライターがいるから、すぐ行かせるわ。住所教えてもらえる?」
水上が、興奮気味に声を上げながら、デスクの上のメモ帳を引き寄せ、ペンを走らせる。
話の内容は聞こえなかったが、何が起きたのかは、何となく予想がついた。
「勝村君。タイミングいいよ。また出たって」
電話を切った水上が、
「山猫ですか?」
「そう。山猫」
「でも、なんで山猫なんでしょうね」
勝村は、受け取ったメモの住所を確認しながら、不意に浮かんだ疑問を口にする。
「現場に残されていた告発メモに、山猫って書いてあったんだって」
「自分で名乗ってるわけですか……」
以前に、犯行現場に自分がやった証拠として、
今回の山猫といい、窃盗犯というのは、自己顕示欲が強い人間が多いのかもしれない。
勝村は、カバンの中から、携帯用の地図を取り出し、住所を確認していて、思わぬことに気がついた。
──この住所の場所を知っている。
2
現場は、環状七号線沿いにある八階建てのオフィスビルだった。
エントランス前には黄色いロープが張られ、制服警官が警備にあたり、それを取り囲むようにヤジ馬とマスコミの姿があった。
「ついてないわ」
さくらは、落胆のため息をついた。
週末の夜、環状七号線は混み合っている。それを見越して、裏道を走ったのだが、余計に時間がかかってしまったらしい。
近くの路上に車を停めたさくらは、人の群れを
「何があったんですか?」
途中、
現場に到着したばかりなので、質問に答えられるほどの情報を
さくらは、警備に立つ制服警官に手帳を提示し、黄色いロープの内側に入った。
「随分、遅かったじゃないか」
同僚の
白塗りをした芸者のように肌の色が白い。
ギャンブル好きで、外見に
「福原が、一番乗り?」
「俺も、十五分ほど前に来たところだ」
悪気はないのだろうが、福原は独特のねちっこい
「救急車が来てるけど、ケガ人が出たの?」
さくらは、肩まである髪を後ろでアップにしてヘアクリップで留めると、ジャケットのポケットから白い手袋を取り出しながら
「死体が一つ」
福原は、
「死体?」
「さっき、救急隊員が死亡を確認した」
「
さくらは、思わず表情を
「刑事なんだから、一般人みたいな反応すんなよ。今さら、死体が怖いわけじゃないだろ」
福原は、おどけた調子だった。
その態度に、無性に腹が立ったが、口に出すことはなかった。
さくらは、仕事柄、今まで数え切れないほどたくさんの死体を見てきた。だが、いつまで経っても、それに慣れることはない。
つい数時間前まで、息をして、食事をとり、人と話をしていた。それが、ほんの一瞬で肉の塊と化す。
その光景を、日常化することに抵抗を感じていた。
「無線では、山猫って窃盗犯だっていってたけど……」
さくらは、訊ねた。
「いや、間違いなく奴だ。現場に、いつもの貼り紙もあったらしい」
山猫は、自分の犯行現場に、ご丁寧に署名入りの貼り紙を残していく。
義賊を気取った、小悪党だ──。
「死体は、どういうこと?」
さくらは、そこが引っかかっていた。
山猫は強盗ではなく、窃盗犯だ。窃盗の現場に、死体というのは、明らかに不釣り合いだ。
混同している人間が多いが、強盗と窃盗では、根本的に違いがある。
簡単に言えば、他人から無理矢理奪うのが強盗。人知れずに奪うのが窃盗。侍と忍者くらい違う。
「どうもこうもねぇよ」
福原が、
「ちゃんと答えてよ」
「まだ、はっきりしたことは分かってねぇけど、誰もいないと思って窃盗に入った山猫が、被害者と鉢合わせになった」
「それで、居直ったってこと?」
「多分ね。顔を見られたか何かして、慌てて首を絞めて殺しちまったんだろ」
福原は、自分の首を絞める真似をして、だらしなく舌を出した。
「絞殺されたの?」
「ああ。首にロープが巻き付いてたって……」
「身元は?」
「このビルに入ってる会社の社長で、今井
──一応の筋は通っている。
だが、なぜかさくらの胸には、もやもやとした雲が残った。この雲を晴らすには、自分の目で現場を確かめる必要がある。
さくらは、白い手袋を
エレベーターで、犯行現場となった七階のフロアに向かう。
目的の階に到着して、エレベーターを降り、廊下に出る。そこには、鑑識の人間がごった返していた。
さくらは、隙間を抜けるように廊下を進み、突き当たりの部屋に足を踏み入れた。
「めちゃくちゃね……」
さくらは、現場の惨状を目の当たりにして、思わず
五十坪ほどの事務所スペースの至るところに書類が散乱し、デスクの引き出しが片っ端から開けられていた。
まるで、嵐が通り過ぎたあとのようだ。
部屋の奥へと進んださくらは、窓際の床に、白いチョークで人型が描かれているのを目にした。
──ここで、今井が殺された。
さくらは、人型の前に
必ず、犯人を捕まえる。そのことだけを強く念じる。それが、自分たちにできる唯一の供養だ──。
〈第2回へつづく〉
ご購入はこちら▶神永学『怪盗探偵山猫』| KADOKAWA
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
▶神永学シリーズ特設サイト