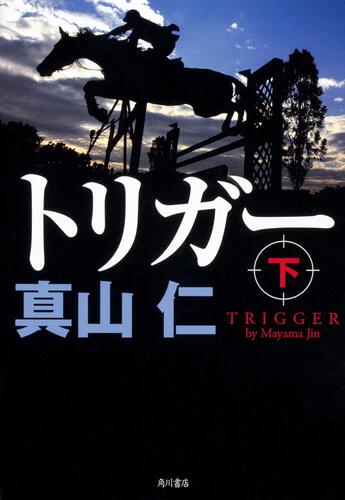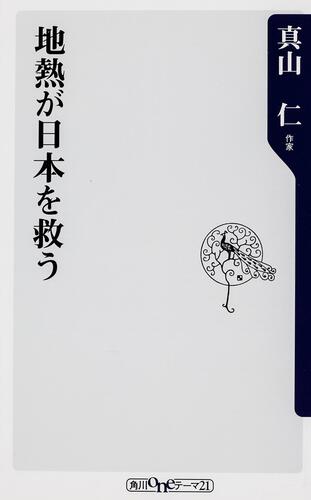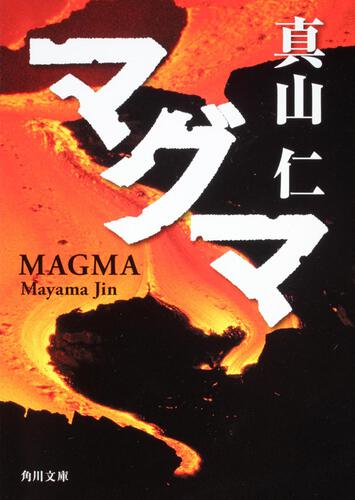人気シリーズ「ハゲタカ」をはじめ、様々なテーマに取り組んできた真山仁氏の最新『トリガー 上下』が2019年8月30日に発売となります。小説家デビュー15年目の著者が挑んだのは、東京五輪を舞台にした“謀略小説”。緊迫の展開が連続する本作の冒頭を公開します!
第一章 呼び出された男
1
五月半ばだというのに、台風に直撃されたような豪雨だった。
おかげで、いつもは順番待ちの行列ができる店が、ガラ空きだった。
一口食べたところで、携帯電話が鳴った。発信者を確認すると
「何だ?」
「殺しです。
「で、君は今、どこにいる?」
「今、捜一を出たところです。係長は、
中村は曜日毎の昼食場所を決めており、特別なことがない限りこのローテーションを守っている。
「そうだ。拾ってくれるか」
「了解しました。では、虎ノ門一丁目の交差点でピックアップします」
つまり、土砂降りの中で待てというのか、望月……。
腕時計で現在時刻を確認して、店に戻った。
中村は飲み込むようにして
車は、まだ、到着していなかった。
雨はさらに激しくなった。風は真横から吹きつけてくるし、傘を差す意味もない。ものの数分で、中村は顔から足元まで、びしょ
サイレンの音が高まり、車が脇に急停止した。路面を川のように流れる雨水が、大きく中村の方に跳ねた。
中村は舌打ちしながら助手席に乗り込んだ。
「すみません! こんな
ハンドルを握る望月は、本当に申し訳なさそうだ。
「気にするな。それより、こんな酷い雨なんだ。安全運転で行け。相手は死んでるんだ、逃げないからな」
最後の一言は、中村が部下に対して必ず口にするフレーズだ。
拙速こそ捜査の最大の敵だ。
「了解です」
そう言いながら、望月は車を急発進させた。
「現状で、分かっている情報は?」
「ガイシャは、女性のようです。しかも、アメリカ人だとか」
それは面倒な。
「現場に向かっているのは?」
「所轄とウチだけです」
警部である中村は、警視庁捜査一課第四係の係長で、望月巡査部長は、係で下から二番目に若い刑事だった。
視界が悪すぎるせいか、ハンドルにかじりつくようにして運転する望月は、刑事なんかより丸の内あたりのOLの方が似合いそうな風体だ。
かつては女刑事と言えば、男まさりの女傑か、地味なタイプが多かった。
それが、最近は望月のように身だしなみに気を配り、居酒屋よりビストロを好むような女性刑事が増えつつある。
捜査一課に配属されて一年余り、むさ苦しい男どもの中にあって、望月は結果も出してきた。ただ、せっかちで先走りしすぎる。
「追加情報としては、ガイシャの身元が、かなりヤバいとか」
「ヤバいって何だ?」
「米軍の将校なんだそうです」
それは、かなり厄介だな。
サイレンを響かせて、雨で渋滞する車列の間を縫うように車は疾走する。
アシストグリップを握りしめた中村は、望月は英会話が
ホテル・ガーデンプレイスは、東京オリンピックに合わせてオープンした外資系の高層ホテルだった。構えからして貧乏人には用なしの雰囲気がぷんぷんで、絶対にカネを落としたくないと、中村は思った。
四十七階のエレベーターフロアに着くと、四係主任の警部補
「お疲れ様です。鑑識は来ましたが、医者はまだです」
2
ラテックスの手袋とシューズカバーを装着して部屋に入ろうとしたら、池永に止められた。
「上着も脱いだ方が、いいです」
雨のせいで、中村は全身びしょ濡れになっていた。
すかさず望月が上着を脱がせてくれた。
室内には、ムッとした湿った空気が漂っていた。人が大勢いるせいだ。
所轄の刑事課長が迎えた。
「ご苦労様です」
「ご
課長の顔色が悪い。ベテランでも気分が悪くなるほど遺体の損傷が酷いのか。概要説明があるかと思ったが、課長は何も言わず、壁際に後退した。
「ガイシャは、アメリカの女性将校だと聞いたが」
「ええ。身分証を持っていました」
証拠保存袋に入ったIDカードを見せられた。
レイチェル・バーンズ、三十二歳。証明写真では、金髪で聡明そうな美人だった。
「望月、所属と階級は何て書いてあるんだ?」
「アメリカ陸軍国際技術センター・
IDカードを覗き込んだ望月が、すらすらと答えた。
三十二歳で、中佐か。相当のエリートじゃないか。
部屋の中央にキングサイズのベッドがあったが、捜査員が集まっているのは、窓際だった。
「そこ、どいて!」
課長が声をかけると、人だかりが二つに分かれ、彼らが何に注目していたのかが分かった。
窓際には、椅子が一脚あった。
そして、椅子の背もたれに女が顔をあずけてこちらを向いている。もちろん、生きてはいない。ガーターベルトで留めた黒いパンストを
血まみれだった。
中村の隣で、望月がうめいた。
「口の中に、何が入ってるんですか」
望月が指摘した異物に、中村も気づいていた。誰も答えないので、二人は遺体に近づいた。
「これって」
望月はそれ以上、言葉にできなかったらしい。
池永が補足した。
「舌が切断されて、押し込まれている」
3
キム・セリョンは、実家に構えた
彼女の部屋は、
今日は絶好調だった。
このところ、本業の検事の仕事に忙殺されて、トレーニングの時間が削られていた。
しかも、捜査は完全に行き詰まって、イライラが募るばかりだ。そこで、思い切って有給休暇を取った。
久しぶりに愛馬タンザナイトに会うと、大歓迎してくれた。
セリョンが抑えようとしても、パワー全開で馬場を疾走した。
午後の障害訓練でも、タンザナイトの張り切りぶりは続いた。
お陰で、セリョンを悩ませていた不安と
気持ちの良い汗をかき、オリンピックに向けての確かな
東京オリンピックまで、あと二ヶ月余り、そろそろ検事の仕事を休止しなければならない。
シャワーを浴び、湯上がりにモエ・エ・シャンドンのハーフボトルをグラスに注いで、リビングの窓際に立った。
眼下には、ソウルの母なる川、
今日は、いい日だったなあ。
お代わりを注ぐついでに、郵便物をチェックする。
たいして魅力のないエステやレストランなどのダイレクトメールに混ざって、厚みのある封書があった。差出人が記されてない。
検察官としての警戒スイッチが入った。
手袋を嵌め、慎重に開封すると、数枚の写真が入っていた。
ジョンミンとのツーショットの写真が数枚。他には、検察庁から出てきた時の姿、女友達との食事まで撮られている。さらに、タンザナイトとトレーニングしている時の写真もあった。
なんだ、これは。
最初は、ジョンミンの悪妻が送りつけてきたのかと思ったが、それにしては、不貞現場以外の写真が多すぎる──つまりこれは、「おまえを、いつも監視している」というメッセージらしい。
最後の一枚が目に入った途端、ギョッとして写真を落としてしまった。その写真には赤い塗料で書かれた文字だけが写されていた。
〝五輪に専念しろ。余計な好奇心は死を招く〟
このつづきは製品版でお楽しみください▶真山仁『トリガー 上』| KADOKAWA
▷トリガー【上下 合本版 電子特典書き下ろし短編付き】(電子書籍)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。