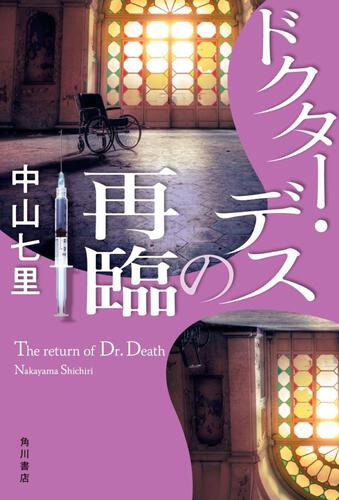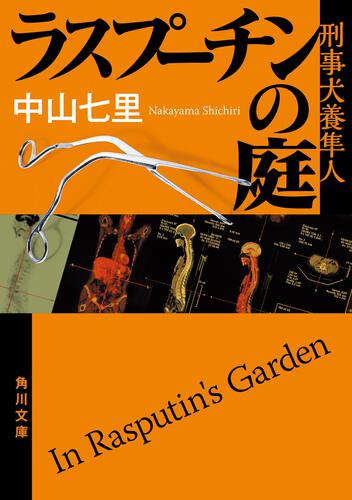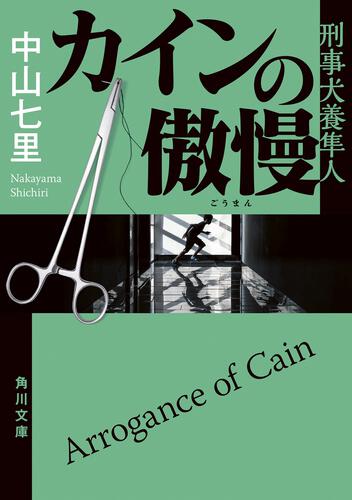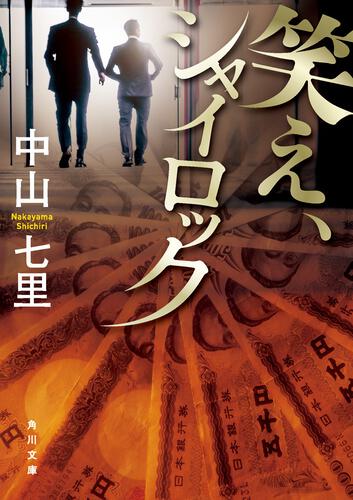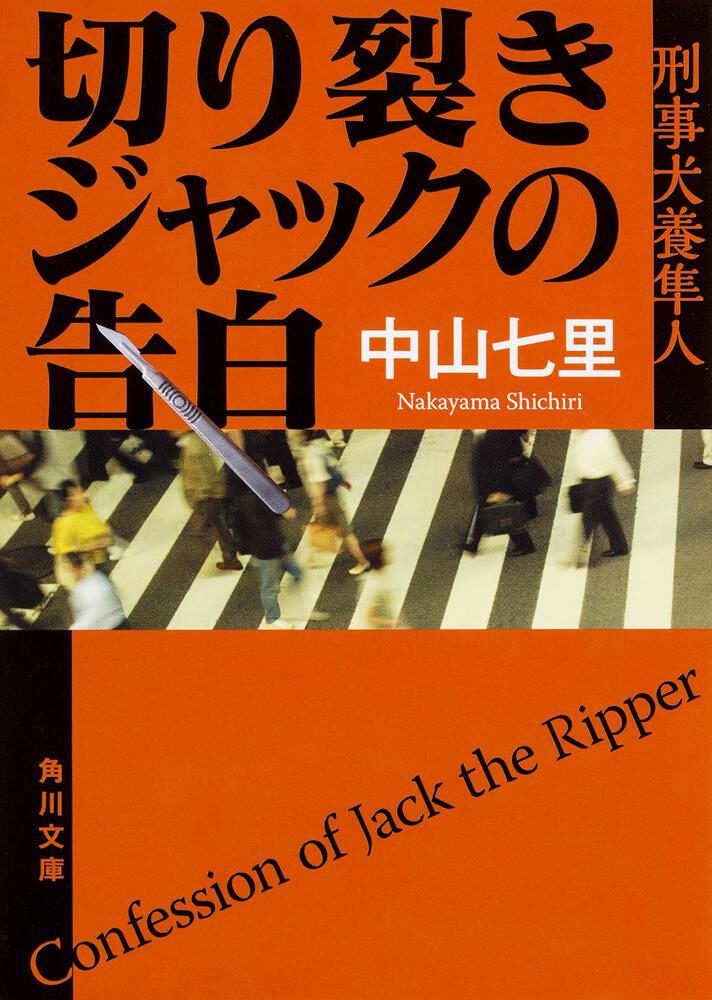家族全員にかけられた殺人容疑。
無実を証明するためにあがく父親が知ったのは――
悪夢のような家族の裏の顔だった。
どんでん返しの帝王・中山七里が贈る家族ミステリ『棘の家』の文庫化を記念して、第一章「穏やかな翠」第3節~第二章「棘のある葉」第3節を、大ボリューム特別公開!
事なかれ主義の中学教師・穂刈のもとへ、妻からかかってきた一本の電話。
そこから動き出す物語を、どうぞお楽しみください!
中山七里『棘の家』試し読み
一 穏やかな翠
3
穂刈にその知らせがもたらされたのは授業中のことだった。
小テストの最中、教室内が静まり返っている時、穂刈のスマートフォンが着信を告げた。マナーモードに設定していたが、鉛筆の走る音と生徒の息遣いしか聞こえない中ではバイブレーションの振動音も飛び上がるような大きさに聞こえる。
「ちょっと出てくるから、みんなそのままで続けていてくれ」
廊下に出てスマートフォンを取り出すと発信者は里美だった。授業中にはメールもしないよう取り決めをしている。里美も教員だったから事情は
名状しがたい不安に駆られながら通話ボタンを押す。
「いったいどうしたんだ。今が授業中なのは知ってるだろ」
『由佳が』
ひどく
「由佳がどうした」
『小学校の窓から飛び降りて』
一瞬、耳を疑った。
「もう一度言ってくれ」
『あの子、三階の窓から飛び降りて……』
あまりに突拍子もない話で思考がついていかない。頭が真っ白になるというのはこういうことをいうのか。
『……あなた。聞いてる?』
「それでどうしたんだ。由佳は」
『真下にちょうど植え込みがあって、そこに運よく……でも全身を強く打って病院に搬送されて』
「どこの病院だ」
『
「俺もすぐそっちに行く」
電話を切ると、穂刈は職員室に急いだ。教頭でも学年主任でも誰でもいい。事情を伝えて早退する。今、自分ができることはそれしかない。
三階の窓から。
飛び降り。
植え込み。
一向に整理のつかない頭を言葉の断片だけが素通りしていく。
飛び降りだと。それなら事故ではないというのか。
まさか由佳に限って。
飛び降りる理由なんて全く見当もつかない。
由佳の通う
畜生、まだ十二歳なんだぞ。
どうして、こんなことが起きた。
いったい誰のせいだ。
乱れに乱れて収拾のつかないまま、穂刈は職員室に残っていた同僚に伝言を残し、校外へ出る。大通りまで駆けていき、車道まで飛び出してやっとタクシーを捕まえた。
「南千住の美田園病院まで。大至急お願いします」
停止した時には憤然としていた運転手も、穂刈の顔つきを見るなり抗議の色を引っ込めた。
「本当に、早く。制限速度なんか守らなくていいですから」
「無茶言わんでくださいよ、お客さん」
「娘が、高いところから、落ちて」
運転手に子供がいるのかどうかは分からない。それでも穂刈の言葉を聞くと、唇を真一文字に結んで正面に向き直った。
「一応法令遵守しますけど、シートベルトを締めといてください」
病院までの道程、一秒が十秒にも感じられた。
早く着け。
もっと早く。
通りの制限速度が何キロなのか穂刈は知らなかったが、追い越しを幾度も繰り返したお
受付には里美、そして初見の男が二人立っていた。
あなた、と言い掛けて里美がこちらに駆けてくる。何が何だか分からないと顔に書いてあった。
「いったい何があった」
だが、里美はぶるぶると首を横に振るだけで言葉にならない様子だ。状況を確認しようと受付に一歩近づいた時、男の一人が目の前に立ち
「穂刈由佳さんのお父さんですね。千住署刑事課の
「しかし、今、由佳は」
「由佳さんは緊急搬送された後、手術室に入りました。つい先ほど始まったばかりです」
振り向けば里美がこくこくと頷いている。
「まだ予断は許しませんが、不幸中の幸いで由佳さんに致命的な外傷は見当たらなかったそうです。冷たい言い方になりますが、目下のところ穂刈さんたちには待つことしかできません。その間だけお伺いしたいのですよ」
待つことしかできない──そう告げられて穂刈は余計に惑う。伺うとはどういうことだ。こちらは早く詳細を知りたいのに。
坂東は刑事を名乗ったが、ドラマに出てくるような
「わたしたちで分かることなら何でも話します。しかしその前に、由佳が校舎の窓から飛び降りたという状況を説明してください。わたしも妻から知らせを受けたばかりで、さっぱり要領を得ないんです。お願いします」
「では、こんな場所では何ですから別室に参りましょうか」
坂東に促されて穂刈と里美は別病棟へと移動した。そこは手術室のある棟の待合室で、由佳の手術が行われているのと同じフロアらしかった。
「警察は小学校からの通報を受けて現場に向かいました。到着すると既に由佳さんは救急車で搬送された後で、我々は学校関係者からその時の目撃情報を集めただけなのです」
坂東の説明によれば、目撃情報の集積は以下の通りだ。
一時限目の終わり、つまり午前九時五十分頃、由佳のクラスは二時限目の図画工作で特別教室に移動するところだった。ところがクラスのほとんどが特別教室に移動しても由佳の姿が見えなかったと言う。
午前十時、担任がやってきて出欠を取ったが、やはり由佳は不在だった。不審に思った担任が教室に残っていないかを確かめるべく、特別教室を出た。
同時刻、由佳の教室の真下は四年一組が算数の授業中だったが、この際に何人かの児童が上から落下する身体を目撃している。
更に運動場では二年二組が体育の授業で集合しており、校舎に向かって整列していた。この時、やはり数人の児童が教室の窓から飛び降りる女児を目撃している。彼らの証言によれば、教室の窓に見えたのはその女児だけだったらしい。
女児は全開にした窓枠に立つと、
これらの証言を集めると、由佳の自殺未遂説が濃厚になってくる。そこで坂東たちが実施したのは、その原因があったかどうかの訊き込みだった。
「確認したいのですが、由佳さんが思い悩んでいた事実はありましたか。あるいは思い詰めるような問題が家庭内で発生していましたか」
問われて穂刈は考え込む。由佳とは
心当たりはあるのかと視線を送るが、母親の立場でも身に覚えがないらしく里美は切なげに首を振る。
「まだ訊き込みが全て終わった訳ではないのですが、現時点で一部気になる証言が挙がったんです。由佳さんがあるグループからイジメを受けていたという証言です」
まさか、と思った。
声に出したのは里美の方だった。
「そんな馬鹿な。家でもあの子、イジメに遭ってるだなんてひと言も……」
「学校内の証言だけでは不充分だったのでご両親からも事情を伺いたかったのですが。そうですか、家庭ではそんな様子はなかったのですね」
「誰と誰が由佳を苛めていたというんですか」
里美は形相を一変させて坂東に
「いや、奥さん。あるグループというだけで、メンバーが特定された訳じゃありません。イジメ
しかし、と坂東は念を押す。
「現状、それ以外に由佳さんが自殺を企てる理由がないのも確かです。我々は訊き込み調査を継続しますが、いずれにしても由佳さんの回復を待って本人からも事情聴取する必要があるでしょう。その際にはまたご協力を仰ぐことになりますのでよろしく」
坂東はそう言い残すと、もう一人の刑事とともに待合室を出ていった。
しばらくの間、穂刈は
由佳が飛び降りを図ったことは衝撃だが、その原因がイジメだったというのも負けず劣らず穂刈を驚愕させる。
イジメの防止と撲滅は穂刈自身の課題でもある。先日は鳥越の件で中村と協議したばかりだ。
ところが穂刈は最も身近にいた娘の被害を察知できなかった。これでは父親としてばかりか、教育者としての資質を問われても仕方がない。
じくじくと自責の念に駆られていると、真横に座っていた里美がいきなり
穂刈は今更のように、里美の置かれた立場に気づかされる。
親としての資質を問われているのは里美も同様だ。しかも専業主婦ではないとは言え、家で娘に一番接触しているのは母親だから、里美の失意と自責の念は穂刈よりも深く、そして暗い。
嗚咽はやがて
人気のない待合室と廊下に、里美の叫びが長く尾を引いた。
それから一時間も経っただろうか。待合室に女性看護師が入ってきた。穂刈は思わず立ち上がる。
「穂刈由佳さんのご両親ですか」
返事ができたのは穂刈だけだった。
「たった今、手術が終わりました。ご安心ください。命に別状はありません」
すると里美は看護師の腰にむしゃぶりつき、泣きながら礼を言い出した。
「あ、ありがとうございました。ありがとうございました……」
途端に穂刈は腰を抜かした。へなへなとだらしなく膝を折り、床に両手を突く。
よかった。
本当によかった。
「今、会えますでしょうか」
「申し訳ありません。手術が終わったばかりで、まだ麻酔も効いています。一時集中治療室に移しますので、面会は一般病室になってからとなります」
会って訊きたいことが山ほどある。確かめなければならないことも嫌になるほどある。それでも今は由佳の安静が最優先だ。
穂刈は思い出したように深く深く溜息を吐く。
里美は相変わらず泣き続けていた。
女性看護師に連れられて、二人は執刀医の
由佳は飛び降りる際、足から落ちた。しかも植え込みがクッションの役目を果たし、頭部の外傷はほとんどなかった。ただし内臓の一部が破裂し、右手首と右足首を粉砕骨折している。命に別状はないものの、リハビリが成功しなければ後遺症の残る可能性も捨て切れないと言う。
「飛んだ地点がさほど高くなかったのが幸いしました。様々な条件が偶然に合致した結果の
穂刈にはまるで福音のように聞こえたが、医師は最後に一つ付け加えるのを忘れなかった。
「こんな幸運は二度も続きませんよ」
原因の一端はあなたたちにあるんじゃないのか──医師の目は暗にそう告げていた。
坂東ら千住署の聞き取り調査は当日から本格化していた。穂刈は初めて知ったのだが、同じ証言者に事件発生直後と同じ質問をしたらしい。そうすることによって、本人も忘れていた新しい情報が発掘されたり、内容の
聞き取り調査の対象は七十人以上に及んだ。由佳のクラスメートと担任は言うに及ばず、所属していたクラブ、委員会、児童会関係者にまで範囲が広げられ大小の証言が
問題は、その結果の全てが穂刈たちに報告されないことだった。
「やはりイジメは存在していたようですね」
穂刈家を訪れた坂東は、開口一番そう言ってのけた。
「クラス全員と担任の先生はイジメの事実を把握していました。もっとも先生の方はイジメではなく、ただの仲
証言によれば、イジメの発端は由佳の正義感にあったらしい。
クラスに生活保護を受給している家庭の女の子がいた。最初は、生活保護の何たるかを人伝に聞いた子供たちがこの女の子をイジメにかかった。本人ではどうにもならない経済的事情をネタに迫害するという、子供らしい残酷な仕打ちだ。これに反発を示したのが由佳だった。彼らの振る舞いを担任に報告し、彼女の盾になったらしい。
その瞬間からイジメの対象は由佳へと方向転換した。告発した人間を攻撃するという、これまた明確な基準だ。
由佳に対するイジメの内容は更に陰湿だった。持ち物を隠す、破壊する。掃除バケツの水を被せる。土下座させ、その姿をスマートフォンで撮影する。衣服で隠れた部位を内出血するまで
「いったい、誰と誰がイジメに加担したんですか」
報告を聞いていた里美が
そんな仕打ちを受けながら両親にひと言も洩らさなかったと聞き、穂刈は
ただし沈黙を守っていた自尊心の強さには頷ける。家の中でも発揮している性格だ。だからこそ自分が虐待されているのを恥ずかしく思っていた。己さえ我慢を続けていれば他の誰にも危害が及ばないと考えていたのだろう。
娘の心根を思うと胸が張り裂けそうになる。クラスメートに虐待されている姿を想像しただけで、
「奥さん。誰がイジメに加担していたかは申し上げることができません」
「どうしてですか。あの子はそのために死にかけたんですよ」
「残酷な言い方になりますが、遺書すら残そうとしていない以上、イジメと自殺未遂の間に因果関係があるとはすぐに断定できません。それに加害児童から供述を得たわけでもありません。現状、我々が踏み込めるのはここまでです」
さすがに腹に据えかねたので、つい口が出た。
「わたしたちが被害届を提出すれば、腰を上げていただけますか」
心なしか坂東の表情が困惑に
「もちろん被害届を出されたら、我々は徹底的に捜査をします。加害児童からもきっちり聴取します。しかしそうすることによって、新たな紛争が
説明されるまでもない。
中高生ならともかく当事者同士が小学生の場合、加害者意識が希薄だったり、イジメの認識自体が曖昧だったりというパターンが多い。また加害者責任を追及する過程で今度は加害者が被害者に転換し、相手の保護者から逆に訴えられる可能性もある。そうなればクラスの中で訴訟合戦が始まり、親同士も泥仕合になる。
どちらの側に立とうと学校に居づらくなるのは自明の理で、いずれは転校の憂き目に遭う。早い話が、遺恨を晴らすつもりが双方に深い傷を残してしまうケースがほとんどだ。だから我が子が殺されたなどという甚大な被害でもない限り、大抵のイジメ事案は被害者側の泣き寝入りに終わることが多い。今回の事案がまさにそれに該当する。
「皮肉なことに穂刈さんご夫婦が教員でいらっしゃるので、わたしの説明もより深く理解していただけるでしょう。繰り返すようですが被害届を提出されれば、我々は粛々と職務を遂行します。しかし捜査によって派生する紛争なり被害なりには責任を持てません。その辺の事情を充分に考慮してから行動してください」
最後に同情の意を示してから、坂東は立ち去った。
一方、由佳は三日目の昼に意識を回復した。術後の経過も良好で、骨折部分の癒合を待ってリハビリが開始される運びとなった。
回復自体は喜ばしいことだったが、問題は由佳の態度だ。恐る恐る里美が水を向けても、決してイジメについては口を割ろうとしない。無理に訊き出そうとすると頭から布団を被り、穂刈たちとの接触を拒む。
被害者になってしまった自分を恥じているのか、それとも加害児童の名前を告げれば、
こうした一連の流れに際立った反応を見せたのが駿だった。
「俺が直接、由佳から訊き出す。それからイジメの張本人に仕返ししてやる」
妹を思うあまり、駿は突飛な行動に移る危険性がある。父親としては
「何で親父が怒らないんだよ。由佳が死にかけたんだぞ」
「父さんだって怒っている」
「それなら被害届でも何でも出せばいいじゃないか。教師なら、向こうの学校に怒鳴り込むことだってできるだろ」
「そういうのを公私混同というんだ」
「自分の子供が殺されそうになったんだ。そんな時に公私混同もクソもあるかよ」
物言いが
危うくお前は楽でいいと口走りそうになる。こちらは怒りたくても教師という立場が邪魔をして、言いたいことも言えずにいるのに。
「世の中というのは、お前が考えているほど単純なものじゃない。少しは頭を冷やせ」
「あんたは親父なのか、教師なのか、どっちだ」
胸の真ん中を
「さっきから聞いてたら体面の話ばっかじゃないか。また性懲りもなく家の中まで教師面を押し通すつもりかよ」
「黙れっ」
「そういうのは由佳に汚い言葉をかけたヤツに言えよ。それとも向こうの校長や先生や親と渡り合うのが怖いのか」
思わず手が出た。
左頰を打たれた駿が真横へ吹っ飛ぶ。
力を入れ過ぎたか。しかし
「親父が手を上げるのは、自分の子供だけなんだよな」
「手を上げるのが教育じゃない」
「誰が教育してくれなんて頼んだよ。親なら子供の
捨て
「何か言いたいことでもあるのか」
問い質してみても、里美は力なく嘆息するだけで何ら意思を表明しようとしない。
いや、違う。
口に出さずとも、その目が夫を非難していた。目の色は駿が見せたものと酷似している。父親である前に教育者であろうとする穂刈を
「……病院にあの子の着替えを持っていきます」
そう言って、里美もリビングを出ていった。
後に残された
駿と里美が自分に望んでいることは痛いほど分かる。教師の衣を
考えてみればこれほど愚かしい話もない。イジメの防止と撲滅を唱えながら足元の被害に気づきもしなかった。教師が聞いて呆れる。いったい、どこに目をつけていたのか。駿と里美がそっぽを向くのも無理はない。
否定された教育理論。
二つとも穂刈が己の指針として信奉していたものだ。
今回の事件が起きる前はかけがえのない財産でもあった。その財産が今、みすぼらしいガラクタに
己はどこで道を間違ったのか。
己は何を見誤ったのか。
自問し続けても、答えはどこからも返ってこない。
いつの間にか夕暮れになっていた。
4
由佳の飛び降り事件は当日のニュース番組で報道されたため、多くの者が知ることとなった。学校名や由佳の名前は伏せられているが、子供を千住小学校に通わせている保護者や関係者には丸分かりだろう。
そしてまた学校関係者の横の
穂刈の家族構成はプロフィール表を通じて中村が把握しているので、勤務先に由佳のことが知れるのも時間の問題だった。
他校のイジメが事件化した際に情報共有がされるのは他山の石として教訓に使うからだが、よもや自分の家庭がその教訓になるなどとは想像もしていなかった。
まさか由佳を題材に勉強会を開くような真似はしないにしても、正直中村や同僚たちに事件を知られるのは
だが、嫌な予感ほど的中する。
看護休暇の明けた翌朝、穂刈は職員室に入った途端に空気の異変を感じ取った。
「おはようございます」
「おはようございます」
交わす挨拶がどこか白々しい。まるで穂刈と向き合うのを避けているかのように視線を逸らしている。
間違いなく知られていた。
穂刈は
職員全員に知れ渡っているのなら、早晩生徒にも情報が洩れるだろう。噂の広まり方はそれほどまでに早い。
もし穂刈の生徒が由佳の事件を知ったら、何を思うだろうか。たとえばイジメの告発をした朋子は、昨日までとは違う目で穂刈を見るのではないか。
今から生徒たちの侮蔑が見える。
その時、卓上の電話が鳴った。表示を見ると内線で掛かっている。受話器を取り上げると中村の声が流れた。
『十分ほど、時間をいただけますか』
予鈴までにはまだ二十分ある。話の内容はおおよそ見当がつくが、拒否する訳にもいかない。重い足を引き
「今回は大変だったようですね」
開口一番、中村は
「もう、わたしの名前が出ているんですね」
「イジメから派生した事件には敏感ですからね。皆さん、我がことのように捉えているのですよ。その後、娘さんの容体はどうなのですか。もし看護休暇の延長が必要なら、直ちに対応しますが」
「いえ。お
順調に回復云々は強がりに過ぎない。実際は未だリハビリに移行する
中村の方も強がりだったらしく、それ以上は突っ込んだ質問をしようとしない。だが、どちらにしても愉快な話題ではなかった。
「何でも、苛められている子の盾になったがために、とばっちりを受けたとか……さすがに穂刈先生のお子さんですね。潔癖な正義感と勇気。お話を聞いて感激しましたよ。いや、わたしのみならず学校関係者は皆そう感じていると思いますよ」
聞きながら少なからず驚いた。いくら横の繫がりが強いとはいえ、そこまで詳細な情報が流れているのか。
あっと思った。
それなら当事者の家族である自分にも伝わっていない情報も、入手している可能性が高い。
「お子さんが受けた仕打ちの数々を思うと残念でなりません。そんな状態に陥っていたにも拘わらず、千住小学校では何ら具体的な指導も解決への模索もなかったというのですから。現場の怠慢が悲劇を招いたという好例です。いや、好例というのは語弊がありますね。失礼しました」
失礼と感じている素振りではなかったが、中村は気にもしていないようだ。
「改めて考えさせられます。こうした悲劇を未然に防ぐのは、やはり日頃からの指導と管理体制なのだと。公私とも大変でしょうが、これからも穂刈先生には生徒の動向に目を光らせてもらって」
「教えてください」
穂刈は続く言葉を遮る。このくらいの強引さがなければ主導権を奪えそうにない。
「その分だと、娘のイジメに加担した生徒たちの氏名も分かっているんでしょう。いったい誰と誰なんですか」
意表を衝かれたかたちの中村は口を半開きにしている。
「今まで通り、ウチの生徒にイジメが発生しないように努めます。しかし、一番身近に起きた事件をこのまま放っておく訳にはいきません」
「……お子さんからは加害者生徒について聞いていらっしゃらないのですか」
「命に別状はなかったのですが、まだ安静を強いられている状況です。精神的なショックを考えると、直截に問い質すこともできません」
中村は束の間穂刈の顔色を
「それはいけませんよ」
口調がいくぶん硬くなっていた。
「千住小学校ではその子のイジメも含め、穂刈先生のお子さんの飛び降りがイジメに起因するものであるのか、まだ結論を出していません。わたしのところに回ってきたのも言わば未確認の情報です。おそらく穂刈先生の許にも所轄の刑事さんが事情聴取にやってきたと思いますが、彼らはこの未遂事件をイジメによるものだと断定していましたか」
「いえ」
「穂刈先生もまだ被害届は出していないのでしょう。それは加害生徒を追及し始めたら、現場のみならず多くの関係者を巻き込むのを承知されているからでしょう。他でもない、イジメ問題に直面していたあなただからこそ、軽率に動いたら取り返しのつかないことになるのを知っているはずです。違いますか」
父親の立場では理不尽と思える理屈だが、教育者としての立場では反論できない。中村の言説は由佳の事件が起きるまでは、穂刈自身が信念としていたことだからだ。
被害生徒からの証言だけではなく、加害生徒からの証言と、イジメの事実を示す物的証拠。最低その三つが揃わなければ、即座にイジメと認定するのは難しい。いみじくも坂東が言ったように被害届を提出すれば警察も動いてくれるが、教育機関は例外なく警察の介入を嫌う。捜査が成果を挙げても不首尾に終わっても現場には根強い禍根が残る。端的に言ってしまうと警察の介入はどんなかたちであっても不祥事であり、教育委員会は容赦なくマイナス要因として評価する。
言うなれば教育現場にとってイジメ問題は地雷にも等しい。下手に踏むよりは慎重に撤去するか、それが不可能なら見て見ぬふりをするのはそのためだ。
「とにかく生徒一人が自殺未遂をし、ニュースでも大きく取り上げられたのです。千住小学校もこのまま放置しておくことはないでしょう」
俄には信じられなかった。学校の隠蔽体質は教員である自分が一番よく知っている。
「理性的な態度で臨んでいる限り、事態も必ず理性的に収束します。穂刈先生には
締めの言葉で穂刈は呼び出された理由をようやく理解した。
穂刈とその家族を気遣うのではない。穂刈の暴走を
「では通常業務に戻ってください」
校長室を出る際、胃の辺りが前にも増して重たく感じた。
父親と教員との
授業は予想していたよりも平穏に進んだ。朋子に鳥越、そして森山の態度は普段と
おそらく由佳の素性が知れ渡ったのは教員のレベルに留まっているのだろう。堤の一穴が開けば、後は雪崩を打ったように噂が噴出する。それは今日かもしれないし、明日かもしれない。
集中には程遠い授業だった。生徒ではなく、穂刈の側に問題がある。新単元で文章を朗読させるだけだったから事なきを得たが、作品の内容に踏み込んだら途中で
中村の厳命は教員として
だが穂刈の父親の部分が大声で異議を唱えていた。駿に
このままでいいはずがない。
放っておいたら、自分は父親でなくなる。
生徒の朗読を上の空で聞きながら、穂刈は自問自答する。
中村は自重しろと言った。
それなら、被害生徒の家族として常識の範疇で行動するなら構うまい。
教員としての立場を断ち切れないのは我ながら意気地のない話だったが、今はそれが精一杯だろう。
由佳の見舞いを理由に、その日は定時で帰路に就いた。里美とは既に連絡を取って待ち合わせの場所も決めた。これから二人で千住小学校に赴く計画だった。
由佳の件で担任の先生と相談したい。
千住小学校の学年主任を名乗る人物にその旨を告げると、先方は一も二もなく応諾した。穂刈が同じ教員であることが幸いしたのかもしれない。午後六時。大部分の生徒たちが下校した後という時間帯も考慮されたに違いない。
校舎というものは特異な事情がない限り、どこも似たような造りで似たような臭いがする。千住小学校の正面玄関を潜った穂刈は、最初にそう思った。勤め先と全く変わらぬ雰囲気は、逆に奇妙な違和感を抱かせる。
応接室で待っていると、ほどなくして由佳の担任と名乗る男が姿を現した。
「
「今回のことでは穂刈さんにご心配をおかけしてしまい、担任として非常に申し訳なく思っている次第です」
深々と下げた頭頂の一部に円形の
「児童の行動には万全の注意を払っているつもりでしたが、特別教室への移動時間ということも手伝い、このようなことになってしまいました。本当に何と申し上げればよいか」
口調は切実だったが、言葉
それは担任という立場では仕方のないところなので深く追及するつもりはない。今聞きたいのは別の話だ。
「ですから病院での無事を聞いた時には思わず安堵しました。あの高さから落下して助かるのは奇跡としか言いようがありません。これも由佳さんの日頃の行いがよかったからでしょう。彼女は本当に正義感が強くて優しい人柄ですから」
「由佳は苛められていた友だちの盾になったと聞いています」
「苛められていたと言うか、そういう風に見えた子を必死で護ろうとしたようですね」
持って回った言い方に引っ掛かる。
「由佳はそのとばっちりを食うかたちで同じ子供からイジメを受けていたと聞いています」
「そういう噂が流れているのは承知しています。今は学校も聞き取り調査を考えている最中なので、結論が出るまでもう少しお待ちください」
「それは変じゃありませんか」
穂刈よりも早く里美が口を挟んだ。
「病院でお会いした刑事さんは、由佳がイジメを受けていたと証言した生徒がいると言ってました。初めてやってきた刑事さんでも聞けた話を、担任の先生が知らないはずはありませんよね。それがまだ調査もしていないなんて」
途端に杉原は慌て出し、穂刈に助けを求めるような目を向ける。
「いや、一部生徒からそういう話が出ているというだけで……あの、穂刈さんは
「ええ」
「それならご理解いただけるかと思いますが、ひと口にクラスと言っても色んな生徒がいます。慎重な子もいれば付和雷同的な子も、また騒ぎ立てるのが好きな子もいます。こういう事件が起きた際には、得てして騒ぎ立てる子の声が大きくなる傾向があります。性急に結論を出すことは、様々な誤解を生みかねません」
「イジメはなかったと言うんですか」
里美の言葉はいつになく
「じゃあ由佳はどんな理由で飛び降りたというんですか。学校以外に原因なんてないはずです」
「イジメがなかったと断言はしていません。ただ現時点では噂ばかりが先行して、実態が摑めていないのですよ」
「杉原先生は担任じゃないんですか。毎日クラスを見ている担任だったら、イジメがあったかどうかくらい分かるものでしょう」
「それを言われると返す言葉もありませんが……いくら担任でも、生徒の交友関係や親子関係、全てを把握している訳ではないのを穂刈さんもご承知でしょう。我々には担任の仕事の他、クラブ活動の顧問や学外活動の指導をはじめとした校務の仕事もあります」
ちらちらと穂刈を盗み見ているのは同意を求めているからだろう。
「言わずもがなですが、イジメ認定には慎重にも慎重を期さなければなりません。特定の生徒を
「聞き取り、してください」
何かに火が点いたのか、里美は一向に
「生徒全員に匿名のアンケートも取ってください。それだけやればイジメがあったかどうかすぐ分かります」
「しかし肝心の由佳さんからイジメの話が出ましたか」
「それは」
「嫌な話ですが彼女は飛び降りる際に遺書らしきものも残していません。つまり被害生徒と目される由佳さん自身が被害を訴えていないのですよ」
「自尊心が強過ぎるからです。自分がイジメに遭ったのが情けなくて、恥ずかしいから口にできないんです。それはあの子の性格を知っている先生なら察しがつくでしょうに」
「察しがつく、だけでは犯人捜しができないんですよ。不用意なひと言や
「杉原先生が逃げているだけじゃないんですか」
自らも教員経験のある里美だったが、容赦はない。穂刈は呆れ半分称賛半分で様子を見守る。これだけ明け透けに、自分の子供を最優先にできるのが母親だ。疎んじられ、
「イジメが認定されたら問題が表面化し、更に裁判にでも発展したら学校と杉原先生の評価は落ちます。慎重にも慎重をと
「それはちょっと、あんまりな言い方です」
杉原は
「保身のためにイジメの事実を隠すつもりは毛頭ありません。ただ、他の生徒に無用な苦痛を与えたくないだけです」
聞いているうちに、腹の底で点いていた火が燃え上がった。
「それでは由佳が受けたのは当然の報いだと仰るのですか」
「いや、穂刈さん。そんなことを言っているのではありません。あなたも教員なら分かっていただけるでしょう」
口調に哀願が混じっていた。
「事は非常にデリケートです。イジメに加担した生徒とその家族に留まらず、多くの関係者の人生に影を落としかねない」
「だからウチの娘は
杉原の声に軟弱さを聞き取ったのか、里美の声はますます鋭くなる。
「そんな、蔑ろにするだなんて。現に生徒に対する聞き取り調査は職員会議で議題に上がっています。我々は決してこの問題を棚上げにすることなくですね」
「議題に上がっている? それってつまり、まだ実施もされてないってことですよね。事件が起きたのは、もう四日も前のことなんですよ。それなのに基本的な調査さえできていないなんて怠慢にもほどがあります」
「怠慢というのは心外です。聞き取り調査にしてもアンケートにしても、いち担任が軽率にできることじゃありません。職員会議に諮って意思統一をし、学校側の判断として実施しなければ意味のないことで」
逃げているだけだ、と穂刈は判断した。それらしい理屈を並べているが、杉原の言葉からは憤りも失意も感じられない。
怒りが胸元にまでせり上がってくる。今口を開けば、自分も罵倒じみた言葉を吐いてしまう予感がする。
その時、不意に杉原の左手を見た。
薬指に食い込んだ指輪。
この男も家族を背負っている。
そう思った瞬間、わずかに気が
「あなたは担任なのに、生徒一人の悩みも受け止めることができないんですか」
「担任だからこそなんですよ、お母さん。担任だからクラス全員の気持ちや影響を考えなくてはなりません。誰か一人だけを重視しろというのは無理です」
「分かりました、もう杉原先生には頼りません」
里美は相手を
「警察に被害届を出します」
「それは考え直してくれませんか。さっきも申し上げた通り、事が変に大きくなれば有形無形の損害をこうむる人間が出てきます。わたしのクラスでも疑心暗鬼に陥る子供が出てくるでしょう。また、仮に警察の捜査が入ったとしても学校側の意思統一がされないままでは、碌に捜査協力もできません。結果的にイジメが立証されようとされまいと、由佳さんは学校に居づらくなります。それでもいいんですか」
後の言葉は脅し文句に近かった。
教職にある者が脅し文句に頼らなければならないほど追い詰められているのだ。杉原の言葉は全くの噓ではない。このまま穂刈たちが被害届を出せば、学校側もおいそれとは捜査に協力しないだろう。これが死亡事故ならともかく、目下のところは自殺未遂だから警察の矛先も鈍る。
相手の態度を硬化させてはいけない。後々のことを考えれば、ここは可能な限り情報収集に努めるところだ。
穂刈は身を乗り出しかけている里美を片手で制した。
「杉原先生、あなたの仰ることは理解できました。しかし到底納得はできない。納得するには最低限教えていただきたいことがあります」
「何でしょうか」
「噂の範疇で構いません。由佳のイジメに加担したという生徒が誰と誰なのかを教えてください」
聞き終わるのを待たずに杉原は首を横に振る。
「まだ当方で調査中です。根も葉もない噂を当事者にお伝えすることはできません」
「一人だけでも名前を」
「本当に、勘弁してください」
杉原はテーブルに額がつくほど頭を下げた。その姿はひどく哀れで、穂刈は自分が加害者になったような錯覚に陥った。
被害者と加害者がころころと入れ替わる。その度に穂刈の立ち位置も変わってくる。その目まぐるしさに
杉原は平身低頭したまま微動だにしない。
里美は言葉を忘れたように、円形脱毛症の頭に目を落としていた。
結局、学校側からは何一つとして情報を引き出すことができなかった。穂刈たちは敗北感に打ちひしがれて正面玄関に戻ってきた。気落ちした分、来た時よりも足が重い。はらわたは煮えくり返っているのに、思考だけが
嫌な傾向だと思った。悪感情が
悔しい、と横で里美が洩らした。
「何やかんや言って、学校は泥を被るまいとしているだけじゃない」
今更な話だ。里美もかつては教員だった。それなら学校という組織の体質を知悉しているはずだ。いや、知悉しているからこそ頭を下げ続ける杉原を見て、何も言えなくなったのだろう。
「あのう……」
背後でか細い声が聞こえた。
振り返ると、そこに少女が立ち尽くしていた。背の低い女の子だった。
「由佳ちゃんのお父さんとお母さんですか」
怯えた口調で尋ねてくる。
「君は誰ですか」
「由佳ちゃんと同じ二組で、
そう名乗ってから、こちらに近づいてくる。おどおどした態度を見て、ぴんときた。
「ひょっとして、由佳が庇ったというのは」
「はい、わたしです」
夏菜は二人の前まで来ると、いきなり頭を下げた。
「ごめんなさい。わたしのせいで、由佳ちゃんがあんなことになって。ごめんなさい。ごめんなさい」
同じ頭を下げられるのでも、こちらの方が数段胸に
「あなたは謝らなくていい」
「でも、わたしが弱かったせいで由佳ちゃんは」
「あなたが強い子でイジメに遭わなかったとしても、由佳は別のイジメに遭っていた子を護ろうとしたと思う。だからあなたのせいじゃないわ」
「由佳ちゃんは……大丈夫なんですか」
「まだベッドから起きるのは無理だけど大丈夫。必ずよくなって学校に戻ってくるから、その時はまた仲良くしてやってね」
「仲良くしてもらうのは、わたしの方です」
夏菜は目に涙を
「前は、そんなに話す仲じゃなかったんです。でもイジメが始まってからは、いつもわたしの前に立ってくれて……何度も助けてくれました。普段は優しいのに、その時だけは怖いくらいに相手と闘ってくれたんです」
目が覚める思いだった。
いったい自分は由佳の何を知った気でいたのだろう。
穂刈の知る由佳はいつも太平楽な顔をしている平凡な娘だった。この世には正義も悪も存在せず、だから自分も争いごとには無関係なのだと決めてかかっているように見えた。
だが実際は違っていた。
世界ではなく、もっと身近にある悪意に刃向かい、自分よりも弱い立場の人間に手を差し伸べる
まだ小学生なのに。
まだ十二歳なのに。
「教えてくれてありがとうね、夏菜ちゃん」
里美は相手と同じ目線になるように腰を落とす。子供と親しくする際の基本だ。
だが、穂刈は里美の視線に
「由佳のこと、大切に思ってくれてたのね」
「はい」
「だったら教えて。クラスで由佳を苛めてた子は何ていうの」
夏菜の表情が不安に染まる。しかし里美は追撃をやめようとしない。
「担任の杉原先生に訊いても教えてくれなかった。ねっ、絶対あなたから聞いたのは秘密にする。だから教えて。お願い」
里美の切羽詰まった熱意に押されたのか、あるいは
しかしやがて苦いものを吞み込むような顔で唇を開いた。
「何人かの取り巻きみたいな子がいたけど……中心になっていたのは、同じクラスの
二 棘のある葉
1
穂刈と里美は夏菜を喫茶店に誘い、改めてイジメの話を聞いた。もし夏菜の作り話だったのなら、また新たな火種になりかねない。慎重の上にも慎重を期したい穂刈の気持ちだった。
「彩ちゃんも、その仲間も普通の子で、どこが特別ってことじゃないんです」
夏菜は出されたイチゴパフェを一度
「今のクラスになった時は何もなかったんですけど、わたしのウチが母子家庭で生活保護を受けているのが、お母さん同士の話から
その時の状況を思い出したのか、夏菜の口が不意に重くなる。聞いている穂刈の方も
「それで由佳ちゃんがわたしを
夏菜はいったん言葉を切り、許しを
穂刈は浅く
「本当だったら、今度はわたしが由佳ちゃんを
後は聞かなくても分かる。夏菜は由佳の陰に隠れたまま、顔を出そうとしなかったのだ。一度イジメの被害に遭った少女の気持ちは痛いほど理解できる。その盾になったのが我が子だというフィルターを通しても、穂刈は夏菜を責める気になれない。
「由佳は、それで君に恨み言の一つでも言ったのかい」
「いいえ」
「だったら気に病むことはないよ。由佳は君を護るために立ち上がった。改めて君を矢面に立たせようとはしなかったと思う」
「すみません……すみません」
夏菜は何度も小さな頭を下げ続けた。
「由佳ちゃん、どんなに苛められても泣いたり謝ったりしませんでした。自分が絶対に正しいのに、何で謝らなきゃいけないんだって。それでますます彩ちゃんたちのイジメがエスカレートして」
穂刈は聞きながら
誇らしい気持ちとともに切なさが募る。己の正義を胸に孤軍奮闘している由佳に、少しも気づいてやれなかった。教師であり父である自分が、何の手も差し伸べてやれなかった。
「あの日、教室の窓から飛び降りた日も、由佳ちゃんは普段通りでした。だから、飛び降りたと聞いた時はびっくりして、怖くなって、自分が情けなくなって……強がっていたけど、やっぱり由佳ちゃんも限界だったんだなあって。わたし、助けられたのに全然知りませんでした。勝手に、由佳ちゃんはどんな仕打ちにも負けない強い子だって決めつけていました。でも、違ったんです」
再び夏菜は声を震わせながら泣き出す。
「由佳ちゃんも、わたしと同じだったんです。
「こうなったら直接、向こうの家に抗議しましょうよ」
帰宅するなり里美が提案してきた。
「犯人の名前が分かったのなら、親の名前も住所も分かるでしょ。二人で乗り込んでやりましょう」
「児童名簿は非開示のはずだぞ」
穂刈は思わず
こうした問題で当事者の親同士が接触しても
彩という子を問い詰めたい。その親に向かってどんな教育をしているのだと責め立ててやりたい──胸の底から
「児童名簿は担任が作成しているが部外秘で、セキュリティがしっかりしているなら洩れることはない」
「連絡ルートや何やらで母親の名前や大まかな住所くらいは分かるのよ。母親同士の情報網を甘く見ないで」
「少しは落ち着けよ。そんなことをしたら騒ぎがますます大きくなって……」
「そうよ。騒ぎが大きくなって、学校側はだんまりを決め込んでいられなくなる。どうしてそれが悪いの」
里美は矢庭に突っかかってくる。
「あなたは腹が立たないの? 自分の娘が苛められた挙句に自殺未遂をしたのよ。相手の子供や親に何も感じないの」
「そりゃ感じるさ。憎いとも思っている。しかし、今こっちにあるのは夏菜ちゃんの証言だけだ」
「あの子が信じられないっていうの」
「信じない訳じゃないが、それだけじゃ相手を特定するには根拠が足りない。アンケートを実施し、複数の児童が大輪彩という子を指す。そして本人とそのグループがイジメの事実を認める。そうして、やっと双方が話し合いのテーブルに着くことができる」
「話し合い。話し合ってどうなるのよ。それで由佳の傷が
こちらを
「ただ向こうの家に怒鳴り込んで抗議するだけじゃ、何も解決しやしない」
「どうして解決なんてさせなきゃいけないのよ」
言葉がどんどん
「ウチは被害者側なのよ。学校やクラスが丸く収まるかどうかの前に、由佳がどうなるのか、由佳の自殺未遂の責任を誰がどう取るのかが先決でしょう。この際はっきり言うけど、今度の件で千住小学校や担任の杉原先生が世間から非難されるのは当然じゃない。相手の彩という女の子も他人から石を投げられればいい」
「それじゃあ、ただの腹いせだ」
「腹いせのどこが悪いのよ。娘をあんな目に遭わされて、腹いせを考えない方がどうかしているのよ」
胸倉に
「わたしは由佳を追い詰めた人間に仕返ししてやりたい。でも、あなたはどうなのよ。まだ教職がどうとか世間体がどうとか
突然振られた二者択一に、心臓を
いい加減にしろ。
「とにかく加害者側の主犯が分かったんだ。これで千住小学校も知らぬ存ぜぬを通せなくなる。こちらの要求が通りやすくなったんだから、正攻法で学校側に解決を求めよう」
「あなたは、まだそんな
「イジメなんて卑劣なやり方で被害を受けたのなら、こっちは卑劣じゃなく正々堂々とした方法で訴える。それが一番理想的だと思わないか」
「それはわたしに
「由佳は、まだ碌に話もできない状態じゃないか」
「わざわざ話さないと、あの子の気持ちも分からないの」
そう言って、里美は唇の端を
まるで自分の妻とは別人のように思えてきた。
翌夕、穂刈は単独で千住小学校を訪ねた。里美を家に置いてきたのは、言うまでもなく
昨晩のやり取りから、杉原の対応は予想できた。だから単刀直入に話を切り出す。大輪彩の名前を出すと、杉原の表情が一変した。その様子から察するに、夏菜の証言はやはり真実だったらしい。
「誰から彼女の名前を訊き出したんですか」
「そういう言い方をされるからには
さすがに腹に据えかねたので、皮肉の一つも返したくなる。
「そんな、箝口令だなんて……わたしたちは、まだ事実認定されていないことが風評被害にならないよう、慎重を期しただけです。学校ではっきりしていないことは口外してはならないと」
「年端もいかない子供たちを自由に
杉原はきまり悪そうに視線を
「噂ばかりで調査が進んでいないというのも、どうやら真実ではなかったようですね。担任のあなたは、ちゃんと主犯格が誰であるかを承知していた」
穂刈が見据えても、杉原は視線を逸らしたままでいる。
「先生は調査が
「もちろん、児童とそのご家族です」
「しかし、イジメの加害者はほぼ特定できていたのでしょう。だったら今更、損害をこうむるも何もない。ただやったことの償いを求められるだけだ。それは損害とは言わない。ただの罰ではありませんか」
「でも相手はまだ十二歳の小学生なんですよ」
「ウチの由佳も十二歳の小学生です。そしてイジメを受けた被害者です。杉原先生、わたしもあなたと同じ教員です。だからあなたが悩んでいることにも大方の見当はついている。あなたが心を砕いている関係者というのは、千住小学校の先生たち、
イジメの存在を学校側が
「正直、ウチの中学にもイジメらしき話はありますよ。だから先生の置かれた立場も理解できますし、言いたくても言えないことだって知っています。先生が守っているのはこの学校の体面でしょう。この学校にイジメなど存在していなかった。仮にあったとしても、由佳の自殺未遂の原因ではなかった……それが学校関係者の希望する着地点なのでしょう」
「そういう言い方をされては身も蓋もありませんけど……そうですね、決して間違ってはいらっしゃいません」
杉原は面目なさそうに目を伏せる。
「校長先生か教頭先生か……そういう圧力があったんですか」
「穂刈さんも同じ教員でしたらご推察いただけるでしょう。誰かからの明白な威迫や強制があった訳ではありません。何というかつまり、空気みたいなものです」
「本当にひどい言い方になりますが……娘さんの自殺が未遂に終わって感謝しているんです。万が一亡くなりでもされたら、それこそ警察も黙ってはいられないし、学校側も態度をはっきりさせなければなりませんでした」
申し訳ないという意思表示なのだろうか、杉原は
「杉原先生、あなたの立場や気持ちは分かりますが、あなたとわたしには決定的な違いがあります」
「何でしょうか」
「わたしはあの子の父親なんですよ。教員である以前に」
すると、ようやく杉原はこちらを見た。ひどく恨みがましい目だった。
「あなたがわたしの立場だったら、この問題をうやむやにできますか」
「わたしにはまだ子供がいなくて……仮定の話には答えられません」
答えられないのではなく、答えたくないのだろう。
「少なくともわたしにはできません。杉原先生、わたしが警察に被害届を出す前に、大輪彩ちゃんたちの処分を決めてください。イジメの原因追及だとか再発防止の手立てを協議する前に、今回の後始末を学校自らが行ってください」
穂刈にすれば、それが最後
だが口にした時、穂刈は罪悪感を覚えずにはいられなかった。目の前の杉原にもどことなく申し訳ない気がする。
我ながら厄介な性分だと思った。教員としての体面を口にしている時は、父親が顔を
「勘弁してください」
杉原は深く頭を下げる。頭頂部の
「現状、特定の児童を
「もう、事実は事実として受け止めてください。千住小学校や大輪彩という子の親御さんがなかったことにしたくても、現に由佳は心身ともに傷ついてベッドに
「しかし穂刈さん。穂刈さんは当然のことながら被害者としての権利を主張されますが、問題を大きくすればするほど、矢は娘さんにも飛んでくるのですよ」
杉原は
「イジメがあったと認定されれば、被害を受けた子も今まで以上に衆目に
前回の脅し文句の再現だった。
覚悟を決めてきたはずなのに、由佳の処遇を持ち出されるとやはり決心が鈍る。最悪の場合は転校させることも視野に入れなければならないが、由佳本人がそれを良しとするかどうかも問題だった。
結局この日も杉原からは明確な返事を引き出すことができず、穂刈は
家に戻ると里美の姿が見当たらなかった。がらんとした家で誰かいないかと声を掛けると、駿が部屋から出てきた。
「母さんはどうした」
「知らない。俺が帰ってきた時は誰もいなかった」
「由佳の見舞いにでも行ったのか」
「聞いてない」
もう午後七時を回っている。家族に連絡も入れないで、いったいどこをほっつき歩いているのか。
こちらから連絡を取ろうとスマートフォンを取り出した時だった。
居間の固定電話が久しぶりに着信を告げた。穂刈家は家族四人ともスマートフォンを持っているため、固定電話が鳴ることは滅多になかった。
勧誘や縁起の悪い知らせ以外は。
「はい。穂刈です」
『夜分に恐れ入ります。千住警察署
警察署という響きが不安を倍増させる。
『奥さんは穂刈里美さんですよね』
「それが何か」
『大橋交番で保護しております』
すぐには事情が
「どうしてウチの家内がそちらに保護されているんですか」
『ええっとですね……実は町内のあるお宅と口論になったようで』
不安がゆっくりと明確なかたちになっていく。
「どなたのお宅で
『大輪さんという方です』
その名前で不安の正体に気がついた。
「今からそちらへ行きます」
『よろしくお願いします』
駿に留守を頼み、穂刈は大橋交番へと急ぐ。駿に余計な心配をかけたくなかったので、行き先も目的も告げずに出た。
電話では詳しいことを教えてくれなかったが、里美の行動には大方の見当がついている。おそらく穂刈が千住小学校で杉原と面会している時、里美は単身大輪家に乗り込んだに違いない。何を勝手に、と思ったものの、よくよく考えてみれば昨夜からの言動が普段と違っていた。注意すべきは千住小学校の出方ではなく、里美の精神状態だったのかもしれない。
交番では特に拘束されるでもなく、里美がパイプ椅子に座らされていた。
「ああ、お待ちしていました」
対応した
「家内がどうもご迷惑をおかけしまして」
未だ怒りが収まらない様子の里美を
「いや、一応通報があったので駆けつけたのですが、調書を取るような事案でもないので」
磯村巡査は机の上にあるバインダーを取り上げてみせる。〈事案対応記録〉とタイトルが付されており、A4サイズの紙が
「いったい、何をやらかしたんだ」
「被害者家族として当然の権利を主張したまでよ」
里美は悪びれる様子もなく言い放つ。すると
交番に通報があったのが午後六時を少し過ぎた頃というから、やはり穂刈がちょうど杉原と話している時だ。通報者は近隣に居住する大輪
「大輪さんのお宅は住宅街の一角にあるんですが、この方が家の前で大きな声を出して迷惑をしている、と。ただの口論ならともかく、近所に迷惑がかかっているとなれば放置はできませんので」
現場に駆けつけたところ、閉ざされたドアに向かって里美が大声を浴びせていた。その内容は「本人を出しなさい」とか「あなたはイジメを助長するのか」といったもので、これを住宅街の真ん中で叫ぶのは確かに迷惑であり、下手をすれば侮辱罪にも発展する可能性もある──磯村巡査はそう判断し、事件発生以前の対処として里美の身柄を保護したのだと言う。従って里美に対しては注意だけに
「お話を聞けばイジメで自殺未遂をした娘さんがおられるとか。現状では警察より学校や親御さんの間で解決する問題でしょう」
口にはしないものの、穂刈に気を遣ってくれているのが分かる。穂刈は素直に感謝したくなった。
「もう、こんな真似はさせませんから」
磯村巡査に礼を言い、里美を伴って交番を出た。自宅まで歩けない距離ではなかったが、どうにも里美を衆目に晒すのは気が引けてタクシーを拾う。
「どうして俺に黙って、こんなことをしたんだ」
「相談したところで、パパはどうせ賛成してくれないでしょ。それにパパは杉原先生のところへ
「どういう理屈だ」
「二人で一カ所を攻めるより、二人で二カ所を責めた方が効率的じゃない」
「確たる証拠もなしに抗議したって軽くあしらわれるだけだ。現に巡査の話じゃ、門前払いみたいな扱いだったんだろ」
「門前払いじゃなかったわよ」
悔し紛れの口調だった。
「最初に穂刈由佳の母親だと名乗ったらドアは開けてくれたのよ」
「家の中に入ったのか」
「ううん。玄関口で、あなたの娘がイジメの主犯格だと話し出した頃から、出ていってくれって言われた。まだひと言も謝罪されてないのよ。おめおめ帰れるはずないじゃない。向こうは知らぬ存ぜぬを通そうとするし、挙句の果てにはでっち上げだとか言い出すし」
「それで口論になったのか」
性急に過ぎると思った。百歩譲って相手を責めるにしても、客観的な証言を集めて外堀を埋めてからでなければ、易々と逃げられてしまう。
「証言はちゃんと夏菜ちゃんがしてくれたじゃない」
「彼女一人では
これは穂刈の方が道理が通っているからか、里美は口を
「大輪さんというのはどんなだった」
「家が? それとも奥さんが?」
「両方」
「いたって普通よ。家は二階建てで結構古かった。あれは親の代からの建物ね。大してお金持ちでもなければ、貧困家庭にも見えない。奥さんも普通。十人並みの容姿で
「イジメの加害児童が育つ家庭に見えたか」
「ほんの十分か十五分話しただけよ。そんなこと分からないわ」
「元小学校教師でもそれは無理か」
「少なくとも子供を虐待するような母親には見えなかったけど、そんなこと関係ない」
里美はぼそりと
「大輪さんの家庭の事情なんてどうでもいい。彩って子がどんな風に育ったのかもどうでもいい。とにかく由佳をあんな風にした償いをしてもらわなきゃ、由佳があんまり可哀想過ぎる」
里美の様子をじっと見ていて、ようやく違和感の正体に気づいた。
職業的倫理も体面も全てを放棄した純粋な母性。我が子のためなら他人の家庭や子供など一顧だにしない凶暴さ。自分はまだ教師と父親の間を行ったり来たりしているのに、里美はとうの昔に母親として臨戦態勢に入っている。その温度差が二人の間に不協和音を生じさせているのだ。
「お前の気持ちは分かったから、今後は勝手な行動を慎んでくれ。必ず俺に相談してくれ」
「相談したら、ちゃんと話を進めてくれる?」
挑発するような物言いだった。
「パパは杉原先生のところに行ったんでしょ。アンケートを実施するとか、学校側で調査して結論を出すとかの話になったの」
「いや」
事を荒立てれば、結局は由佳もまた傷つくと
「どうして、そんなに簡単に丸め込まれるのよ。学校側の思うつぼじゃないの」
「しかしな、由佳が今以上に追い詰められる可能性があるというのは本当だぞ」
「だからって泣き寝入りしろって言うの」
「そんなことは言ってないだろう」
「由佳が追い詰められないように護ってやればいいじゃないの。それが家族の役目でしょ」
里美の挑発は止まらない。
「被害を受けたのはウチなのにこのままわたしたちが何もせずにいたら、それこそ由佳の将来に影響が出る。被害者意識に凝り固まって、いつまでもいつまでも今度のことを引き
里美は
目から
挑発は挑発でも、穂刈に対してのものではなかった。里美は己を奮起させた上で戦端を開こうとしている。
「パパ。もう、真剣に被害届を出すこと、考えて」
臨戦態勢にある里美には、警察の捜査を入れて徹底究明させるのは至極当然の成り行きに違いない。顔つきからも口調からも、それによって由佳と穂刈家が受けるであろう次の被害への覚悟が
杉原の態度は相変わらず逃げに終始した。いや、わざとやる気のなさを見せて、穂刈の怒りに冷水を浴びせようとしたのかもしれない。
里美の怒りの
家に帰ると、駿が二人を待っていた。
「いったい、どこで何していたんだよ」
自分だけが
「相手の家に殴り込みかよ」
話を聞いた駿は
「まあ、家ん中でめそめそしているよりは、よっぽどマシか」
「わたしたちがどうとかじゃなくて、由佳をどうやって立ち直らせるかが問題なのよ。駿はどうなの。被害届を出すことに賛成してくれる?」
しばらく駿は考え込んでいる風だったが、珍しく言葉を選ぶように話し始めた。
「由佳がイジメに遭ったことを小学校の希望通り隠しておく手はないと思う。だけど警察を介入させるのもどうかと思う」
「どうしてよ」
「ウチの中学がそうなんだけど、先生っていうのは同じ公務員のくせして警察官が校内に入ってくるのを嫌うよな。去年だったか、学校が荒らされた時に刑事とかやってきたんだけど、教頭も担任もすっごく嫌な顔してた。何か、自分の庭に入られた、みたいな。親父さ、実際学校にはそういうのってあるのか」
話を振られて一瞬穂刈は返事に窮するが、ここは教師の立場を離れるべきだろう。
「学校というのは、どこも警察権力の介入に不安を抱いているだろうな。戦前戦中の学校教育が軍国主義に染まったことへの反動もあるだろうし、学校自治の観点からどうしても警察は敬遠されやすいし……」
駿は見下したように言う。
「校内に警察が踏み込んでくるのは、どうしたって不祥事なんだから、学校側はいい顔しないんだろ」
「そういう言い方をするもんじゃない」
「どんな言い方しても一緒だよ。今は学校の体面よりは由佳を護ることが先決なんだろ。その辺を踏まえて考えるとさ、被害届を出して警察
全ての教師が人格者という訳でもなく、全ての教師が公正中立という訳でもない。校内に警察を入れた張本人として由佳を恨む教員などいないと、穂刈には断言できない。
駿の提示した懸念には、里美も興味を示したらしい。
「親父は慎重過ぎるし、オフクロは軽率なんだよ。二人とも極端だ」
「じゃあ、どうすればいいって言うのよ、駿は」
「オフクロが向こうの家へ怒鳴り込んだことで、何かあるんじゃないかな。少なくとも向こうの家では自衛手段として何かしら考えるだろうしさ」
「それで事態が動くと思うの」
「そこまで読めないよ」
駿はあっさりと手を上げる。
「理想的なのはさ、警察の力を借りずに事件が大ごとになってくれることなんだよ。そうすれば世間に知られたのは不可抗力ってことになって、学校側も嫌々ながら犯人捜しに乗り出すだろうし、由佳が逆恨みされることもない」
「……お前、ずいぶん冷静じゃないか」
穂刈が感心して言うと、駿は
「冷静になろうと思ったからだよ。こういう時は頭に血が上ったヤツが不利になる。由佳をあんな目に遭わせたヤツを懲らしめるのなら、じっくり考えないと」
駿の言葉を
慎重に過ぎる父親。
血気に
冷静なようでいて、その実一番執念深い兄。
まとまりもなく、ばらばらな対応をしているが、しかし三人とも由佳を最優先に考えていることだけは確かだった。
2
大輪家に直談判したことがどれほどの波紋をもたらしたのか、残念ながら穂刈には知る由もなかった。里美のママ友から情報を得られたらいいのだが、由佳の自殺未遂以降は誰からも距離を置かれているらしく、千住小学校の様子を窺う
美田園病院には里美が毎日のように通っており、穂刈も一日おきにだが同行している。手術した由佳の内臓は順調に回復しており、若さのお
だが、治りが早いのは身体だけで、精神の方は未だ事故直後から一進一退を続けていた。二人が見舞いに行っても顔を背けるだけで、碌に返事もしない。
「恥ずかしがらなくてもいいのよ」
何とか閉ざされた扉を開けようと、里美は思いつく限りの言葉を尽くそうとしているようだった。
「いつでもどこでも強い人間なんているはずないんだもの。第一何で被害者の由佳がそんな風に怯えてなきゃいけないのよ」
いくら元小学校教師だったといっても、やはり長きに
それなら自分は父親らしい開け方をするまでだ。
「やったのは大輪彩という子か」
毛布に包まれた肩がびくりと大きく上下した。
「娘に理不尽なことをされて、俺たち両親が黙っている訳にはいかない。俺もママも駿も怒っている。絶対にこのままでは済まさない。必ずまた由佳が笑って通学できるようにする。だから由佳はこれ以上
言葉は続かなかった。話が終わる前に由佳は布団に潜りこみ、聞くことさえ拒否する素振りを見せたからだ。
この程度で
「今、学校を通して向こうにも抗議している。誰が悪かったのか、誰が見逃していたのかをはっきりさせる。学校がダメなら、警察に被害届を出すことも検討している」
「やめて」
滅多に聞くことのできない返事。しかし、それは尖って穂刈の胸を刺す。
「放っておいて」
「放ってなんておけるか」
「二人とも出てって」
声に力はない。しかし言葉に拒絶の力があった。
娘が自殺未遂に追い込まれるまで何も知らなかった教育者且つ父親。その無様さに気づきもせず、今もまた娘から拒絶されている。
「また来るから」
そう残し、里美とともに病室を出た。
「今日も詳しい話は聞けずじまい、か」
無力感に
そう考えると、里美が好戦的になっている理由も察しがつくような気がする。自分が無力だと知った人間の反応は大きく分けて二つある。自分の不甲斐なさを認めて殻に閉じ
里美は紛れもなく後者なのだろう。母親だというのに娘の力になってやれない惨めさ口惜しさを、イジメ加害者に向けている。
「ねえ、知ってる?」
「何を」
「駿も毎日見舞いに来ているのよ」
初耳だった。
「だってあいつ、いつも同じ時間に帰ってきているじゃないか」
「学校が終わると病院に直行して、十分か十五分いたかと思うとすぐ帰っちゃうんだって。看護師さんから教えてもらった」
「何で俺たちに黙ってるんだ」
「訊かれれば答えた、とか言いそうね」
駿が妹思いであるのは承知している。それを照れて隠していることもだ。だから穂刈や里美が訊かない限りは素直に答えないのは理解できる。
「由佳、駿相手には結構話すみたい」
「今の、由佳がか」
「これも看護師さんから聞いたんだけど、その十分か十五分の間は病室から話し声が聞こえるって……」
「親や教師に相談できないことも、兄弟には言えるらしいからな。きっと、そういうものなんだろう」
穂刈自身は一人っ子だったので、兄弟の何たるかも知らずに育った。だから駿と由佳の間にある
「お前、弟がいるから分かるだろ、そういうの」
「
「そういうものなのかな」
いつしか二人は病院から出ていた。これからまた駿を交えて
そろそろ職場からは平常運転に戻ってほしいという圧力を感じている。由佳が入院してからはずっと定時に帰宅しているので雑務も
明日は以前のように残業しようか──そんなことを考えていると背後から穂刈さん、と声を掛けられた。
振り返ると、そこに男が立っていた。どこか軽薄そうな、それでいて油断のならない目をした男だった。
「失礼しました。わたし、こういう者です」
唐突に差し出された名刺には〈帝都テレビ アフタヌーンJAPAN
「帝都テレビの〈アフタヌーンJAPAN〉……記者の方ですか」
「記者ではなくてADなんですが、まあ何でも屋みたいなものですからそれもありでしょうね」
「わたしたちに何のご用ですか」
「由佳さんが自殺未遂に至った件についてお伺いしたくて」
途端に里美が顔色を変えた。
「どうしてそんなことをテレビ局が知ってるんですか。まだ警察沙汰にもなっていないのに」
「そう。そこなんですよ」
兵頭は目を輝かせる。
「この話は警察沙汰どころか、学校関係者の間でも箝口令が敷かれているそうですね。お二人はそれでよろしいんですか。娘さんがイジメに遭っていた事実を、このまま闇に葬っていいとお考えですか」
兵頭の目に不穏なものを感じ取った穂刈は無視しようと片足を踏み出す。ところが里美はその場を動こうとしなかった。
「どうやら奥さまはわたしの提案にお耳を傾けてくれそうな雰囲気ですね」
「早合点しないでください」
里美は警戒心を隠そうともしない。
「由佳の事件を面白おかしく扱うつもりなら……」
「とんでもない。イジメは面白おかしく扱うような題材ではないと、わたしは考えています。古くて新しい問題です」
「でも、結局はニュースのネタにして消費するんでしょ」
「それはお二人からどんな情報が得られるかによります。それに、お二人がわたしどもをネタにして利用するという役立て方もあるのですよ」
兵頭は意味ありげに笑ってみせる。
「行くぞ」
里美の手を引っ張る。
ところが里美は動かなかった。
「まあ、話だけでも聞いてもらえませんか。それならこうむる迷惑も受ける被害もないでしょう」
碌でもない話なら、時間を費やすこと自体が迷惑だ。だが里美はそう思っていないらしい。
兵頭は、笑みを顔に貼りつけたまま恭しく手を伸ばした。
「立ち話も何ですから、ゆっくりできる場所に河岸を変えませんか」
兵頭に連れていかれたのは、表から二本奥に入った通りにひっそりと
「最初にネタばらしをしますとね。ウチのスタッフの中に、子供を千住小学校に通わせているのがいたんですよ。それで穂刈由佳さんの名前と自殺未遂の件を知った訳で」
そういう事情なら納得がいく。学校関係者に敷かれた箝口令にも思わぬ穴があったということだ。
「ただ学校側の情報管理が厳しくて、被害者となった由佳さんの名前は出てきても加害者グループの名前が出てこない。もちろん実名報道をするつもりはありませんが、せめて名前だけでも分からないと調査するにしても
「それでわたしたちから訊き出そうという訳ですか」
「ええ。率直に申し上げれば」
油断のならなそうな相手なので、穂刈は里美を横に押し退けて応対する。少しでも
「わたしの職業をご承知の上でそう仰っているんですか」
「中学校の先生をしておられるそうですね。しかしご自身の娘さんが自殺を図ったとなれば教師も何もない。純然と父親の立場を主張するべきじゃありませんか」
第三者だから、そんな風に割り切った考え方ができるんだ──反論しようとしたが、隣に座る里美がしきりに頷くのでそれもできない。
「我が〈アフタヌーンJAPAN〉では今回の事件を社会の歪みというだけではなく、学校の事なかれ主義という側面から追及する方針です」
「わたしたちが帝都テレビさんを利用するという話は、何のことですか」
「箝口令が敷かれているということは、責任追及や損害賠償の件が迅速には進んでいないことを意味します。当然、被害者側である穂刈さんたちには大いに不満がある。違いますか」
兵頭は反応を
「センシティヴな話なので学校名や関係した児童の氏名などは匿名になるでしょう。学校の遠景もはっきりとは映せない。しかし子息を通わせている保護者や近隣住民なら、一部を見ただけで千住小学校だと分かる。それだけでも学校関係者には結構なプレッシャーになりますよ。〈アフタヌーンJAPAN〉は高視聴率のニュース番組です。一度取り上げれば、どこの学校が舞台になったんだとネットでの特定作業が始まります。まあ、学校名が明らかになるのは時間の問題でしょう。そうなれば次に週刊誌が食いついてきます。次第に箝口令は有名無実のものとなり、穂刈さんたちは交渉のテーブルに着けると、そういう青写真を描いているんですけどね」
「そんなに
「経験則ですね。穂刈さんもそうだから非常に言い
悔しいかな兵頭の言葉には頷かざるを得ない。普段からお堅い職業やら聖職者やらと持ち上げられている分だけ、不祥事や醜聞に弱い。毅然とした態度で臨む以前に、つい隠蔽しようとする。事なかれ主義ということもあるが、リスクマネジメント能力が根本から欠如しているから、まず逃げようとしてしまうのだ。
「わたしに加害児童の名前を告げたところで公表はできない。しかしニュースが起爆剤になれば必ず関係者以外の者にも広まります。向こうの親御さんもいつまでも無視を決め込むことができなくなる。解決しなければ自分たちがどんどん窮地に追いやられるからです」
「それがあなたたちの正義という訳ですか」
まさか、と兵頭は首を横に振る。
「わたしたちの正義は隠された事実を白日の下に晒すことです。その後の方向性は世論に任せますよ」
お世辞にも兵頭は好人物といいかねる。口にしていることもどこまでが真意か判然としない。普段の穂刈なら、目の前に置かれたコーヒーに口もつけずに席を立つところだ。
だが、この時は駿の言葉が脳裏にあった。
『理想的なのはさ、警察の力を借りずに事件が大ごとになってくれることなんだよ。そうすれば世間に知られたのは不可抗力ってことになって、学校側も嫌々ながら犯人捜しに乗り出すだろうし、由佳が逆恨みされることもない』
何ということだ。理想的な展開が向こうからやってきたではないか。
「さあ、教えてください。由佳さんを自殺未遂に追い込んだ加害児童は何という名前なんですか」
しかしそれでも尚、穂刈は
その時、里美が
次の穂刈の言葉は
「大輪……大輪彩という子です」
3
兵頭の話では、たとえ加害児童の氏名が判明したとしても実名報道は一切されないので心配いらないという。
「BPO(放送倫理・番組向上機構)との兼ね合いがありますので、尖った報道姿勢で知られる〈アフタヌーンJAPAN〉もこういう問題には慎重にならざるを得ません。先ほども申し上げましたが、娘さんも加害児童も、そして校名も伏せます。ただし校舎自体にモザイクをかけたとしても保護者の方には一目
すると里美が不思議そうな顔をして兵頭に訊く。
「周辺状況って、どんなことですか。テレビでは校舎にモザイクがかかるから判別なんてできないでしょう」
「それをやっちゃうヒマな連中がいるんですよ」
兵頭は悪臭を払い
「ネットに既婚女性専用の掲示板がありましてね。そこにスレッドが立つとモザイクの範囲外にある標識や立木から場所を特定しちゃうんですよ。最近ではモザイクを外すハイテクな技術を持ったネット民もいて、まあ、そのうち大輪彩ちゃんのみならず、両親の氏名住所、果ては父親の勤務先までネットでバラされる羽目になるでしょうねえ」
「どうして事件に関係のない人たちが、そこまで犯人捜しに躍起になるんです。正義感からですか」
「うーん、正義とかじゃなくって、わたしはただの鬱憤晴らしだと思いますよ。何と言っても他人の不幸は
「そんなものなんでしょうか」
「金持ち喧嘩せずって言うでしょ。普段の生活が満ち足りている人は、他人が幸せだろうが不幸だろうが関心ありませんから。世に言う底辺を
どこか露悪的な物言いだったが、穂刈には決して頷けない話ではない。イジメの構図は弱者が弱者を虐げることだ。その理屈でいけば、ネット住民が加害者とその家族を叩く構図はまるでそれと
「我々表のメディアは事実のみを伝え、問題を提起します。だけどネットでは加害者をとことんまで追い込む。口さがない連中は業務分担などと言ってますが」
兵頭の言説に違和感を覚える。テレビや新聞といった表のメディアは事実のみの報道と問題提起に徹していると言うが、穂刈の印象では加害者への糾弾もネットと競っているように映る。
いずれにしても兵頭に大輪彩の名前を告げた段階で、彼女とその家族への追及が始まる。それは由佳と穂刈たちの憤怒を代行した私刑に等しい。
教育者である自分がその幕を切って落とそうとしている。公の立場では到底許されることではない。
だが、父親としての立場ではどうだろうか。
まるで共犯者を求めるかのように、穂刈は妻の横顔を窺う。
里美の顔はほんのりと上気していた。兵頭の言説を拒否するどころか、昏い期待に彩られている。
穂刈も背中を押されている。いや、腕を取られて引き摺り込まれようとしている。
泥濘に身を
すると兵頭が物欲しそうな顔をこちらに向けてきた。
「あとですね、穂刈さん。その大輪彩ちゃんが写っているような写真とか動画はありませんか。それからその子や由佳ちゃんに関するエピソードか何か。ああ、もちろん画像は加工しますよ」
穂刈はわずかに身構える。
悪魔の
「探してみます」
「おい」
「由佳の話や彩ちゃんのエピソードも知っている限りお話しします」
「それは有難いですね」
「ただし条件があります」
「取材費ですか。それなら局で規定された取材協力費の範囲内で」
「おカネじゃありません。こちらが情報を提供するんだから、帝都テレビさんからも情報をください」
いったい何を考えているのか、不安に駆られる穂刈を尻目に、里美は身を乗り出す。
「なるほど、情報には情報ですか。道理ですね。しかしどんな情報をご所望なんですか」
「帝都テレビさんがこの事件を取り上げてくれれば、千住小学校も問題を隠しきれなくなり、わたしたちが交渉のテーブルに着けると仰いましたよね」
「ええ。あくまでもそういう青写真ですけどね」
「当然、帝都テレビさんは一度きりの報道で終わらせるつもりはないんでしょうね」
「もちろん続報を前提で考えています。その他の保護者さんたちや学校関係者への取材も続けますし」
「わたしたちが欲しい情報というのは、帝都テレビさんが調査する過程で得られた大輪さんの情報です。本人が事件についてどう思っているのか、ご両親がどんなお仕事をして、今度の事件にどう向き合おうとしているのか。いずれあちらのご家族とテーブルを挟む時の材料にしたいんです」
穂刈は横で聞いていて
「被害者のご両親とすれば当然のお気持ちでしょうね。承知しました。それではその都度情報を交換するようにしましょう。ただし、こちらも調査のとば口を探す手前、先に穂刈さんの方から提供してほしいですね。その条件でいかがですか」
「結構です」
「ではめでたく利害が一致したということで。これからよろしくお願いします」
兵頭は席を立つと同時に、テーブルの上にあった注文票を素早く摑み上げる。
「ここは払っておきますので」
コーヒー代で情報を買われたような気がしてむっとしたが、兵頭の逃げ足は声を掛けることさえ許さなかった。
後には穂刈たちと冷めたコーヒーが残された。穂刈も夢から
「何だって、あんな申し入れをしたんだ」
「ああでもしなきゃ、わたしたちが大輪さん
「それでもテレビ局と協定を結ぶなんて」
「指を
振り向いた里美もまた醒めた顔をしている。ただしこちらは、目的のためなら手段を選ばないと決断した潔さゆえというべきだろうか。
「娘をあそこまで追い詰めた張本人とその家族なのよ。絶対に償わせてみせる。そのためなら自分の手を汚してもいい」
里美の目が穂刈を挑発している。お前は娘のために手を汚すこともしないのかと、
穂刈は何も言えずにいた。
胡散臭く見えた一方で、兵頭は有言実行の男だった。穂刈から大輪彩の氏名を入手した直後に独自取材をしたらしく、翌日の〈アフタヌーンJAPAN〉は早くも千住小学校で発生した女子児童自殺未遂事件を報じた。兵頭の予告通り、番組は〈
ただし番組のスタンスからの批判は忘れなかった。女性キャスターは芝居気も
「実際に自殺未遂が起きたのは七日も前のことなんです。つまりその間、学校側が完全な箝口令を敷いていたために事件が表面化しなかったんですね」
これに呼応して相方の男性キャスターも憤る。
「こういうニュースをお伝えしていていつも
「はい。そうして、イジメの原因を放置したままにするからいつまで経っても解決しないんですね」
「まさに悪循環という訳ですね。教育現場がこの体たらくでは、我々は安心して自分の子供を預けられませんねえ」
「本当にそう思います。この事件は女児の自殺が未遂に終わったのがせめてもの救いですが、だからといってこの問題をこのまま終わらせる訳にはいきませんね」
「か弱い女児の命が
ニュース自体は十分足らずだったが、早速ネットでは現場捜しと犯人捜しが開始された。
ネットの拡散の速さと
『〈アフタヌーンJAPAN〉見たあ? また出ましたねー、イジメ放置のクソ学校。これはわたしたちが解決しなけりゃいけない案件ですね』
『あれ、どう見ても五階建てよね。足立区内の小学校で五階建てとなると結構数が絞られると思うけど』
『はーい、モザイク除去しましたー』
『仕事早いわー』
『これって千住小学校ね。ストリートビューでイチモクリョーゼン』
驚いたことに千住小学校が特定されるまでに二十分も要していない。昏い情熱の
『はいはーい、集合写真の鮮明な画像がこちらでーす』
『すごい鮮明でいいんだけどさ。これだけじゃ人間の特定はできんよ』
『他に情報はよ』
『昔はさ、小学校では全員に名札つけさせてたけど、今は違うものね。やりにくいったらありゃしない』
『昔話はいいから、新しい情報はよ』
『三階の窓から飛び降りたんだから当然救急車とかパトカー来たよね。近所に知られないはずがないよね』
千住小学校の事件を扱うスレッドは他にも存在し、どれもが被害者と加害者の特定に躍起になっていたが、どこもまだ
「……5ちゃんねるというのは知っていたけど、これはまた
「女とは限らないと思う」
画面をスクロールしながら、里美はひどく冷静だった。
「詮索好きの男が女を
「ああ、調査能力の
そうね、と言いながら里美はパソコンの前から動こうとしなかった。
掲示板の冷酷な文章も気味が悪かったが、穂刈はそれを眉一つ動かさずに見入る里美にも違和感を抱いた。
次の週になって由佳の退院が決まった。破裂した内臓も無事に回復し、骨折部分も、まだ歩行には
退院の土曜日に穂刈と里美、そして駿が病院へ迎えにいくと、由佳は目を伏せたまま呟いた。
「……ごめんなさい」
「あなたが謝ることじゃない」
里美は由佳に駆け寄り、その小さな頭をかき抱いた。
「わたしたちに黙っていたのは心配かけまいとしてでしょ。もういいから。由佳は立派だった」
穂刈も歩み寄ってひと声掛けようとした。退院してもこれからリハビリが控えている。イジメがあったクラスに即刻戻りたいとも思わないだろうから、しばらくは自宅療養が続く。どちらにしても元気づける言葉を掛けてやりたい。
「由佳」
だが、その先が続かなかった。こちらを見た由佳の目が死んでいたからだ。
生気がなく、眼前で何かが動いても反応が鈍い。眼球に幾層もの膜がかかっているようで、およそ感情が読み取れない。
大丈夫か、と口に出して横にいた駿に睨まれた。
「大丈夫な訳ないじゃないか」
駿はそう言うと、手を伸ばして由佳の肩に置いた。
「よお、また喧嘩しようぜ」
ほんの一瞬だけ由佳の目に光が宿ったように見えた。
家族に囲まれているうちに元の由佳に戻るだろう──そう楽観視して、病院の玄関を出た時だった。
「穂刈由佳ちゃん、退院おめでとうございます」
突如、死角から二つの人影が現れた。一人は兵頭、そしてもう一人はテレビカメラを担いだ撮影スタッフらしき男だった。
「今日が退院予定日と聞きましたので、こうしてお迎えに参上しました」
幽鬼のような目をしていたはずの由佳が、誰よりも早く反応した。怯えきった小動物のように顔を隠し、駿の背後に回り込む。
「えーっと、できたらご家族でぐるっと由佳ちゃんを囲んでいる
穂刈も口より先に足が動いた。
「兵頭さん、娘を撮るのはやめてください」
「うん? でも退院なんてめでたい話じゃないですか」
「モザイクをかけてもらっても、ネットに上がった段階ですぐに外される。あなたはウチの娘を晒し者にするつもりか」
「心温まるトピックだと思うんですけどねえ」
「撮影は断固拒否します」
「そこまで仰るのであれば諦めますが、結果は同じですよ」
兵頭は涼しい顔で言う。
「どういうことですか」
「あれ、ご存じないんですか。千住小学校の自殺未遂、飛び降りたのが由佳ちゃんで苛めたのが同じクラスの大輪彩ちゃん。もうネットの掲示板には実名も出ているんですよ」
何だって。
穂刈は二の句が継げなくなる。
「ひどく驚いた顔をされていますけど、そんなに意外なことですか。ネット民というのは偏執狂じみた人間の溜まり場みたいなものですからね。いずれ事件関係者の実名が明らかになると、わたしそう言いませんでしたか」
「しかし、こんなに早く」
「こういうニュースは常時光の速さなんですよ」
兵頭は物憂げに首を振る。
「だからこそバランスを取るかたちで、由佳ちゃんの退院をニュースにしたかったんですけどね。穂刈さんから取材拒否されたら仕方がないか。おい、撤収するぞ」
兵頭とカメラマンは何事もなかったかのように、その場を立ち去る。現れる時も消える時も素早い男だ。
「何だよ、今の」
駿は由佳を背後に隠したまま、穂刈に食ってかかる。
「あのレポーター、親父の知り合いか」
「そんなんじゃない。ただの番組制作者と取材対象だ」
「取材対象にさせるなよ。こんなになってる由佳を全国ネットに流させるなよ」
「だから断った」
「断る以前に、そんな隙を見せるなって言ってんだ」
駿の
「ああいうヤツは相手を見て出方を決めるんだ。
「もう、やめなさい。駿」
里美がとりなすが、駿の怒りは醒めやらないらしい。ずっと父親を憎々しげに睨んでいる。由佳はその背後に隠れ続けていて顔も見せようとしない。
折角の退院日だというのに気まずさだけが残った。穂刈は胸の底に
車中、四人はひと言も言葉を交わさなかった。
自宅に到着した穂刈が最初にしたことはネットの検索だった。パソコンの前に座るや否や、里美がお気に入りに登録していた匿名掲示板を開く。
兵頭の言う通りだった。いつの間にか掲示板では穂刈由佳の名前も大輪彩の名前も特定され、あろうことかイジメの原因が夏菜であることまで特定されていた。
誰が情報提供者なのかという疑問もあるが、それ以上に由佳の実名が掲示板に表示されている事実の方が衝撃的だった。
彼女たちの書き込みを上から順繰りに読んでいく。救いだったのは彼女らの関心がもっぱら彩とその親に向けられており、集中砲火を浴びせていることだった。
『父親は大輪
『自営じゃなくてサラリーマンなのね。勤務先を特定できないかしら』
『建築関係の従業員名簿、誰かはよ』
『生活保護受けてる子を庇おうとして、イジメの対象にされちゃったんでしょ。これはもう両成敗なんて話じゃないよね。大輪家は叩くべきだわ。生活保護を理由に苛めるなんて子供の発想じゃない』
『まあ、夫婦がそういう見下した会話を日常的にしてんだろね。子供って変に純粋だから、親の喋ったこと、そのまま学校とかで口にするから』
『ダンナの会社に
『ダンナの勤務先の特定はよ』
『待ってて。名前が特定できたから、何とか分かると思うよー』
『自宅の電話は。最近、固定電話設置してある家庭少ないっしょ。家族がケータイ持ってたら不便ないしね』
『大輪家も加害者だけど、もう一人加害者いるよ! 担任の杉原巧って先生。こいつがイジメを見て見ぬふりしたから、こんなことになったんだよ。ひょっとして、一番悪いヤツこいつじゃね?』
『学校と教育委員会に抗議電話』
『生温い。殺せ』
『何でもさ、苛めた子の土下座写真をスマホで撮ったり、お腹とか内出血するまで
『でもさ、いいカッコして巻き添え食った子も自業自得っちゃ自業自得よ。変に正義の味方すると代償が大きいよ』
『そりは厳しい』
それ以上読む気力を失くし、穂刈は
兵頭は
自分たちでは手の届かなかった大輪家に、今無数の悪意が襲い掛かろうとしている。それを全く望まなかったと言えば噓になるが、そうかと言って
悪意はまるでバケモノだ。どこかで生まれたかと思うと瞬く間に巨大化し、拡散する。相手構わず吞み込み、また巨大化して人を襲う。
兵頭に詰め寄られた時、己の中には確かに悪意が存在し、大輪彩の名前を口に出させた。あの時、穂刈の悪意も一緒に吐き出され、兵頭という増幅装置を得て巨大化し拡散したのだ。
悪意は獲物を選ばない。今はよくても、いずれ穂刈とその家族に
世評という名の
いったい何がいけなかったのだろう、と思う。よもや自分が世間の悪意を
後悔に心を重くしているところに、里美がやってきた。
「由佳、寝かせてきたわ。さっきの撮影騒ぎがよくなかったみたい」
「退院を早まったかな」
「身体の方は回復したってお医者さんは断言したから。まだ心が充分に立ち直ってないのよ。自宅でゆっくり療養させるしかない。ところで何見てたの」
「お前が見ていた掲示板だ。やっぱり由佳の名前も割れている。それどころじゃない。大輪さんの方は両親の名前まで特定されている。この分じゃご主人の勤め先が特定されるのも時間の問題。全く
「そうでしょうね」
里美はひどく落ち着いていた。
「だって大輪彩ちゃんの名前をネットに流したのはわたしだもの」
穂刈はまたも言葉を失う。
「掲示板に書き込んだのは、ほんの十文字、『イジメ加害者は大輪彩』。それだけ。後はスレッド民さんたちが裏取りしてくれたり、親御さんの名前を調べてくれた。その手際の良さはさすがだと思ったけど」
「どうしてそんなことをしたんだ。加害者の名前を明らかにしたら由佳の名前だって特定されるに決まっているだろ」
「由佳を悪く言う声も出るだろうけど、向こうさんを責め立てる声はその十倍よ。それに由佳のことは尻すぼみになっても、大輪家に対する攻撃は止まない。相手の骨を断つ気なら、こっちも少しくらい肉を切らないと」
「いくら何でもやり過ぎじゃないのか」
「あの子、駿には話したのよ。彩ちゃんたちからどんなイジメを受けていたのか。土下座写真をスマホで撮られたり、お腹が内出血するまで抓られたりというのは刑事さんが教えてくれたけど、それ以外にもひどいことをされた。上履きの中にカエルの
喋っているうちに語尾が震えていた。
聞いている穂刈の心も震える。その場の光景を思い浮かべると自然に拳が固くなる。
しかし、だからと言って里美がしたことは全肯定できない。
「自分が何をしたのか分かってるのか」
「わたしのしたことが褒められたものじゃないことくらい分かってる。でもいい。他人に褒められるより、わたしは由佳の
「まさか杉原先生の名前も」
「それは知らない。だけど特定されたクラスの担任の名前を調べるなんて、あの人たちにしてみれば造作もないことでしょうね」
非難を重ねようとして、穂刈は自分にその資格がないことを思い出す。
そもそも彼女たちがニュースを取り上げたのも、穂刈が兵頭に彩の名前を告げたのがきっかけだった。言うなれば里美の暴走も穂刈が種を
「由佳を自殺未遂にまで追い詰めた人間を、わたしは決して許さない。でも、学校も警察も動いてくれようとしない。だったらわたしたちが動くしかないじゃない。わたしたちがあの子の仇を取ってやるしかないじゃない」
穂刈の中で、里美に同調したい自分と反旗を翻したい自分がいる。どちらに与してもおそらく心穏やかになれそうもない。
それが己に与えられた懲罰なのかもしれなかった。
(気になる続きは本書でお楽しみください)
作品紹介
書 名:棘の家
著 者:中山 七里
発売日:2025年04月25日
家族全員、容疑者。人間の裏の顔を描く家族ミステリ。
穂刈は、クラスで起こるいじめに目を逸らすような、事なかれ主義の中学教師だった。
しかし小6の娘がいじめで飛び降り自殺をはかり、被害者の親になってしまう。
加害児童への復讐を誓う妻。穂刈を責める息子。家庭は崩壊寸前だった。
そんな中、犯人と疑われていた少女の名前が何者かにインターネットに書き込まれてしまう。
追い込まれた穂刈は、教育者としての矜持と、父親としての責任のあいだで揺れ動く……。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322410000623/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら
著者プロフィール
中山七里(なかやま・しちり)
1961年岐阜県生まれ。2009年『さよならドビュッシー』で第8回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞。圧倒的なリーダビリティとラストの意外性で話題に。同作は映画化もされベストセラーとなる。また、『贖罪の奏鳴曲』はWOWOWで連続ドラマ化された。他に『切り裂きジャックの告白』『七色の毒』『ハーメルンの誘拐魔』『ドクター・デスの遺産』『カインの傲慢』や、デビュー作を含む「岬洋介」シリーズ、「御子柴礼司」シリーズ、『連続殺人鬼カエル男』『騒がしい楽園』など著書多数。2020年にデビュー10周年を迎えた。