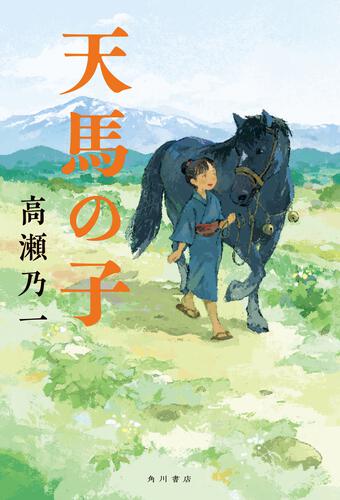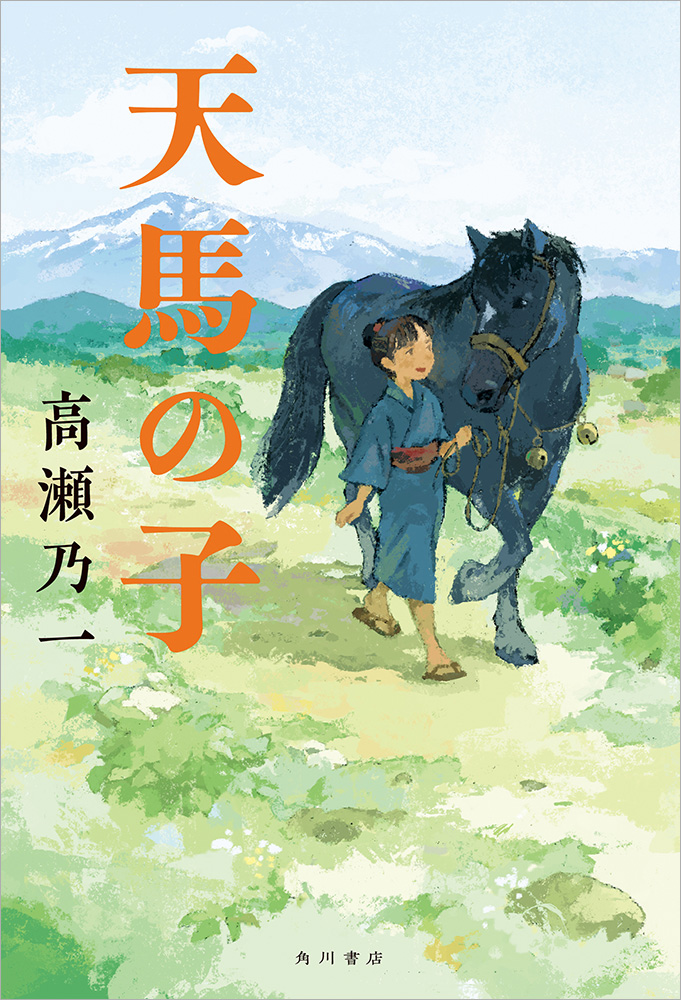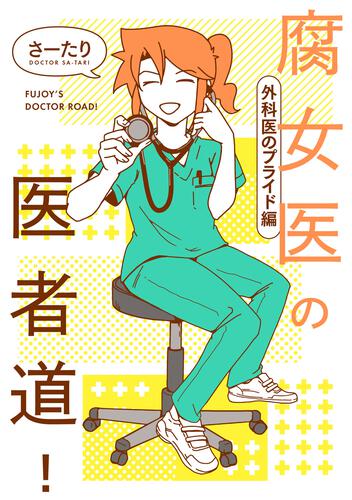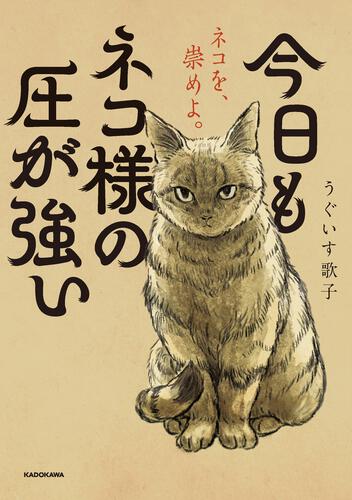デビュー作『貸本屋おせん』(文藝春秋)で第12回日本歴史時代作家協会賞新人賞を受賞、『梅の実るまで 茅野淳之介幕末日乗』(新潮社)が第38回山本周五郎賞、第13回野村胡堂文学賞、第31回中山義秀文学賞の各候補となるなど、いま最も注目される新鋭・高瀬乃一さん。最新作『天馬の子』の刊行を記念して、第1章「柳の穴」全文を特別公開します。
高瀬乃一『天馬の子』試し読み
第一章 柳の穴
一
雪
「見ろよ、生築。
手を伸ばしてみる。なにもつかめない。
「まだ背丈が足りねえみてえだ」
背伸びして、もういちど試してみる。山さ、無理だな。せめて空を流れる雲ならば。
「おい、リュウ。なにしてんだ?」
「あの白いの、つかめんかなあって」
「
「んだか? 馬っこの背に乗ってもだめか」
「そったら馬鹿げたことで馬っこさ乗ろうだなんて、リュウくれえなもんだ」
セツの笑い声に引き寄せられるように、生築と堤の坂を下りていく。
生築は首にぶら下げた馬鈴を打ち鳴らしながら、市川の岸へゆっくりと向かっていった。手綱を外してやると、川岸に生える草を
柔らかな日があたる土手に寝転がってフクベラの茎をつまみ、くるくるとまわしていたセツが、筋の通った鼻先に日差しをうけてくしゃみをした。
そのひょうしに白い花びらが吹き飛び、見ていたリュウは腹ばいになって笑い転げた。川沿いにはすでに青い草が芽生えはじめている。
もうすぐ春彼岸だが、八高田の頂には白い筋が残り、ふもとの集落の日陰にもうっすらと固まった雪が残っていた。それでも春の風は甘い雪融けの匂いを運んでくれている。
「まだ、馬の
雪が
尻尾っていえば、とセツが声をひそめた。
「このまえ
「うちのじっちゃも、夜明け前から出かけたすけ、狼を追い払いに行ったんだべか」
「あいつらは藩の境目なんて気にしねえべ」
セツは八戸藩
リュウが暮らす
村の大人たちは集まりがあると、楢の木を植えてまわった時の苦労を語りだす。植樹していると、すぐ横で八戸長根村の衆が柳の木を植えていくが、互いに顔見知りだから奇妙なもんだったと、昔をなつかしむのが、酒の席の決まり事のようになっている。
目の前の市川を渡るとセツの長根村。
ザッと
生築の馬鈴の音が、風にのり聞こえてきた。
「ころんころん、ええ音するな」
と、セツが耳を澄ませる。
「ころん? おかしな耳しとるな」
「リュウはどう聞こえるんじゃ」
うーん、とリュウは目を閉じる。腹が鳴った。笑い転げたセツは、ふっと空を見て
「いげね、そろそろうちさ戻らねえと」
八戸領の方角から昇ってきた日は、すっかり中天にある。リュウも「オーラ」と生築を呼びよせた。だが、一向に動く気配がない。まだ草を食べ足りないのだろう。馬はとにかくよく食べる。もう一度呼ぶと、丸い
「いつもは言うこときくんだよ」
セツが口に手をあて、目をほそめてクツクツと笑う。大人びた顔つきで、末は八戸一の
「あーあ、もっとセツと話してえじゃ。わぁな、うちじゃあいっつも口閉じてろって叱られるすけ、腹の中もぞもぞしてしかたねえじゃ」
「おめさんらしいわ」
いつものようにリュウが愚痴をこぼすと、セツは優しく笑った。
だが、そんな子どもじみたことばかり言ってもいられない。
今年は母のキヨについて
「リュウにおとなしく畑仕事できないべ?」
「ばっぱは目悪くて畑さ出られねえし、男手がねえから、しかたながんべ」
リュウの父、
リュウが大人ひとり分の仕事をこなさなければ、家が成り立たないのだが、手足がひょろりと細長く腰回りも薄い。畑仕事に向いていない体型だと井三郎からがっかりされている。体力も技量も兄には遠く及ばず、井三郎の口癖は「おめが男だったら」だ。
リュウは生築のもとに駆けていき、手綱を
「次こそめんこい
川に掛かった丸太橋を渡りきったセツが、手をふり叫んだ。
「んだな。できりゃあ駄馬がええ。だったらうちで面倒見れるからさ」
ひと月前、生築が産み落とした仔馬は立ち上がることができず、間引かれてしまった。その前の年も死産している。井三郎は生築のせいだとひどく怒って、これをもらってきたキヨにまで怒りをあらわにした。
母馬は仔を産んだあと、ひと月ほどで発情する。そのときがもっともつぎの仔ができやすいからと、明日には井三郎が村名主のもとへ種付けに行くそうだ。
村で生まれた仔馬が駄馬(
「セツ、あした穴さ行くけど、おめさんも来る?」
「いけたらな!」
向こう岸で川の土手を上がりながら、セツが振り返った。
リュウたちが集まる〈柳の穴〉は、「
冬のあいだは穴の入り口を雪が覆っていたが、そろそろ
「そういやあ、うちの長根の
「口かてえ?」
「石よりかてえ」
「だば、いいよ。その子の印は〈ごつごつの岩〉じゃあ」
「そりゃぴったりじゃ」
明日は井三郎が生築の種付けに出かけて留守だし、母のキヨもトコロを掘りに村の女衆と集まると言っていた。
「家の手伝いが増える前の息抜きじゃな」
と、リュウが眉を上下させると、まるで大人みたいなことを言うとセツにからかわれた。
セツはまた明日と大きく手を振り、土手の向こうへ消えていった。
リュウも生築の手綱をとった。「シー、シー」と声をかけると、生築はよだれをたらして頭を振る。カラカラとふたつの馬鈴が鳴り、水辺に浮かんでいた鴨が驚いて水面を駆けながら飛び立っていった。
強く引っ張ると、ようやく頭をもたげた生築が、荒い鼻息をリュウに吹きかけた。
二
「リュウ。おめ、まだ血抜いてねえ生築を連れて出かけただろ」
囲炉裏の炭を寄せながら、井三郎がぼそりと口をひらいた。
「村の決まり事さやぶっちゃなんねえ。
「んだども……もう雪融けたっけな」
「おめの好き勝手するんじゃねえ」
「血抜き」は、長い冬の間じっとしていた馬が、急に動き回り怪我をするのを避けるためと、その先も健やかに育つように、
わかってはいたが、
麻の
「狼がうろついているって噂あるべな。生築が襲われたらどうすんだ」
キヨがリュウをにらみつけた。
「大丈夫だよ。馬鈴つけていたし」
「あげな
母の小言はいちどはじまったら最後、リュウが寝床に入るまで止まらない。
それを察したのか、厩の生築がいなないた。うるさいねえとキヨが深く息をついたので、いそいでリュウは厩へ下りた。
リュウの家は厩になっている土間が広く造られている。人と馬が同じ屋根の下で寝起きするので、馬の気配をすぐに察することができた。
父の作蔵は生前、藩の所有する御牧を守る猟師として奉公していた。とくに
木崎野の野馬は、冬の間、ここから一日ばかり南に登った
本家(名主一家)以外では、リュウの家だけの栄誉でもある。
兄の幸吉も、父の血をよく継ぎ、乗馬の腕前は忍野村随一だった。十三という若さで、野馬捕りで先頭に立って馬を追いかける「
「名子」は、木崎野を守る「
リュウの家は、遠くさかのぼれば小比類巻の分家筋の血を引いているため、幸吉が名子と同様に馬に乗ることを許されたらしい。兄は十三から十五まで、三度の名子を務めあげた。この歳を下まわる名子は、後にも先にもいない。
「生築、こんどこそ丈夫な仔っこできるすけな」
「馬っこに必ずはねえ。油断するとしっぺ返しくらうわ」
井三郎の言葉で、祖母のカズの糸繰の手が止まった。キヨも針を動かしながら、ちらと義父を見て、すぐに目を伏せる。
「そりゃあわかってるけんど……」
「口答えするなじゃ。ろくに働きもできねえくせに口だけは一人前じゃ。幸吉さ生きとったら、もっどわぁらも楽さできるのに」
(しっぺ返しうけたら、もういっぺんひっくり返しゃあいいが)
と、反論できたらいいが、そんなことをいった瞬間、祖父の固いげんこつを食らうだろう。
(なあしてみんな馬っこのことになると目くじら立てるんじゃ。こんなにめんこいのに)
リュウは生築の体をなでながら、この先生まれる仔馬に思いをはせた。
生築は薄い茶の
ただ、南部の殿さまやご家来衆は、乗合が良い馬よりも、ことのほか見目を重視するものらしい。毛色で尊ばれるのは、色の濃い青毛や栗毛、
馬は生まれ落ちた瞬間に一生が決まる。
だけど、いまはまだそんなことは心配しなくていい。
どうか、元気で丈夫な仔馬が生まれてきますように。
毎日おいしい草を食み、野を駆けられますように。
そう願いながら、リュウは生築の首をポンとたたいた。
田起こしが終わり、里にカッコウがおりてきたら稗まきがはじまる。
水田に稗を植えるようになったのは、リュウのじっちゃのじっちゃの頃からだという。
このあたりは冷害がひどく、南の地から伝わってきた稲はなかなか育たない。かわりに稗、大豆、麻を順繰りに
稗植えまでに、男たちは焼切りをし、女たちは機作業を済ませ、村総出で
そんな忙しい合間をぬって、井三郎は生築を本家の
「ばっぱ、わぁもちょっと出るすけ」
「どこさ」
「雲馬のお蒼前さん」
「ああ、そりゃあいい心がけだ」
雲馬は昔このあたりを
言い伝えでは、良馬が多く生まれた年に、神様の使いが現れるとされた神聖な場所だ。「ウンマ」は蝦夷のことばで「馬」だという。それが言い伝えと相まって、「雲の馬」という字があてられたと、死んだ兄から聞かされたことがある。
長い年月の中で幾度も領主は替わったが、山頂にある蒼前さまの御社だけは変わらない。奥馬の繁栄と武勲のために村々を守ってくれていた。
山の側面には無数のけもの道がある。その道をたどった先に大きな洞穴を見つけたのは、リュウとセツだった。幸吉が亡くなると、冬の間じゅう家には悲しみが満ちていた。ようやく川面の氷が融けても、リュウの心は涙が凍ってしまったようにがちがちだった。いつも兄に遊んでもらった雲馬へ一人で出かけたが、寂しさが募るばかりだった。蒼前さままで登り、まだ雪の残る社の前に座って泣いていると、同じ年ごろの女の子がひょっこり現れたのだ。その子はリュウを見て、どうしたと近づいてきた。
セツと名乗ったその子は、家の手伝いが嫌で逃げだして、藩境を越えてしまったという。雲馬は長根村からも眺めることができるので、好奇心から山道を登ってきたらしかった。
兄が死んだと告げると、「泣いたって
ふたりでリスを追いかけたり、ウサギの
「柳の穴」と名付けたその隠れ家に行きたい子は、先に仲間になった子に連れられてくる。大人に殴られても穴のことを告げ口しないと誓うと、仲間だと認められ、野馬一頭ごとに焼きつける「馬印」のように、その子だけの印が与えられるのだ。
リュウは「馬の目」、セツは「フクベラの花」だ。どこかに書いて残すことはしていないが、誓いの
いまでは忍野村やその周辺の集落のみならず、藩境をこっそり越えてきた八戸領の子も仲間にくわわり、リュウが知っているだけでも十を超える子が、柳の穴に出入りしていた。
「おお、リュウ。相変わらず不細工の面してら」
「おめこそ、団子みてえな頭がデコボコして不細工じゃ」
茂みを割って道にとび出てきたのは、
千加良は生まれつき毛があまり伸びないたちで、くりくりの坊主のように
「千加良、その格好で柳の穴さ行くのけ?」
千加良は村の子たちが身に着けているつぎはぎの着物ではなく、領主さまや木崎野の
「なんじゃ、坊主が婿にでも行くみてだな」
「本家に漢学の偉い先生が
どうやら強いて行かされたらしい。千加良の母親は、治五平の囲い者だ。村はずれに立派な家をあてがわれ、母子ふたりで暮らしている。
千加良は包みをひらいて、数冊の書物をリュウに見せた。難しい字が紙面いっぱいに並んでいる。
「ほええ、おめさん、こったらもん読み書きできるんだか」
「やらねえと、あっぱが鬼さなるすけよ」
「ええなあ。わぁも字さ読めるようになりてえな」
「なしてじゃ」
「セツと文のやりとりしてえ。そしたらいつも一緒にいられるべな。我ながらいい考えだろ?」
「いいなあ。そりゃ、いい」
千加良は、セツのことをひそかに好いている。リュウとセツが並んで歩いていると、
雲馬の山頂へつづく古道を登っていくと、蒼前さまの社に至るが、そこまではおしゃべりをしながらあっという間にたどり着く距離である。昔山城だったこともあり、石垣に使われた大きな石が、そこかしこに転がっていた。
道のわきにはキマンサクが咲き乱れている。花の咲き具合で、この年の豊凶を占うことができるが、はたして今年はどうなのだろうか。千加良に聞くと、そったらこと知らんと返された。
「学問しとって、なしてわからん」
「そったらこと教わらんもん」
「役にたたんのお」
「ええんじゃ、どうせおらは本家の厄介もんだすけ」
しっとりとした水融けの香りが黒土の匂いとまじりあい、通り道を吹き抜けていく。その風といっしょに、セツが息を切らして駆けあがってきた。うしろにはおどおどした顔つきの見慣れぬ男の子がついている。こいつが口の堅い
「いまな、ふもとに見慣れねえ男がいたよ」
「木崎野のお役人さんじゃねえか?」
足を止めて忍野村の方角に目をやると、はるか遠くにうっすらと白い煙が立ちこめている場所があった。南部藩が抱える九つの牧で最も広い敷地を擁する木崎野である。
その放牧地の焼切りをしているのだろう。冬の間敷地内に残った枯草を一気に燃やして、若い新草が生えやすくするもので、春の訪れを告げる風景のひとつだ。
それが終わり夏になれば、里馬の生育を確かめるために、木崎野の役人が村を巡ってくる。それを「馬改め」といった。この時期は、馬を飼う家は粗相がないようにと気をもみながら、役人たちを迎え入れるのである。
だが、セツは違うと思うと首を振った。
「その人、左の
千加良が「ひい」と
社のお参りを終えると四人で列になり、細いけもの道を伝って残雪が凍った
「となりの家の
腹違いの兄しかいない千加良にとって、近所の赤子が妹のようにかわいいらしい。たまに子守りを頼まれると、返したくなくてたまらないと目じりを垂らす。
「わぁも見に行っていいべか」
リュウがいうと、セツが「わしも行きてえなあ」とうらやましそうにつぶやいた。
穴にはすでに数人の子がいて、リュウたちと入れ替わりに、家の手伝いがあると帰っていく子もいた。
穴の中は、リュウの家がすっぽり収まるくらいの大きな空洞になっており、奥に行くほど狭くなる。山に蓄えられた清水が壁を伝って穴の外へ注がれ、天井には乳白色の岩がぬるぬると広がっていた。
穴の入り口には、雪の下で冬を越えた松ぼっくりや枯れ葉や木の実が押しつぶされている。袴をまくり上げ草履を脱いでつま先立ちで穴に飛び込んだ千加良が、松ぼっくりに足をとられて勢いよく
三
日が暮れかけたころ、キヨが身なりを整え、カズに
「こったら遅くにどこさいくの?」
表から
昼は畑仕事が忙しく、冬の間織った麻の反物を、染屋へ納めに行けなかったのだろう。そんなことならリュウが遣いに行ったのにと思いながら、遠ざかる母の後ろ姿を見送った。
ふいに厩の生築が頭を上下させた。耳を倒して後ろ脚を踏み込み後退しようとしている。
「おめも
キヨが生築をもらい受けてきたのは、幸吉が死んで半年ほどたった夏の盛りのころだった。歯のすり減り具合から十歳前後。そのときすでに仔を
「大丈夫だ。今度こそめんこい仔っこ生まれるべ。心配するな、生築」
生築は体から湯気をくゆらせながら、静かに
家に戻ると、カズが曲がった腰を
「そこさ立って背見せろ」
リュウが土間に立ったまま
「ちょうどよがんべ。なんじゃあ、ずいぶん
「ばっぱはだんだんちっこくなるなあ」
「ヒヒ、そのうち豆粒になっちまうわ」
長年の畑仕事で腰が曲がっているカズは、ぐっと背をのばしてもリュウより小さい。近ごろは目が悪くなったというが、糸撚り台に向かって錘をかけ、機にかける麻糸をつくる速さは目を見張るものがある。その麻糸を織って反物に仕上げていくのが、村の女たちの仕事のひとつだ。
忍野村では、女の子は七つになれば
翌日、リュウは昼ちかくまで
昼飯は朝の残りの稗飯に寒干大根の味噌汁をかけてカズと食べた。腹がふくれると、カズがうとうとと居眠りをはじめる。
リュウは籠に焼き餅と漬物を入れ、生築を連れて家を出た。
近くの稗田で草刈りをしている井三郎とキヨに昼飯を届けると、ふたりが刈った草を生築に
「生築、たんと食っとけよ、わぁ柳の穴さ行ってくるすけな」
生築は食欲が
空にはぐずぐずとした雲が広がっていたが、右手に見える八高田の峰は光が満ちている。いまの時季は土が干からびるくらいがちょうどいい。あの空なら雨はしばらく降りそうにないなと
善蔵の女房のマツだった。
マツに背負われた赤子が、指をしゃぶりながら、横を通るリュウを見つめていた。白い小さな手が、夏の風をつかもうとしている。
「その子、年明けに生まれた子け?」
リュウが声をかけると、マツがゆっくりと振り向いて、そう、と小さくつぶやいた。
「さわっていい?」
「いいよ」
そっと小さな紅葉のような手の、さらに小さな細い人差し指をつまんでやると、赤子はくすぐったいのか、よだれを垂らしながらリュウに満面の笑みを向けた。
「なんってえ、めんこいの。いいなあ、わぁも妹が欲しいじゃ!」
善蔵夫婦の赤子がかわいくて仕方ないと目じりを垂らしていた千加良の気持ちがわかる気がした。
「ねえ、この子の名前、なんていうの?」
「まだねえのさ」
「なして?」
忙しくてね、とマツが目を伏せる。
「いい名前つけてやれるといいな」
声が大きすぎたのか、赤子が驚いてぐずりだした。
リュウはマツと赤子に手を振り、川を上っていった。
雲馬のふもとで
今日は屋敷に大人たちが集まっており、子らは脇街道沿いの草刈りへ行くように命じられたらしいが、怠け心が出て柳の穴で一服やろうとなったらしい。
(千加良、穴におらんとええな)
この兄弟と千加良が柳の穴で出くわすと、きまってけんかになるのだ。
千加良はふたりが働く本家では良く思われていない囲い者の子だから、借子たちも千加良に対して
リュウの家から少し北に
先日、畑へ行く途中に杉蔵に出くわしたが、彼は薪を背負う老いた母に、早く飯を食わせろと
三人で柳の穴につくと、捨吉ら長根村の子が数人車座になって、なにやら笑い転げていた。セツはどうしているか尋ねると、捨吉が知らないと首を振った。
「リュウ、麦餅、食うか?」
すすっとリュウに近寄ってきたのは、長根村の娘でハヤという。リュウより三つ年上で、柳の穴の仲間では年長者としてみんなの世話を焼いてくれる。セツが初めて連れてきたのがこのハヤだった。昔から姉のように慕っていると紹介してくれた日から、リュウも身内のような気がしている。
「食う食う、腹ぺっこぺこだべ」
「あいかわらず食い意地はってるなあ。そう思って、たあんと持ってきたべな」
こうして家から食い物を持ち寄れば分け合い、具合の悪い子がいれば、賢い子が山から薬草を採ってきて看病してやる。親からひどい
リュウは、ハヤからもらった麦餅を半分ちぎると、穴のくぼみに身を隠すように座っている、スミと呼ばれる娘に差し出した。スミはあたりを見回し、そっと近づいてくると手を伸ばして麦餅をつかみ、一気に飲みこんだ。
いつも隅っこにいるからスミという。本当の歳も名前も分からない家無し子だ。着物は破れ、帯
大人たちは、スミとは関わるなという。気にかければ、家についてきてしまうからだ。だから柳の穴の仲間ではない。「印」もついていなかった。
湧き水がたまった泉のそばに集まる男の子たちは、騒々しい声をあげている。
輪の中心にいる勝次が、懐から火打石を取り出して藁に火をつけはじめた。
「父っちゃのとっておきじゃ」
と、
「穴で煙やらねえでけろ」
リュウたちが
千加良は煙草の匂いに気づくと、頬をふくらませて
「寄ってかねえのか」
リュウが声をかけると、
「今日はいい」
と叫んで帰っていった。
稗植えがおわると、ようやく忍野村に穏やかな日々が訪れる。稗が
「あっぱ、川さ行ってくる」
土間で
「トナ切りは?」
「おわった!」
厩に虫がたかって、生築が体を気にするそぶりをしていた。市川の水で遊ばせてやれば、虫も流れていくだろう。
「あ、生築、待ってけろじゃ」
リュウが手綱を引いていたはずなのに、いつの間にか生築が速足でリュウを引っ張っていた。「ダア、ダア」と掛け声をかけて生築を立ち止まらせる。
抱えていたむしろを生築の背にかけ、縄をぐるりと回して結ぶと、その背にひょいと乗った。草と
「オーラ、オーラ」と首を撫でてやると、気持ちよさそうに鼻息を吐き出してゆっくり歩を進めた。
荷駄馬に木材を積んでいく村の男たちとすれちがった。畑の仕事は一段落したが、男衆は秋を迎える前に街道沿いの道や、木崎野の周辺に連なる長い
リュウは恥ずかしくて顔を伏せた。賢い奥馬だが、この毛並みでは下馬には違いない。奥馬は、殿さまの家来衆に認められてこそ価値があると、大人たちは口にしていた。
そんなリュウの気持ちを察したのか、生築はリュウを振り落とさんばかりに首を振る。
「すまねえじゃ。そんなに怒るなよお」
気まずさを鼻歌でごまかしていると、市川の土手の下を善蔵が歩いていくのが見えてきた。その後ろに顔をふせたマツがついている。
ふたりは川沿いを行ったり来たりして、川面を指さしながら言葉を交わしていた。
ぬるい夏の風が、八高田から吹いてくる。
リュウはふたりからすこし離れた上流まで行き、生築から飛び降りて縄を解いた。
水遊びがおわったら、柳の穴へ行ってみよう。作付けが終わるまで仲間たちは家の手伝いで集まることができなかったが、そろそろ怠け心がうずいてくるころだ。
土手を下りゆるやかに流れる
顔をあげると、下流ではまだ善蔵たちがうろついていた。ふたりはしばらく川面を眺めていたが、やがて踵を返して土手を登っていった。
(
岩場から首をのばしてみると、すぐに小さな魚影が目にとびこんできた。
「なんじゃ、おるでねえか」
そっと川に入って、手づかみで数匹捕まえる。腰にぶら下げた麻袋にいれた。
すっかり気持ちよくなった生築は、岸に上がると身を震わせて水滴をとばし、柳の穴のある上流へむかって前脚をかつかつと鳴らした。
柳の穴に続くけもの道は細いので、生築は連れていけない。山のふもとの堀跡のちかくの茂みに放つと、崖に生い茂るヒメザサの葉を食みはじめた。
穴には千加良とセツがいた。ふたりは向かい合わせに腹ばいになって、一冊の書物を繰っている。リュウと一緒に文字を教わりはじめたセツだが、リュウと違って
「どした、リュウ? ぼんやりした顔して」
ふたりの横にひざをついたリュウが、いつもより大人しいことにセツがすぐに気づく。
「川で善蔵さたちがおっかねえ顔して歩いてたじゃ」
ちらりと見ただけだが、マツは泣いていたかもしれない。
「けんかでもしたんじゃろか」
もしかしたら、リュウが名前はないのかとたずねたので、言い合いになったのかもしれない。
あとで魚を届けてやろうかなとリュウがいうと、セツが静かに書物を閉じた。なにか言いかけたとき、穴の外の立木の枝ががさりと揺れた。
「間引くんじゃ」
穴にやってきた勝次だった。三郎も腰ぎんちゃくのようについている。
「ふたりで川さ見ていたなら、そういうことだべな」
勝次の言葉に、千加良が「ああ」と
「あっこはもうふたりの
寝たきりの老婆も養っているし、昨年善蔵が体を悪くして、身重のマツだけではどうにもならず、稗と豆の畑を枯らした。そこに三人目の女の子が生まれれば、暮らしはひっ迫していただろう。畑を駄目にした善蔵一家は、本家や結仲間へ助けを求めることなどできなかったにちがいない。
千加良はそう言って、書物に目を落とした。その紙面に、ぽたぽたと涙がおちる。口をとがらせ涙を止めようとするが、うまくいかないようだった。
リュウも、おひさまに照らされて笑っていた赤子の笑顔と小さな指が、
「おらたちの間にも、ひとりいたんだべ」
三郎が言うと、勝次が「んだな」とつぶやいた。
「もしかしたら、わしらみんな、間引かれていたかもしれねえんだよな」
セツはそう言って、穴の隅に座ってこちらをみつめているスミに目をやった。
穴の外から、生築のいななきが聞こえた。それはひどく悲しげで、リュウには怒りを含んだ声にきこえた。
四
「いいか、ぜったいに、姿見られちゃなんねえぞ」
リュウが念をおすと、千加良と三郎が同時にうなずいた。勝次とスミは下流で待機している。リュウたちがしくじったら、勝次たちが流れてくる籠を捕まえることになっていた。
千加良が隣の善蔵の家を見張ること三日目。
畑仕事を終えた善蔵が、藁で編まれた赤子の寝床を抱えて家を出た。赤子を川に流すのだ。
すぐに千加良は本家の横に建つ借子小屋へ走り、勝次と三郎を誘い出した。
三郎がリュウの家に知らせにきたのは、ちょうどカズとキヨが麻布を染屋に納めに行き家をあけているときで、井三郎も薪を採りに出ていた。
市川へ向かう途中、
三郎は背丈ほどもある葦を一本引き抜いて、青い穂先で千加良の顔をつついている。まったく男の子というのはいつまでも幼子のようであきれるばかりだ。これから行うことが、どれだけ尊いことなのか分かっているのだろうか。
リュウは顔を上げて、茂みから八高田の頂に潤みながら落ちていく光を見つめた。あたりの雲の端が真っ赤に燃える。あまりのまぶしさに、リュウは目を細めた。
どうして日は嶽の向こうに落ちていくのに、雲のずっと上のほうが赤くなるのか。逆さまではないかと不思議に思って、幸吉に尋ねたことがあった。ふたりで蒼前さまの社に手をあわせ、預かっている野馬が丈夫に冬をこせますようにと祈った帰り路だった。
――帰るとき、あたりが暗くなっちまったら家がどこにあるか分かんねえべ。その目印に八高田の上が燃えてんだ。
幸吉は、いつもリュウの「なぁして」に根気強く付きあってくれる優しい兄だった。
「なあ、リュウ。こったらことして、本家の
三郎が声を震わせた。今になっておじけづいたらしい。
「見つかったら、言い出しっぺのリュウが謝ってくれろ」
「ええよ。こんなすっからかんの頭さ、いっくらでもさげてやるべな」
何年か前、リュウは奥入瀬川で魚を獲っているとき、流れていく赤子を見つけた。
仏のもとへ旅立つ赤子を、他人がどうこうしてはならない。それが、おとなたちの言い分だった。
「だども、あの子はまだ生きとる」
こんどこそ、この手で
リュウはふたりの帯紐を握り、力いっぱい引っ張った。やめろじゃ、と男ふたりがひっくり返る。
やがて、三人の耳にか細い赤子の泣き声と足音が聞こえてきた。
リュウの心の臓が痛いほど速く鼓動を打っていく。
「ええか。善蔵さがいなくなったら、すぐに寝床さ追っかけて拾いあげるんじゃ」
リュウの言葉に、千加良と三郎がうなずく。
「
足元をなでるような湿った風が川面をゆらしている。善蔵は、籠を抱えたまましばらく川べりに立っていた。一度しゃがんだが、やがて立ちあがり、赤く染まる空を見上げて木のように立ち尽くした。
もしかしたら、思い直して赤子を連れ帰るのかもしれない。そう、リュウが思ったとき、
「あっ!」
とっさに声をあげた千加良の口を、リュウは慌てて押さえつけた。善蔵は、前触れもなく籠を川に流すと、一目散に川から離れていった。
はじめに駆けだしたのはリュウだった。かき分ける葦の穂先が目に刺さった。頬が切れてじりっと痛みを感じた。
「おい待ぢろ、リュウ!」
千加良の声を振り切り、リュウは籠の横まで走っていくと、そのまま川に飛び込んだ。大きな川ではないが、川底が深い場所もある。籠が速く流れていくように、善蔵はあえてそこを選んだのだろう。
足裏にぬるりとした石の感触を覚えた直後、足がふわりと浮いて、リュウの体は川の流れに押されていった。なんとか籠に追いつき、その端をつかんだ。籠の中では薄目をあけた赤子が青い夏空を見つめている。
千加良と三郎が、リュウを追って横を駆けている。
「リュウ! こっちさ来い!」
下流から駆けつけた勝次が、リュウに手を伸ばしている。その手をつかもうとするがうまくいかない。
「阿呆かあ。おめまで一緒に死ぬとこだったべな」
千加良が籠から赤子を抱き上げた。
「捨てられたっでのに、
このあと赤子を柳の穴に連れて行き、なんとか七日をやり過ごして密かに親元へ返せばいい。
間引かれた子が七日後まで生き延びることができたら、この世が恋しいのだろうと情けをかけて、親はその子を連れて帰る習いがある。善蔵たちも、赤子が戻ってくれば、天の御意志だとありがたがってくれるにちがいない。
「スミはどんな印だ?」と、スミがリュウにまつわりついてくる。千加良は
だが、子どものたくらみなどそうたやすく成功するものではない。
リュウたちが川に飛び込み、赤子を救い上げたのを見ていた大人がいたのだ。
雲馬へ行く道中、村人数人が駆けてきて、「なんちゅうおろかなことを」とリュウたちをしかりつけ、赤子を奪い取っていったのである。
五
間引かれた赤子を、村の子らが川から拾いあげてしまった。その出来事は、瞬く間に千加良の父でもある本家の治五平に知られることになった。
リュウと千加良は、母親ともども治五平のもとへ突き出され、さんざん説教をうけた。
千加良は、母親からもしばらく外出するなと命じられ、泣きながら家に連れていかれてしまった。
翌日、リュウはキヨに連れられて善蔵の家にむかった。
善蔵に頭を下げる母の姿を見るのはつらかったが、どうしてもリュウは納得できなかった。縁でマツが乳をやっているのが見える。
「なぁして?」
ふいにリュウが声をあげると、キヨがリュウの腕をつかみ上げた。母の手を振りはらったリュウは、もう一度善蔵に向かって、「なぁしてなの?」と詰めよった。
「マツさ、あんなに泣いてるよ。なぁしてあの子捨てるの?」
「勘弁してくれろ……。キヨ、おめは娘にどんな
善蔵が鼻筋にしわを寄せてキヨをにらみつけた。
「どんだけ、わしらが、わしらが……」
言葉尻が徐々に小さくなっていくと、マツのすすり泣く声が大きくなっていった。
「今度生まれてくる時は、もっと長い命を持てるようにと願って流したんだ!」
「次の世まで待つの? 善蔵さとマツさは、あの子を長生きさせられねえの?」
善蔵の腕が振り上げられた。とっさにキヨがリュウの頭を抱えるように覆いかぶさる。母の腕の中から、リュウは善蔵の顔を見た。喉が上下し、両目は血走っているがどこかうつろで、振り上げたこぶしは宙で震えている。
「おめも、もう分かる歳だべな!」
父親の怒鳴り声に驚いたのか、赤子が泣き声をあげた。
「わかんねえじゃ! 奥馬みたいに大事にすればいいべ。なぁして人の子はこったらカンタンに殺すんじゃ」
「殺すだって?」
キヨを押しのけた善蔵が、リュウの着物の襟を掴んで地面に投げ倒した。土間に積まれた
キヨが善蔵の足元に
「勘弁してけろ。うちの子さ、頭さ悪いっけ、もうしわけねえ」
目を真っ赤にした善蔵が、さらにリュウに近づいてくる。
すると、マツが「やめてくれ」と声をあげた。
「この子、乳ば飲んで眠いっきゃ。このまま寝かしてやりてえ」
腕の中の赤子の頬は、川の水と涙にさらされ、ひび割れて血がにじんでいた。今は母親に抱かれて幸せそうに眠っている。
善蔵は、マツに「明日、いいな」と告げた。マツは赤子を抱きしめたままかすかにうなずき、リュウたちに背を向けた。細い肩が小刻みに震えている。
リュウは、
あの子はまた川に流されるのだ。
赤子を善蔵夫婦に返すことだけ考えていた。そうすれば、必ず幸せになれると思ったからだ。だが実際は、あの子はまた冷たい川に捨てられる。
マツに駆け寄ろうとしたリュウを、キヨが腕をとって引き留めた。
「いいかげんにしろ。親に捨てられた子の行く末は、スミ見ていてわかってるじゃろ」
スミがなぜひとりで柳の穴にいるのか、その詳しい事情を話してくれる大人はいない。
ただ、村の衆はスミを居ないものとして暮らしている。ときどき表に食い残しを置きっぱなしにしてしまうのは、家の者がうっかり仕舞い忘れたものだ。朝になってそれらが食い荒らされていると、猪か
スミを助けたら、この先の子もみんな救わねばならない。だから、村の大人たちはスミを里に下りてきた獣だと思いこもうとしていた。
こんどの騒ぎでも、いないように扱われ、ひとりで雲馬に逃げ去っていったスミを思うと、言いようのない苦みが胸の奥に広がった。
「なさけをかけるなら、その先その子の命をぜんぶ抱える覚悟をもってしろ。そうでなけりゃあ、口出すな。生半可なおめが、いっとう残酷だ」
家に帰る道すがら、リュウは涙があふれて止まらず、なんども道から外れて茂みに転がった。そのたびに、キヨが腕を引っ張って立ち上がらせてくれる。
赤子を川から拾いあげたとき、リュウはおのれが仏か何かになった気がした。いつも力強く優しかった兄に一歩近づけた気がした。みんなが、ようやったと褒めてくれると思った。
だが、それは赤ん坊をもう一度同じ恐ろしい悲しい目にあわせてしまう浅はかな行為だったのだ。
「あっぱ、わぁは……わぁは……」
「言わんでいい」
キヨの手は、
薄闇に響くリュウの泣き声に呼応するように、どこかから狼の
その知らせを聞いたのは、五日ほどたったあとのことだった。
大人たちが草刈りに出ているあいだ、
「あの子、今朝、もらわれてった!」
「善蔵さの?」
「ああ。父っちゃが仲立ちしたすけ、もう捨てられんですむ。リュウのおかげだ」
「わぁの?」
「おめのおせっかいで、善蔵さ、気がくじけたって」
ふたたび赤子を川に捨てる算段をした善蔵だったが、どうにも後味が悪く決心がにぶってしまった。
悩んだ末に、治五平のもとを訪ね、どこかに赤ん坊を欲しがっている者はいないか相談したという。
治五平も、息子の千加良のせいで善蔵の決心がゆらいでしまったことを心苦しく思い、ひそかに周辺の村に子を望む家がないか探りを入れてくれたという。
すると、隣の八戸領ではあるが、先日赤子が病で死んで気落ちしている母親がおり、今も乳が出て困っているという。
間引くことは、家族が生きるためにしかたのないことだ。この先、もしもまた善蔵とマツに新しい赤子が生まれたら、同じ選択をするかもしれない。だが、あの子に限っては、この世への未練が強くて引き戻されたのだ。
今朝がた、マツが千加良の家へやってきて、リュウに伝えてほしいと告げていったという。
「あの子にあげられなかった名前、別れの前につけて送りだしてやれたって」
「なんて名だ?」
「せい」
「せい?」
「生きる、のせいだな」
「わからん」
「リュウは阿呆だすけ、字読めねえからな」
でも、すごくいい名前だと、千加良が笑ったので、リュウもそうなのだろうと泣くと、つられるように、厩の生築がいなないた。
(気になる続きは、ぜひ本書でお楽しみください)
作品紹介
書 名:天馬の子
著 者:高瀬 乃一
発売日:2025年09月02日
何度でも立ち上がる。歩き続ける。冬の大地を春へと駆ける少女の物語。
『貸本屋おせん』で日本歴史時代作家協会賞新人賞受賞、
『梅の実るまで』で山本周五郎賞候補となった注目の新鋭が満を持して放つ感涙の長編時代小説!
南部藩の村に生まれたリュウは馬と心を通わせる10歳の少女。厳しい自然のなかで名馬「奥馬」を育てる村では、時に人よりも馬が大切にされていた。リュウの家にも母馬が一頭いるが、毛並みの良い馬ではない。優れた馬乗りだった兄が二年前に亡くなり、家族は失意のなかにあった。祖父は孫娘に厳しく、母は小言ばかり。行き場のない言葉を抱えたリュウが馬の世話の合間に通うのは「柳の穴」と呼ばれる隠れ家だった。姉のようにリュウを見守る隣村の美少女セツ。村の有力者の優しくてドジな次男坊チカラ。「穴」に住む家無しのスミ。そこでは藩境を隔てて隣り合う村の子どもが集まり、自由な時を過ごしていた。
ある日、片腕のない見知らぬ男が「穴」に現れる。「仔は天下の御召馬になる」。馬喰(馬の目利き)の与一を名乗る男はリュウの育てる母馬を見て囁いた。将軍様の乗る御馬、即ち「天馬」。しかし天馬は天馬から生まれるのが世の道理。生まれにとらわれず、違う何かになることなどできるのだろうか? リュウは「育たない」と見捨てられた貧弱な仔馬を育て始める。
村を襲う獣、飢饉、「穴」の仲間や馬たちとの惜別。次第に明らかになる村の大人たちの隠しごと。与一との出会いから大きくうねり始めるリュウと仔馬、仲間たちの運命。なぜ人の命も馬の命も、その重さがこんなにも違うのか。馬も人も、生まれや見た目がすべてなんだろうか。いつか大人になったら、すべてわかる日が来るのだろうか?
生きることの痛みも悔しさも皆、その小さな体に引き受けながら、兄の遺したたくさんの言葉を胸に、少女と仔馬は生きる道を切り拓いていく。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322404001478/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら