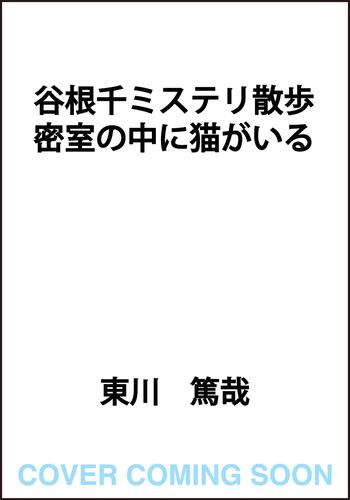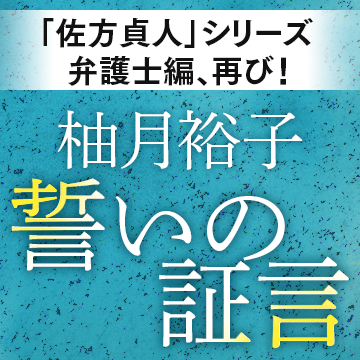ある日、大阪の理事から森の部屋に電話が入った。そして、村山の入会は見合わされることになるかもしれないと言うのである。
森は耳を疑った。「何でですか」と言う自分の声が震えているのがわかった。
理事の説明によると、京都の
そう説明されても森には何がどうなっているのかさっぱり見当がつかない。「どういうことですか」と聞きながら、何か
理事の話によると、村山は森ではなく本来は灘の弟子なのだということである。
伸一が最初にプロ入りの相談をもちかけた篠崎が、奨励会時代からお
森にしてみれば
プロ入りはまだ早いと言いつつも、篠崎はきたるべき聖のプロ入りを準備していたのである。それに篠崎には、聖は自分が
灘蓮照九段といえば当時の関西を代表する名棋士である。
灘にしてみれば四段になりたての森はひよこのようなものであった。
自分が親友から頼まれて、弟子にしたはずの子供がなぜか、森門下で奨励会試験を受けている。それは灘には
森は困り果てた。篠崎や灘の怒りはもっともである。しかし、自分は何の事情も知らなかった。それに、それはすべて大人の世界の話であり村山君には何の罪もないじゃないか。そう思い、森は師匠の
だいたいの情報をつかんだ森はすぐに広島へ飛んだ。篠崎に会うためにである。
森は篠崎の教室を訪ね、そして
「何とか村山君を奨励会に入れさせてやってください」と何度も何度も頼みこんだ。
森の誠意が通じたのか、わかったと篠崎は言ってくれた。
胸の中の氷が解けるような思いで森は新幹線に乗り大阪へ帰った。「よかったなあ、村山君」と心の中で何度も叫んでいた。明日の朝、いちばんで電話をかけてやろうと思った。
しかし、森が電話をかけるより先に森の部屋の電話が鳴った。
妙な
「昨日はああ言ったけど、もうわしの力じゃどうにもならんのじゃ。この問題はわしの手の届かないところにいってしまっておる。悪いけどもうどうもできんのじゃ、わかってくれ」
そう言って電話は切れた。
それならば、と森は思った。残る手段はただ一つ、灘に直接かけ合うしかない。
森は意を決して灘に電話をかけた。電話口に出た灘は低い声で森にこう言った。
「あきらめろ。これ以上このことで
このひとことで森の腹は決まった。大人たちの
斬られようが、将棋界を追放されようが自分はどうなったっていい。もし村山君が将棋界に入れないようなことになれば、そのときは自分も将棋をやめよう、そう決心したのだった。
考えてみれば、この1週間ろくにものも食べずに、ほとんど
弟子という言葉が胸に
村山君はわしの弟子や。はじめてのわしの弟子や、どんなことがあっても守ってやらな……。
そう思う気持ちと自分の無力さ、その
翌日から森は作戦を変えた。
心の底から、怒りがこみ上げた瞬間、森は冷静になった。
不合格を受け入れよう。その代わり、来年の試験に何の
森は師匠の南口に調停を頼んだ。こちらの非を認め今年の入会は断念する。しかし、来年は水に流して自分の弟子として再度受験させてやってほしいというものだった。
その調停案は功を奏した。灘にしても、たかが子供一人のことにいつまでも
森は村山家へ無念の報告をした。
「今年は
伸一はそのことを聖に告げた。そして森から聞いたことを包み隠さず教えてやった。
森が聖を電話口に呼んだ。
「つらいだろうけど、
森の言葉をじっと聞いていた聖がはじめて口を開いた。
「どうして、どうして僕、奨励会に入れないの」
「しかたないんや。将棋界はいろいろ
「どうして?」と言った聖の声がみるみる涙ぐんできた。
「どうして、僕」と言ってとうとう泣き出してしまった。そしてわんわん泣きながらつづけた。
「奨励会に入れないの」
聖の無念の気持ちは森には痛いほどわかった。試験の成績は
「来年、来年や」と森は聖に語りかけた。
「どうして?」
泣きじゃくりながら、聖はやっとその言葉を振りしぼった。その言葉は森の心の奥深くを鋭くえぐった。
「とにかくいまは我慢してや」
そう言って森は静かに受話器を降ろした。
その夜、聖は血相をかえ伸一にいますぐ篠崎教室へ連れていってくれと言い出した。
「
もう、どうにもならないことは伸一にはわかっていた。しかし、大人の一方的な理屈で夢を打ち砕かれた聖の納得のいくようにしてやるしかないと思った。自分が篠崎に電話を一本入れていれば、何の問題も起きずにすんでいたのかもしれないのだ。そう思い、伸一は聖を車に乗せて、トミコと一緒に篠崎教室の近くの
篠崎が喫茶店に現れるなり聖は深々と頭を下げた。
「お願いします。一生のお願いです。僕を奨励会に入れてください。そうなるように、してください」
しかし、篠崎の答えはつれないものだった。
「そうしてやりたいのはやまやまだが、もうわしにもどうすることもできんのじゃ」
それは正直な篠崎の気持ちだった。
「わかってくれ」
そう言うと篠崎はそそくさと喫茶店を出ていってしまった。
沈黙の時が少しだけ流れた。
「僕は何も
喫茶店に残された聖は父と母の前でそう言った。
「何も恐くない」
もう一度そう言った目にみるみる涙があふれ、病気でむくんだ
「恐いのは大人じゃ」と言ってわんわんと泣き出した。
両手の拳を握りしめ、自分の
「僕は病気だって死ぬことだって恐くない。恐いのは人間じゃ、人間だけじゃ」
そう言ってとめどもなく流れる涙をぬぐおうともせずに泣き叫んだ。
「大人は
頭がおかしくなってしまうのではないかと心配になるほどに、聖は泣いて泣いて泣きじゃくった。
伸一もトミコも、気が触れたように泣くわが子をどうしてやることもできなかった。
幼い日から、病院で暮らしてきた聖のことを伸一は思った。
将棋を知るために、強くなるために自分をコントロールし、ありとあらゆる努力をただの一日も欠かさずにつづけてきた。誰の力も借りず、そうやって聖は自分の道をたった一人で切り開いてきた。しかしまるでそのゆく手を閉ざそうとしているかのような大人たち、そしてそれを
「人間は
どんなに泣いても叫んでも、聖の悲しみは止まらなかった。
木から
1年、と大人は簡単に言う。しかし、同じ1年でも意味が違う。自分にはわかっている。時間がないということが、健康な人間たちとは与えられている時間の絶対数が自分には不足しているということが。もしかしたら、生きてさえいられないかもしれない気の遠くなるような1年。それをいったいどんな思いで待てというのだろうか。
「大人は嫌いじゃ」
もう一度聖は体の奥底からしぼり出すような声でそう叫んだ。それは魂を揺るがすような切ない叫びだった。そして、聖の
ぜんまいが切れたおもちゃのように、聖はぐったりと気を失ったように静かになった。泣きやんだのではなく、もう泣くことすらできなくなったのである。
翌日から聖は寝こんだ。
奨励会入りを目前にして、光り輝いて見えた自分の道が突然姿を消した。名人位が目に見えないところに遠ざかってしまったように思えた。その夜を境に中学入学以来、何の問題もなかった聖の体調に異変が起きた。熱がつづき、体は重く動かない。悔しさと
そのすきを
ネフローゼ再発。
病院で医師から
いまいかなければ間に合わない、それどころか自分が歩く道すら閉ざされてしまっていた。
病院のベッドの上で、窓から差しこんでくる月の光をぼんやりと聖は眺めていた。何をする気力も起きなかった。ただ、時間がすぎてくれることだけを願っていた。
あまりにもつらい、秋。
昭和57年、聖は13歳の落ち葉の季節をどうしようもない
聖の翼はもう少しで折れてしまいそうだった。
〈このつづきは製品版でお楽しみください〉
★作品詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/321501000146/
★関連記事:大公開! 角川文庫仕掛け販売プロジェクトの裏側【2024年3月】