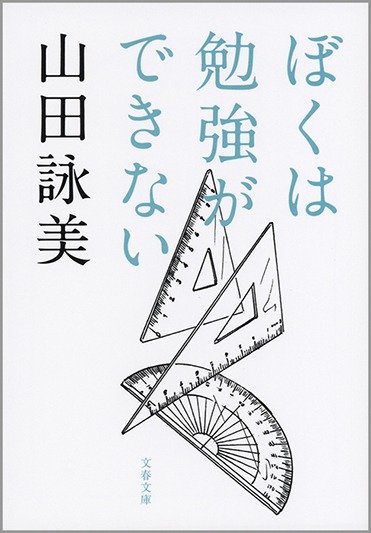ないものねだりの君に光の花束を

彼はアイドルなのに分かっていない。ふたりで歩くことがどれほどの影響を及ぼすのか。『ないものねだりの君に光の花束を』試し読み⑥
6月18日(木)に発売された『ないものねだりの君に光の花束を』の刊行を記念して、6回に分けて試し読みをお届けします!
芸能活動が忙しいのにも関わらず勉強も完璧にこなす真昼くんに、影子はさらに別世界に住む〈主人公〉だと感じるのであった。そんな彼と、ひょんなことから一緒に図書委員をすることになって!?
◆ ◆ ◆
>>前話を読む
帰りのホームルームの時間に、二、三学期の係決めが行われた。
担任が黒板にずらりと委員会の名前を列挙していき、みんな口々にあれがいいこれは嫌だと言い合っている。
私は一学期は美化委員をしていた。そのまま続けるか、別の係に変えるか、どうしようか。美化委員はあまり仕事がなくて楽だったけれど、みんなそれを知っているから争奪戦になるだろう。それに参戦してまでやりたい係でもないし、一年のときにやっていた保健委員にするか、当番の日以外は暇な交通安全委員にするか。生徒会や体育委員、文化祭実行委員などの忙しい上に目立つ係は気が乗らない。そのへんは活発な子たちが立候補するだろう。
まあ、余りものでいいか。結局は投げやりな結論に落ち着き、
うちの学校は図書室の活動が活発で、図書委員はかなり仕事がある。週一回の図書だより発行、月に二、三回当番が回ってくるカウンターの受付係、イベントの準備と飾りつけなど、ひっきりなしに仕事が割り振られるらしい。
それを知っているので、毎日練習がある運動部の生徒はまず立候補しない。それに、図書だよりやイベントで『僕、私のオススメ本』を毎月のように紹介しないといけないので、本を読まない人にはハードルが高いのだ。
「誰か希望者はいないか? 図書委員、ふたり。やりがいがあるし、勉強にもなるぞ」
担任の言葉にも、みんな顔を見合わせるだけで挙手をする人はいない。
じゃあ、やろうかな。本は好きだし、帰宅部だから放課後も暇だし、新規図書や返却の情報も早く入手できそうだし。そう思って手を挙げかけたとき、視界の端で何かが動いた。
え、と驚いて横を向く。まさかと思ったけれど、鈴木真昼がすっと手を挙げた。
「他に希望者がいないようなら、僕がやります」
私はさっと手を下げた。
クラス中の視線が彼に集まる。私だったら居心地の悪さに下を向いてしまいそうだけれど、見られることに慣れている彼は、平然と穏やかな笑みを浮かべたままだった。
「大丈夫か? うちの図書委員は放課後けっこう忙しいぞ。仕事のこともあるだろう」
担任は少し心配そうな顔で言った。彼が「いえ」と小さく首を振る。
「来週からはそれほど詰まっていないので、放課後でも大丈夫です。たしか活動は遅くても六時までですよね?」
「ああ、六時閉室だから、それ以降に活動することはないが……。まあ、当番はそれぞれ都合のいい日で希望制になってるから、融通はきくと思うし、なんとかなるかな」
「はい、大丈夫だと思います」
はっきりとした声で言って彼が頷くと、担任も安心したように首を縦に振った。
「じゃあ、鈴木にお願いしよう。あと、もうひとりは……」
担任の視線がすっと横にずれて、私に留まった。
「染矢、さっき手を挙げてたよな」
う、と声が詰まる。まだちゃんと挙げてはいなかったのに、しっかり見られていたらしい。
正直なところ、鈴木真昼が図書委員をやるのなら、私は他の係にしたかった。でも、挙手するのを見られていたのだから、今さら否定なんてできるわけがない。
「やってくれるか?」
「……はい」
私が答えたと同時に、周囲が明らかに肩を落とす気配を感じた。彼と同じ係になりたい人はたくさんいるから、もう一度希望をとれば何人も手を挙げるだろう。あと少しタイミングがずれていたら、彼が先に立候補していたら、私は他の係にしたのに。でも、後の祭りだった。
係決めが終わったあと、いくつかの委員会はさっそく今日の放課後に話し合いがあるので指定の場所に集合するように、と連絡があった。図書委員も役割分担を決めるということで、終業後すぐに図書室に行くよう指示される。
「染矢さん、よろしくね」
号令のすぐ後に、鈴木真昼から声をかけられた。
「あ、うん、よろしく」
しどろもどろに答える。さっさと図書室に向かおうと思っていたのに、話しかけられてしまってはできないじゃないか。
荷物を
「行こうか」
たっぷり三秒ほどフリーズしてから、え、と声が洩れる。目を見開いて彼を見つめ返す。
今のはどういう意味だ。まさか、図書室まで一緒に行くということか? いやいや、無理無理。鈴木真昼と一緒に校内を歩くなんて、それこそ分不相応にも程がある。学年一可愛い女子ならまだしも、この私が。すれ違う生徒たちからどんな目を向けられることか。
「すぐ行ける? それとも何か用事ある?」
「……え、用事? ……は、ないけど」
混乱した頭ではこの流れを断ち切る方法など思いつかず、
「じゃあ、行こうか。遅れちゃうといけないし」
「あ……うん」
断りも言い訳もできず、私は壊れたからくり人形みたいにぎこちなく首を縦に振った。
彼は私が荷物の整理を終えるのをさりげなく待ち、ゆっくりと立ち上がった。私ものろのろと腰を上げる。苦肉の策で、極力ゆっくりと歩いて、彼との距離をとろうとした。でも、彼はすぐに気づいて振り向き、「大丈夫?」と声をかけてくる。
「えっ、大丈夫大丈夫! 行こっか」
私は何とか笑顔を貼りつけて言った。「うん」と頷いて廊下に出た彼の後について、重い足を引きずるようにして歩き出す。
案の定、廊下にいた生徒たちが一斉に彼を見て、それから、すぐ後ろを歩いている私を
自然、足取りはさらに重くなり、彼の背中が小さくなっていく。このまま離れて歩いて、間違っても一緒に行動しているなんて思われないようにしよう、と決心した矢先、
「染矢さん、何か遠くない?」
くすりと笑って彼が振り向いた。
「話しにくいから、並んで歩こうよ」
「……あー、うん、ごめん」
仕方なく足を早めて、立ち止まって私を待っている彼の横に並んだ。そうなるともう、周囲からの視線はさっきとは比にならないくらい鋭くなった、気がする。
当然だ、あの鈴木真昼と、見るからに平凡な私が肩を並べて歩いているのだから。一体どんな人間が彼の隣を我がもの顔で占拠しているのか、と値踏みされるに決まっている。そして、なんだこの程度か、と苦笑されるか、よくもまあ平然と隣にいられるものだ、と憤慨されるかのどちらかだ。
彼は分かっていないのだ。自分が女子とふたりで歩くことが、周りにどれほどの影響を及ぼすのか。クラスメイトだろうが、係が同じだろうが、そんなことは関係がない。不可侵の聖域みたいな存在に無神経に近づくなんて、本人は気にしなくても周囲が許さない。
次々に浴びせられる
彼が図書室のドアを開けた瞬間、ざわめきが起こった。
鈴木真昼だ、鈴木真昼が来た、と驚くみんなの心の声の吹き出しが見えるようだった。
クラスも学年も違う人からすれば、彼はやっぱり同じ高校の生徒というより、芸能人の鈴木真昼だろう。そんな彼が突然、同じ部屋に入ってきて、動揺しないわけがなかった。
そんな反応を向けられることには慣れているのか、彼は気にするふうもなくホワイトボードに書かれた座席表を確認し、「2のAはここだって」と指で示しながら私に目を落とした。その声の近さにどきりとしてしまう。
「あ、そうだね、窓際の最前列……あそこかな」
私は必死に平静を装いつつ、ずらりと並んだ椅子の配置と座席表を照らし合わせる。
指定の席に腰かけると、さらに動揺に拍車がかかった。教室でも隣の席に座ってはいるけれど、もちろん机はそれぞれ別だ。でも、ここは長机なので、当然同じ机に並んで座ることになる。
机がつながっているというだけで、こんなにも距離が近い感覚になるなんて。別に密着しているわけでもないのに、妙に同席感が強くて落ち着かない。
早く終われ、と始まる前から念じているうちに、司書の先生がやって来て資料を配布し始めた。
プリントを後ろに回し、目を通すという動作ができることにほっとする。黙って座っているよりもずっと気が楽だった。
鈴木真昼はすぐにペンケースから蛍光マーカーを取り出し、何かラインを引きながら内容を読み始める。先生からの説明が始まると、赤ペンで細かく書き込みながら真剣に聞いていた。
真面目だな、と感心する。私は、大事なところだけ聞き逃さないようにすればいいか、とぼんやり耳を傾けていた。
「……というわけで、クラス単位で仕事を割り振りますので、ふたりで話し合ってどれがいいか決めてください。五分後に希望をとります。重なった場合はじゃんけんで決めますね。それでは、話し合いを始めてください」
みんなが一斉に隣と向き合って話し始める。私は何となく横を見られなくて、役割分担表の内容を確かめるふりをしてプリントに目を落とした。
しばらくしてから、鈴木真昼が「染矢さん」と声をかけてきた。柔らかくて甘い声。私はどきりとして彼に目を向ける。いつもより近くで見る顔は、すぐそばの窓から射し込む光に照らされているせいか、いつにも増して輝いているように見えた。
「染矢さんはどれがいい?」
「え、私? 私は別にどれでも……。鈴木くんのやりたいやつでいいよ」
鈴木真昼を差し置いて自分の希望を主張したりできるわけがない。
どれでもいいよ、と繰り返すと、彼は小首を傾げ、それから「強いて言えば?」と言った。
え、と私は息をのむ。
「俺もどれでもいいから、染矢さんの希望でいいよ。強いて言えば、どれ?」
私は手を頰に当てて、うーんと
「えー、強いて言えば……? まあ、カウンターやってみたいかな……」
別に貸出や返却の受付係をしたいというわけではなく、借りたい本が返却されたときにすぐに分かったら便利だな、という自分本位な考えだった。
「じゃあ、それにしよう」
私の下心などつゆ知らず、彼はにこりと頷いた。
そのとき、「鈴木くん、染矢さん」と呼びかけながら司書の先生が私たちの横に立った。
「はい、なんですか」
鈴木真昼が姿勢を正して先生のほうを向く。私も慌てて彼に倣った。
「あのね、ちょっと言いにくいんだけど」
「……? はい」
「鈴木くんたち、2のAさんは、カウンター以外のお仕事にしてほしいの……」
「えっ、なんでですか?」
私は思わず声を上げた。と同時に、無意識に隣を見る。
彼は一瞬目を見開いたあと、何かを察したように「あ」と口を開いた。
「ああ、そうですよね。すみません、気がつかなくて……」
「え、どういう……」
訳が分からず首を傾げると、彼は申し訳なさそうな表情で「ごめん、染矢さん……」と
なんで謝るの、と口に出しかけたとき、先生が声を落として説明してくれた。
「鈴木くんがカウンターにいるってなったら、ほら、ね? 本来の図書利用者じゃない生徒がたくさん来ちゃうかもしれないから……。そうなったら、本当に本を借りたい人たちが入りにくくなっちゃうでしょ」
やっと合点がいって、私は「そっか」とひとり
ここの図書室はあまり広くないので、読書以外の目的──学習やグループ活動などでは利用しない、というルールがある。代わりに校内での自習用スペースとして会議室や講義室が開放されていた。だから、図書室は本を借りたり返却したりする生徒や、中で読書をする生徒しか利用しないのだ。いつ来てもだいたい十数人しか利用者はいない。
でも、もしも鈴木真昼がカウンターで受付係をするとなったら、彼を近くで見るために来室したり、彼との接触を目的に読む気もない本を借りたりする生徒で、図書室がごった返すかもしれない。というか、多分そうなるだろう。
「それでね、あなたたちには書庫整理の係をやってもらいたいのよ」
先生の言葉に、私はなるほどと思う。先ほどの説明によると、書庫というのは司書室の奥にある部屋で、図書室に入りきらなくなった古い蔵書や貴重な資料などを保管してある場所らしい。入室も制限されていて、利用するのは授業のための資料を探す先生たちや特別に閲覧許可を得た生徒だけだという。図書室をよく利用している私も、存在さえ知らなかった。
だから、鈴木真昼が書庫の中で仕事をする分には、確かに大きな問題は起こらないだろう。
「ごめんなさいね、鈴木くん。完全にこっちの都合なんだけど」
「いえ先生、謝らないでください。むしろ僕の都合なので……ご迷惑おかけして申し訳ないです。書庫係で希望を出します。……染矢さん、それでいい?」
彼が眉を下げて
「うん、いいよ。全然大丈夫」
私がそう答えると、先生は「ありがとう、よろしくね」と言って前に戻って行った。
「ごめん、染矢さん、本当にごめん……俺のせいで……」
係決めが終わったあと、鈴木真昼がそう言って深々と頭を下げてきたので、私は驚いて首を横に振った。
「ちょっと、鈴木くん、そんな謝ることないよ。鈴木くんが悪いわけじゃないんだから」
どちらかと言えば、興味本位で見境なく追いかけてくる野次馬の方が悪い。普段から、彼が廊下を歩いていると、用もないのにぞろぞろとついていく生徒がたくさんいるのだ。せっかく人気アイドルが同じ学校にいるのだから少しでも近くで見たい、と考える気持ちは分からなくもないけれど、なんてデリカシーのない人たち、といつも私は内心呆れていた。
それでも彼は
「ていうか私の方こそ、カウンターやりたいとか言っちゃってごめん」
彼が受付をしたらどうなるかなんて容易に想像できることだったのに、何も気がつかず考えなしに口にしてしまった。そのせいでこんなふうに彼に気を遣わせることになったのだ。
「そんなことないよ、染矢さんは全く悪くない」
彼は静かに何度か首を振った。
「本当にごめん、俺のせいで染矢さんがやりたい係ができないなんて、申し訳なくてもう……」
「いやいや、本当に気にしないで」
そうは言ったものの、彼の性格的に絶対に気を
「私、別にカウンター係に思い入れがあったわけじゃなくて、下心で言っただけだから」
私の言葉に彼は「えっ?」と意表を突かれたような顔になった。
「何て? 下心? 下心って言った?」
確かめるように訊き返してくる。どうやら自分の聞き間違いかと思っているらしい。
「うん、下心って言った」
私が頷きながら答えると、今度は
何だかおかしくて、私の唇からくすりと笑いが洩れた。
「下心かー……。染矢さんの口からそんな言葉が出るとは意外だな……」
彼はまだ呆然としている。私は「そう?」と少し首を傾げた。一体彼の目に私はどんなふうに映っているのだろう。下心なんて持ちそうにもない、単純な人間?
「カウンター係がいいっていうのは、借りたい本が返ってきたときにすぐ分かって最初に借りれるっていう職権濫用目的で言っただけだから。別にどの係でも構わないよ」
「職権濫用って」
彼がふっと噴き出した。それから
「染矢さん、面白い」
「え……そう? そんなの初めて言われたけど……」
こんな平凡な人間のどこに面白みなんて感じたんだか。やっぱり芸能人になるような人は、普通の人とは視点や感覚が違うのだろう。
「それに、カウンター係より書庫係の方が楽しそうだし。今まで本屋さんでは見たこともないような本がたくさんあるかも、って思うと普通に楽しみだよ」
書庫整理の仕事は、さっそく明日から始めることになった。明日の放課後には書庫の中を見られるのだと思うと自然と頰が緩む。
「染矢さん、本が好きなんだね」
「好きっていうか……まあ、部活とか習い事もしてないし、他に趣味もないから、暇なときはだいたい本読んでるかなって感じなだけ」
そう答えながら、まさか鈴木真昼とこんなふうに話す日が来るなんて、と思う。我が事ながら内心驚きを隠せなかった。
他のクラスメイトならまだしも、いちばん遠い存在のはずの彼が当たり前のように隣に座っていて、しかも業務連絡以外の会話をしている。昨日までの私が見たら、いや、つい一時間前の私が見ても卒倒するだろう。
でも、こうやって今までより砕けて話をしたおかげか、あんなに憂鬱だった彼との委員会活動が、さっきまでとは比べものにならないくらい気楽に思えるようになった。
「俺もたまに本読むよ」
「そうなの? 知らなかった。あ、ドラマとか映画の原作?」
「いや、仕事で読むこともあるけど、普通に自分の趣味でも読むよ」
「そうなんだ。どういう……」
どんな本が好きなのか気になって訊ねようとしたとき、司書の先生が「あと五分で閉めます」と言う声が聞こえてきた。「あ、そっか」と私は時計を見る。
「今日は会議があるから早めに閉室って言ってたね」
「そうだった。じゃ、帰ろうか」
心の中で、えっと小さく叫ぶ。
その言い方だと、一緒に帰るように聞こえるんですけど。
私の勘違いかもしれないけれど、もし万が一勘違いじゃなかったら、とても困る。
「えーと、私、返却しないといけない本があるから、ちょっと残るよ。あ、鈴木くんは先に帰ってね」
ちょうど鞄の中に借りている本が入っているのを思い出し、そう告げた。本当は明日までに返せばいいのだけれど、体よく言い訳に使わせてもらうことにする。
「そっか。じゃあ、また明日」
私の言葉に頷き、彼はまるでドラマのワンシーンのように
ドアの向こうに消えていく姿勢のいい後ろ姿を見送りながら、私はまだこの急展開に心の整理が追いつかず、深々と息を吐き出した。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
試し読み最終回です。
(このつづきは本書でお楽しみください)
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▼汐見夏衛『ないものねだりの君に光の花束を』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000671/