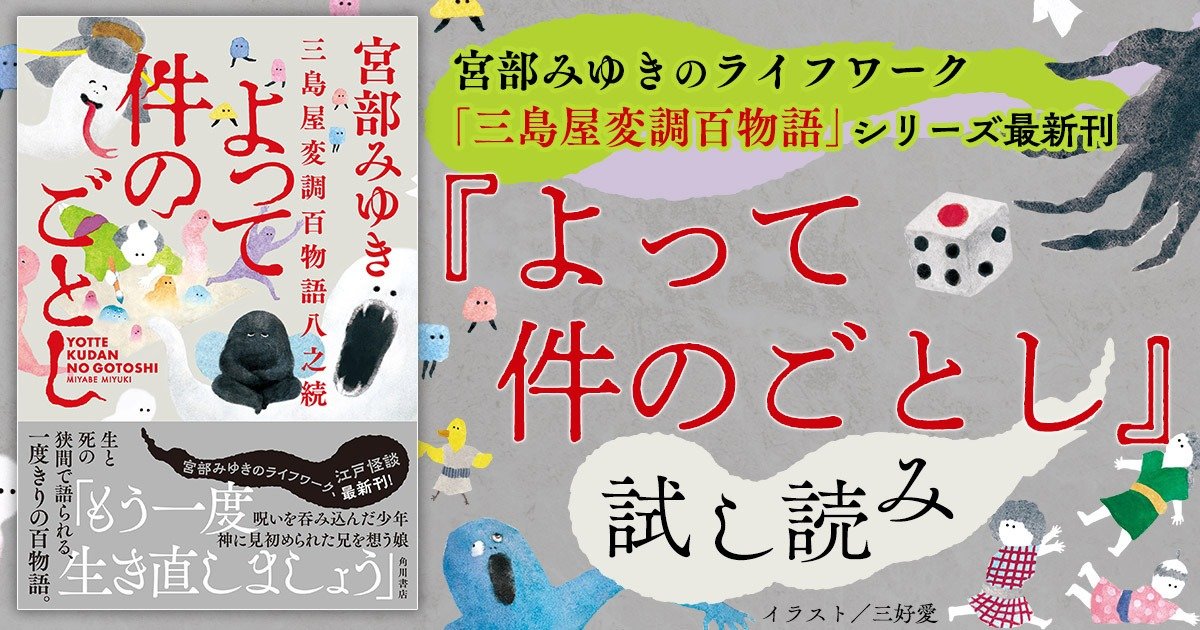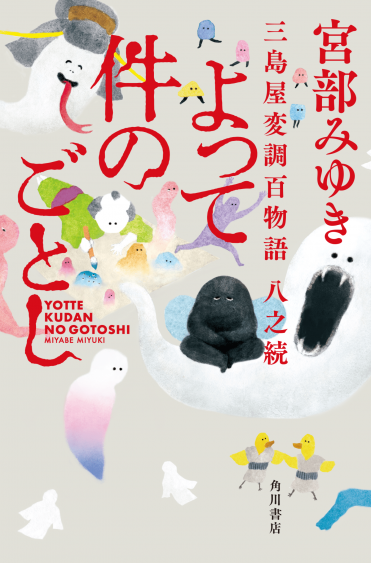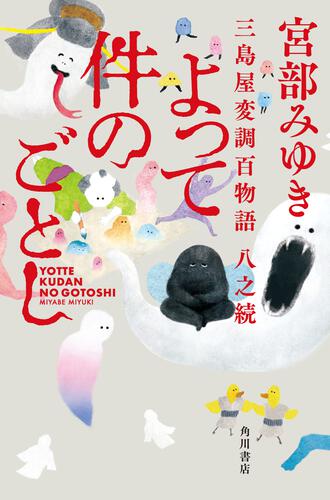ジャンルを超えて様々な作品の執筆をつづける宮部氏が「いつも自分の一番そばにある、原点に近い仕事」と語るライフワークともいえる「三島屋変調百物語」シリーズ第八弾。
『よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続』の冒頭を特別に公開!
▼【三島屋シリーズ】特設ページはこちら
〈〈〈宮部みゆき「三島屋変調百物語」シリーズ特設サイト〉〉〉
宮部みゆき『よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続』試し読み
序
江戸は
語り手が一人に、聞き手も一人。語られる話は一つだけ。いちいち蝋燭を灯すことも消すこともない。
「語って語り捨て、聞いて聞き捨て」
その場の話はその場限りで、語り手は語って重荷を下ろす。聞き手は、受け取ったその重荷を黒白の間の限りで忘れ去る。
主人・伊兵衛が酔狂で始めたこの変わり百物語は、最初の聞き手を務めた姪のおちかが嫁いだあと、次男坊の富次郎が引き継ぐことになった。絵心のある富次郎は、語り手の話を聴き終えると、それをもとに墨絵を描き、〈あやかし草紙〉と名付けた桐の箱に封じ込めるという独特の工夫をして、時には聞き捨てるべき話の重みに負けそうになるところを、どうにかこうにか踏ん張っている。
おちかは暗い影を引きずる孤独な娘だった。ほんの少し浮ついた娘心が災いして許婚者を失い、身近な男を人殺しに堕してしまったと、我が身を責めていた。しかし変わり百物語の聞き手を務め、この世の数奇で不思議な出来事を耳に入れてゆくうちに、傷ついた心を縫い合わせ、その痕を抱えながらも立ち上がる強さを持っていた。
さて、富次郎はどうだろう。まだ慌てて将来のことを決めなくてもよい気楽な立場。本人はそれなりに、他店の釜の飯ならさんざん食ってきた、てんで世間を知らぬわけじゃありませんよと己を恃んでいるけれど、その心におちかほどの強い芯はあるのか。
優しく、気さくで頼りない。そんな富次郎の背中を支えるのは二人の女中、怪談語りが呼び込む怪異から三島屋を守る禍祓いのお勝と、三島屋のこれまでを全て知っている古参のおしまだ。
人は語りたがる、光も闇も。三島屋の変わり百物語に、今日も新たな語り手が訪れる。
第一話 賽子と虻
しのびやかな小雨が、江戸の町を覆う。
道行く人の額や頬に、小さな雨粒がひやりと触れる。この雨は
秋が来た。
黒白の間の縁側に敷いた
暦の上の秋分を過ぎ、変わり百物語が迎えた語り手は小柄な男で、やや足が弱いようだった。一人で歩めぬほどではないが、一歩ごとの足取りがふらついている。上座に腰を落ち着けるところまで、
顔つきや肌の
女なら、
色あせた
そう、それが
変わり百物語の語り手は、初めのころからずっと、
このお人だって、やっと順番が回ってきたんじゃないのか。進んで語りたがっているんじゃないのか。違うのか。嫌々なのか。それだから、わざわざ職人の仕事着の股引をはいたまんまやって来たのか。
─灯庵さんの嫌がらせかな。
あの蝦蟇仙人なら、富次郎への意地悪に、およそ変わり百物語には無縁な人を無理に説き伏せて、あるいは金を払って雇って、語り手に仕立て上げて送り込んでくることぐらい、やりかねない。
─だったらこっちは、どうしたもんか。
富次郎の内心の、ふつふつとする怒りと戸惑いを感じとったのか、語り手は思いっきり不機嫌そうな顔のまま、思いっきり畳に額をぶっつける勢いで頭を下げた。
「すまんこってす。あっしはこういういけすかない野郎でござんすが、けっして三島屋さんに含むところがあるわけじゃねえ。ここで語れるのも有り難いと思ってるんですが」
わわわっとぶちまけて、顔を上げた。額どころか、頬骨のところにまで畳の跡がついている。
「十一のときに、笑い方を忘れました。それっきりいっぺんも笑ったことがねえ。
声を聞いたら、
「お気づきかもしれませんが、あっしは足がよろけます。力仕事はできません。今の奉公先じゃ、
しゃべっているうちに、語り手のくすんだ顔にじっとりと汗が浮かんできた。
「そんな働きぶりですから、毎日食わせてもらえるだけで有り
またぞろ、額を畳にぶっつける。
「そこまで!」
思わず、富次郎は声を張り上げた。
「そこまででよござんす。お手をお上げください。口入屋からお聞き及びではありませんか。この黒白の間は無礼講、お武家様でも
語り手はそろりそろりと起き直った。汗がいっそうひどくなっている。居ながらにして雨に打たれているかのようだ。
「どうぞお使いください」
富次郎が差し出した手ぬぐいを握りしめ、語り手は下を向いた。ややあって、握りしめた
ああ、この人から語りを引き出すのか。そう思うだけで胸がつぶれそうになるから、富次郎はわざと別のことを考えた。
おしまが供していった本日の茶菓は、香り高いほうじ茶と紅葉の形の
「重ね、重ね、みっともねえ」
手ぬぐいを顔に押し当てたまま、語り手が声を振り絞る。
富次郎はその目の前に、ほうじ茶の湯飲みをそっと差し出した。
「どうにも語ることがむつかしければ、わたしといっとき茶飲み話だけしていただいて、お帰りになってくださってかまいません。この変わり百物語は三島屋の酔狂でございます。ただの酔狂でお客様を苦しめることがあっては、
思いつきの
「─あきんどのじごく」
子供が
「そんなら、侍にはさむらいの、職人にはしょくにんの地獄がありますかねえ」
何なら百姓の地獄、芸人の地獄に岡場所の地獄、
富次郎は
「あっしも、いつかはどっかの地獄に行くんでしょう。行ってみるまでは、どんなところかわからねえ。けどね、三島屋さん。あっしがよく知ってるところが一つあるんだ」
そこは地獄ではないけれど、地獄にいちばん近い場所だった。
「その話をしたいんですよ。あっしの名前は
毎年、こういうひそやかな秋雨が降ると。
その雨粒を頬に受けると。
軒を打つ雨音に目が覚めると。
この餅太郎さんは泣きたくなる。大きな声で叫び出したくなる。よろける足で地団駄踏んで、暴れ出したくなる。
その
「わたしは信じますよ」
富次郎は胸をぱんと
*
餅太郎の
互いの
大畑村は山越えの街道の旅籠町でもある。まずこの村で養える口の数が増え、増えた人手で道の整備と耕作が進むと、ほどよい距離のところに一つ分村を作り、さらに養える口と畑を増やしてゆく─という繰り返しで、一ツ木村、二ツ沢村、三本木村、四辻村、
餅太郎の生家は父ちゃんと兄ちゃん、姉ちゃんと餅太郎の四人暮らしだった。父ちゃんの
母ちゃんは餅太郎を産んで、そのお産が重くて死んでしまった。だから餅太郎は母ちゃんの顔を知らないのだが、知っている人はみんな、姉ちゃんは母ちゃんにそっくりだと言う。名前も、母ちゃんは「りく」で、姉ちゃんは「りん」だ。
とりわけ器量よしではないけれど、色が白くて頬が赤い。気性は明るく優しく、手先が器用で糸繰りも草木染めも上手な姉ちゃんは、餅太郎の自慢だった。
小作人小屋に住まい、持ち物といったら
「おりんちゃん、大畑村の〈
猪鼻屋とは、麻と木綿の糸を扱う仲買問屋である。
そんなお店の一人息子の嫁に、畑間村の百姓の娘を?
普通ならとんだ人違いか、真っ昼間から夢を見てるんじゃねえよとどやしつけられるようなお話だ。なのに夢ではなかったのは、これが当の一人息子、名は
玄一郎はおりんに恋をしていた。いったい、どこでどうして見初めたのか。その謎を解いてびっくり、餅太郎の担ぎ売りが結びの神だったのだ。
炭や薪は商売敵が多いので、餅太郎はもっぱら
旅籠町の大畑村で、歩き疲れ草鞋にも疲れている旅人に、この編み込み草鞋は喜ばれた。餅太郎が売り歩きながら、
「このきれいな草鞋を思いついたのは、うちの姉ちゃんやさ」
「姉ちゃん、糸繰り歌をうたわせたら、畑間村どころか六つの分村でいちばんだ」
悪気なく素直に言いふらすもんだから、さらに評判になった。
そしてあるとき、その評判が、猪鼻屋の玄一郎の耳に入ったのだ。どんな娘なのか見てみたい。強く気を
玄一郎が訪ねたとき、おりんは村の
種々の糸を繰り手をうごかしながら、女たちは独特の節回しで歌をうたう。それが糸繰り歌だ。餅太郎の自慢は嘘ではなく、おりんはこれが本当に
たちまち、玄一郎は魅せられた。おりんの歌声としなやかな手つきと、丸い額に浮かぶ
嫁にもらうならこの娘だ。働き者だしけっこうじゃないか。しかし、二人の身分と立場の違いは歴然としている。猪鼻屋の父母も、やすやすと許してはくれまい。
思い悩む日々に、玄一郎はみるみる青白く
これはもう仕方がない。
思えば、玄一郎が糸繰りに巻き取られる糸のようにつるつると畑間村へ向かってしまったときから、こうなる
とんでもなさすぎる良縁に、最初のうちは
大村長は、大畑村と六つの分村を全て束ねる長だ。地主や山持ちよりも偉い。その養女であるならば、猪鼻屋の嫁としてもけっして恥ずかしくなかろう。
この条件を、おりん本人よりも先に、父ちゃんと兄ちゃんが受け入れた。
それから数日のうちに、おりんは身の回りのものをまとめて、大畑村の大村長の屋敷に移っていった。付け焼き刃でもやらないよりはましだから、祝言まではひたすら行儀見習いだ。大村長のおかみさんは、お花と踊りを仕込むと張り切っていた。
肝心の祝言は、神無月(十月)の九日と決まった。本店の猪頭屋の隠居が
姉ちゃんの玉の
「祝言はどこでやるん?」
「大畑村の猪鼻屋さんだな」
「おいらたちも、姉ちゃんの花嫁姿を見られるさ? おいら、おぎょうぎよくしとる」
「いや、おめえもおらも、父ちゃんも祝言には呼ばれん」
「なんで? なんで呼ばれんのさ」
「おめえ、わかっとらんの。おりんは、うちの娘じゃのうなった。大村長とおかみさんがおりんの
もともと口数の少ない父ちゃんは、おりんを養女にやってさらに寡黙になり、そのむっつりとした顔からは、娘のこの降ってわいたような幸せを、本当に喜んでいるのかどうか読み取れない。ただ、朝夕に思いついたように村はずれの墓地へ足を運んでは、母ちゃんの墓の前でうずくまってじっとしている。
「母ちゃんと二人で喜んでるんさ。邪魔しちゃいかんで」
寂しいさ。けど
「いいか、もち」
父ちゃんも兄ちゃんも、餅太郎をこう呼んでいた。もち、こっちゃ来い。もち、よぉく聞け。
「担ぎ売りに行っても、おりんを訪ねちゃならんぞ。たまたま見かけたって、なれなれしく近寄ったらいけん」
─もう身内じゃないんさけ。
幼い餅太郎の心にも、二人の言い聞かせはじわじわとしみ込んで、
─もう会えねえ。姉ちゃんはもう、おいらの姉ちゃんじゃねえ。
やっとこさ