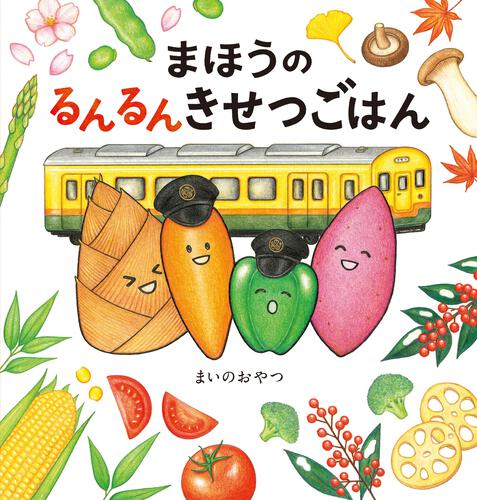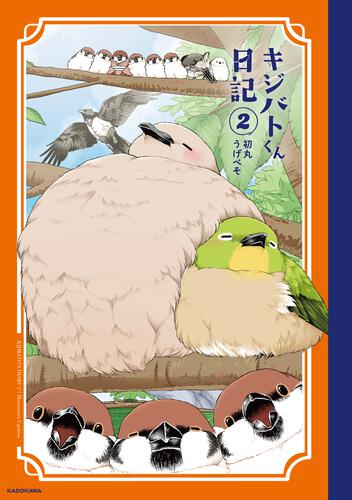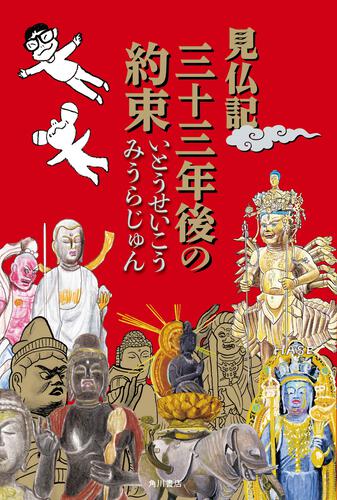「本の呪い」が発動して、街が物語の世界に? 本嫌いの少女が、街を救うために書物の世界を冒険――。深緑野分さんの最新刊は、本の魔力と魅力を詰め込んだ、まさに空想の宝箱。10月8日の刊行を記念して、深緑さんイチオシの第三章、オイシイところを試し読み!
※「第一話 魔術的現実主義の旗に追われる」の試し読みはコチラ
>>前話を読む
深冬の号令で真白は地面を強く蹴り、銀の獣の前に躍り出た。青い目がぎょろりと動く。ばっくりと開いた口、真紅の舌と喉が間近に迫る。生臭い独特の臭気が深冬の敏感になった鼻を刺激して、思わず顔を伏せた。獣の鋭い牙に貫かれて死ぬかもしれない。けれど深冬はただ真白の体を強く抱くだけだった。ここにいれば大丈夫だと思えた。
真白は右に左に飛んで、獣が口を噛み合わせる間際にすり抜け、元の洞窟の中へと誘導する。囮作戦は見事にはまり、銀の獣はエレベーターに群がる狐たちを無視して、真白を追いかけてきた。
洞窟状の作業場を真っ直ぐ抜け、二匹は獣の足音を背後に聞きながら、反対側へ向かう。しかし細い廊下を通り、ゲートを越えてスロープに出ると、運搬口がどんどん狭まっていた。先に避難した作業員たちが獣を閉じ込めるべくシャッターを閉めようとしていたのだ。
「待って!」
だが声が届くはずもなく、シャッターは容赦なく降りていく。真白の速度が上がる。日の光が消えそうなほど完全に閉じかけたその隙間を、火の輪くぐりのライオンのように、真白は跳躍してくぐり抜けた。
ひやりとした風が体に吹き付け、おそるおそる顔を上げてみると、無事に外へ出ていた。
「えらい、すごいよ真白!」
深冬が両手足をばたつかせて喜びをあらわにし、背中の白い毛がもみくちゃになるほど撫で回すと、真白は照れたようにぽっと顔を赤らめた。
ここは先ほどの代謝物処理場だ。先に逃げた狐たちが豆粒に見えるほど高く飛ぶと、あの黒い土砂めいた代謝物で一面埋め尽くされた処理場が、まるで孤独なキノコのように見えた。外側にある他の工場群からも独立し、どこにも接していない。まわりは深くえぐれて底の見えない暗い堀がぽっかりと口を開けている。カッキーたちはこの堀のせいであの場所から外へ出られないのだろうか、と深冬は思った。
「……読長町は本当に元に戻るのかな」
やがて、先ほど代謝物とイメンスニウムをより分ける機械があった、二階建ての建物が見えてきた。ひときわ小柄な狐たちが家の前に集まっていて、こちらを見上げて手を振っている。
「あれ、カッキーたちじゃないかな」
深冬が合図すると、真白は減速してひらりと体を返し、地面に降り立った。
「すげえな、空飛ぶ犬だぞ!」
子狐たちは真白を取り囲んで歓声を上げたが、変身を解いて少女の姿に戻ると、あからさまにがっかりした。
「なあんだ、人間になっちゃうのか」
「つまんないの」
「お姉さん、今のどうやったの?」
キイキイと口々に言いながら子狐たちは真白に一層群がるので、深冬は間に割って入った。
「はいはいそのくらいにして! あんたたちもみんな狐になっちゃったんだね」
「はあ? 狐? 俺たちは人間だけど」
なるほど、自覚はないのか。そういえば確かに、耳が生えても尻尾が生えても、みんな驚きもしなかった。
「あんたは無事だったのか。銀の獣が暴れて逃げたって聞いたけど」
子狐たちの中でもひときわ体格が良く、ひとりだけはしゃいでいない狐が、深冬に話しかけてきた。人間の時の風貌がどことなく残っている。カッキーだろう。
「そう、まだ作業場内にいるはずだよ。シャッターが壊されてなければ、だけど」
それにしても、深冬もだんだん狐を見慣れてきたようで、顔立ちの微妙な違いや、仕草や背格好の特徴を摑みはじめていた。
「……飼い主が同じ柄の猫の中から自分の猫を捜し出せるみたいなもん?」
「何言ってんのかわかんねえけど、やっぱ避難すべきだろうな」
「そうだね。早く逃げた方がいいと思う。エレベーターホールのドアは簡単に壊されちゃったし」
「よし。メギ、レダ、大人たちに知らせてくれ。〝あれ〟を使う時が来た」
カッキーが命じると子狐の中の二匹が頷き、地面を蹴って建物の中へと駆けていく。残った他の子狐たちはカッキーに率いられ、列を成してどこかへ行こうとする。
「真白、どうする? カッキーたちについて行く?」
そもそも泥棒狐はここに逃げ込んで、まだそう遠くへは行ってないはずだ。泥棒と盗まれた本を見つけさえすれば現実に戻れ、銀の獣がどうなろうと関係なくなる。しかしすぐには難しいだろう。
「餌にされる間際に逃げた泥棒狐が、ここに逃げたのは見たんだ。でもみんな狐になっちゃったら、もうどう捜したらいいの?」
すると真白は腕を組んで小首を傾げ、考える仕草をした。
「……あのカッキーという子は、たぶん〝サーシャ〟の役なんだね」
「誰?」
「小説の主人公を助ける親友で、浮浪児たちのリーダー」
「小説? ああ、この世界の原作の話ね。そんなもんあったなあ。それで?」
「原作だと、主人公が銀の獣を手懐けるの。主人公は〝どんな生き物でも正常な姿に戻せる〟機械を持っていて、獣の本当の正体を暴くことができて──つまり主人公に会えたら一挙両得。獣も大人しくなるし、泥棒を人間に戻せるかも」
「マジで? 主人公ってどこにいるの?」
「カッキーについていけば会えるんじゃないかな」
「早く言ってよ! すぐ追いかけなきゃ」
ふたりがカッキーたちに追いつくと、彼らはドーム型のハッチの前にいた。緑色の錆びついたハッチで、どっしりと重たそうだ。鍵はかかっていないようだが、子狐が五匹がかりで把手を引っ張り、うんうんふうふう息を切らしても、ほんの数センチしか開かない。
「貸して」
たったひとり人間の姿のままの真白が把手を摑み、「ふんぬっ」と息を吐きながらがに股で持ち上げると、ハッチは蝶番を軋ませながらゆっくりと開いた。深冬はおそるおそる近づいて、中を覗き込む。てっきりマンホールのように深い穴が掘ってあって、下に行けば避難所か何かに繋がっているのかと思いきや、違った。
「何これ」
穴には薄茶色の布で包まれた大きな荷物が詰まっていて、人間どころか狐一匹隠れられそうもない。深冬が怪訝な顔をしていると、色違いレンズのメガネ狐がにやりと笑った。
「下に降りるための穴じゃないんですよ」
「それじゃ何のための……?」
「兄貴! メガネ! 装置も外に出ましたぜ!」
尖った耳やふっくらしたお腹を汚した子狐が報告する。どうやらハッチの外側にある、代謝物に埋もれていた装置を発掘していたようだ。装置はハッチと同じ緑色で、ハンドルと赤い球をつけたレバーがあった。
「全員後ろに下がれ!」
カッキーの号令で子狐たちはハッチから離れると、輪になってぴしっと敬礼した。カッキーが黒い手でハンドルを回す。さすがのカッキーも狐になれば力仕事は難しいようだったが、真白が助けるとくるくる動き出す。
まったくもって、深冬はこのような光景を見たことがなかった。回るハンドルに反応して穴がイメンスニウムの紫色に輝き、がりがりと激しい音が立ったかと思うと、突然、薄茶色の丸っこい布がぼんっと膨らんで顔を出した。まるでふくらし粉を入れすぎたスポンジケーキだ。
「な、何なの」
不安げにたじろぐ深冬の目の前で、丸っこいスポンジケーキはどんどん膨張し、みるみるうちに巨大キノコへ、巨大キノコから公園の遊具サイズへ、そして見上げるほど大きな、丸いガスタンクサイズになった。
後ろに下がって、手で眉庇を作る。もはや銀の獣と同じくらいの大きさまで膨れ上がった布は、ぱんぱんに張って、ゴスンという音と共に、ふわりと宙に浮かび上がった。係留ロープがするする伸びていく。
「これって……ひょっとして気球?」
深冬が知っている気球よりも大きい。薄茶色だった布は、いまや紫のイメンスニウム色に発光して、ロープに繋がれた状態で風に揺れている。
汗だくになったカッキーと真白がふうふう息を吐きながらレバーを横に倒すと、地面の下で何かががこんと大きく揺れ、蒸気が噴き上がった。
「みんな、離れろ!」
慌てて子狐たちの後についていく。するとさっきまで立っていた場所に溝が生まれ、中から何かがせり上がっていった。
蒸気が晴れると、気球の下に船のような形の、屋根付きのゴンドラが出現していた。普通のボートよりも大きく、深冬のクラスメイトがここにいたとしても全員乗れそうだ。船尾の部分に大きなプロペラがついている。
「すごい。アニメみたい」
深冬はおそるおそる近づいて、鋼鉄のゴンドラに触れる。ゴンドラの入口には緑色のハッチがついている。さっきのマンホールの蓋だろう。
「ぼんやりしてないで、どくか乗るかしてくれよ。後がつっかえてるんだから!」
いつの間にか大勢の、大人サイズの狐たちがやってきていた。慌てて深冬がハッチの前からどくと、子狐たちが先にゴンドラへ乗り込み、大人たちが後に続く。深冬はどうしようかと思ったが、好奇心の方が勝って、自分もゴンドラに乗り込んだ。
内部は鉄のにおいがした。子狐たちはこの奇妙な乗り物にはしゃぎ、丸窓に群がったりベンチとベンチの間を走り回ったりと大騒ぎだったが、それでも余裕があるほど中は広かった。
とはいえ、短い距離を移動するための乗り物なのか、ベンチ以外の設備はなく、寝泊まりするような部屋は用意されていなかった。後方に歯車とピストン式のエンジンがある。
へえ、ほお、と嘆息を漏らしながらあたりを見回っていると、狐たちが悲鳴を上げた。
「あ、あれ!」
工場の運搬口から銀の獣の顔が覗いている。獣はついにシャッターを壊し、開けた処理場に姿を現した。ゴンドラにエンジンがかかり、蒸気を噴きながら宙に浮かび上がったのと、銀の獣がこちらに気づいたのは、ほとんど同時だった。
回転するプロペラとエンジンの推進力、そして気球の浮力で鉄のゴンドラは飛翔する。深冬は急いで窓にへばりつき、外の様子を窺った。真白の姿が見当たらない。ゴンドラに乗っていないのだ。
銀の獣は美しい声で歌いながら、太い足で地面を揺るがす。そして長い首をぶんぶん振ると、ゴンドラに向かって走り出した。
「急げ、追いつかれるぞ!」
操縦席から大人たちとカッキーの声が聞こえる。深冬は窓ガラスに頬を押しつけて顔を歪めながら、「真白、どこ?」と呟く。
ゴンドラは蒸気をまき散らしながら懸命に逃げようとするが、銀の獣の脚力は強い。あっという間に追いつかれ、窓のすぐ近くに青い目が見える。瞳孔が小さくて黒く、まるで猛禽類の目のようだ。
銀の獣は再び歌う。その声は滑らかで透明感があり、聞いているとだんだん頭がぼうっとしてくる。餌場で、泥棒狐が食べられそうになった時と同じ歌だった。誰かが「あれを聞くな、耳を塞ぐんだ!」と叫んだが、すでに全員、獣の歌の虜になっていた。目つきがとろりとなり、操縦席の面々も体を傾がせる。ゴンドラのスピードがどんどん落ちていく。
その時、白く大きな犬が飛んできて、ゴンドラと銀の獣の間に入った。
「真白!」
真白は鳥のように軽やかに銀の獣の目の前をかすめ、くるりと回ってUターンする。先ほどと同じ囮作戦。銀の獣の気を引いてゴンドラから遠ざけようとしているのだった。獣は歌うのをやめ、ぎょろりとした青い目で真白の動きを追っている。
「今のうちだ、取り舵いっぱい!」
「待って、真白が!」
しかし深冬の叫びは聞き入れられない。ゴンドラはスピードを上げて、真白と争っている獣とは反対の方向に傾いて進む、距離がどんどん離れていく。深冬は窓にへばりついたまま、真白の無事を祈るしかなかった。
ゴンドラが工場の敷地上空を出て、まわりを囲う黒い堀を飛び越えると、真白も獣から離れて、こちらを追いかけようと方向転換した。目も意識もゴンドラにばかり注がれていたのだろう。堀に足止めされた銀の獣が、最後のあがきとばかりに首を伸ばして、大きく口を開けた。
その瞬間、深冬は悲鳴も上げられなかった。銀の獣の口はばくんと閉じ、真白の姿はどこにもない。あるのは蒸気の靄だけで、処理場は見る間に遠くなっていった。
「お願い、引き返して! 真白が食べられちゃった!」
半狂乱になった深冬が操縦席の面々に摑みかかり、ゴンドラは激しく揺れた。
「食われちまったのならもう遅い、戻ったって無駄だよ!」
深冬は全身から血の気が引いていくのを感じ、そのままふらふらと床にうずくまった。膝に額をあてて目をつぶり、早く夢が覚めることを願う。ここは物語の世界。登場人物は街の人だけど、何もかもが現実と違っていて、独自のルールがある。
「真白を助けなきゃ。真白は死んでない。絶対死んでない……」
そう自分に言い聞かせるよう繰り返し、ぎゅっと拳を握った。真白を助けなければ。
(このつづきは単行本でお楽しみください)