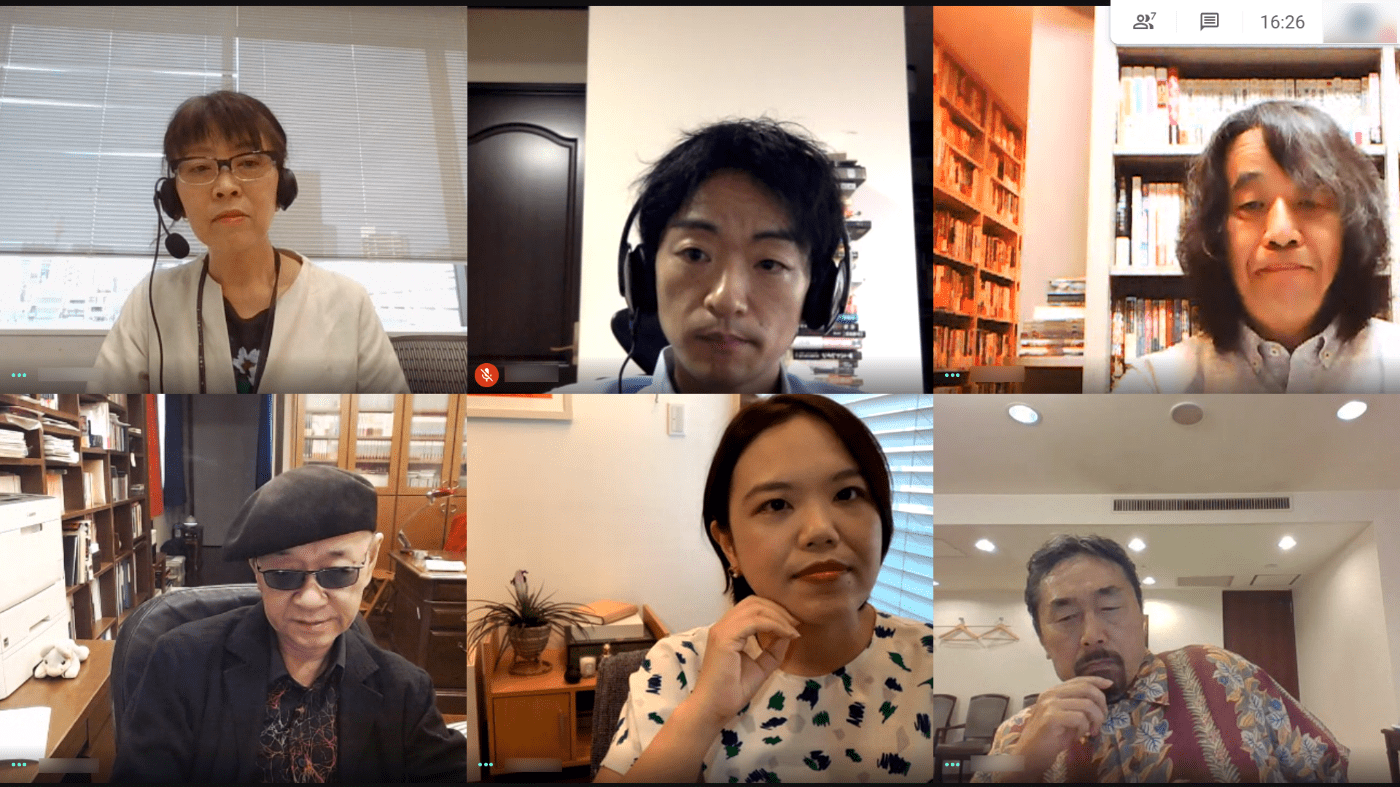KADOKAWAの新人文学賞として、ともに四半世紀以上の歴史を持つ「横溝正史ミステリ大賞(第38回まで)」と「日本ホラー小説大賞(第25回まで)」。
この2つを統合し、ミステリとホラーの2大ジャンルを対象とした新たな新人賞「横溝正史ミステリ&ホラー大賞」が2019年に創設されました。
そして2020年、2つの賞の統合後、はじめての大賞受賞作となったのが『火喰鳥を、喰う』です。
選考委員の有栖川有栖氏が「ミステリ&ホラー大賞にふさわしい」と太鼓判を押し、同じく選考委員の辻村深月氏が「謎への引きこみ方が見事」と激賞しました。
2025年10月に実写映画の公開も決定した本作の第一章の試し読みを特別に公開いたします。
ミステリとホラーが見事に融合した衝撃のデビュー作、是非チェックしてくださいね。
>>試し読み④へ
原浩『火喰鳥を、喰う』第一章試し読み⑤
昭和十八年一月六日
内地より釜山に戻りて早々、我ら二百九飛行場大隊に夏衣の支度せよとの伝達有り
やはり、いずれか南海の戦線に移送される様子
皆、意気軒昂 勇躍ス
一月七日
終日器材等積込作業 そのまま船上の人とナル
生命を託す輸送船の名は愛あい國丸
威容はすこぶる頼もしく不安も無い
乗員は全員が海軍軍人 輸送船とはいえ巡洋艦の兵装、魚雷発射管の備えアリ
一月八日
未明、艦は埠頭より離岸 いざ南海航路
我が故郷よサヨウナラ 父よ母よ サヨウナラ
一月十二日
終日波浪穏やかなるも日増しに暑さは厳しくなる
満州の極寒とはカワルモノダナア
一月十四日
赤道も越え日没後は灯火管制
海面油を引くが如く 波間に夜光虫がきらめき、夜空には南十字星が高く輝く
血戦の海近しといえども、船旅の如く全く平穏である
一月十五日
夕刻ニューブリテン島ラバウルに入港 青々茂る椰子の木々と美しい海に心は逸る
明日の揚陸に向けて船内準備
晩に夜間空襲あり 港内の艦船より対空火器で応戦ス
戦線に来るを実感スル
久喜貞市の部隊は年明け早々より、南方戦線に派兵されたらしい。日記の文字を追う私たちに玄田がカメラを向けている。寡黙な仕事人は次々にシャッターを切った。
「この、ニューブリテンってどこですか? フィリピン?」
亮の疑問に与沢が答えた。
「現在のパプアニューギニアです。地図上ではオーストラリアのすぐ北。この時は日本の占領下でした」
「へえ、随分遠くまで日本は進駐していたんですね」
「この頃の日本は拡張主義で、オーストラリアを窺うところまで版図を拡大していたんです」
伸子がのんびりと口を挟む。「でも、ここまでは呑気な南洋への船旅みたいよね」
確かに今のところは血生臭い記述は無い。楽しげにさえ読める。大伯父もこの時点では、戦地への不安より、前途洋々たる高揚感が勝っていたのではなかろうか。
私は日記を前にして、赤の他人の独り言を盗み聞きするような、どこか気恥ずかしいよそよそしさを覚えていた。なにしろ、ここには保の他に久喜貞市に面識のある者はいない。保ですら、貞市の出征時はまだ七歳。十三もの年齢差があったため、実兄の記憶はわずかなものなのだ。肉親の遺品を見る寂寞とした親しみよりも、戦時の生々しい史料を垣間見る物珍しさが勝っている。他人とは言わないまでも、どこか断絶した感があるのだ。
「正月の記憶はあるな。少しばかり」外した老眼鏡を袖で拭いながら、保が天井を仰ぐ。「前ん年の暮れには出征が決まってたもんで、正月を内地で過ごしたんだ。ほいで、おれを抱っこしてくれたわ。留守中、父と母を敬い言い付けをよく守るようにって。優しい兄貴だったような気がするな」
そう言うと、保は仏壇の引き出しの奥から一枚の写真を取り出して、卓上にぽいと置いた。
「こりゃ、元旦に撮ったもんだ。貞市兄貴の写真は唯一これだけ」
その黄色く退色した白黒写真には、口髭を生やした和装の男性と幼い子供を抱いた婦人、その二人に挟まれた中央に軍服の若者が写っていた。どうやら家の玄関口で撮影されたらしい。驚いたことに、瑣末な点を除いて戦中からこの家はあまり変わらないようだった。掲げられた日の丸を背景に四人が並んで立っている。
こんな写真が残っていたのかと伸子が感嘆の声を上げた。亮は何に感じ入ったのか、白黒ですねえとしきりに頷いている。
保が写真の人々を指差す。
「この、真ん中の軍服のが貞市兄貴。お袋に抱っこされとる子供が俺で、こっちのが親父」
「貞市さんは、少し雄司に似てるかね?」伸子がつるの緩んだ老眼鏡を押し上げながら言う。
写真に写る貞市の首はがっしりと太いが、顔はどちらかといえば細面だ。どこか柔和そうな印象は確かに自分に似ているかもしれない。とはいえ、古写真ゆえに粒子が粗く劣化も進んでいる。しかも帽子の影が落ちて目元が黒く潰れているので、貞市の顔つきはよくわからない。それでも頼もしげにきりりと結んだ唇からは意志の強さを感じさせた。
与沢記者が写真の貸し出しを保に求めてきた。信州タイムスでこの顛末を全て記事にするらしい。七十数年の時を経て遺族の元に辿り着いた日本兵の日記。読み物としては面白そうだ。
「稲刈りには帰れるら、って言ってたけえど、それどこじゃねえ。結局、今生の別れになっちまったな」保はそう言いながら、与沢に写真を渡した。
▼原浩『火喰鳥を、喰う』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322203001804/