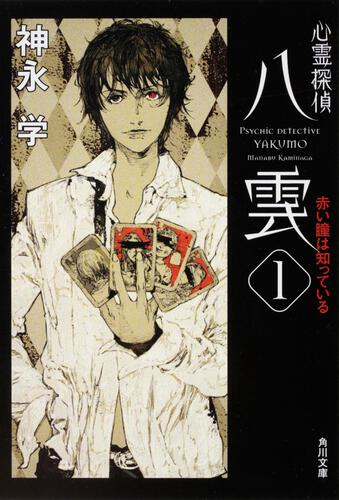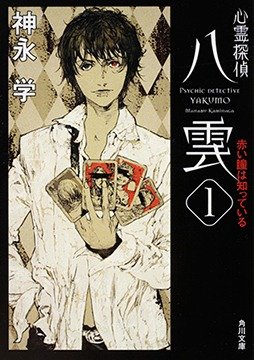本日9月12日(木)発売の「小説 野性時代」2019年10月号では、神永学さんの新連載「心霊探偵八雲 ANOTHER FILES 沈黙の予言」がスタート!
カドブンでは、この試し読みを実施します!
七の月の最後の日――。
緑に囲まれた、黒き水。赤い三角の下、過去の罪が暴かれる。
悔い改めなければ、三つの魂が地獄に落ちる。
第一話 予言
1
「やあ」
小沢晴香は、声を上げながらそのドアを開けた――。
明政大学のB棟裏手にあるプレハブの、一階の一番奥――〈映画研究同好会〉部室だ。
この場所は、大学が部活やサークルの拠点として貸し出している。いわばサークル棟の一つだ。
しかし〈映画研究同好会〉など存在していない。実体のない活動を大学側に申請し、この部屋を文字通り根城にしている不届きな学生がいる。
いつもの椅子に座っている、部屋の主――斉藤八雲の姿が目に入った。
ぼさぼさの寝グセ髪で、いかにも不機嫌そうに腕組みをしているが、別段機嫌が悪い訳ではない。
これが普段の八雲なのだ。
八雲は、晴香を一瞥したあと、小さく首を左右に振った。
その態度に、少しだけ違和を覚える。
普段なら、「また君か――」とか「トラブルを持ち込むな」とか、晴香の顔を見るなり、文句を口にするのに――。
八雲の向かいの椅子に座ろうとしたところで、晴香はようやく先客がいることに気づいた。
同年代と思われる女性が、ぽつんと座っていた。
背中越しということもあって、顔をはっきりと見ることはできなかったが、僅かに肩が震えていて、泣いているように見えた。
もしかして、修羅場的な感じの場面に出会してしまったのだろうか?
心臓がぎゅっと小さく音を立てた気がした。
「あっ。えっと、ご、ごめんなさい。また、あとで……」
そそくさと立ち去ろうとした晴香だったが、それを八雲が呼び止めた。
「別に構わない。彼女は、もう帰るところだ」
八雲の声は酷く冷淡だった。目の前の女性を追い払おうとしているかのようだ。
女性は、しばらくじっとしていたが、やがてゆっくりと立ち上がった。
「斉藤君なら、きっと助けてくれると信じてます」
女性が絞り出すように言った。
だが、八雲は無視を決め込んだ。
女性は諦めたのか、くるりと晴香の方に身体を向けた。
女性と目が合った。
童顔で、可愛い系の顔立ちをしているのだが、線が細く、どこか翳を背負っているような雰囲気があった。
女性は、晴香に黙礼してから部屋を出て行ってしまった。
「ねぇ。本当に大丈夫なの?」
晴香は、微動だにしない八雲に訊ねた。
詳しいことは分からないが、さっきの状況からして、あの女性は、八雲に助けを求めてやって来たようだった。
それなのに、あんな風に冷たい態度を取ったのでは、あまりに可哀相だ。
「珍しく、いいタイミングで来てくれた」
八雲が呟くように言う。
「いいタイミング?」
「君が来てくれなければ、延々と居座っていたかもしれない」
そう言って八雲は長いため息を吐いた。
「何か頼まれたんじゃないの?」
「いいんだ」
八雲は、あくびを噛み殺しながら答える。
「本当にいいの? 凄く困ってたみたいだけど……」
「らしいな」
八雲の言い様は、完全に他人事だ。
「らしいって……困ってるなら、何とかしてあげた方がいいんじゃないの?」
「そうやって、何でもかんでも首を突っ込むと、どっかの誰かさんみたいに、トラブルメーカーになるぞ」
――むっ!
完全に、晴香のことを言っている。
これ以上、何かを言ったら、過去のことを穿り返されて、小言を頂戴することになりそうだが、どうにも気になることがあった。
「さっきの人、知り合い?」
晴香が訊ねると、八雲の頬の筋肉がピクッと動いた。
やり取りからして、今日が初対面という感じではなかった。もっと前から、お互いに認知しているように晴香には感じられた。
「同級生だ。小学校のときの。確か、六年生のときに同じクラスだった」
「知っている人なら、助けてあげた方がいいんじゃないの?」
「同級生だったというだけで、彼女とは友だちでも何でもない。何かしてやる義理はないはずだ」
相変わらず、冷たい物言いだ。
「でも……」
「これまで、全くの没交渉だったんだ。同じクラスになったのは一回だけ。ろくに会話を交わしたこともない。他人同然だ」
八雲が突っぱねるように言った。だが、そうなると逆に引っかかる。
「どうして急に?」
晴香には、それが解せなかった。
没交渉だった人が、いきなり訪ねて来て、助けを求めるというのは不自然だ。
それに、彼女は「斉藤君なら、きっと助けてくれると信じてます――」と言っていた。あれは、八雲の人となりを知っているからこその言葉な気がする。
もしかしたら八雲は、何かを隠しているのかもしれない。
例えば、本当は、あの女性と八雲は以前、交際していた――とか。
別れたことで没交渉になったが、やっぱり八雲のことが忘れられずに、復縁を迫る為にここに足を運んだということも考えられる。
「言っておくが、君が考えているような下世話なことではない」
八雲がぴしゃりと言う。
まるで、晴香の頭の中を覗き込んでいたかのような完璧な指摘だ。
「べ、別に、下世話なことなんて考えてないよ」
慌てて否定してみたものの、取ってつけたような言い回しになってしまった。
「嘘が下手だな」
八雲の流し目が痛い。
「嘘じゃないよ。そ、それより、没交渉だった同級生が、何を助けて欲しいの?」
晴香が訊ねると、八雲は盛大にため息を吐いた。
「まあ、ひと言で言うなら、君と同類だ」
「同類って?」
「心霊がらみのトラブル」
「ああ」
思わず、納得の声を上げてしまったが、慌てて首を振った。
確かに最初の頃は、ことあるごとに、八雲の許に心霊がらみのトラブルを持ち込んでいて、トラブルメーカーという不名誉な呼称も頂戴した。
今は、黒い色のコンタクトレンズで隠しているが、八雲の左眼は生まれつき赤い。
ただ赤いだけではなく、死者の魂――つまり幽霊を見ることができるという、特異な体質を持っている。
これまで、それを活かして様々な事件を解決してきた。
晴香が、八雲と出会ったのも、ある心霊がらみの事件を持ち込んだことがきっかけだった。
だが、最近は、めっきりその回数が減っている。今日だって、暇潰しに来ただけだ。まあ、威張って言うことではないが――。
「でも、どうして八雲君のところにトラブルを持ってきたの?」
晴香が訊ねると、八雲がうんざりだという風に頭を抱えた。
「叔父さんだ」
「一心さん?」
「そうだ。叔父さんが、余計なことを喋ったせいで、ぼくのところに足を運んで来たというわけだ」
八雲が、苛立たしげに髪をガリガリと掻いた。
なるほど――と納得する。
八雲の叔父である一心は、寺の住職だ。弥勒菩薩のように、穏やかな空気をまとった人物で、会っているだけで癒やされる。
面倒見がよく、困っている人を放っておけない一心のことだ。彼女の話を耳にして、八雲の許に相談に行くようアドバイスしている姿が目に浮かぶ。
「で、どんなトラブルなの?」
晴香は、興味津々で訊ねた。
事件そのものに興味があるのは間違いないが、同時に八雲の小学生時代に対しても関心がある。
さらに昔の八雲が、どんなだったかを知るいい機会だ。
「さっきも言っただろ。そうやって、何にでも首を突っ込むから、トラブルメーカーになるんだ」
八雲がうんざりだ――という風に言う。
「別に話を聞くくらいいいでしょ。話せない特別な事情があるなら、仕方ないけど……」
晴香は意味深長に言うと、八雲の向かいの椅子に座りつつ、上目遣いに八雲の様子を窺った。
八雲は、苦い顔をしながら、ガリガリと寝グセだらけの髪を掻き回した。
そのまま、黙っているかと思ったが、意外にもゆっくりと話を始めた――。
2
「天使冬美という人物の名前を聞いたことがあるか?」
八雲が、眉間に皺を寄せながら口にした。
「知らない。もしかして、さっきの人の名前?」
「違う。彼女は、大地奈津実だ。天使冬美というのは、インターネット上で、預言者を名乗っている人物のことだ。これまで、幾度となく予言を的中させているらしい」
「よ、預言者?」
思わず声が裏返った。
預言者という名称がもつ不穏な響きもそうだが、何より、それが八雲の口から発せられたことが驚きだった。
「そうだ。預言者というワードと、名前で検索すればヒットする」
八雲に言われて、晴香は早速、スマホを使って検索をかけた。
すぐに、〈預言者 天使冬美〉と名乗る人物のホームページを見つけることができた。
爽やかな青がベースの簡素なホームページで、プロフィールの他に、ブログ形式で予言が綴られているらしかった。
一番最近の記事に目を通してみる。
そこに書かれていたのは、次のような一文だった。
七の月の最後の日――。
緑に囲まれた、黒き水。赤い三角の下、過去の罪が暴かれる。
悔い改めなければ、三つの魂が地獄に落ちる。
「何これ?」
思わず声が出る。
「それが予言だ」
八雲が、気怠げに返してくる。
――これが?
改めて目を通してみる。何となく、それっぽく書かれているが、具体性に乏しく、何を言おうとしているのか、さっぱり分からない。
「メンヘラな感じがする」
晴香が口にすると、八雲が顎を引いて頷いた。
「同感だ」
「どうして、この人は預言者だって名乗ってるの?」
「一つ前の記事を見てみろ」
八雲に促されて、改めてスマホに目を向ける。
記事の一覧で、一つ前の項目に、的中という文字が確認できた。タップしてその記事を開いてみる。
そこには、あるニュース記事が貼り付けられていた。市街地で車が暴走し、十字路で歩行者二人が撥ねられ、命を落とした痛ましい事故の記事だ。
そして、記事の下には、以前に天使冬美がした予言の文章が日付とともに書かれていた。
〈十字架の中心。怠惰の末に暴走した鉄塊が、二つの罪なき魂を奪う――〉
「え?」
思わず声が出た。
ここに書かれている文章は、記事の内容に合致している。しかも、天使冬美が予知をしたのは、事故が起こる三ヶ月も前のことだ。
「これって……」
晴香は、スマホの画面を八雲に見せながら口にする。
少しは驚くかと思ったが、八雲は、ふんっと鼻を鳴らして一蹴した。
「まさか、それで予言が当たったなんて思ってないだろうな」
「でも……」
「予言なんて、あり得ない。ほんの些細なことで、未来は変わってしまう。正確に、それを予測するなんて神だって不可能だ」
「少しくらい、可能性はないの?」
「ない。仮に予測できたとしても、未来を観測してしまった段階で、その未来は不正確なものに変わってしまう。シュレディンガーの猫だ」
「何が何だかさっぱり分からない」
晴香が主張すると、八雲はこれみよがしにため息を吐いた。
「君は、相変わらずのアホだな」
こういう言い方をされると、ついつい反論したくなってしまう。
「アホで悪かったわね。不可能だって言っても、現にこの事故の予言は当たってるんじゃないの?」
「こんなものは、偶然に過ぎない。いや、正確には偶然ですらないだろうな」
「どういうこと?」
「カラクリは簡単だ。交通事故が、年間どれだけ起きているか知っているか?」
「それは……」
具体的な数字は把握していないが、数千件の単位で発生していることは確かだ。
「予め、事故で二人が死ぬことを暗示した文章を書いておく。その上で、あとになって同じ数の人が死んだ事故を見つけてきて、的中したと言っているに過ぎない。交通事故は、日常茶飯事だ。放っておいても、いつかは二人が死亡する事故は起きるだろう」
「そうだね……」
いつかは、必ず起こることを、それっぽく書いておくことで、あたかも自分の予言が的中したように演出した――ということだろう。
「一通り目を通してみたが、どれも似たり寄ったりだ。的中していない予言が、幾つもあるが、それについては、時期を明言しないことで誤魔化している」
「期限を設けず、いつかは当たると言い切ることで、外れたんじゃなくて、これから的中するって言い張ることができるのね」
晴香が口にすると、八雲は「正解」と指を鳴らしながら言った。
「かつてノストラダムスの予言というやつがあっただろ」
「ああ。確か、1999年に世界が滅亡するって予言した人だよね」
「そうだ。1999年に、何も起きなかったことは、言うまでもないだろ」
「そうだね」
今、晴香たちが生きているのだから、世界が滅亡しなかったのは事実だが、当時は結構な騒ぎになっていた。
「そもそも、ノストラダムスの予言は詩の形式で書かれていて、明確な表現は一切使われていない。有名な1999年の予言にしても、空から恐怖の大王が来るだろう。アンゴルモアの大王を蘇らせ、マルスの前後に首尾よく支配する――という内容だったんだ」
「全然意味が分からないんだけど……」
「まあ、そうだろうな。意味不明にすることで、あとからどうとでも解釈できるようにしてある」
「世界が滅亡するなんて、ひと言も書いてないね」
「後から、そういう解釈をした人がいて、それが爆発的に広まってしまったというわけだ」
「そ、そうなんだ」
「ノストラダムスの他の予言の中には、的中したものもあると言われているが、さっき言ったように、解釈次第で、どうとでもなる代物だ。あとからこじつければ、何とでも言える」
「天使冬美って人も、同じってこと?」
「まあ、そういうことだ」
――なるほど。
さっきの天使冬美の予言も、交通事故を匂わす文章を予め、それっぽく書いておいて、あとから類似する事故が起きたときに、的中したと宣言すればいいのだ。
「そう考えると、嘘っぽいね」
「ぽいなんてもんじゃない。完全な創作だ。ついでに言うと、この天使冬美のプロフィールにも問題がある」
「どういうこと?」
「彼女のプロフィールには、事故にあって昏睡状態に陥ってから、未来が見えるようになった――と書かれているな」
「うん」
プロフィールを確認してみると、確かにその旨が記載されている。
「これがおかしい」
「どうおかしいの?」
「彼女は、預言者を名乗っている。予言をするなら預言者ではなく、予言者だ」
「違うの?」
「全然違う。預言者とは、神託を預かり、それを伝える役割を担っている者のことだ。だから、預かるという字を使う。自分の力で、未来を予知しているなら、予言者でなければならない」
「へぇ」
予言者と預言者が違うということまで思考がいかなかった。
この天使冬美という預言者が、胡散臭いことは分かったが、すっかり話が逸れてしまっている。
そもそもの問題は、さっきの大地奈津実という女性が、どんなトラブルを持ち込んだのか――だ。
晴香がそのことを問うと、八雲が心底嫌そうな顔をした。
「君は、ぼくが訳もなく、こんな話をしたと思っているのか?」
――思わない。
だからこそ、どうして預言者の話が出てきたのか、その理由を訊ねているのだ。晴香が、それを主張すると、八雲は咳払いをしてから話を再開した。
「彼女は、最近、幽霊の存在に悩まされているらしい」
「どんな?」
幽霊に悩まされているといっても、色々とある。
起きている現象によって、その深刻度なども変わってくるはずだ。
「彼女は、あるペンションでバイトをしているらしいんだが、そこで、人の気配を感じたり、ラップ音がしたりと、まあ、そんなところだ」
「実際、奈津実さんに幽霊は憑いていたの?」
死者の魂を見ることができる八雲なら、すでにその判別がついているはずだ。
「いや。さっき見た感じでは、彼女の近くに幽霊はいない」
八雲が小さく首を左右に振る。
「じゃあ、勘違いってこと?」
「君は、相変わらず学習しないな。だから、成長しないんだ」
八雲が、汚いものでも見るような目をした。
▶このつづきは、「小説 野性時代 第191号 2019年10月号」でお楽しみください!
こちらもおすすめ
▷680万部突破の神永学「心霊探偵八雲」、待望の新作ショートストーリー!「占い師」
▷『心霊探偵八雲1 赤い瞳は知っている』1話まるまる試し読み!①