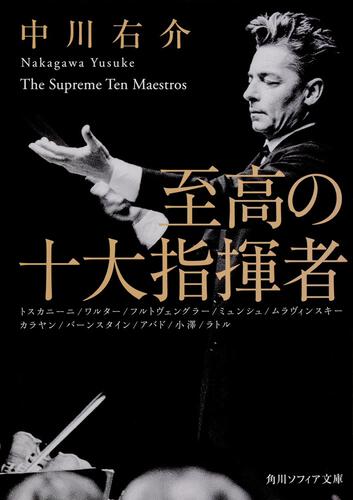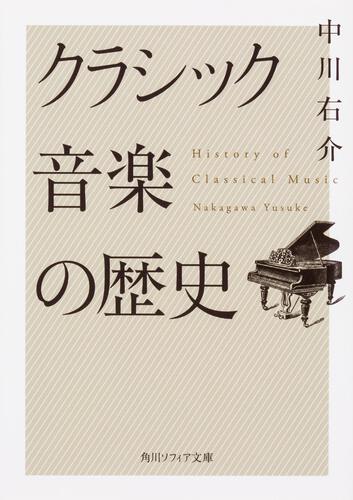日本で最も有名なクラシックの音楽家であり、世界で最も有名な日本人のひとり――。小澤征爾の生涯は戦後日本のサクセス・ストーリーの象徴でもあります。敗戦ですべてを失ったところからスタート、師との出会い、冒険、強運、挫折、再起、さらなる成功。桐朋学園短期大学音楽家の一期生であり、その後、数々の「日本人初」を達成していった小澤。多くの転機のなかでもひときわ大きな影響を与え、小澤がその舞台を日本から海外へと移すことになった「N響事件」について、「クラシックジャーナル」編集長などを務めた作家の中川右介さんの著書『至高の十大指揮者』(角川ソフィア文庫)から、一部を引用してお届けします。
―――――――――
1962年5月、ニューヨークでのアシスタント指揮者の契約が終わると、小澤征爾は日本へ向かった。六月からNHK交響楽団の指揮者になったのだ。
NHK交響楽団、通称「N響」は、1925年(大正14)3月に、作曲家の山田耕筰らによって設立された日本交響楽協会(協会)が前身となる。翌年1月に近衛秀麿の指揮で最初の演奏会を開いた。しかし近衛らは1926年9月に脱退して新交響楽団(新響)を結成した。戦争中の1942年に新響と日本放送協会を設立者とする日本交響楽団(日響)になった。ドイツから指揮者を招くのが伝統となっており、戦後もそれが続いていた。1951年8月にNHK交響楽団と改称し、現在に至る。
小澤は「客演指揮者」という肩書だったが、常任指揮者がいるわけではなく、実質的にはこのシーズンは小澤が常任指揮者だった。6月20日から10月22日までの23の演奏会のすべてと、11、12月の定期公演と「第九」の演奏会を指揮する契約だ。
7月にはメシアン《トゥランガリラ交響曲》の日本初演をするなど、小澤は意欲的なプログラムで取り組んでいた。夏は北海道、10月2日からは香港、シンガポール、クアラルンプール、マニラ、沖縄と海外でも公演した。
しかし、この海外ツアーの頃から、小澤と楽団員の関係がぎくしゃくしてくる。小澤はまだ27歳の若輩で、大半の楽団員は年長だ。しかも、N響の楽団員は東京藝術大学の卒業生が多く、新興の桐朋を出た小澤を見下す雰囲気にあった。小澤が遅刻したとか、ミスをしたとか、さまざまな要因が積み重なったところに、11月の定期演奏会が新聞で酷評されると、楽員代表による演奏委員会が「今後小澤氏の指揮するコンサート、録音演奏には一切協力しない」と表明する事態に発展した。楽団員は積極的に取材に応じ、いかに小澤が無礼な若者か、音楽の伝統を知らないかを吹聴した。マスコミは、小澤を「海外で賞をとり、チヤホヤされて増長した困った若者」という論調で揶揄し、批判した。
これに危機感を抱いたのは、同世代の若い文化人たちだった。演出家の浅利慶太や作家の石原慎太郎は、小澤を救うために団結した。
N響が小澤に「協力しない」と内容証明を送ってきたので、小澤サイドは契約不履行と名誉毀損で訴えるなど、泥沼化していった。小澤はデトロイトへの客演のため1月22日からアメリカへ行くが12月1日には帰国する予定だった。契約当事者でもあったNHKは、小澤との契約期間が12月いっぱいだったので、小澤に「病気になったことにして、12月いっぱいはアメリカにいてくれないか」と、「誰も傷つかないが姑息な解決」を打診したが、小澤は断った。あくまで、12月11日から13日までの定期演奏会と年末恒例の第九を指揮する姿勢を示した。
4日にリハーサルが始まったが、楽団員はボイコットして来ず、翌5日に事務局に小澤の降板を求めた。6日に事務局は楽団員に対し、定期演奏会に出れば、「第九」は小澤に振らせないと密約を持ちかけた。
浅利たちはNHKという巨大組織を巻き込んで戦線を拡大する戦術を取った。「演奏会中止」をNHK側から言わせるよう、12月8日のNHKとの交渉の場であえて挑発的な生意気な態度をとり、曲目の変更、楽団員が協力する保障、NHKが遺憾の意を表明する、の三条件を提示した。NHK幹部は感情的になり、小澤を切ることにし、12月10日、定期演奏会と第九の演奏会の中止を決定し通告した。N響史上初の「定期演奏会中止」だった。
この日は偶然にも、小澤の恩人の田中路子が、声楽としての引退コンサートを日比谷公会堂で開いた日でもあった。
しかし、定期演奏会が予定されていた12月11日、小澤征爾は会場の東京文化会館へ向かった。ステージには楽団員の座る椅子と譜面台が並び、指揮台もあった。楽団員さえ来てくれれば、いつでも始められる状態だった。そんなステージに、小澤はひとりで座り、楽団員を「待って」いた。その様子が取材に来た報道陣に撮られ、新聞には「天才は一人ぼっち」「指揮台にポツン」などの見出しで報じられた。
石原慎太郎と浅利慶太が「誰もいないステージ」の場面で、小澤に「孤独な天才」を演じさせ、カメラマンを呼んで撮らせたのだ。
そういう裏の事情は関係者しか知らない。ステージにひとりしかいない写真で、世論は一気に小澤に同情的になった。「若き天才」を「権威主義で意地の悪い狭量な楽団員」がいじめている構図になったのだ。
指揮者と楽団とのトラブルは世代間闘争へと発展していった。若き天才たちにとっては「他人ごと」ではなかったのだ。中止が決まると、石原、浅利のほか、三島由紀夫、谷川俊太郎、大江健三郎、團伊玖磨、黛敏郎、武満徹といった当時の若手藝術家、文化人たちが「小澤征爾の音楽を聴く会」を結成し、N響とNHKに対して質問状を出すなど、社会問題となっていく。
この渦中に、恩師のミュンシュが来日した。日本フィルハーモニーへ客演するために来日していた。
1963年1月15日、「小澤征爾の音楽を聴く会」という名称の演奏会が、日比谷公会堂で開かれた。オーケストラは日本フィルハーモニーで、小澤の指揮でシューベルト《未完成交響曲》やチャイコフスキーの交響曲第五番などが演奏され、聴衆は熱狂的な拍手を送った。
三島由紀夫は翌日の朝日新聞に「熱狂にこたえる道 小沢征爾の音楽会をきいて」と題してエッセイを書いた。〈最近、外来演奏家にもなれっこになり、ぜいたくになった聴衆が、こんなにも熱狂し、こんなにも興奮と感激のあらしをまきおこした音楽会はなかった。正に江戸っ子の判官びいきが、成人の日の日比谷公会堂に結集した感がある。〉
小澤は、17日に吉田秀和、黛敏郎らの仲介でNHKと和解した。訴訟を取り下げるという意味で、N響へ復帰するわけではない。
18日、小澤は羽田空港からアメリカへ飛び立った。
この一連の出来事は「N響事件」と呼ばれる。これが小澤の勝利を象徴していた。「ベトナム戦争」がベトナムでは「アメリカ戦争」と呼ばれるように、この事件はN響にとっては「小澤事件」なのだが、世間でそう呼ぶ人はいない。誰もが小澤サイドに立ったので、「N響事件」となったのだ。
このとき小澤が「深く反省」し頭を下げてN響に復帰していたら、「世界のオザワ」は存在しない。出世術としても藝術上の成長の面からも、この青年は日本を離れたほうがよかった。すでにヨーロッパとアメリカで名は知られている。カラヤン、バーンスタイン、ミュンシュという超大物の後ろ楯もあれば、最強のマネージメント会社もついていた。日本にいる必要など、なかったのだ。
日本を出た小澤は、以後、そのキャリアのほとんどを「日本人初」として達成していく。
交響曲と好敵手が織りなす人間ドラマ――十人のマエストロたちの人生
『至高の十大指揮者』
著:中川右介
https://www.kadokawa.co.jp/product/321811001059/
本書は「同じ曲でも指揮者によってどう違うのか」といった演奏比較を目的とした本ではない。もちろん、演奏を聴いていただきたいので、それぞれのCDを何点か紹介していくが、名盤ガイドではない。ネット時代のいまは、検索すればたいがいの演奏家の曲がすぐに見つかり、タダで聴くことができる。それがいいのか悪いのかは別として、かつてのような、「この曲はこの人の演奏」「この指揮者ならこの曲」という名曲名盤選びは必要なくなった。
したがって、演奏比較、その特色の解説といった観点ではなく、その指揮者がどのようにキャリアを積み上げ、何を成し遂げたかという人生の物語を提示する。指揮者ごとの列伝なので、それぞれの章は独立しており、興味のある人物から読んでいただいてかまわないが、それぞれの物語にほかの指揮者が脇役として登場することも多いので、第一章から順に読んでいただいたほうが、通史としてわかりやすいかもしれない。
(本書「はじめに」より引用)
目次
第1章 「自由の闘士」アルトゥーロ・トスカニーニ
第2章 「故国喪失者」ブルーノ・ワルター
第3章 「第三帝国の指揮者」ヴィルヘルム・フルトヴェングラー
第4章 「パリのドイツ人、ボストンのフランス人」シャルル・ミュンシュ
第5章 「孤高の人」エフゲニー・ムラヴィンスキー
第6章 「帝王」ヘルベルト・フォン・カラヤン
第7章 「スーパースター」レナード・バーンスタイン
第8章 「無欲にして全てを得た人」クラウディオ・アバド
第9章 「冒険者」小澤征爾
第10章 「革新者」サイモン・ラトル
著者略歴
中川 右介
1960年生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。出版社IPCで編集長を務めた後、1993年にアルファベータを設立し、2014年秋まで代表取締役編集長を務める。2007年からはクラシック音楽、歌舞伎、映画、歌謡曲、マンガ等の分野で執筆活動をおこなっている。主な著作に『戦争交響楽 音楽家たちの第二次世界大戦』(朝日新書)、『歌舞伎 家と血と藝』(講談社現代新書)、『角川映画 1976-1986[増補版]』(角川文庫)、『クラシック音楽の歴史』(角川ソフィア文庫)などがある。